タオルがカビ臭い!生えてしまったカビの取り方や予防法をご紹介

毎日使うタオルにカビが生えていたらショックですよね。たとえば「タオルに黒いポツポツがついている」「タオルがカビ臭い」など、気になった時には早めの対処が必要です。というのも、タオルは、衣類に比べてカビが生えやすいと言われてるから。今回は、タオルにカビが生えてしまう原因や、カビ取りの方法、予防法などをお伝えいたします。
タオルにカビが生えやすいのはなぜ?

タオルの主な用途・役割は、「水を拭き取ること」。そのため、タオルは水をよく吸うように作られています。また、タオルは一度使ったらすぐに洗濯するのが理想ですが、実際はこれが難しく、長時間湿ったままの状態になりやすいのが難点です。たとえば、洗面所の手拭き用タオルは、1日同じものを使い続けているという人が多いのではないでしょうか。
カビは、湿度が高い環境を好みます。タオルは性質上、カビにとって最適な環境が生まれやすいため、カビが生えやすいのです。
カビの生えたタオルを使い続けると、肌荒れの原因になったり、アレルギーを引き起こしたりなど、健康に害が及ぶこともあります。ご家族の健康を守るために、タオルのカビ対策を行いましょう。
タオルにカビが生える原因
次に、タオルにカビが生えてしまう主な原因をみてみましょう。
湿ったまま・汚れたままの状態で放置している
先ほどお伝えしたように、タオルは長い時間湿ったままの状態になりやすいものです。また、一度使用したタオルには、たくさん汚れがついており、雑菌も繁殖しています。カビは、この汚れや雑菌を栄養にして、どんどん増えていくのです。タオルを使ったあと、湿ったまま・汚れたままの時間が長くなるほど、カビが繁殖するリスクも高くなります。
カビにとって最適な温度は25~28度、さらに湿度60%以上の場所で繁殖しやすくなるといわれています。湿度・温度が高い梅雨の時期から秋にかけては、タオルもカビが繁殖しやすい状態になりやすいので、特に注意が必要です。使ったタオルは、できるだけ早く洗うようにしましょう。
洗濯槽のカビが移った
洗濯槽の裏側にカビが生えていると、洗濯している間にそのカビが剥がれ、タオルに移って繁殖してしまうことがあります。このような場合は、ほかの洗濯物にもカビが移っている可能性が考えられます。カビが生えているタオルと一緒に洗濯したものがあれば、カビが生えていないか、カビ臭くないか確認してみてください。
のちほどタオルに生えてしまったカビの取り方を紹介しますが、洗濯槽のカビが移っている場合は、タオルのカビを取っても、洗濯したらまたカビが移ってしまいますので、まずは、洗濯槽の掃除から始めましょう。
長い間収納していた
クローゼットやたんすの中は、カビが好む高温多湿の環境になりがちです。このような場所に保管している間に、タオルが中の湿気を吸収して、カビが繁殖してしまうこともあります。タオルのカビを防ぐために、収納するときもカビ対策も忘れないようにしましょう。
また、収納していた期間は短くても、生乾きの状態や、汚れがついたままの状態で収納すると、カビが生えやすくなります。タオルは、きれいに洗ったあと、十分乾燥させてから収納するようにしましょう。
同じように、保管中に服にもカビが生えてしまうことがあります。服に生えたカビの対処法・予防法については、こちらの記事をご覧ください。
タオルに生えてしまったカビの取り方
ではここからは、酸素系漂白剤を使ったカビ取りの方法を2つご紹介いたします。
1.つけ置き洗い

酸素系漂白剤でつけ置き洗いすることで、タオルに生えてしまったカビをすっきり落とせます。
白いタオルなら漂白・除菌力が高い粉末タイプを、色や柄が入ったタオルなら色落ちしにくい液体タイプがおすすめ。手荒れを防ぐために、必ずゴム手袋を着用して行ってください。
手順は、次のとおりです。
- 手バケツに40~50度程度のぬるま湯を入れて、酸素系漂白剤を溶かします。
- タオルを入れて、しばらくつけ置きします。
- すすぎをして酸素系漂白剤を洗い流したあと、洗濯機で通常どおり洗濯します。
2.煮洗い
つけ置き洗いでも取れない頑固なカビには、煮洗いがおすすめ。煮洗いをするときは、アルミ製の鍋だと変色の恐れがありますので、アルミ製以外の鍋を使用してください。お湯は沸騰させる必要はありません。酸素系漂白剤が効果的に使える温度は40~50度といわれていますので、この温度をキープするように火加減を調節してくださいね。
手順は、次のとおりです。
- 鍋に水を入れて火をつけ、50度くらいでキープします。
- 鍋の中に酸素系漂白剤を入れて、溶かします。
- 小さな泡がシュワシュワ出てきたら、タオルを入れます。
- 箸でタオルを裏返しながら弱火で5分ほど煮たあと、火を止めてしばらくつけ置きします。
- すすぎをして酸素系漂白剤を洗い流します。
タオルが「カビ臭い」と感じる程度なら重曹もおすすめ

目視でカビが確認できるわけではないけれど、「タオルがカビ臭い」と感じる場合は、重曹で煮洗いするのもおすすめ。この場合も、鍋はアルミ製以外のものを使用してください。手順は、次のとおりです。
- 鍋に水を入れて、お湯を沸かします。
- 鍋に重曹を入れ、その中にさらにタオルを入れて、5分ほど煮ます。
- すすぎをして、しっかり乾燥させます。
重曹は、煮洗いのほかにも、つけ置きしたり、洗濯機に直接入れたりすることも可能です。この場合は、重曹は水に溶けにくいので、必ず40度程度のぬるま湯を使うようにしてくださいね。
タオルにカビが生えるのを防ぐ方法
タオルにカビが生えるのを防ぐためには、タオルを清潔な状態で保つことが大切。そのために意識したい、3つのポイントをご紹介いたします。
使ったらすぐに洗濯する
お伝えしたように、タオルは湿ったまま・汚れたままの状態で長く放置するほど、カビが繁殖しやすくなります。使ったタオルは、なるべく早く洗濯するようにしましょう。
また、洗濯後はすぐに干すのもポイント。洗濯機の中に放置したままだと、洗ったあとでも雑菌やカビが繁殖しやすくなるので注意してくださいね。
定期的に洗濯槽を掃除する
タオルのカビを防ぐためには、きれいな洗濯槽を保つことも大切。市販の洗濯槽クリーナーを使って、洗濯槽を定期的に掃除することを心がけましょう。頻度は、1~2ヵ月に1度が目安です。
洗濯機の形状によって、使用する洗濯槽クリーナーのタイプや洗い方は異なります。洗濯槽の洗い方やカビ対策については、こちらの記事をご覧ください。
収納場所のカビ対策をする

収納している間に、タオルがその場所の湿気を吸ってカビが生えてしまうこともあるので、収納場所のカビ対策も忘れずに。除湿剤を置いたり、こまめに換気したりして、湿気がこもらないようにしましょう。洗面台下の収納や、バスルーム横のラックなどは、湿度が高くなりやすいので、収納場所を変えるというのも1つの方法です。
カビは、湿度が高い環境を好みますので、カビ対策では「除湿」が重要です。しかし、「除湿」だけでカビを予防するのは難しいので、あわせて防カビアイテムも活用してみましょう。
ウッディラボでは、天然由来の香りを主成分とした防カビアイテムを取り扱っています。どのアイテムも、置くだけ・貼るだけと使い方が簡単なのも特徴です。できるだけ防カビアイテムを目立たせたくない、という場合には、香りの力でダニよけと同時に、防カビにもなる「ダニよけシリカ」がおすすめです。6cm× 6cm の小さく、薄いサイズで、タオルの下に忍び込ませていても目立ちません。ほのかな香りがタオルについて、リフレッシュにも。

家中のカビを予防したいなら、エアコンやお風呂の防カビ、ダニよけアイテムもセットになった「カビ対策福袋」がおすすめですよ。

タオルのカビを防ぐには、洗濯槽や収納場所のカビ対策も大切!
洗濯槽にカビが生えていたり、収納場所のカビ対策が不十分だったりするために、タオルにカビが生えてしまうこともあります。タオルのカビを防ぐためには、タオルを湿ったまま・汚れたままの状態で放置しないことはもちろん、洗濯槽や収納場所のカビ対策をしっかり行うことも大切。便利な防カビアイテムも活用しながら、清潔な状態をキープすることを心がけてみてください。
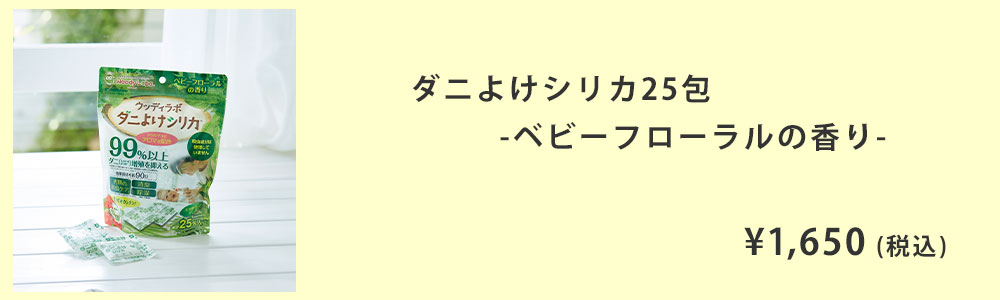
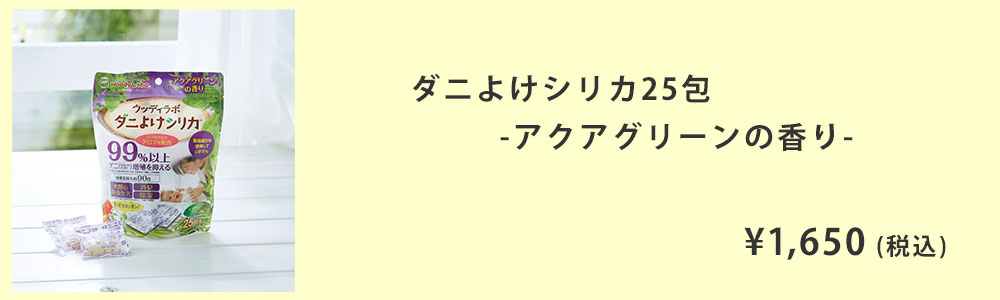
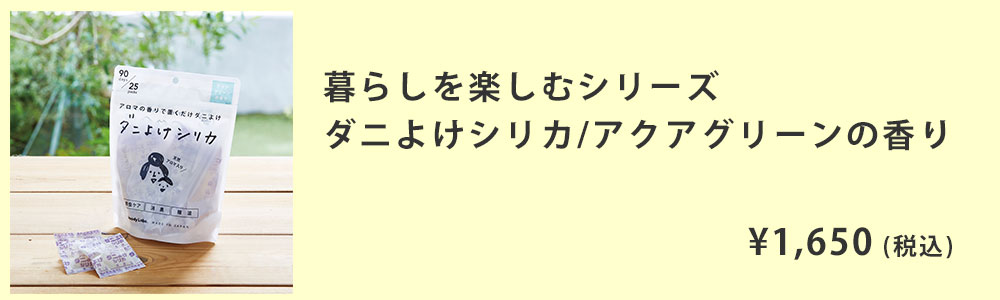
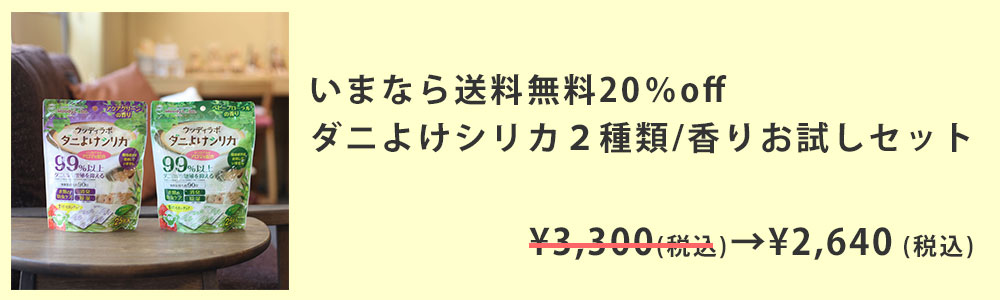
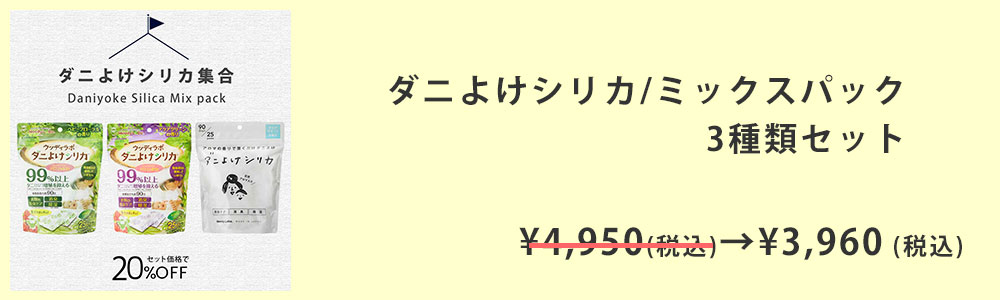
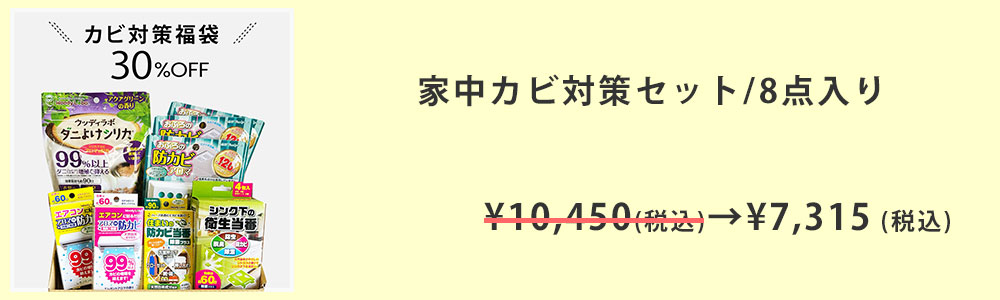

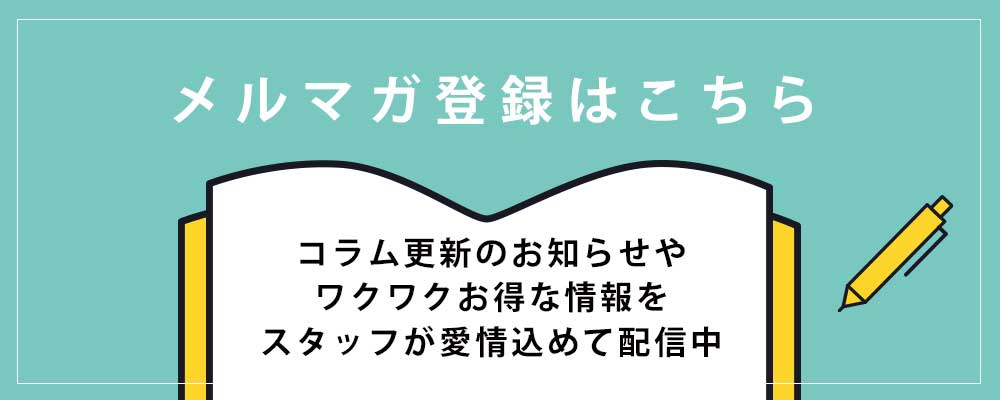
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
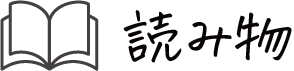
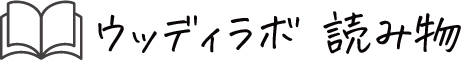


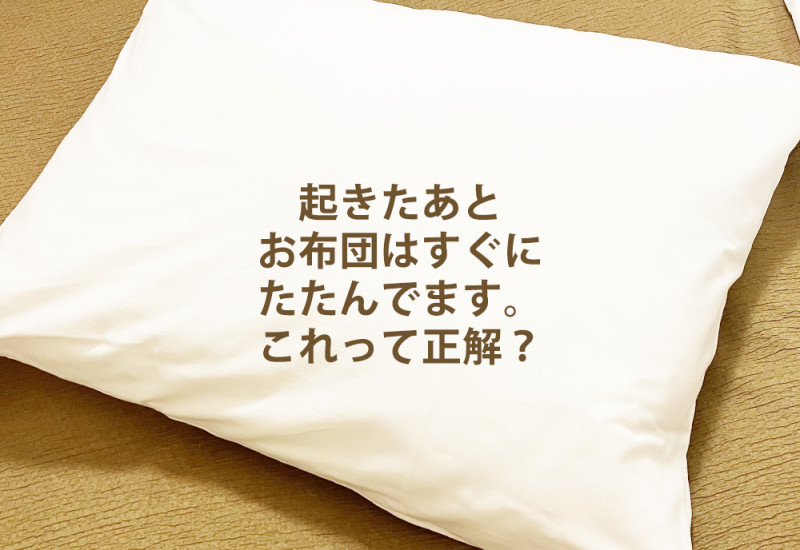
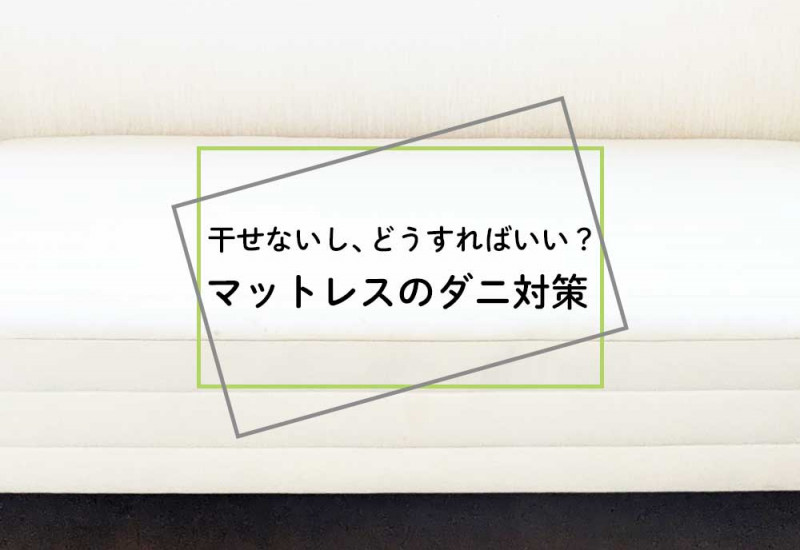
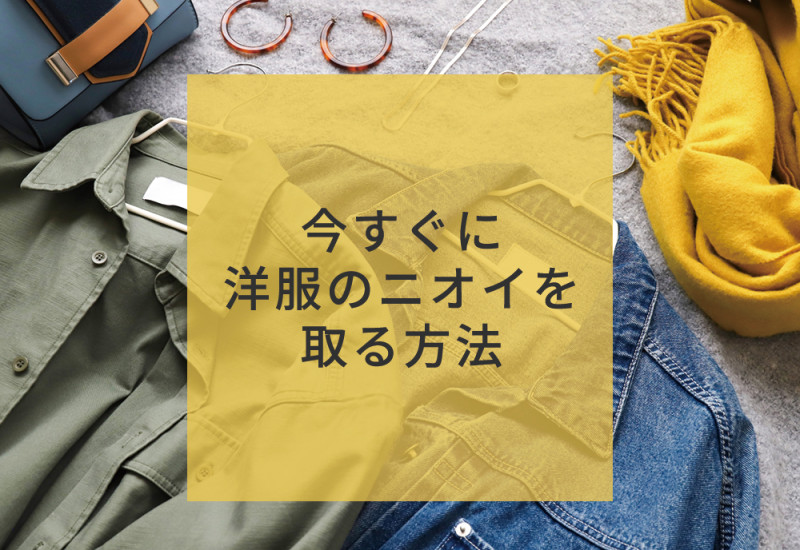
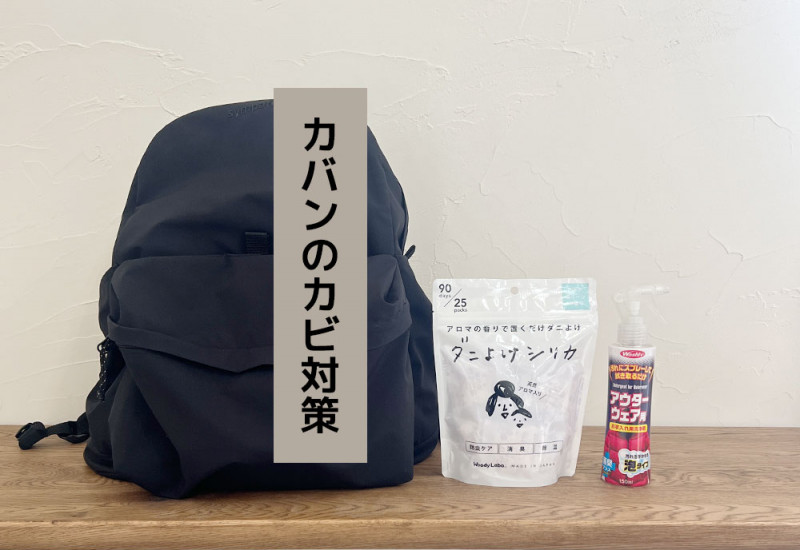


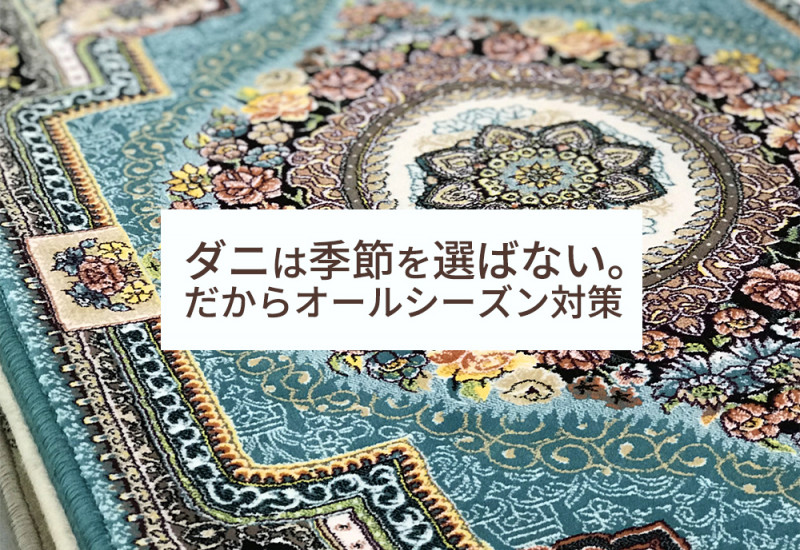


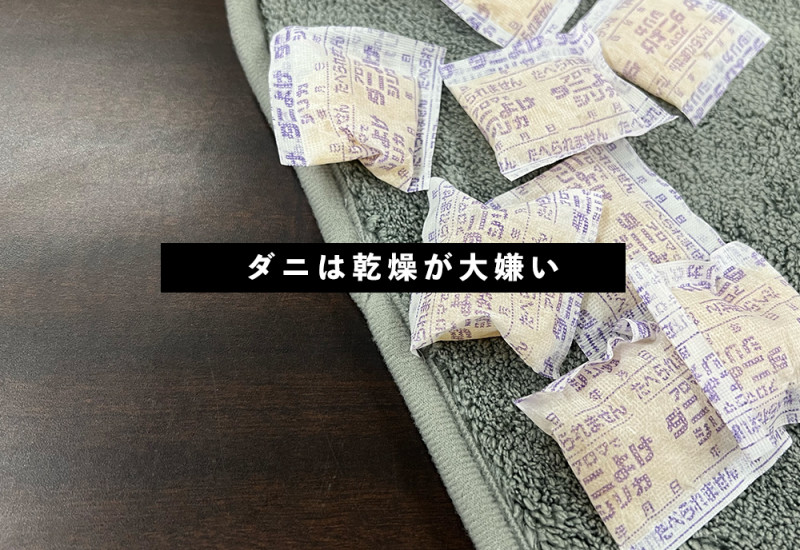


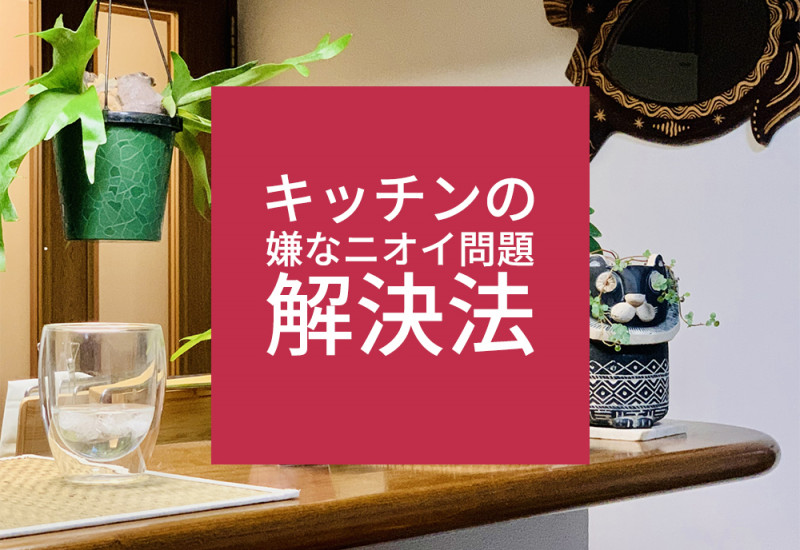
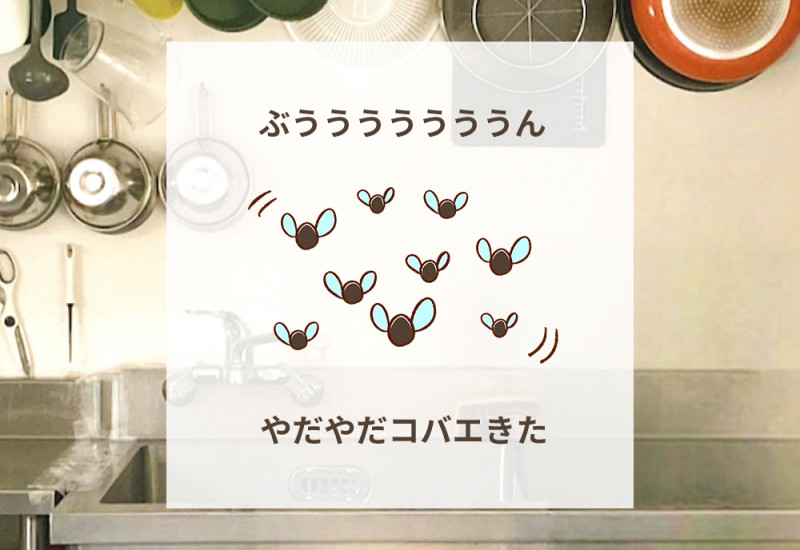

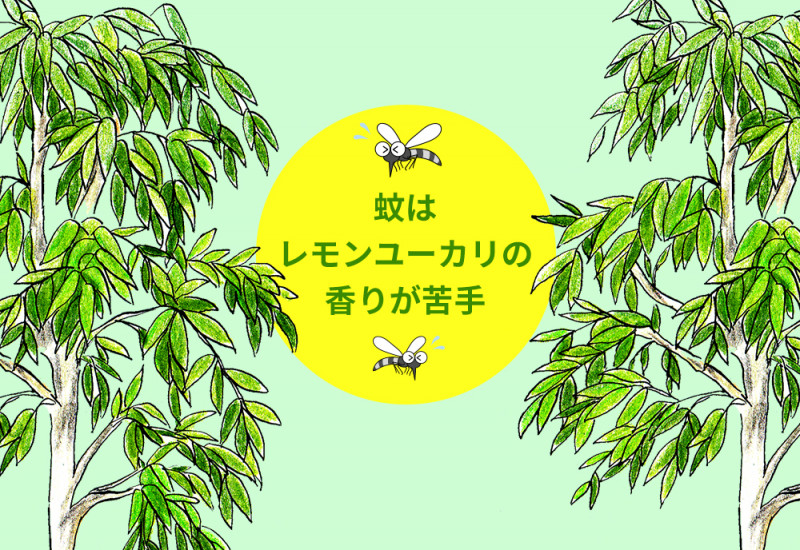
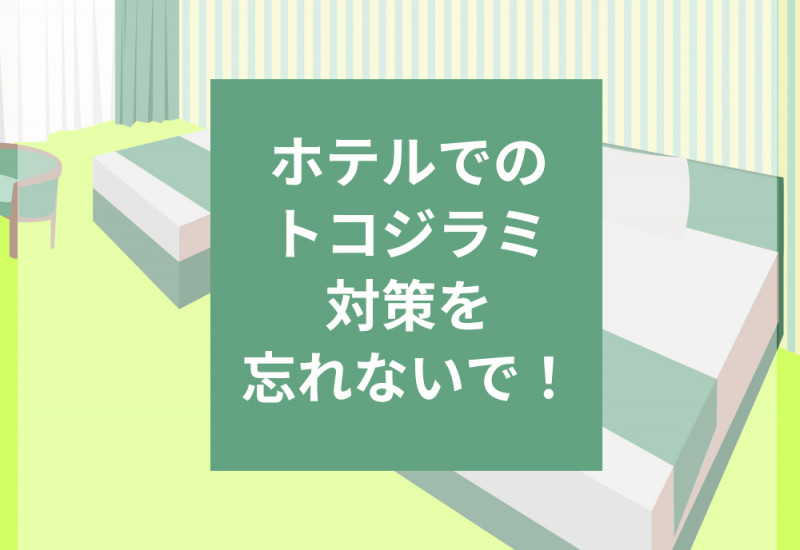



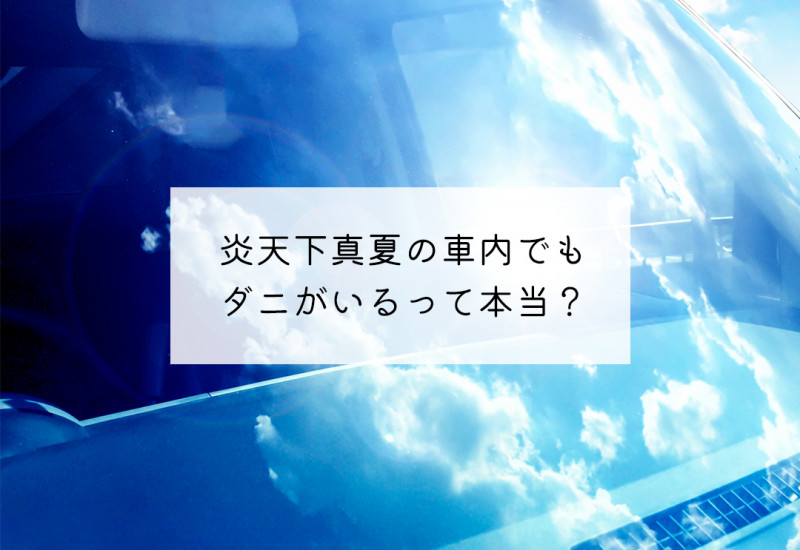
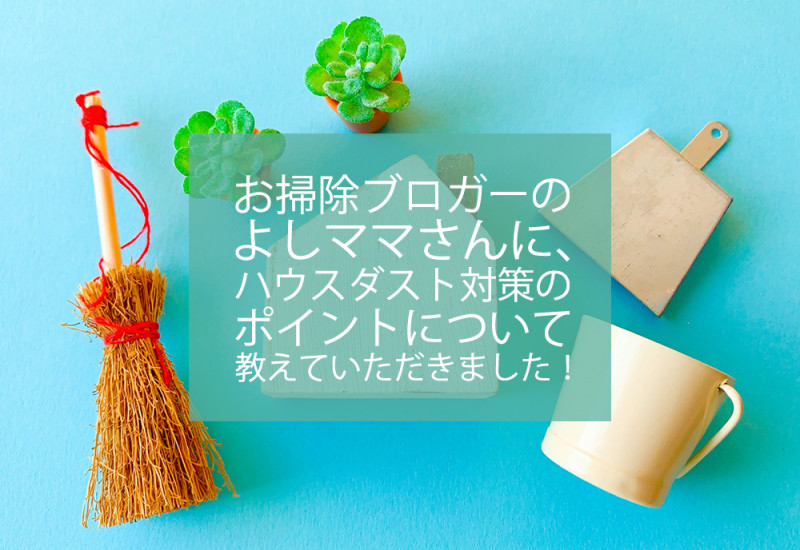
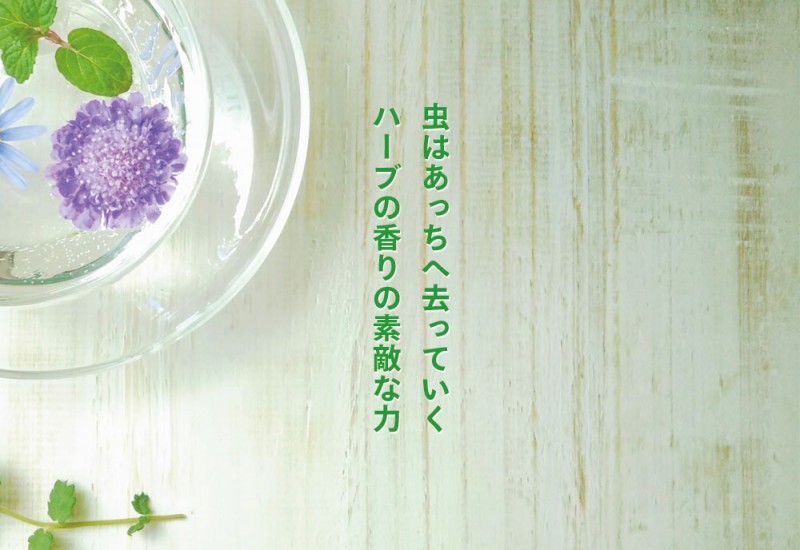
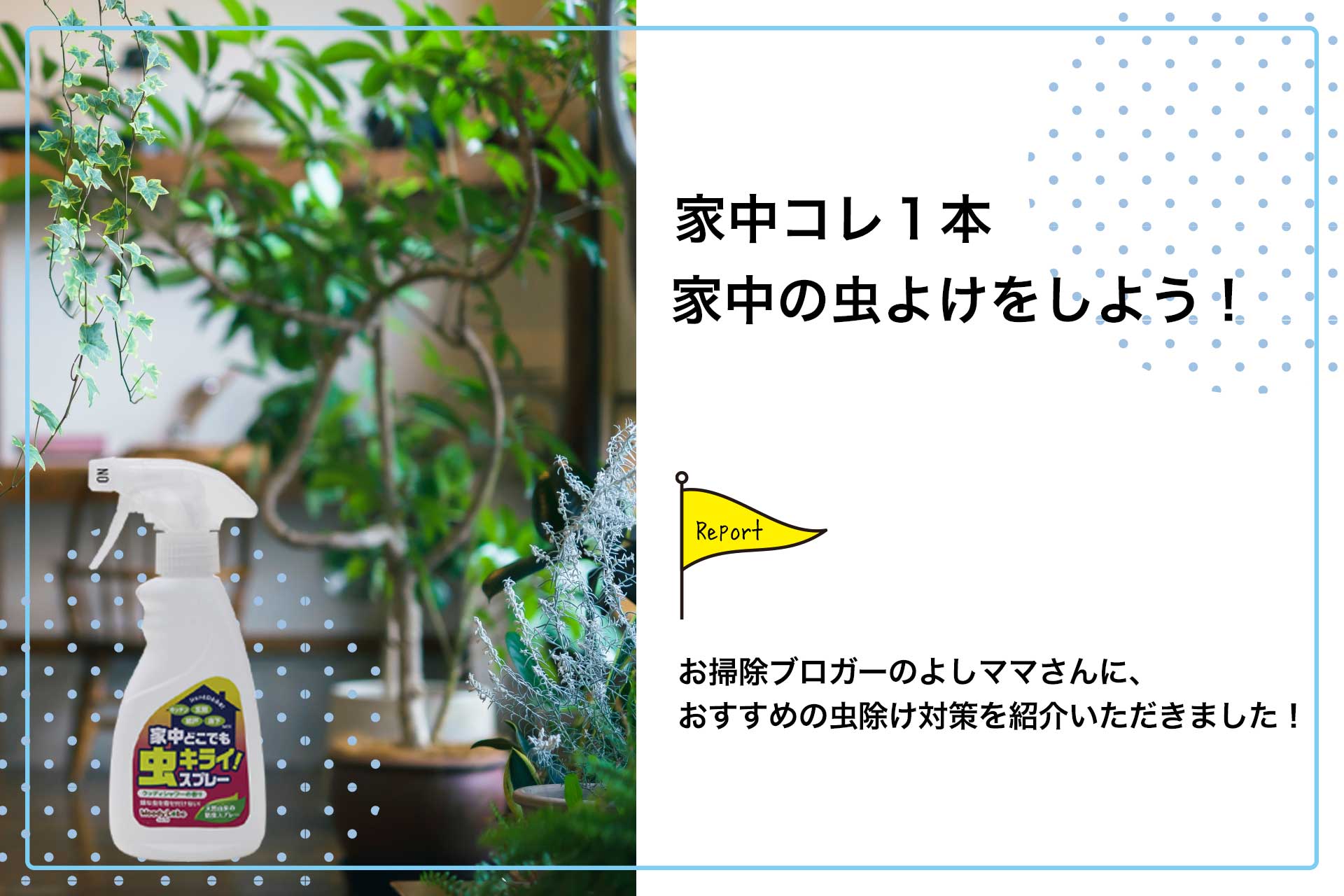
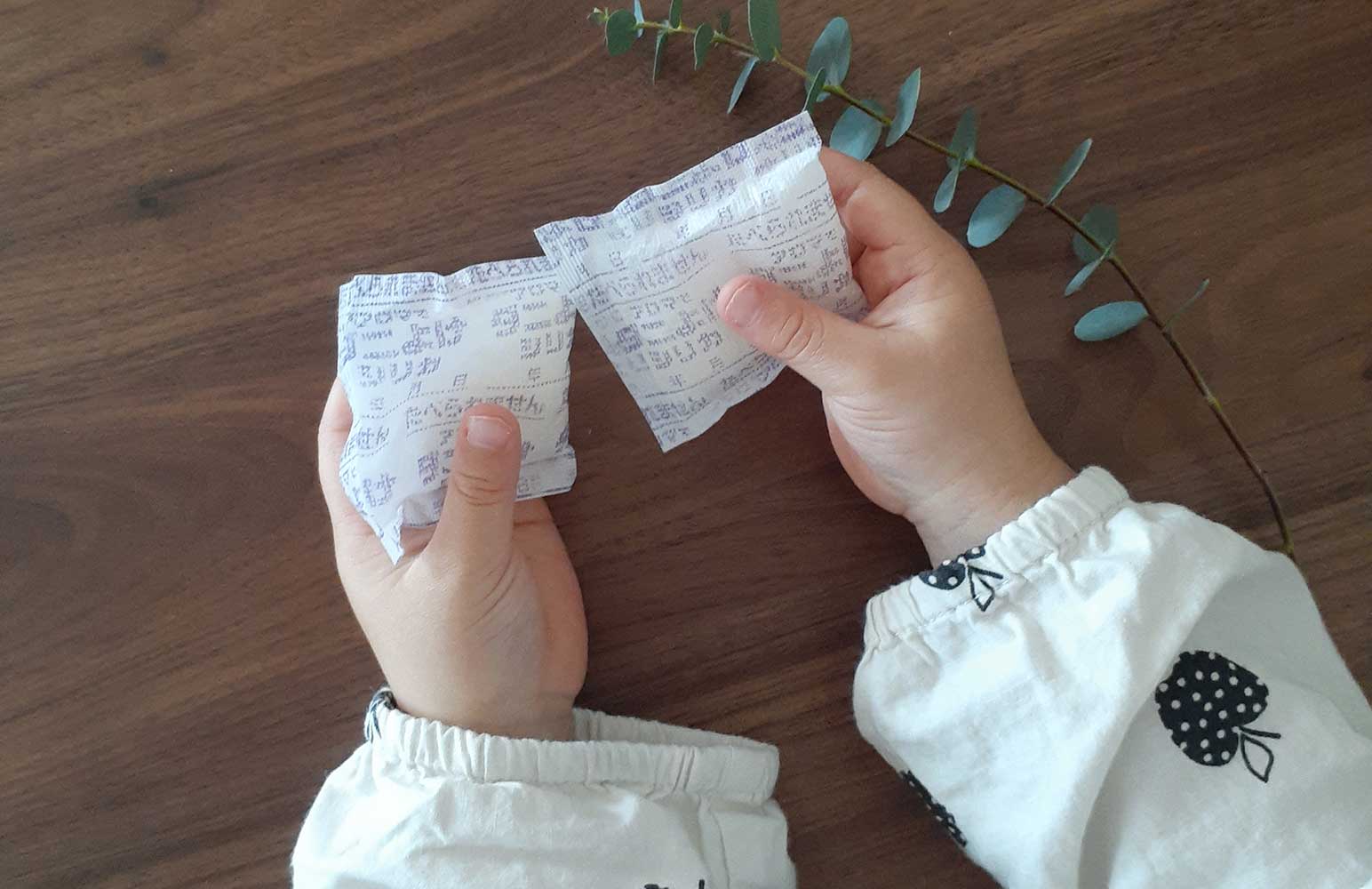

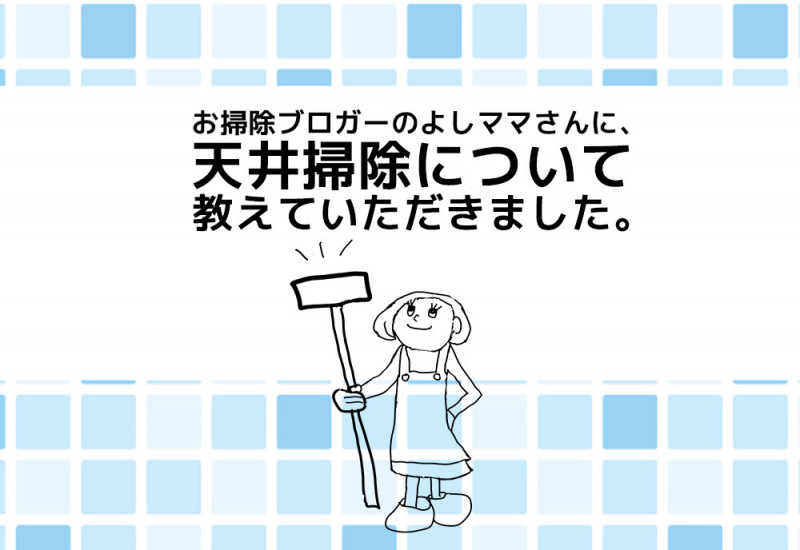
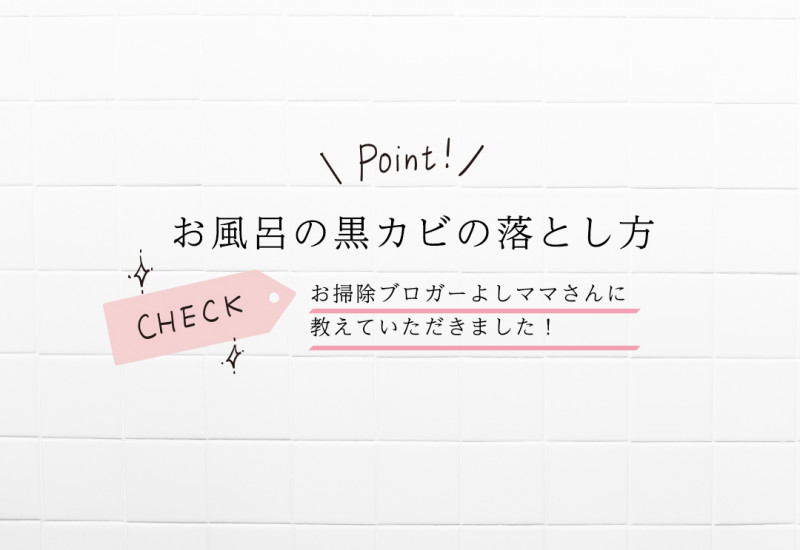



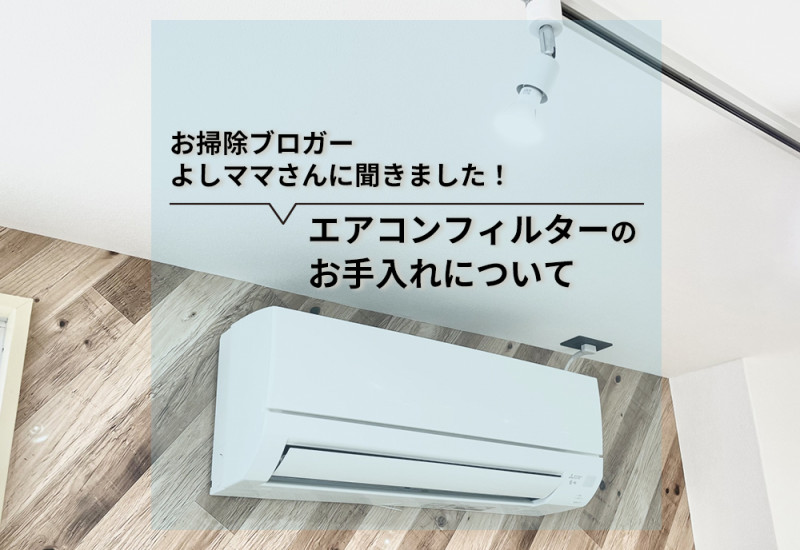
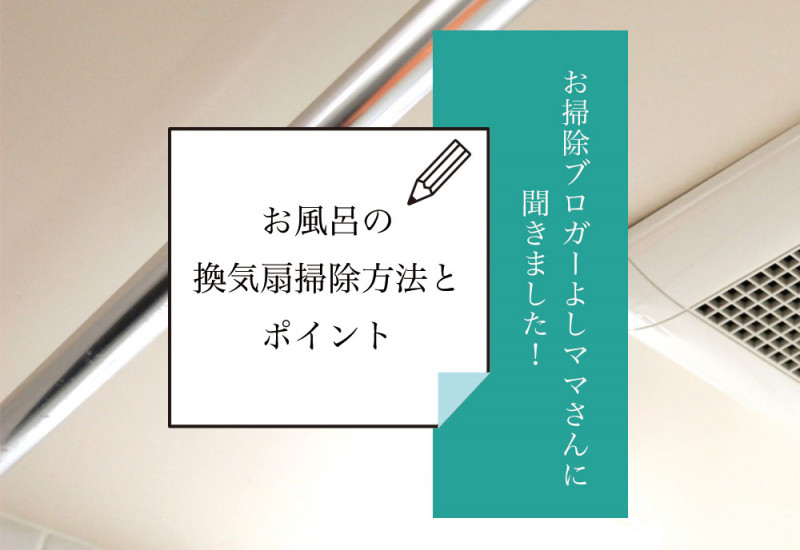

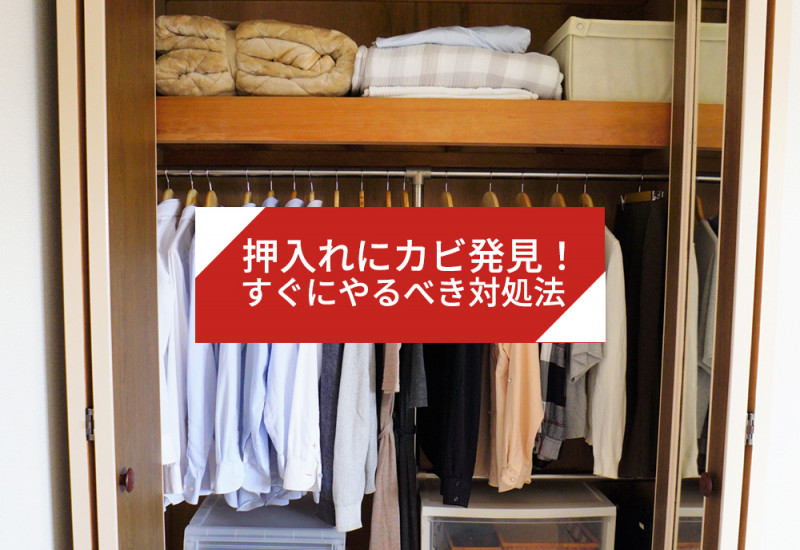



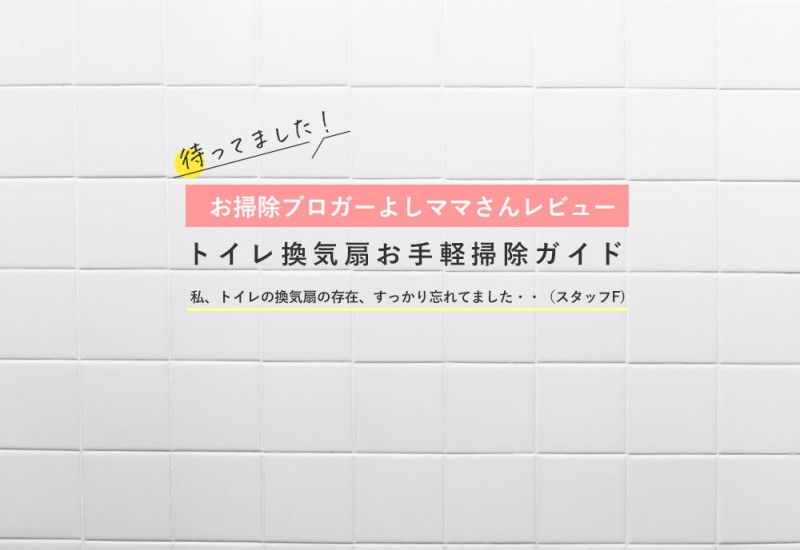
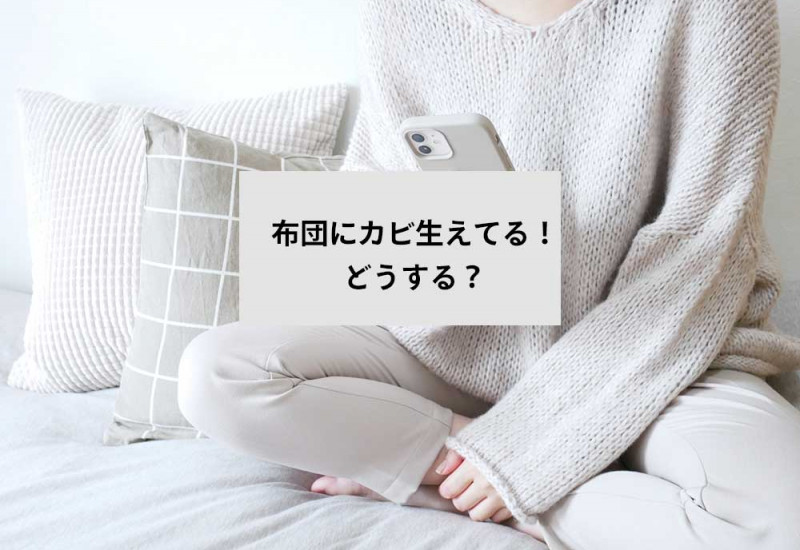
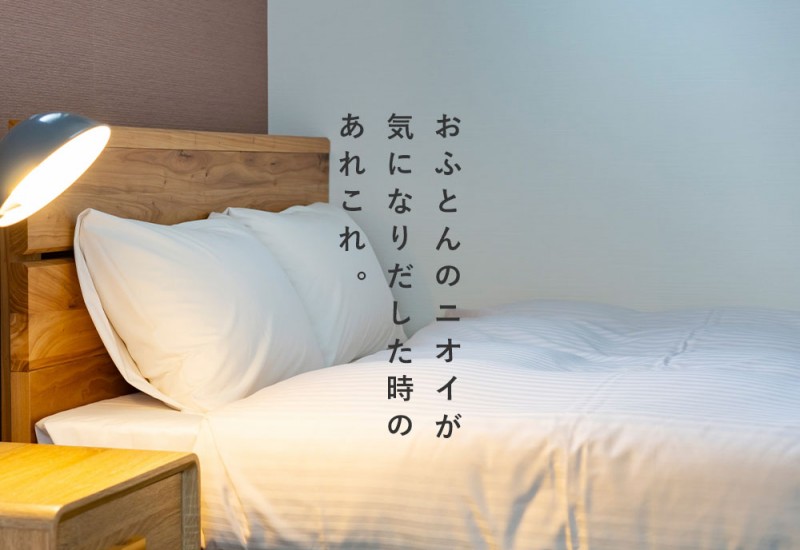
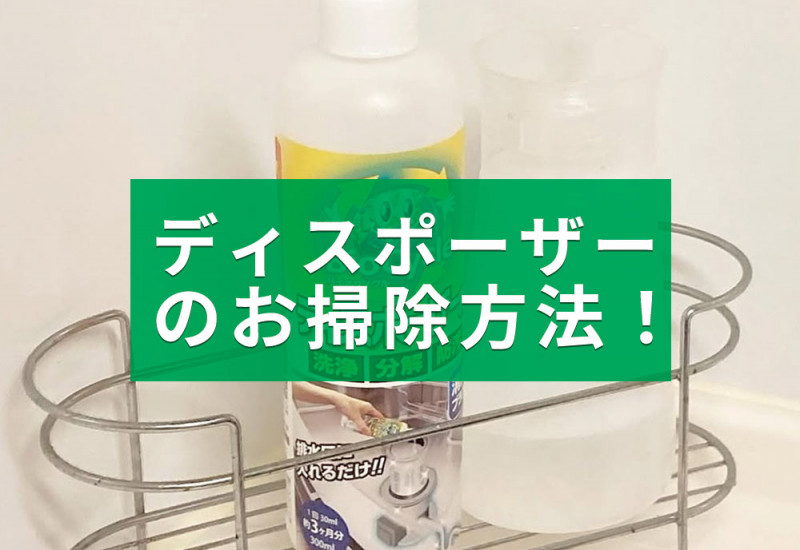

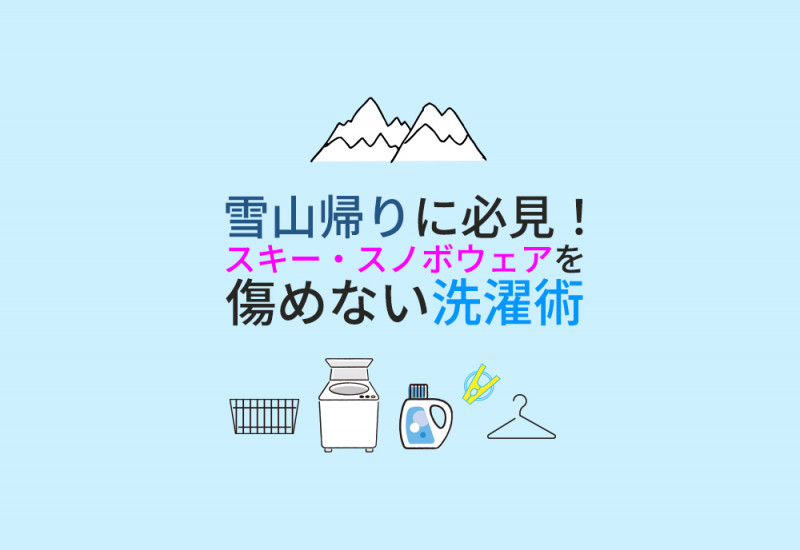
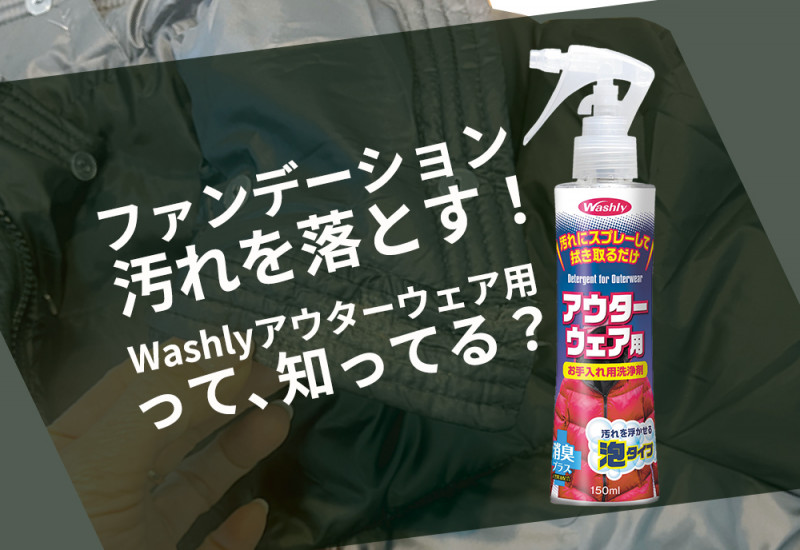


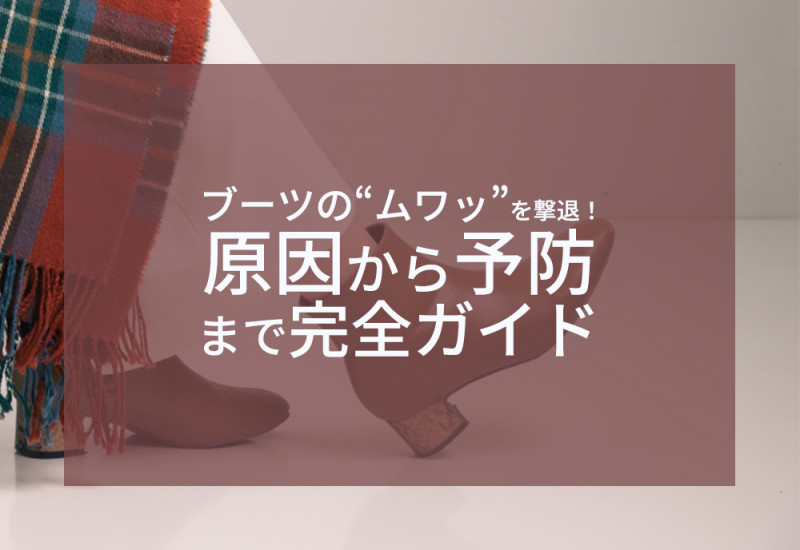
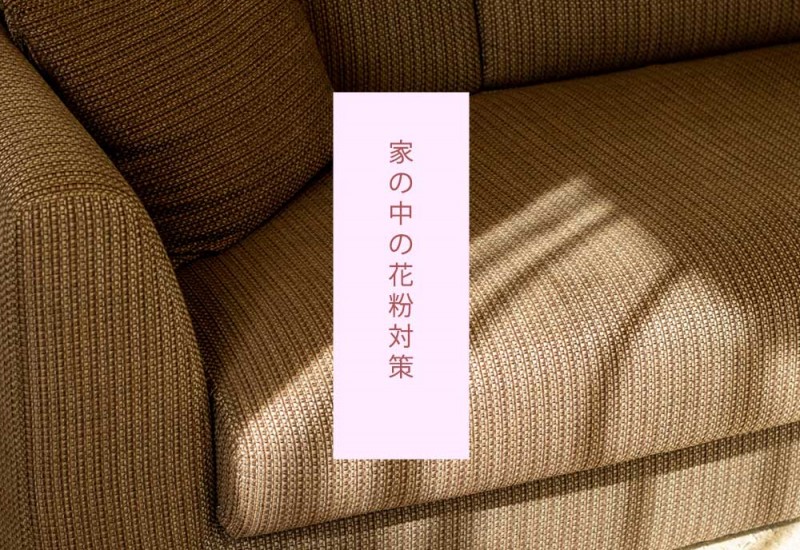

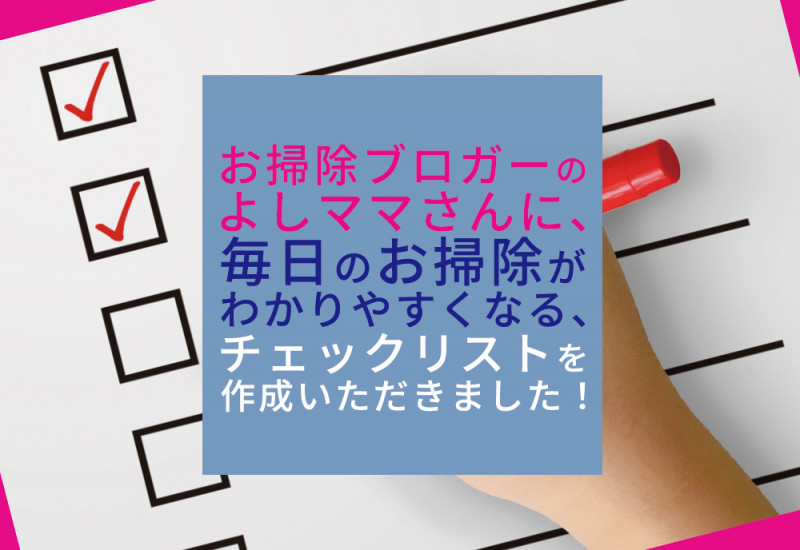

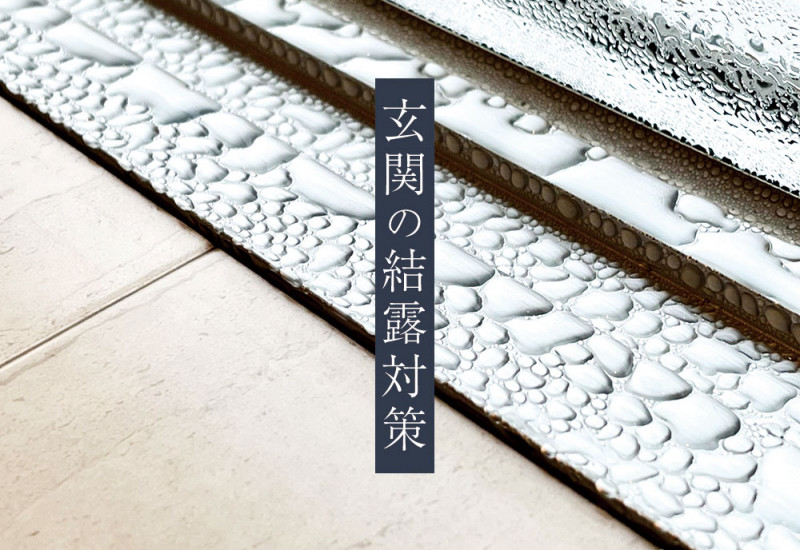

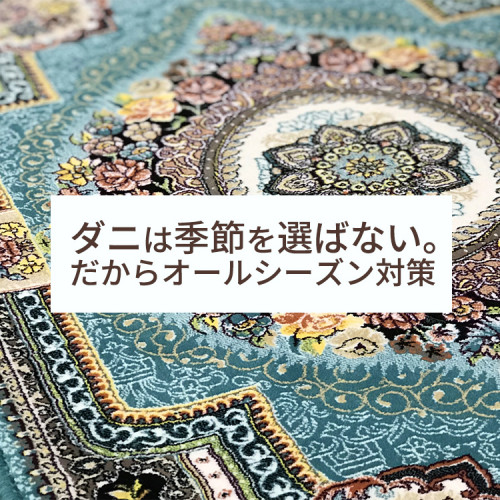

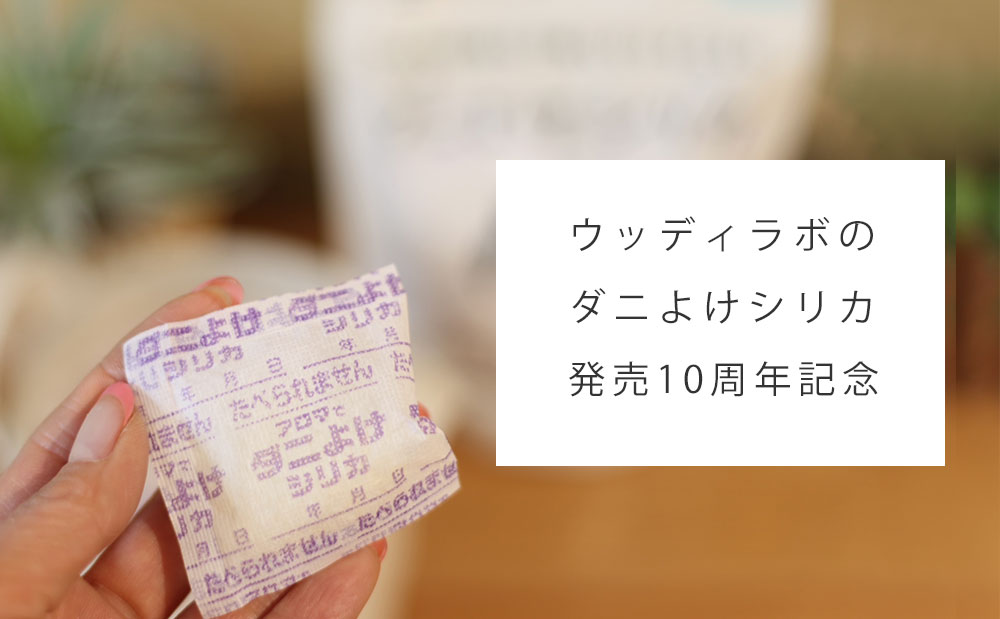


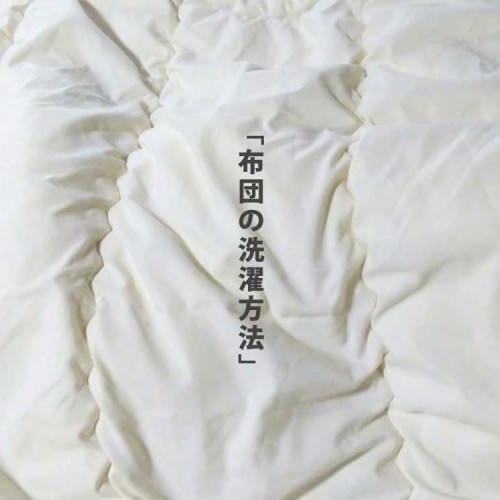


この記事へのコメントはありません。