キッチンのイヤなにおいを消したい!原因別の対処法をご紹介

キッチンは、料理の美味しいにおいだけでなく、イヤなにおいも発生しやすい場所です。放置すると、家中に、イヤなにおいが広がってしまうことも。においを消すには、原因に合った対策が必要です。今回は、キッチンのにおいの原因別に、対策を紹介します。
| <この記事のポイント> ●生ゴミは水気を切って早めに処分 ●排水パイプは重曹とお酢でお掃除 ●コンロ周りは、使用後のひとふきを習慣に ●布巾は、除菌&しっかり乾燥! ●シンク下のにおいは湿気対策と消臭剤を活用して |
キッチンのにおいの主な原因

キッチンのにおいの原因としては、主に以下が挙げられます。
・生ゴミのにおい……三角コーナーや排水口のゴミ受けの生ゴミ、ゴミ箱に捨てた生ゴミ
・排水パイプのにおい……排水パイプの中の汚れ(流れていった食品カス、洗剤カス、油汚れなど)
・油汚れによるにおい……コンロ周り、換気扇などに付着した油汚れ
・布巾のにおい……布巾を濡れたまま放置することによる生乾き臭
・シンク下収納のにおい……収納している食品のにおい、中で繁殖した雑菌やカビのにおい、排水のにおい など
これらのにおいを消すためには、場所ごとに対策が必要になります。次項より、その方法を詳しくご紹介いたします。
生ゴミのにおいを消す方法
まずは、生ゴミのにおいの消臭方法から詳しく見ていきましょう。
生ゴミをこまめに処分する
生ゴミを放置すると、そこから発生したにおいがキッチン全体に広がってしまいます。また、雑菌も繁殖しますし、においに引き寄せられて虫も発生しやすくなります。三角コーナーや排水口のゴミ受けに生ゴミがたまっているなら、放置せずにすぐに捨てましょう。
ただ、水気はしっかり切ってから捨てることが重要です。水気を含んだ生ゴミは特ににおいが出やすいので、そのままゴミ箱に入れると、ゴミ箱自体が臭くなる恐れもあります。
生ゴミの捨て方を工夫する
生ゴミを放置していないのに生ゴミ臭がする場合は、ゴミ箱から生ゴミのにおいが漏れ出している可能性があります。生ゴミの捨て方を、一度見直してみましょう。
具体的には、生ゴミを捨てるときはそのままゴミ箱に捨てるのではなく、新聞紙に包んでからゴミ箱に捨てるようにします。先ほどお伝えしたように、生ゴミが水気を含んでいると、においが発生しやすくなります。しかし、生ゴミの水気を完全になくすのはなかなか難しいものです。生ゴミを新聞紙に包むと、生ゴミの水分を新聞紙が吸ってくれるため、においが出にくくなります。調理中は、三角コーナーの代わりに、新聞紙や広告で作った箱を生ゴミ入れにすれば、調理後そのまま捨てられるのでおすすめです。新聞紙に包んだ生ゴミをさらにビニール袋に入れて、しっかり口を縛ってから捨てると、よりにおいが出にくくなるでしょう。
または、しっかり水気を切った生ゴミを、ゴミ収集日まで冷凍保存しておく方法もあります。冷凍庫のスペースに余裕があるなら、この方法も試してみてはいかがでしょうか。
排水パイプのにおいを消す方法
次に、排水パイプからのイヤなにおいを消す方法をご紹介します。
定期的に掃除をする

排水パイプの掃除を怠ると、においだけでなく虫やカビが発生したり、つまりの原因になったりすることもあります。排水パイプは、定期的に掃除をするようにしましょう。
排水パイプの掃除には、市販の排水パイプ用のクリーナーを使います。もしくは、重曹とお酢で掃除することもできます。重曹とお酢を使った掃除の手順は、以下のとおりです。
1.排水口のフタを外して、ゴミ受けにたまっているゴミを取り除きます。
2.排水口に重曹をふりかけ、その上からお酢をかけます(※シュワシュワと泡が出てきたら、お酢をかけるのを止めてください。)
3.そのまま30分程度放置します。
4.ぬるま湯で重曹とお酢をしっかりとすすいで、排水口のパーツをもとに戻します。
キッチンの排水パイプの掃除、2~3日に1回を目安に行うのが理想です。忙しい時には週に1回でも行ってみましょう。
シンクを使ったあとにお湯を流す
においの原因となる雑菌は、熱に弱いものが多いため、シンクを使ったあとに熱めのお湯をたっぷり流すと、排水パイプのにおい対策になります。ただ、熱湯を使用すると排水パイプが傷んでしまう恐れがあるので、お湯の温度は60度までにしましょう。
そして、お湯を流したあとはすぐに排水口の中に氷をたっぷり入れて、一気に冷やします。お湯を流すだけだと、そのうちお湯が冷めて、雑菌の繁殖に最適な温度(25~40度)になってしまうためです。
油汚れによるにおいを消す方法

油汚れによるにおいを消すためには、やはり油汚れを取り除くしかありません。油汚れは、放置するほど落ちにくくなるため、「コンロを使用したあとは軽く掃除をする」ことを、習慣にするとよいでしょう。市販のキッチンクリーナーか、手作りのセスキスプレー(水200ml+セスキ炭酸ソーダ小さじ0.5杯)で拭き掃除をする程度でOK。数十秒のひと手間で、後の掃除がぐっと楽になります。
また、普段はなかなか掃除ができないレンジフードや換気扇には、カバーをつけておくと油汚れが付きにくくなります。ホームセンターや、100円均一ショップでも販売されていますので、探してみてください。
換気扇やコンロ周りに油汚れがこびりついてしまっているときは、つけおき洗いがおすすめです。手順は以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
布巾の生乾き臭を消す方法
布巾から生乾き臭がするなら、布巾に雑菌が繁殖している可能性があります。この場合、布巾を除菌すれば、においもスッキリとれるでしょう。その方法ですが、まず布巾をしっかり洗って、そのあとで10分程度煮沸します。もしくは、耐熱容器に入れて1分程度電子レンジにかけてもOK。このとき、重曹を入れるとより効果的です。また、除菌後はしっかり乾しましょう。使用しないときは布巾ハンガーに広げてほしておくと、生乾き臭を防げます。
そして、清潔な状態をキープするために、週に1度はしっかり洗うことも大切。酸素系漂白剤でのつけおき洗いをすると、除菌もできるのでおすすめです。
シンク下収納のにおいを消す方法

シンク下収納からイヤなにおいがする場合、複数の理由が考えられます。たとえば、
・シンク下に湿気がこもり、カビが生えている。
・排水パイプにトラブルがあり、においが漏れ出している。
・収納しているもののにおいが混ざって、イヤなにおいになっている。
などです。
原因ごとに必要な対策は異なります。シンク下収納のにおい対策については、以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。
キッチンのにおい対策におすすめの消臭剤「シンク下の衛生当番」
キッチンのにおいが気になるときは、市販の消臭剤を活用すると、簡単ににおい対策ができます。
おすすめは、ウッディラボの「シンク下の衛生当番」。コンパクトなのに、消臭だけでなく除菌、除湿、防カビ、防虫までできる優れものです。置いておくだけで、約60日間効果が続きます。名前のとおり「シンク下」用のアイテムですが、いろいろなところにお使いいただけます。キッチンなら、食器棚やゴミ箱などのにおいや湿気対策にもおすすめですよ。

実際にお使いいただいた方の声をご紹介
ここで、実際に「シンク下の衛生当番」をお使いいただいた方から寄せられた声をご紹介いたします。
『商品の口コミが良かったので購入。棚に2個入れ扉を閉め1時間程度でカビ臭が消えました!嘘のようにカビ臭が消えました!』
『シンクの下が湿気の臭いか、嫌な臭いがしていたので、なにかないかと探していたところ、こちらを見つけて購入してみました。臭いが気にならなくなりました!!』
『シンク内に入れている調理道具にカビが生えていることが判明し、何か良いものはないかと探しておりましたところ、この防カビ材がありましたので使用して見ようと思いました。使い始めてからほぼ2ヶ月毎に交換をしておりカビの発生は抑えられていると思います。』
参照:【楽天市場】シンク下の衛生当番 8個入り(公式 ウッディラボストア) | みんなのレビュー·口コミ
一方で、「思ったよりも香りがきつい」というお声もいただいております。香りが気になる場合には、換気をしながら使用してみてください。すぐに香りが落ち着きます。また、1箱4個入りですが、いきなりすべて設置するのではなく、場所に合わせて1、2個設置して、しばらく様子を見ていただくのがよいかもしれません。
キッチンのにおいを防ぐには、こまめに掃除することが大切
キッチンのにおいの主な原因は、ゴミや汚れです。こまめに掃除をして清潔を保つことで、においは抑えることができます。加えて、便利な消臭剤を活用すれば、においが発生しにくくなるでしょう。
キッチンはにおいだけでなく、雑菌やカビ、虫なども発生しやすい場所です。除菌・除湿・防カビ・防虫までできる消臭剤を選べば、一つでまとめて対策ができますよ。
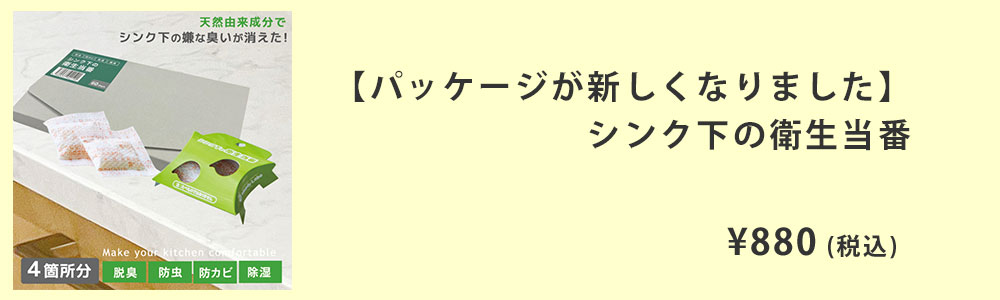

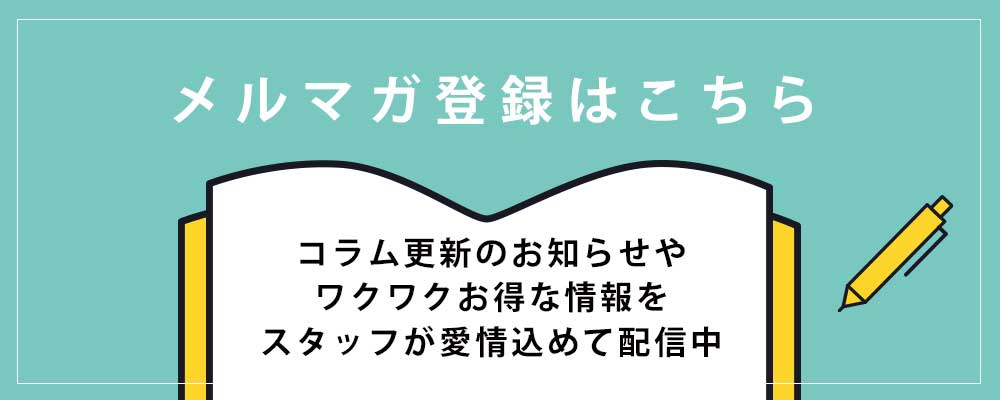
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
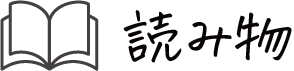
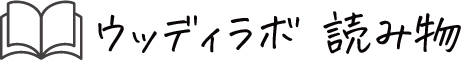


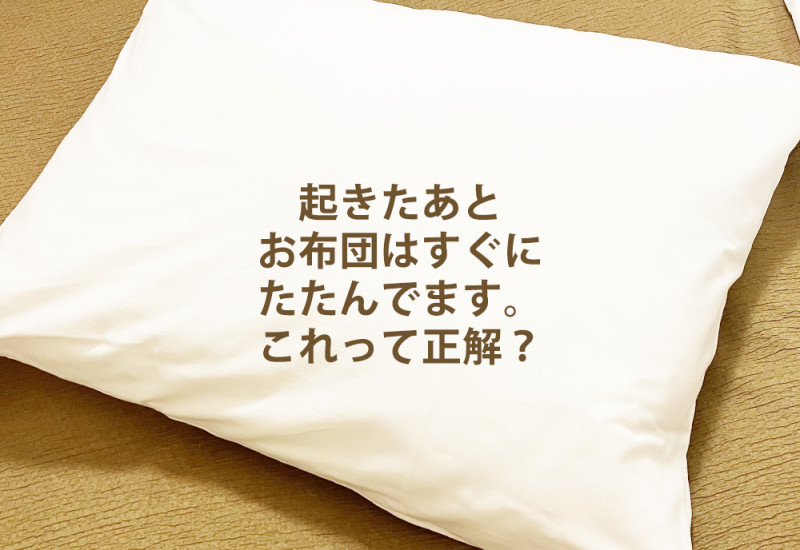
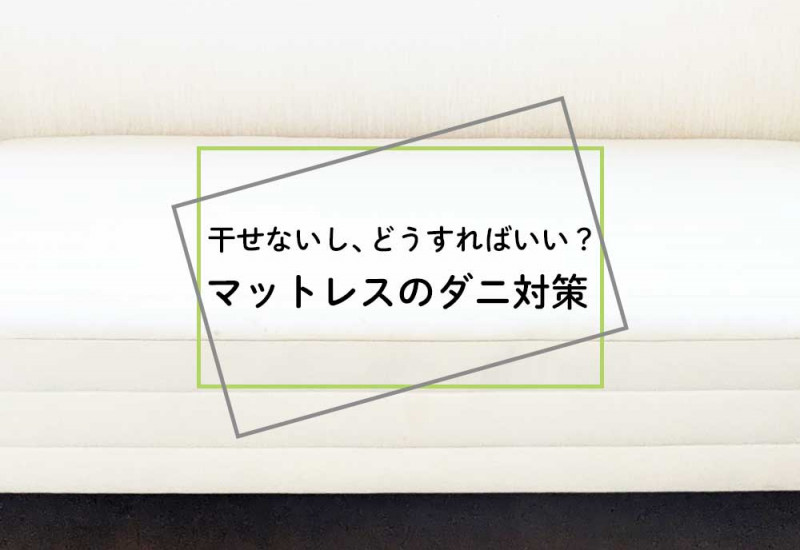
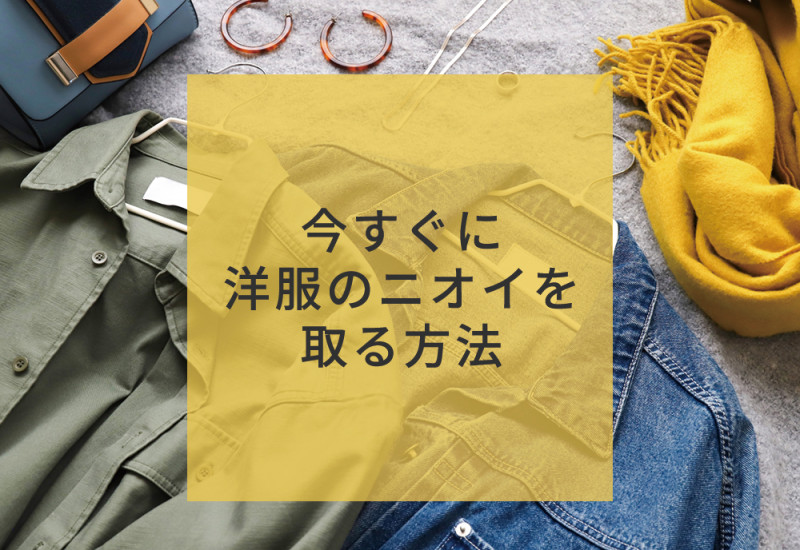
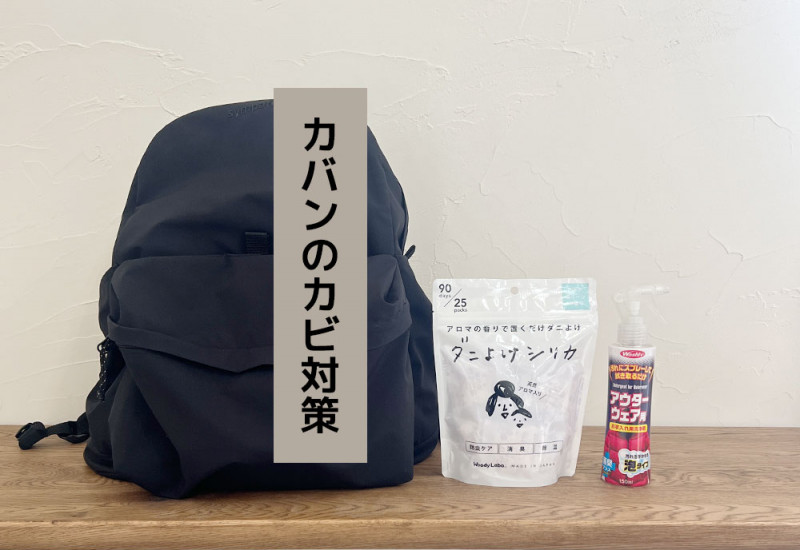





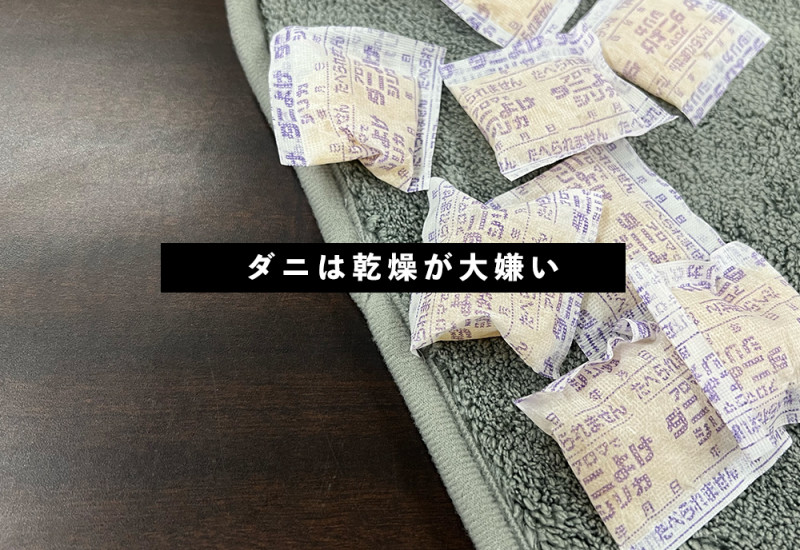


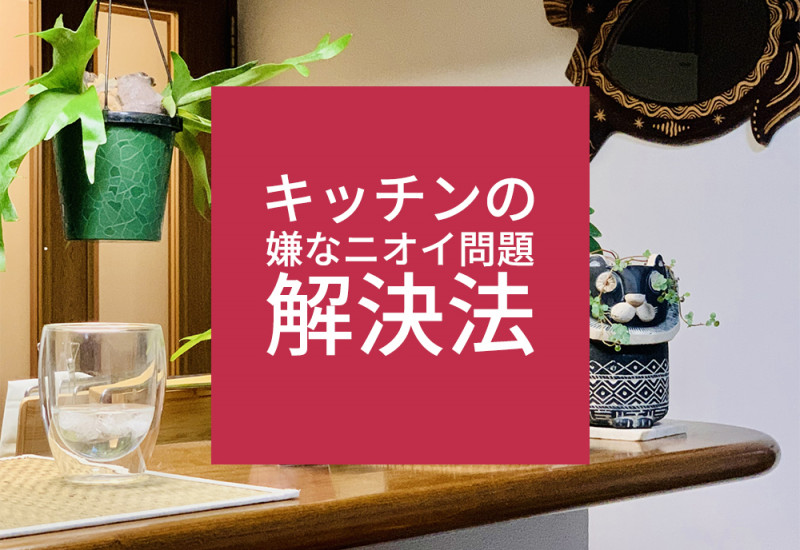
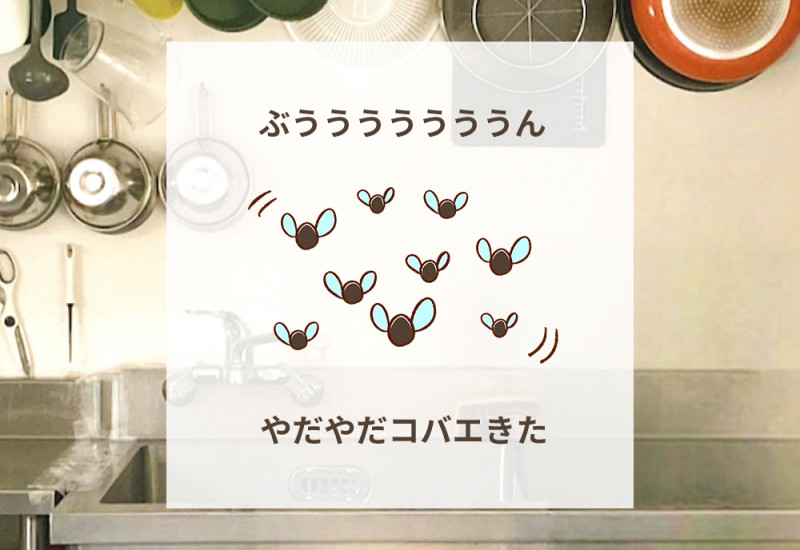

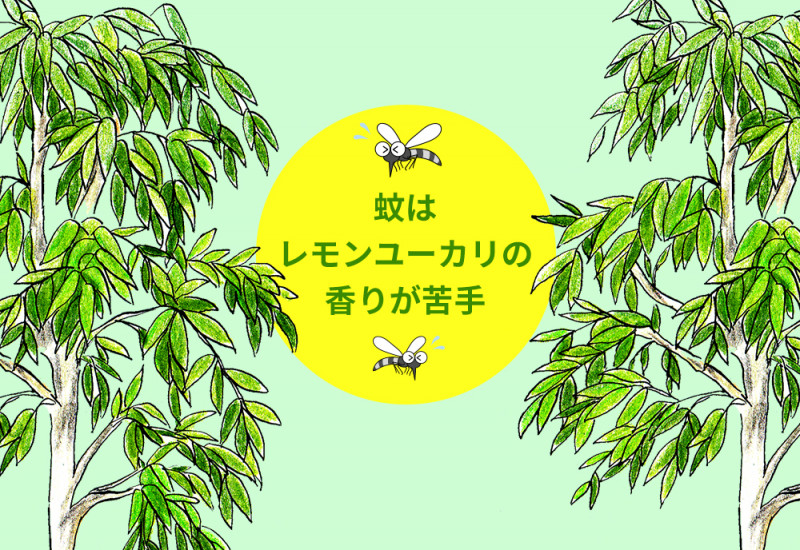
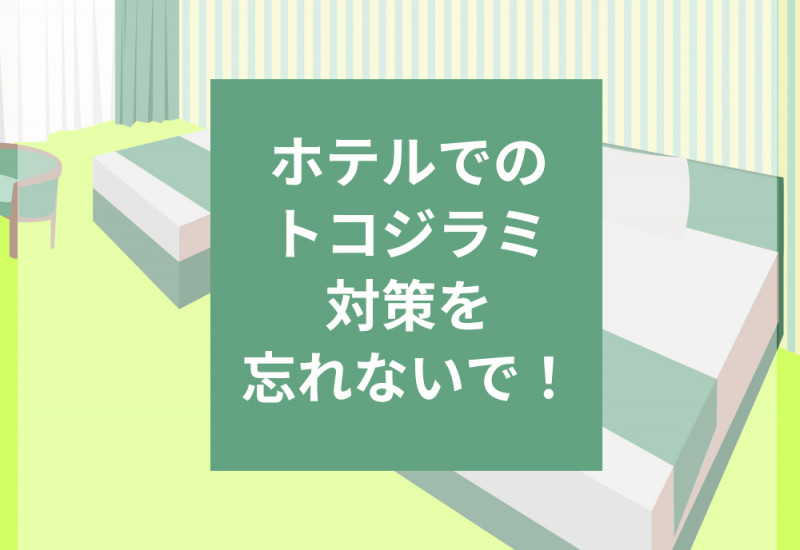



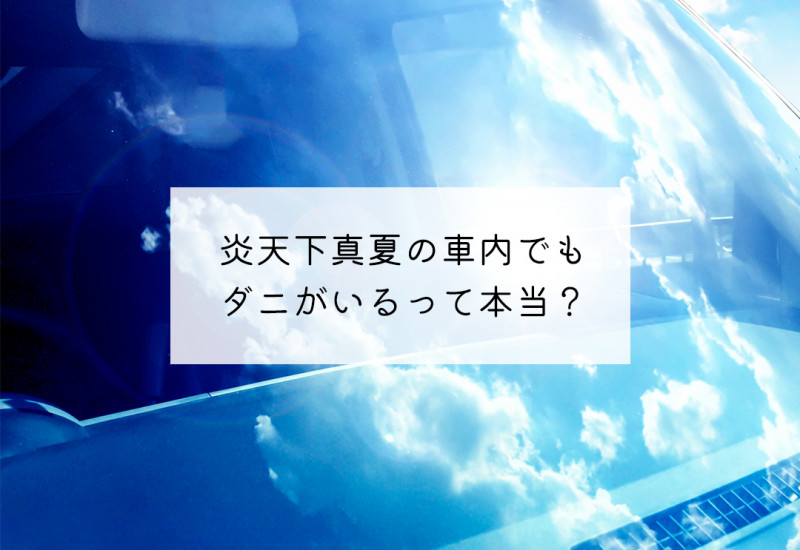
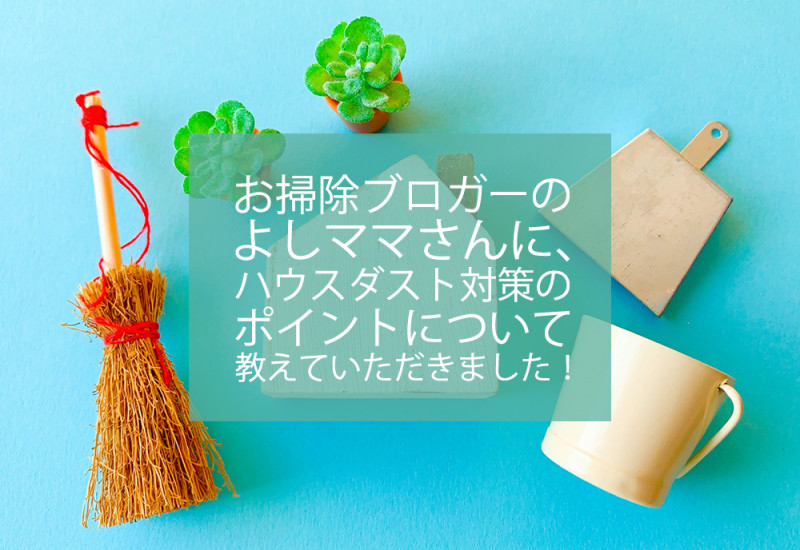
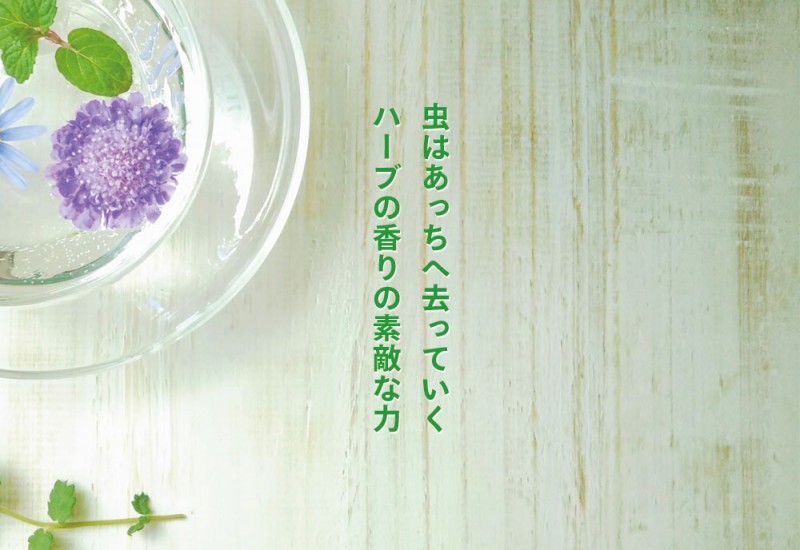
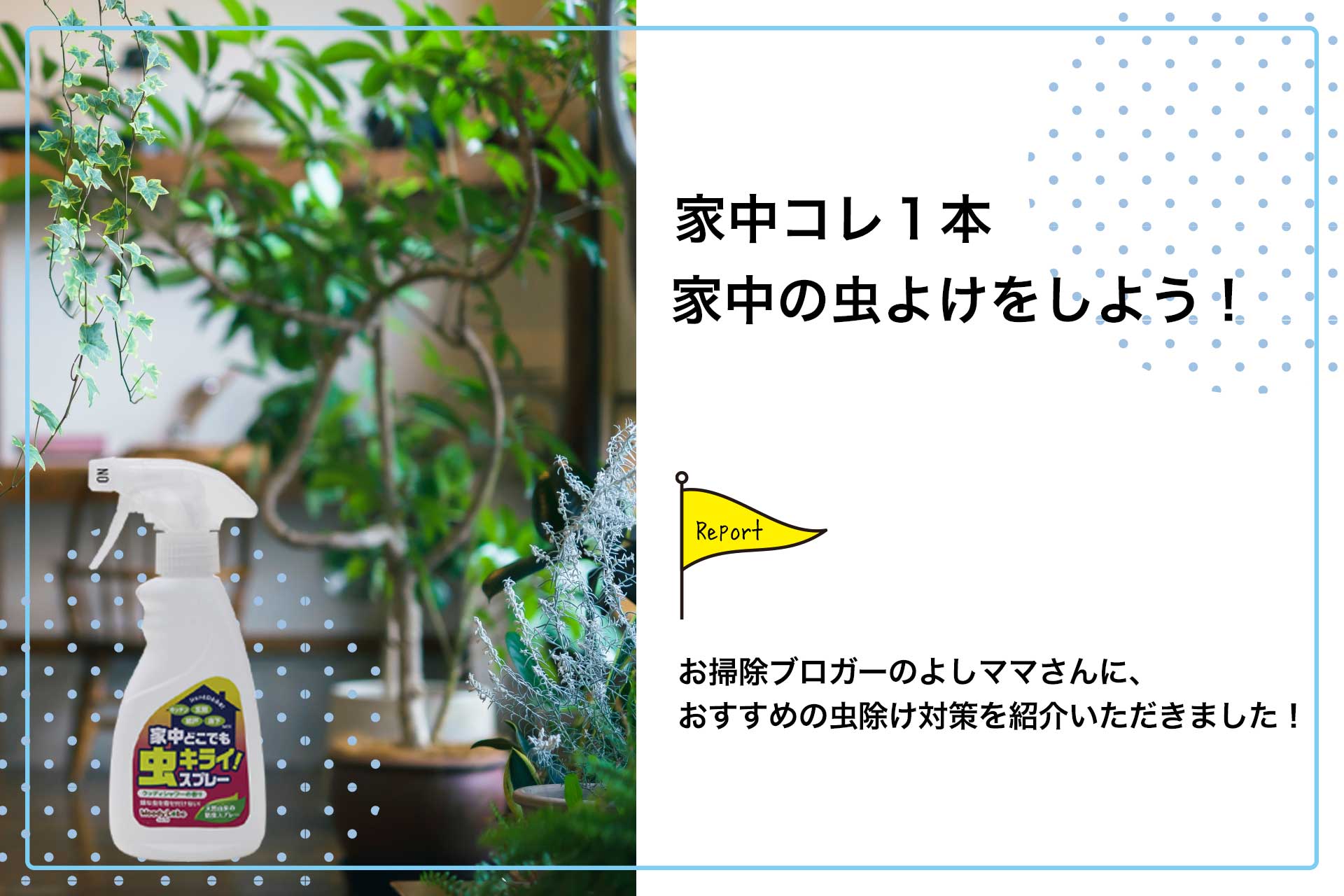
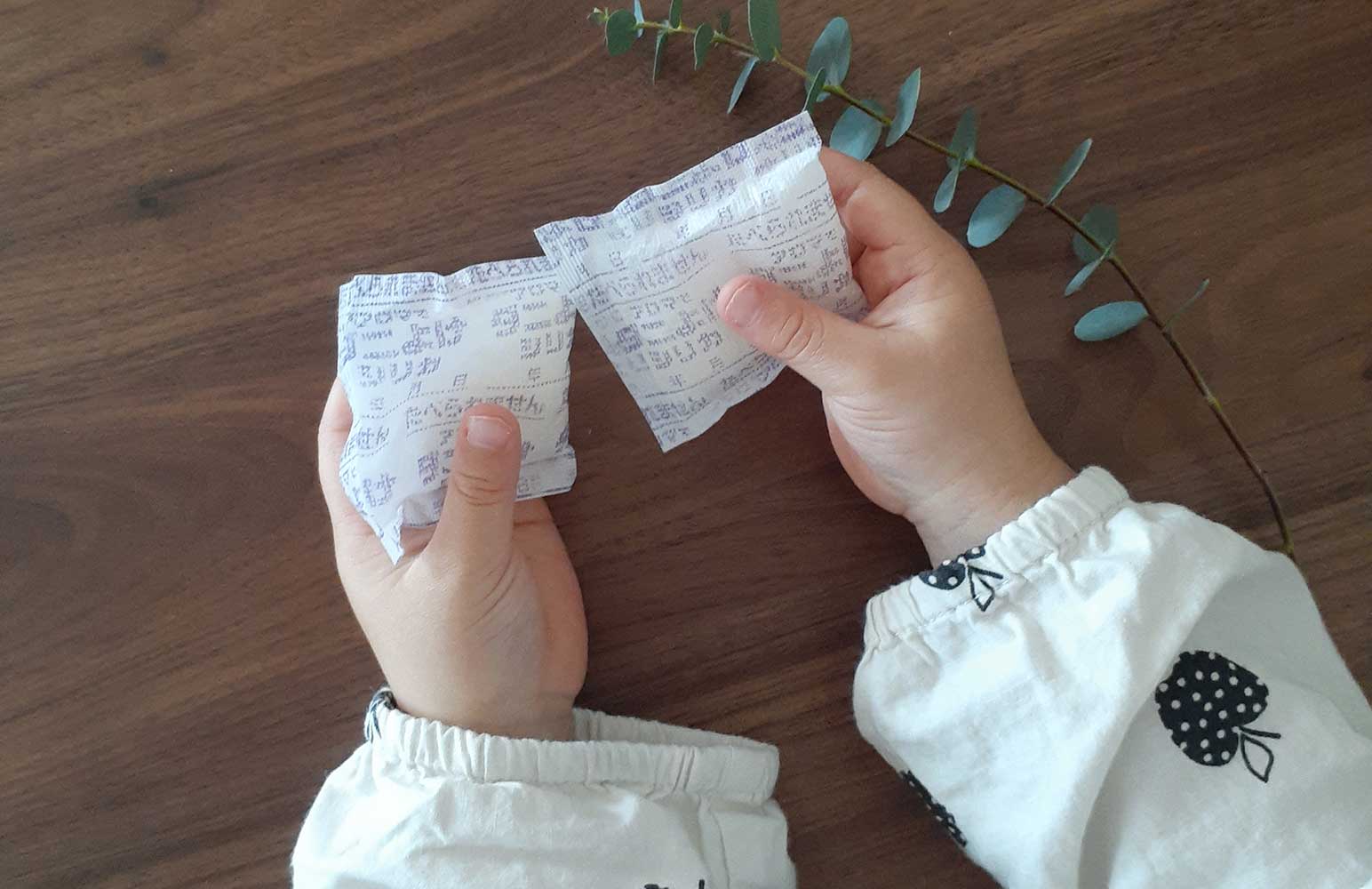

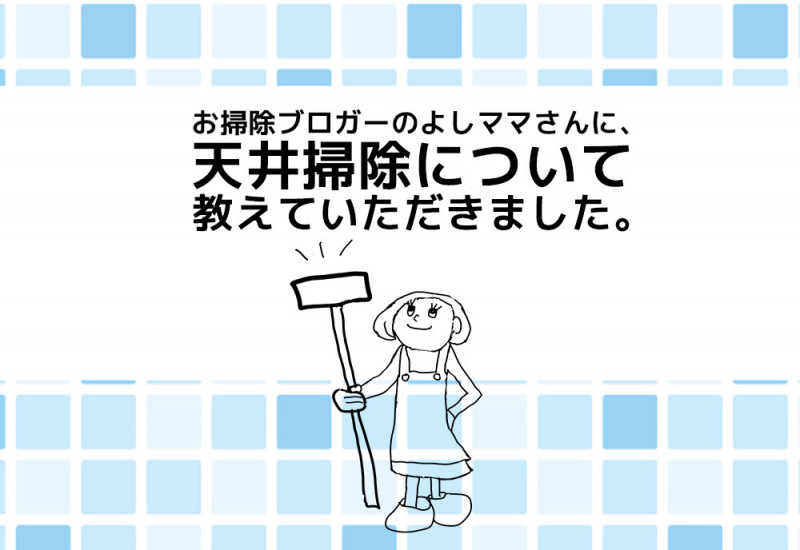
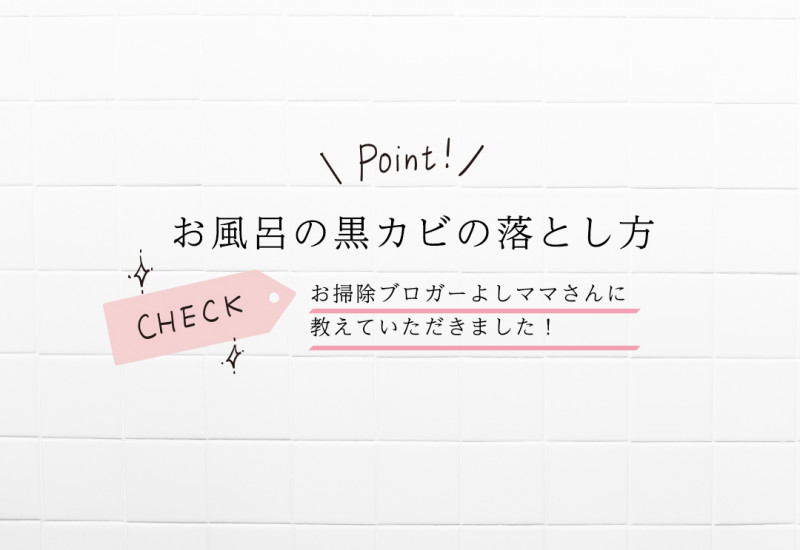


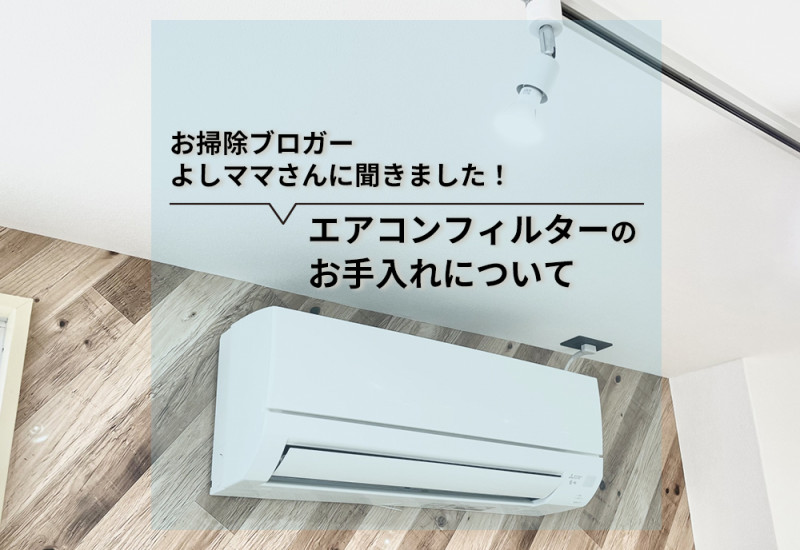
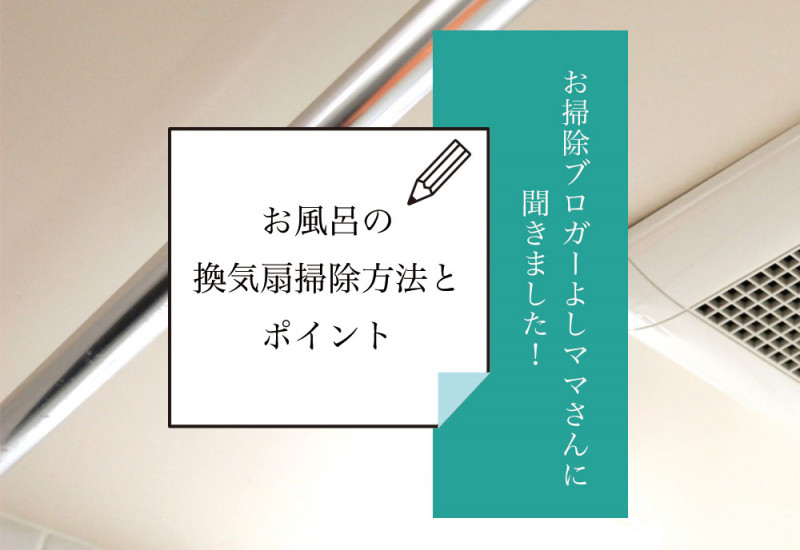
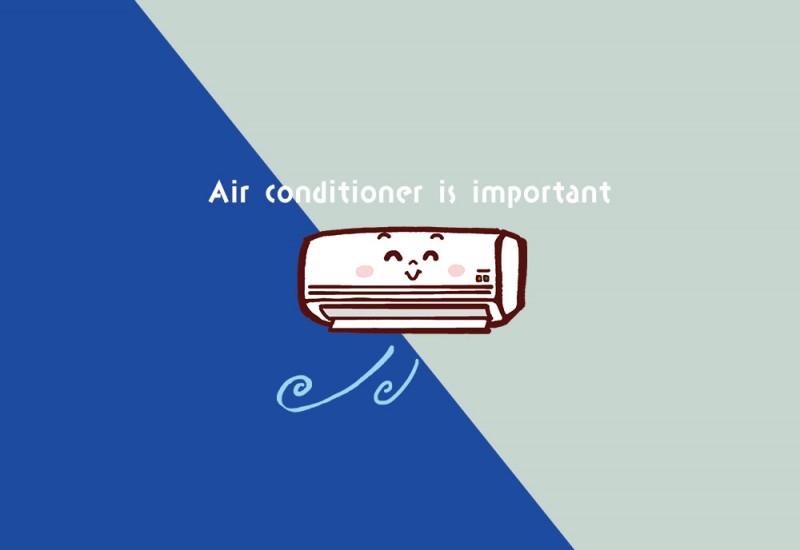

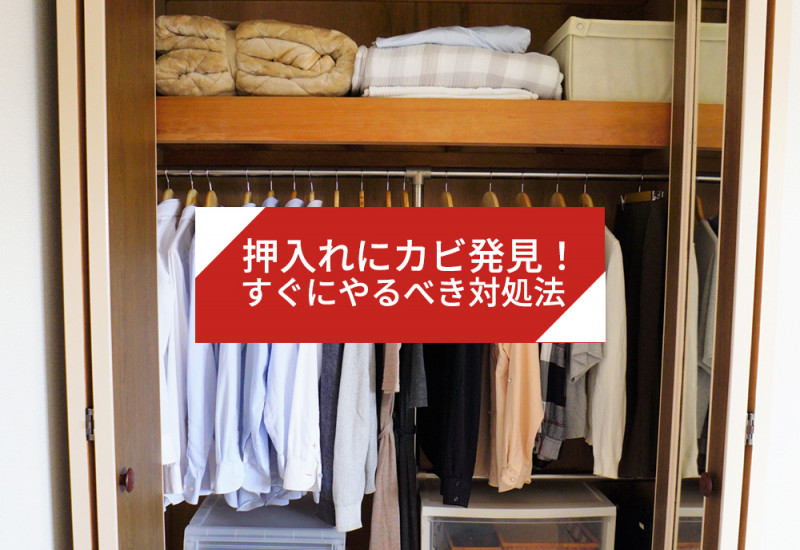



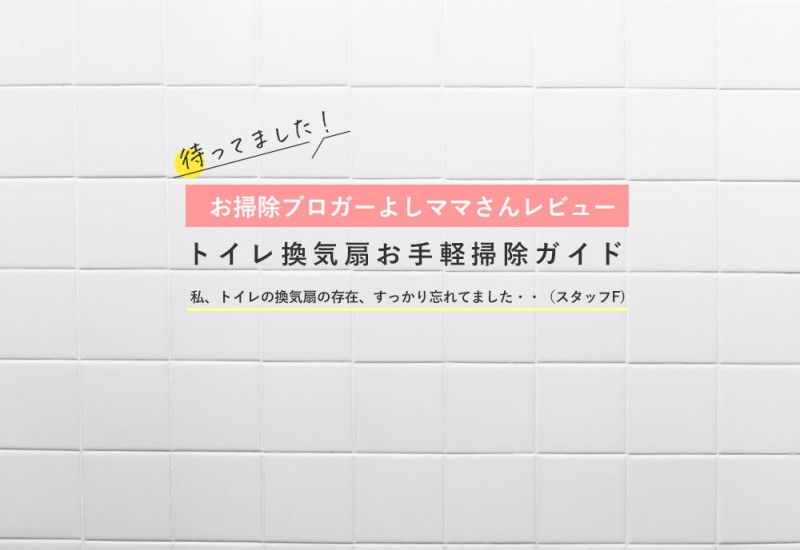
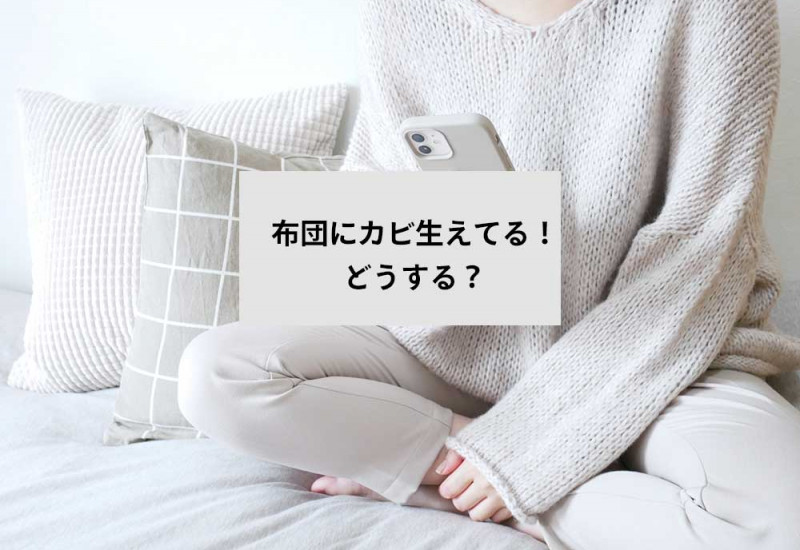
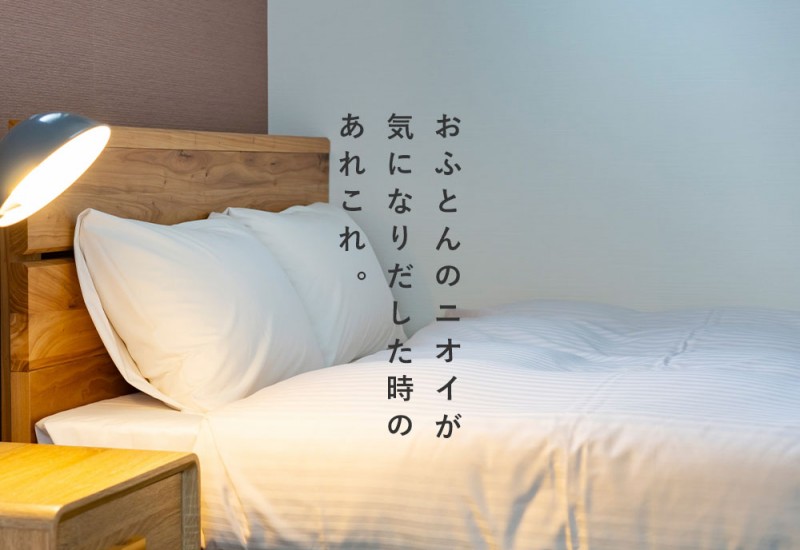
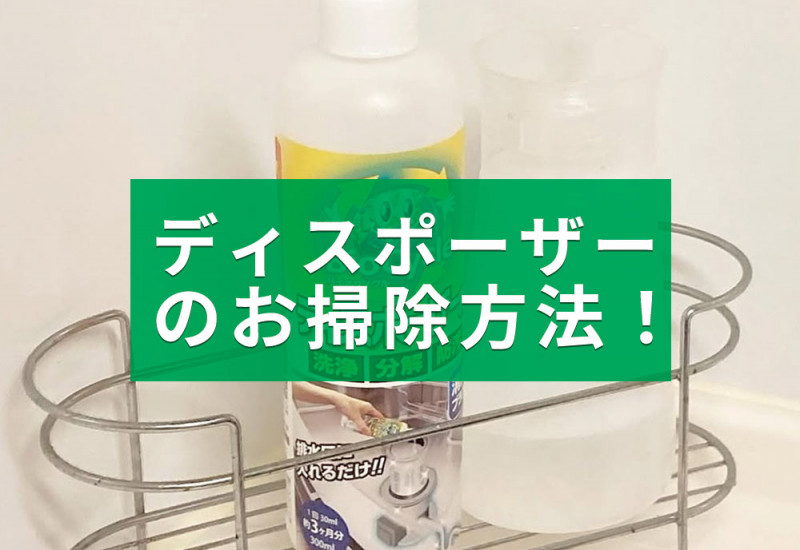



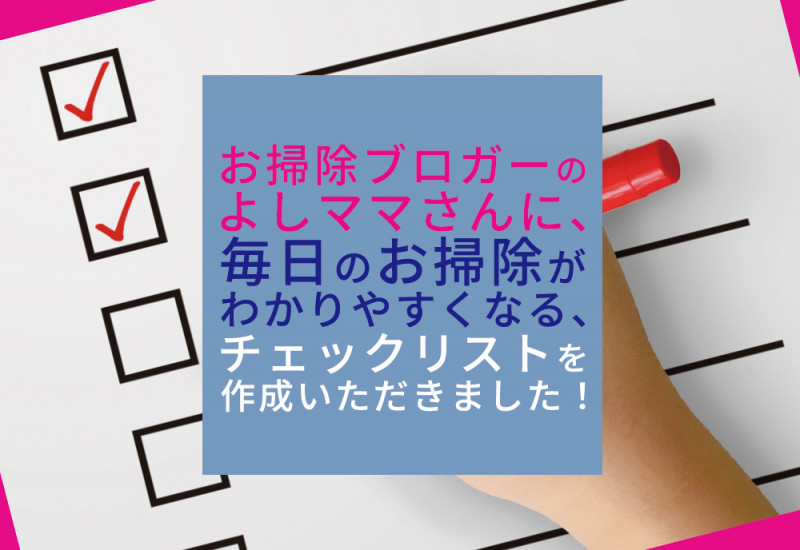
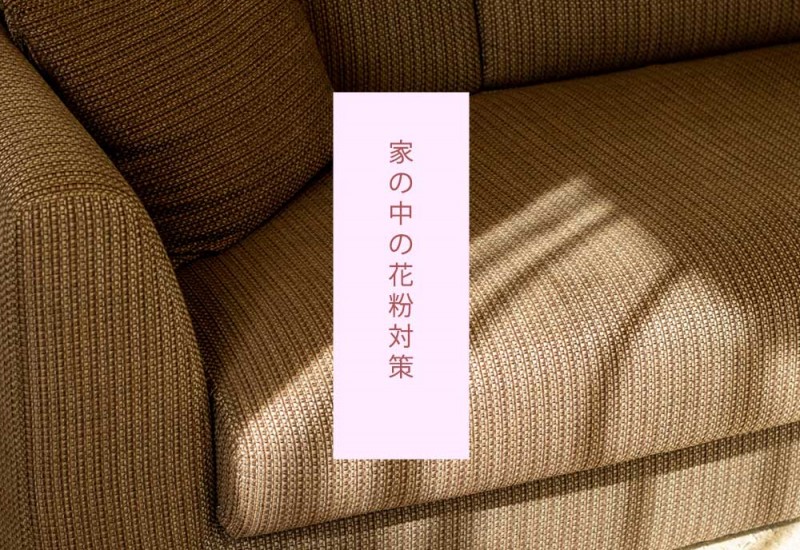

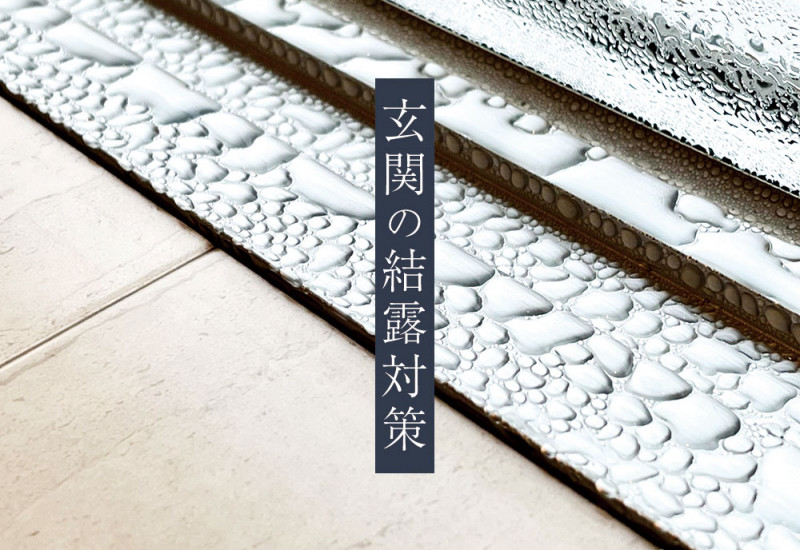

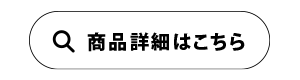







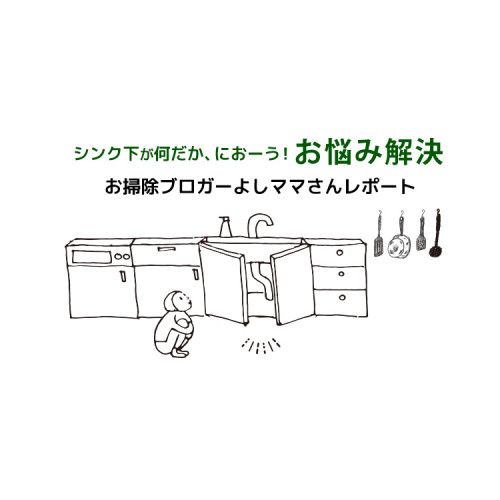


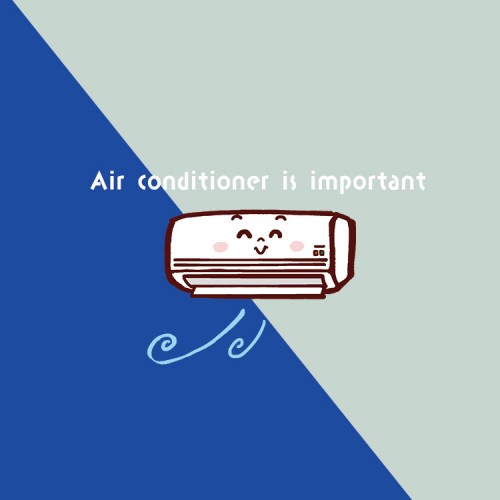
この記事へのコメントはありません。