室内のムカデ対策はどうすればいい?駆除から侵入対策まで詳しく解説
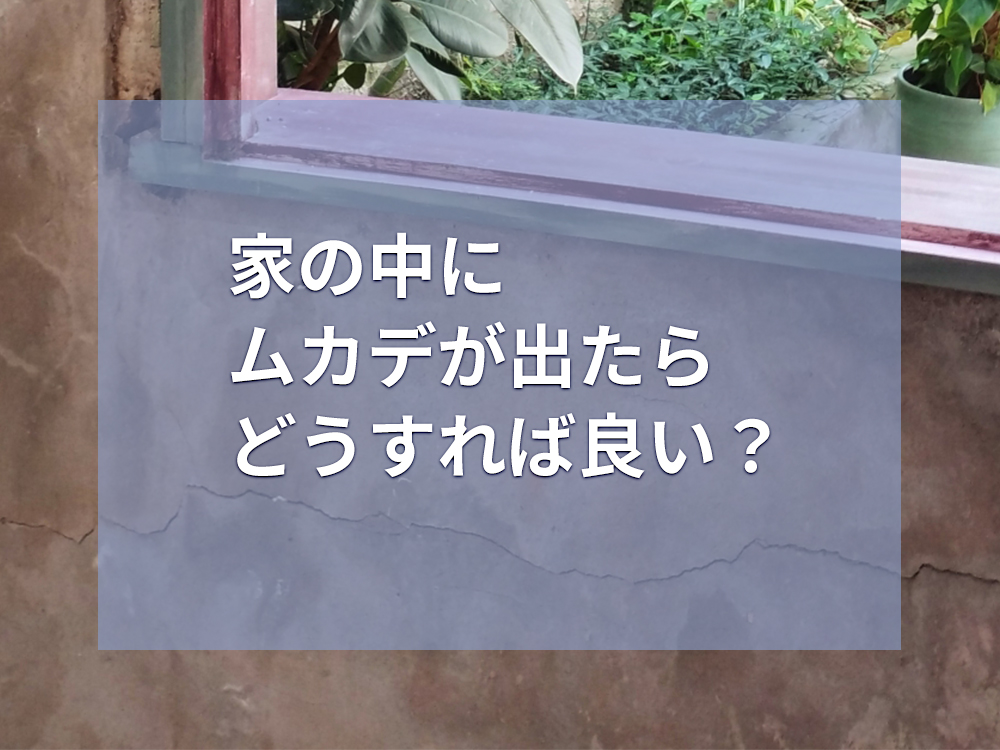
家の中にムカデが出たら、突然のことで「どうしたらいいの!?」とパニックになったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。毒を持つムカデは、刺されると強い痛みや腫れを引き起こすこともあり、特に小さなお子さんやペットがいる家庭では心配が尽きないものです。ムカデが室内に出た時の対処法から、そもそも家に入れないため侵入対策までわかりやすく解説します。
室内にムカデが出やすい時期

ムカデはある特定の時期に活発になり、そのタイミングで室内にも侵入しやすくなります。特にムカデが出やすい時期は5月から10月ごろまでの暖かい季節。春先は冬眠から目覚めたムカデがエサを探して活動を始めるため、住まいの中に入り込んでしまうのです。
7月から8月の真夏の時期は、猛暑の影響でムカデの動きも鈍くなるようです。ですが、この時期は、ムカデにとって子育てシーズン。オスのムカデが動き回るので、思わぬ場所で遭遇してしまうかもしれません。
さらに、9月から10月に入れば、親離れした子ムカデたちがそれぞれに行動を始めます。小さなムカデを見かけることが増えたら、要注意。ムカデが冬眠に入るまで、秋も油断できない第二のムカデシーズンと言えるかもしれません。
ムカデが最も増える時期は?
ムカデは、冬眠明けの春(5月~6月頃)と、子ムカデが活動を始める秋(9月から10月頃)に、特に増える傾向にあります。この時期は、湿度も高く、ムカデの活動に適した環境ということもあり、室内でも油断できません。夜行性のため、人が寝静まった夜間に、エサとなる昆虫を捕まえるために、室内に入り込んでしまうのです。ムカデは、ダニやゴキブリなどの小さな虫をエサとするため、「室内の害虫が増える時期=ムカデも出やすくなる時期」と言えるかもしれません。ムカデが室内に入り込まないようにするには、家の中の虫対策も大切です。
なぜムカデが室内に侵入するの?
ムカデは高温多湿な環境を好み、室内でも湿気の多い場所を好んで入り込みます。例えば、以下のようなケースではムカデが出やすくなるので要注意。
- 濡らした雑巾をそのまま放置している
- 段ボールを重ねて床に置きっぱなし
- 観葉植物の鉢の裏や、受け皿に水がたまりっぱなし
- 室内のすき間にホコリがたまっている
- お風呂場や脱衣所の湿気がこもりがち
また、ムカデのエサとなるダニやゴキブリ、クモなどの小さな虫がいる環境も、ムカデを招く原因に。細長いムカデは、小さなスキマからでもひっそり入ってきてしまいます。ムカデが室内に入り込まないための対策として、「湿気」「すき間」「エサ」をキーワードに住まいの環境を見直すことが大切です。
室内に出たムカデ対策~駆除方法

では、実際に、家の中でムカデを見かけたら、どんな対策をすればよいのでしょうか。駆除することを前提に、いくつかの方法を紹介します。
熱湯をかける
ムカデは熱に弱く、50~60℃のお湯をかけると動きが鈍くなります。さらに70℃以上の熱湯なら、即死するともいわれています。お湯をかけるだけなので、比較的安全で、簡単にできる方法です。ただし、フローリングや家具を傷めないように、使用する場所には注意しましょう。
殺虫スプレーをかける
熱湯がかけられない場所やすぐに用意できない場合に有効なのが、市販の殺虫スプレー剤です。ムカデに直接噴射しても一瞬で退治するのは難しいため、動かなくなるまで数秒~数十秒かけて噴射しましょう。安全な距離を保ちながら駆除できます。
ピンセットやトングで捕まえて処理する
家の中を汚さず退治したいなら、長めのピンセットやトングなどを使ってムカデを捕獲する方法もあります。捕まえたら、熱湯を入れたペットボトルやバケツにムカデを入れて退治してください。ムカデには毒があるので、直接触れるのはNG! また、ムカデはつかまると暴れて逃げようとするので、しっかり挟んで、嚙まれないように十分注意しましょう。
新聞紙やスリッパで叩く
突然現れるムカデへの対処法として、スリッパの裏や丸めた新聞紙などで叩くという方法もあります。ただし、ムカデは生命力が強く、一度で退治するのは難しいでしょう。できるだけ頭を狙って確実に叩くようにして、動かなくなったことを確認したうえで、ピンセットなどで処理してください。ムカデを叩きすぎると、強い臭いのある体液が出ます。放置せずに早めのお掃除を。
燻煙剤をたく
ムカデに逃げられた場合や、他にもいそうで不安、という場合には、室内用の燻煙剤(くんえんざい)を使うの効果的です。煙が家の隅々まで行き渡るため、ムカデだけではなく、ダニやゴキブリ、クモなどの害虫をまるごと駆除できます。ただし、使用時には家電製品や食品、植物などにカバーをかけるなど、事前の準備が肝心です。使用時には、ペットも含めて屋外に避難してください。煙の噴出が終わっても、2時間程度締めきった状態で放置し、その後お掃除をする必要があるため、時間に余裕がある日に行うのがおすすめです。
ムカデが室内に侵入するのを防ぐためには

できれば「ムカデが出てくる前に防ぎたい!」というのが本音ではないでしょうか。そのためには、ムカデが寄りつかない環境づくりがとても大切です。ムカデを家の中に入れないための方法を紹介します。
家の周囲を掃除し、粉剤をまく
まず、ムカデが住み着きにくい環境にすることが基本。落ち葉や石、古い木材などは、ムカデの住み家になりやすい場所をきれいに片付けましょう。その後、家の周囲を一周するようにムカデを寄せ付けない粉剤をまくのがおすすめです。
侵入経路をしっかりふさぐ
ムカデは、小さなスキマからでも入り込んできます。窓や玄関のドアの隙間、ベランダ、エアコンのドレンホースなどの隙間をチェック。隙間テープやコーキング剤を使って隙間をしっかりふさぐことが大切です。夜のうちに室内に入り込んだムカデが、日中は暗く湿っぽい場所として、靴の中や布団の中に潜り込むことがあります。下駄箱や押し入れの中も、チェックしておくと良いでしょう。
ムカデが嫌う「香り」を活用する
ムカデは強い香りを嫌う習性があります。その習性を活かして、ハッカ油スプレーを使用するのも良いでしょう。ハッカ油は、薬局やドラッグストアなどで手軽に購入でき、スプレーの作り方も簡単です。
【ハッカ油スプレーの作り方】

<用意するもの>
・ハッカ油、無水エタノール、精製水(すべてドラックストアで購入できます)
・空のスプレーボトル(100円均一ショップで購入できます)
<作り方>
- 無水エタノール10mlをスプレーボトルに入れる
- ハッカ油を20滴程度、加える
- 精製水90mlを加える
- 全てが混ざり合うようによく振る(※使用前にも軽く振って使用します)
完成したスプレーは、1週間以内に使い切るのが目安です。玄関や窓枠、キッチンの排水溝などムカデが侵入しやすい場所に、こまめに吹きかけましょう。
※注意点※ ペットを飼っている家庭は使用を控えてください。特に、猫はハッカ油の成分を肝臓で代謝できないため、中毒症状を引き起こす危険性があります。
市販の虫除けスプレーを使用する
「粉剤や燻煙剤などの薬剤を使用したくない」、「ハッカ油スプレーを手作りするのが面倒」という場合には、天然由来の成分を使った市販の虫よけスプレーがおすすめです。

ウッディラボの「家中どこでも虫キライスプレー」は、侵入経路にスプレーすることで、ムカデのエサになる小さな虫をブロック。ムカデはもちろん、室内に入り込む害虫全体を減らしてくれますよ。
ムカデのエサとなる虫の発生を減らす
ムカデを室内に入れないために、エサとなる虫を増やさない対策も効果的です。ムカデが好むのはゴキブリやクモ、ダニなどの害虫です。特に目に見えにくいダニ対策には、ウッディラボの「ダニよけシリカ」がおすすめです。気になるスキマに、置くだけ簡単。殺虫剤や忌避剤などの薬剤は不使用。天然由来成分の香りでダニを寄せ付けません。ベビーフローラルのやさしいアロマで、ムカデの好物となるダニを予防できますよ。
もしもムカデにかまれてしまったら?
万が一、ムカデにかまれたときは、すぐに患部を流水にあて、洗い流しましょう。その後、放置せずに、必ず医療機関を受診してください。ムカデにかまれると、強い痛みや腫れやかゆみ、またはしびれなどの症状が出る場合があります。一時的な対処法として市販のステロイド剤などを使う方法もありますが、自己判断はお勧めできません。どうしても市販の薬を使用する場合には、店舗の薬剤師に症状を説明して、適切なものを提案してもらいましょう。
室内のムカデ対策は、「出たときの対処」と「入れない工夫」が大事
家の中にムカデが出ると、かまれるのではないかと不安になりますよね。特に小さいお子さんがいる家庭では、しっかり予防したいものです。ムカデが増える時期や好む環境などを知り、対策をはじめてみませんか。ムカデが出る前に予防策も取り入れながら快適に過ごしましょう。
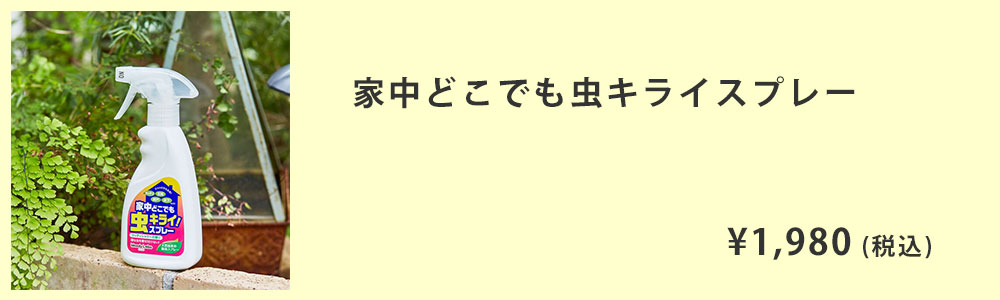
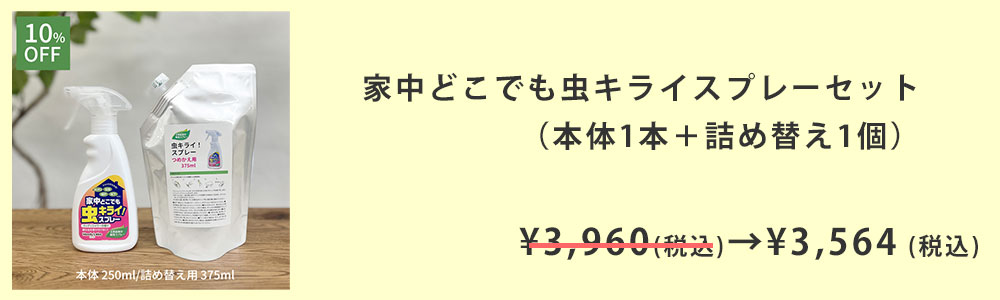
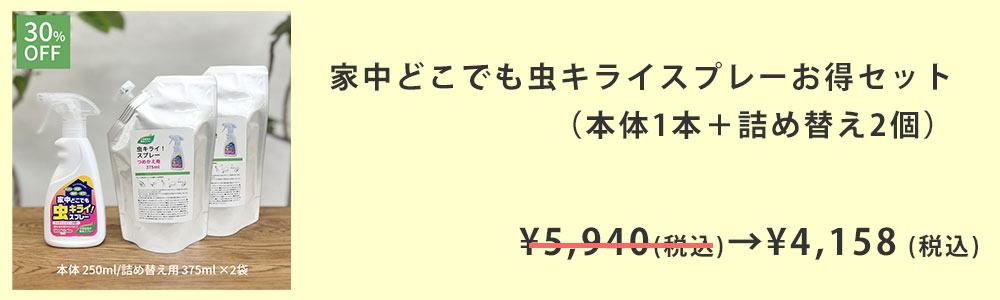

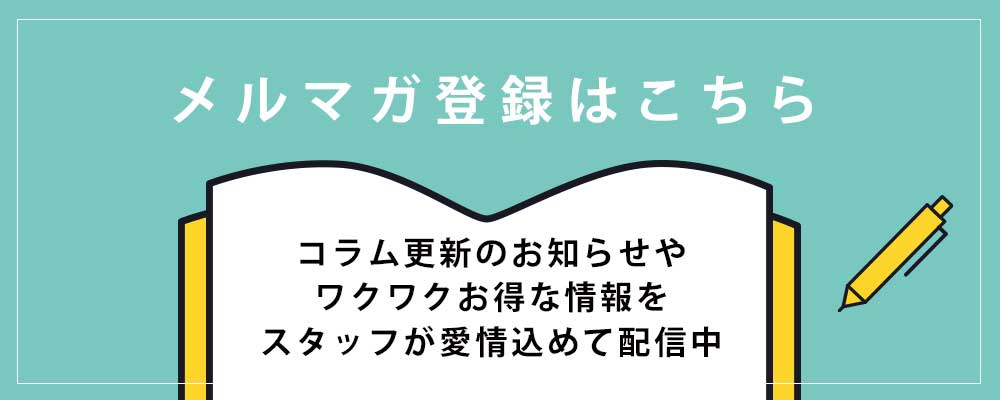
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
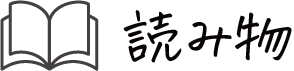
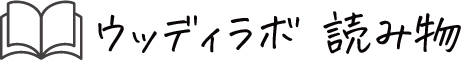


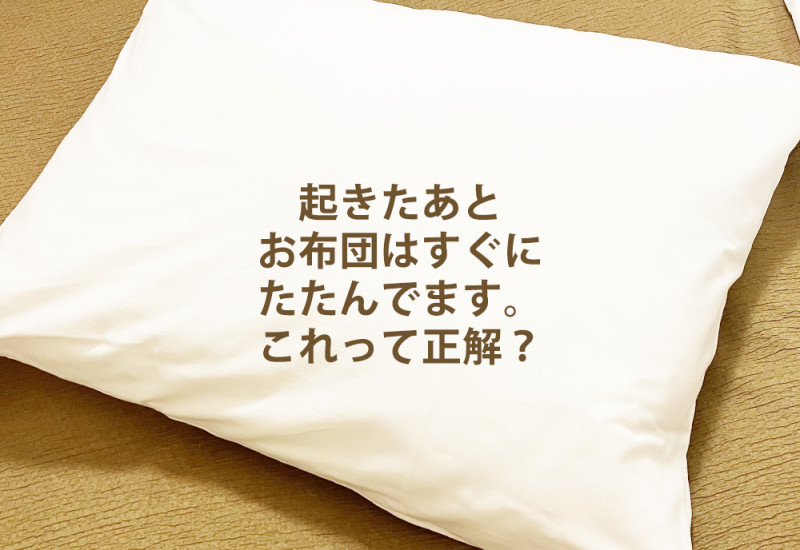
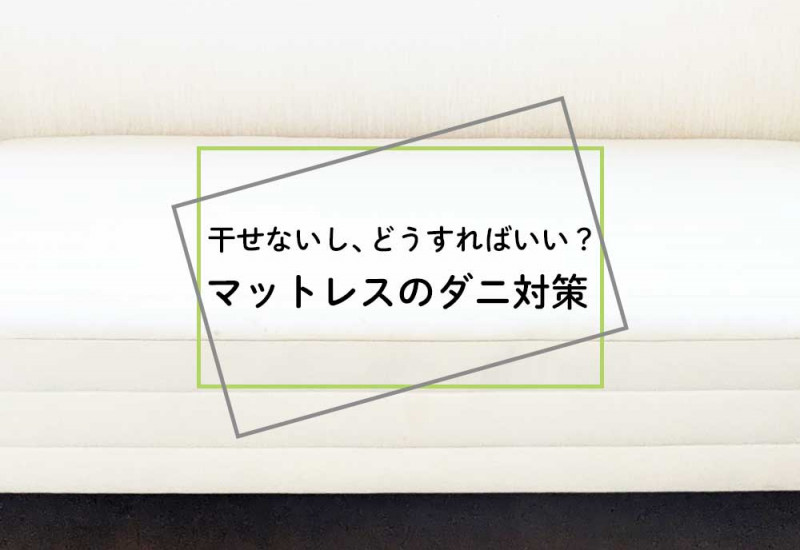
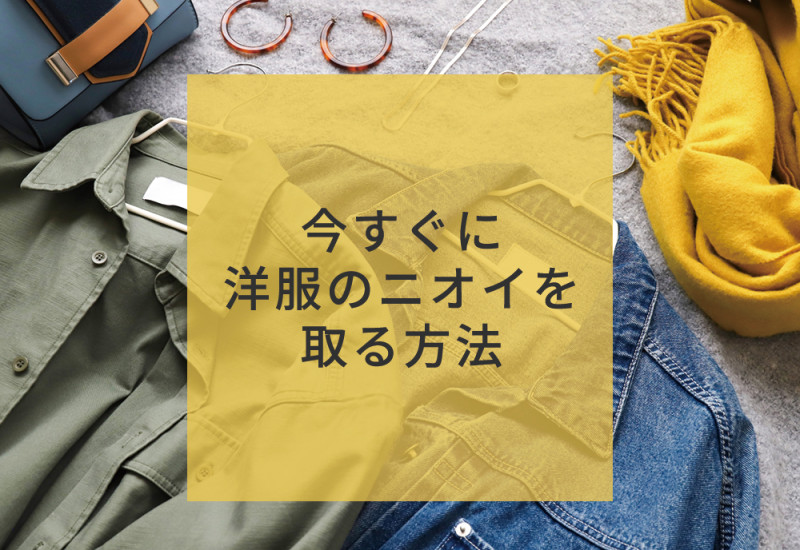
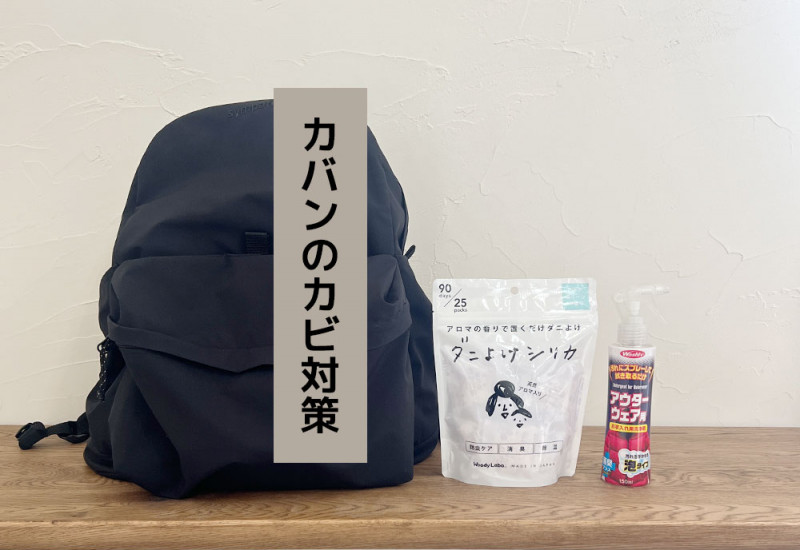


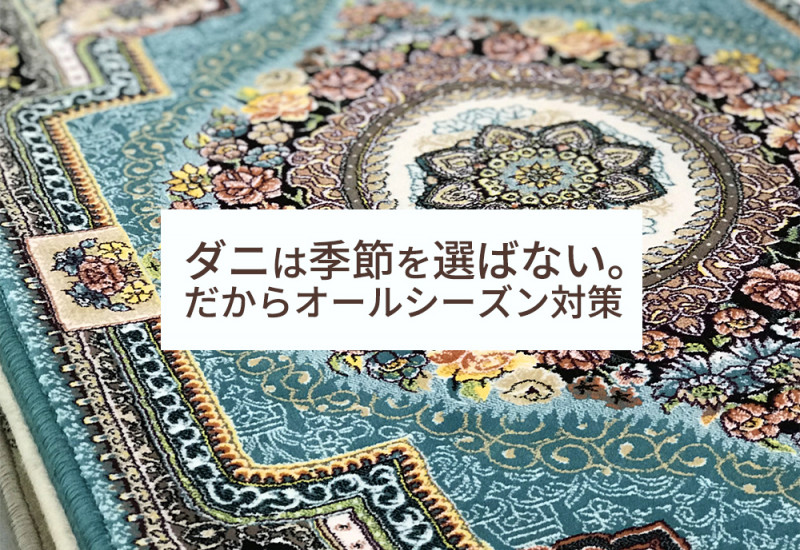


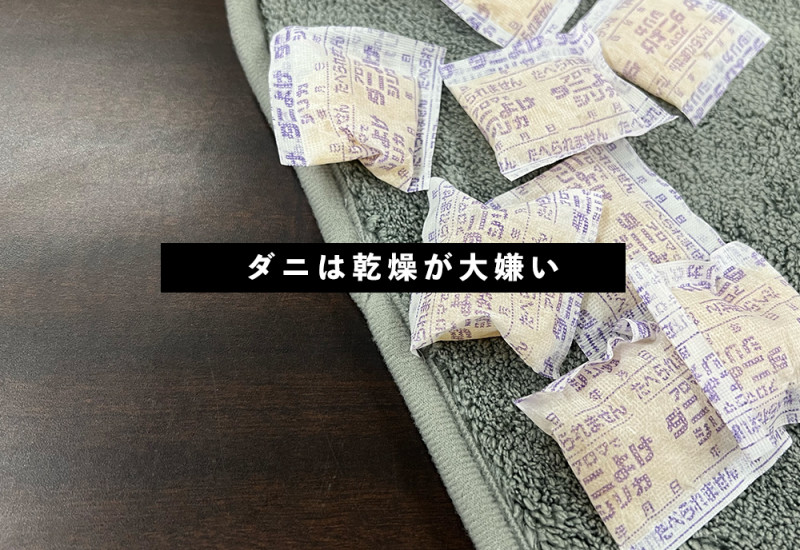


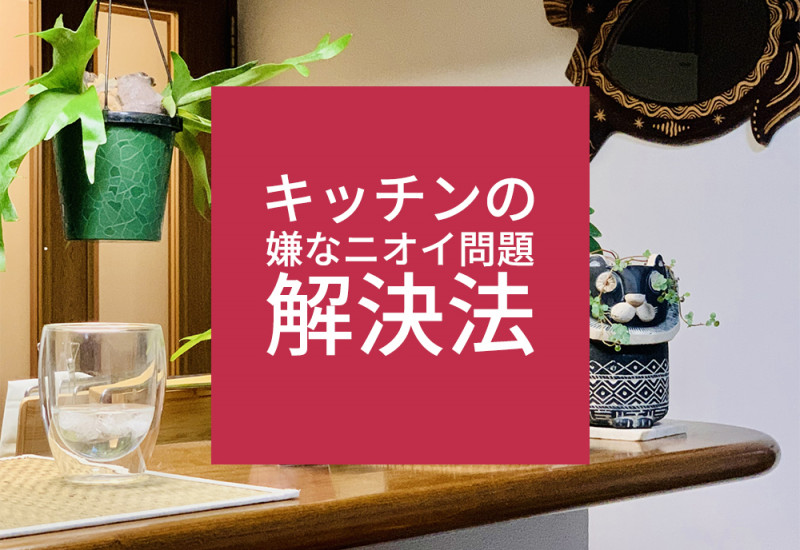
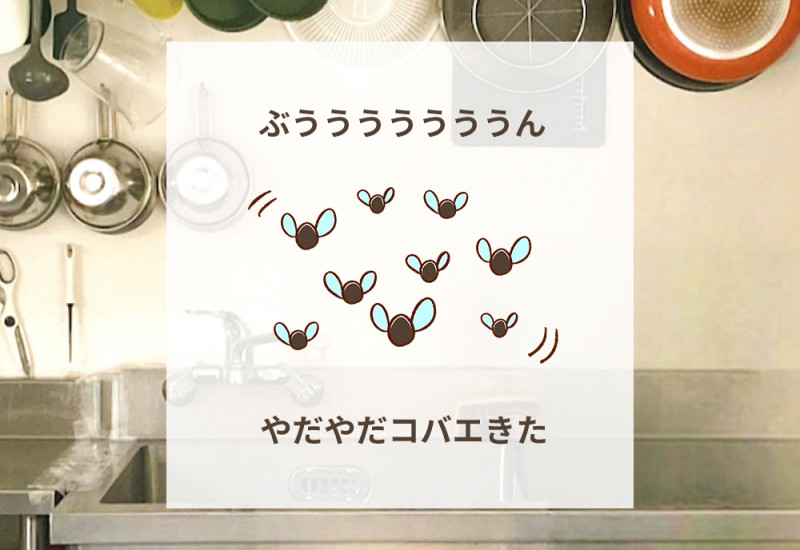

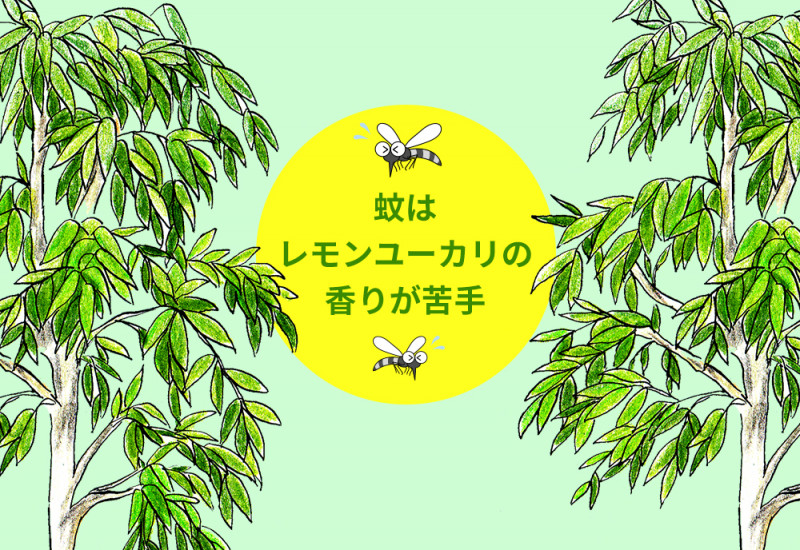
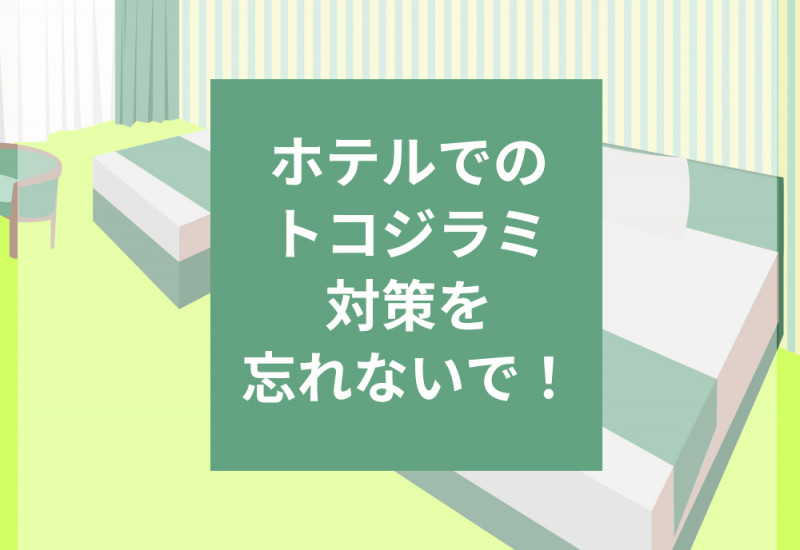



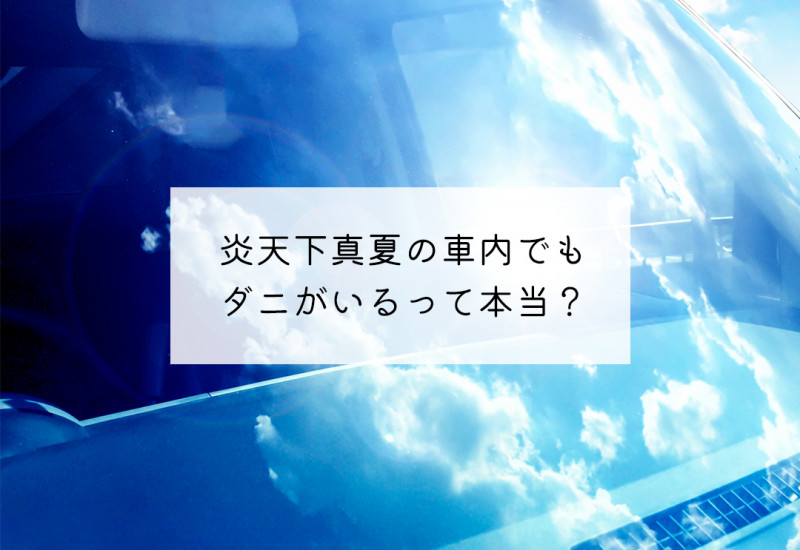
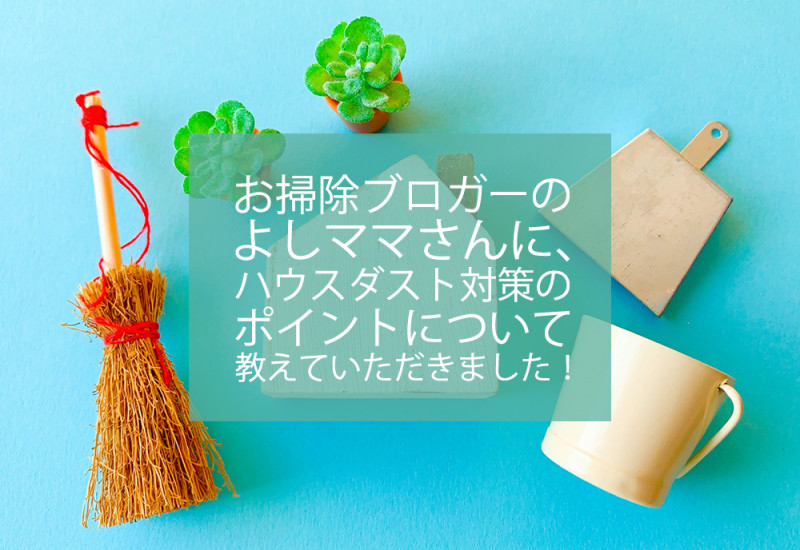
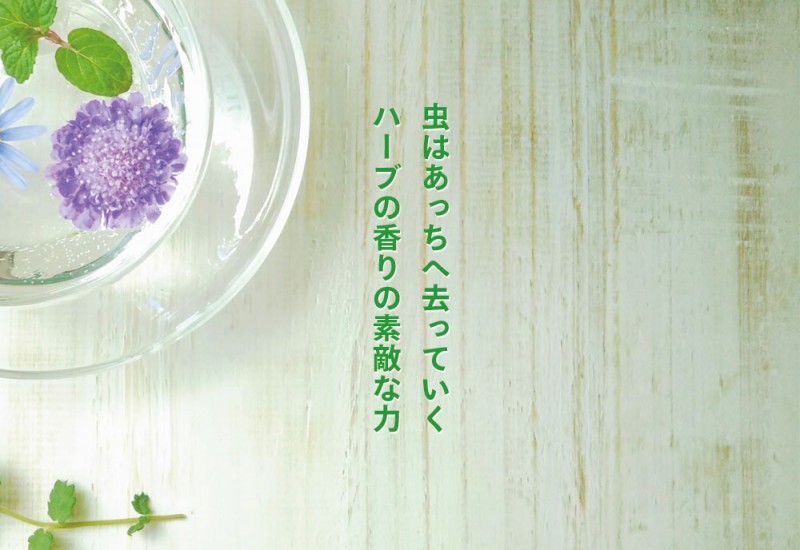
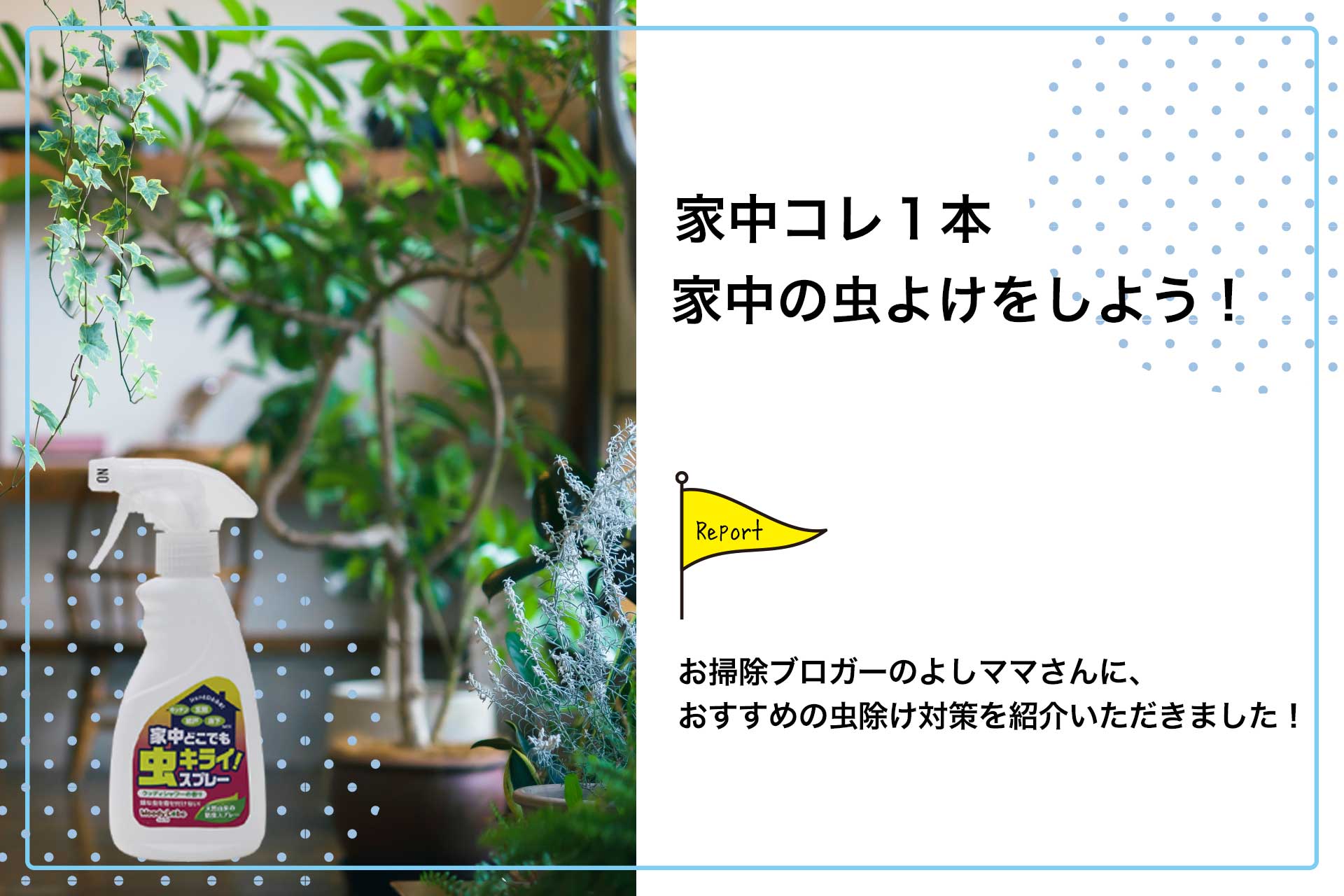
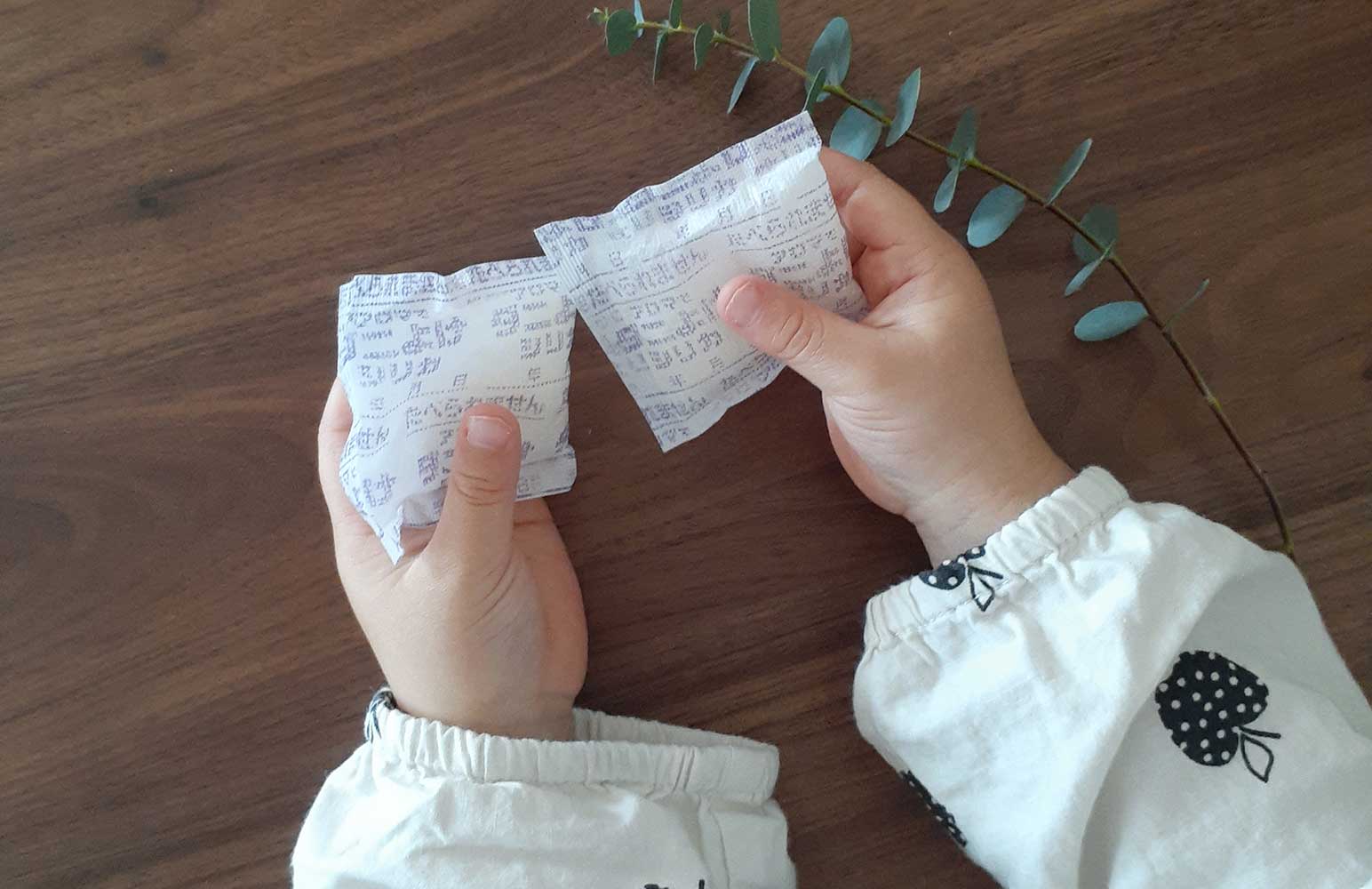

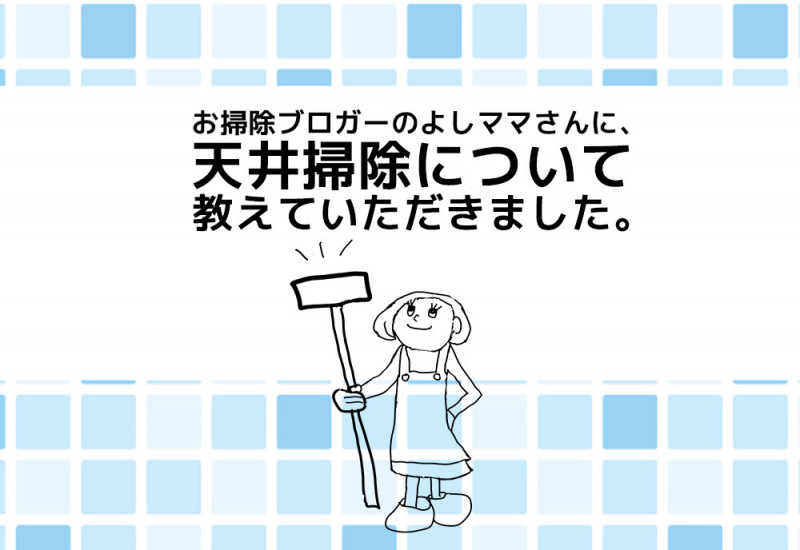
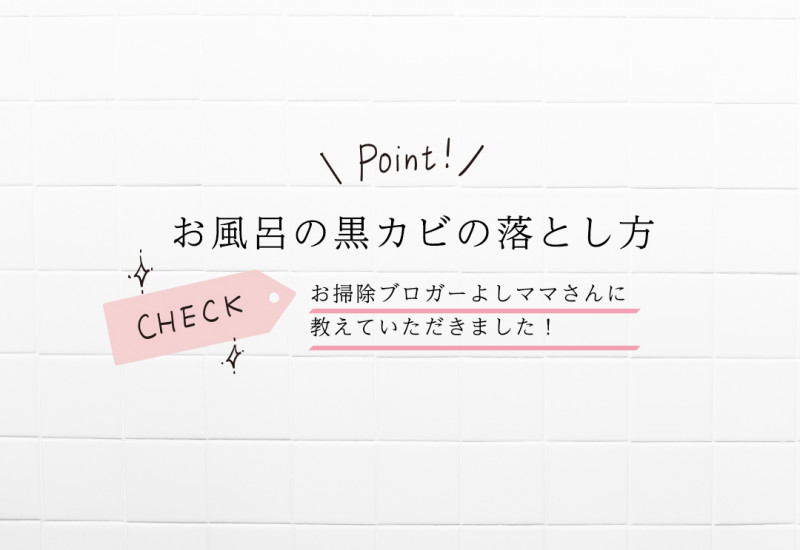



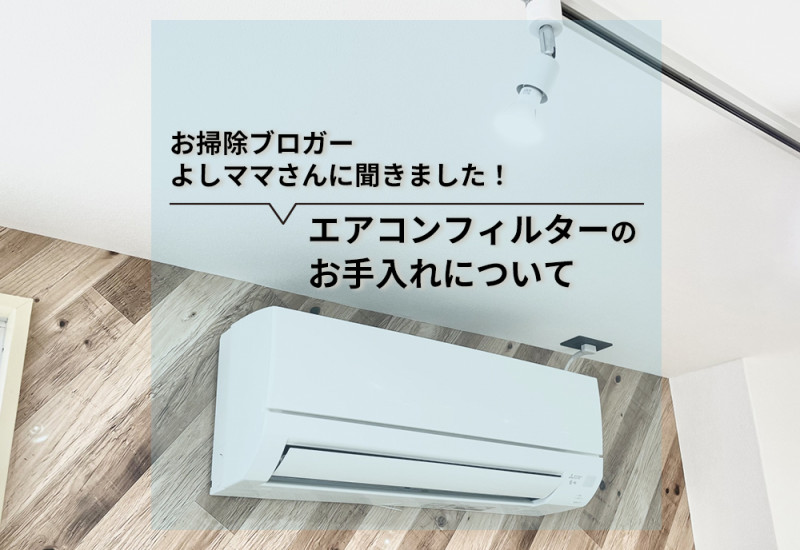
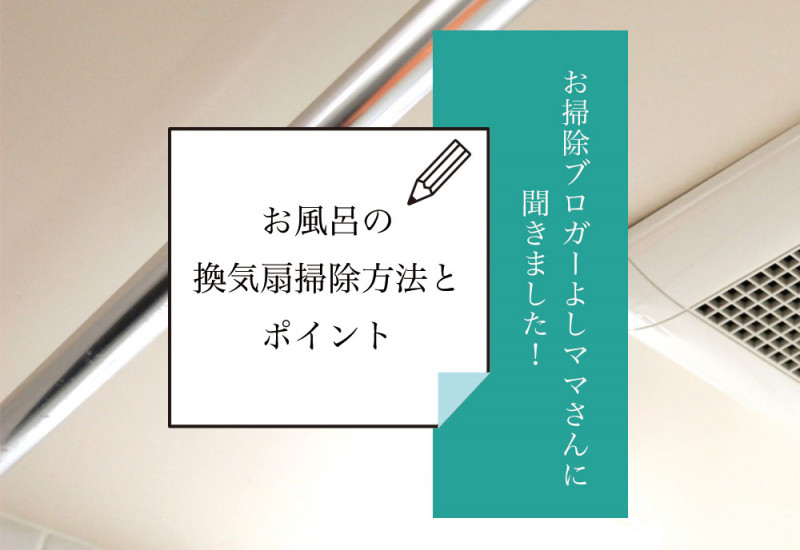

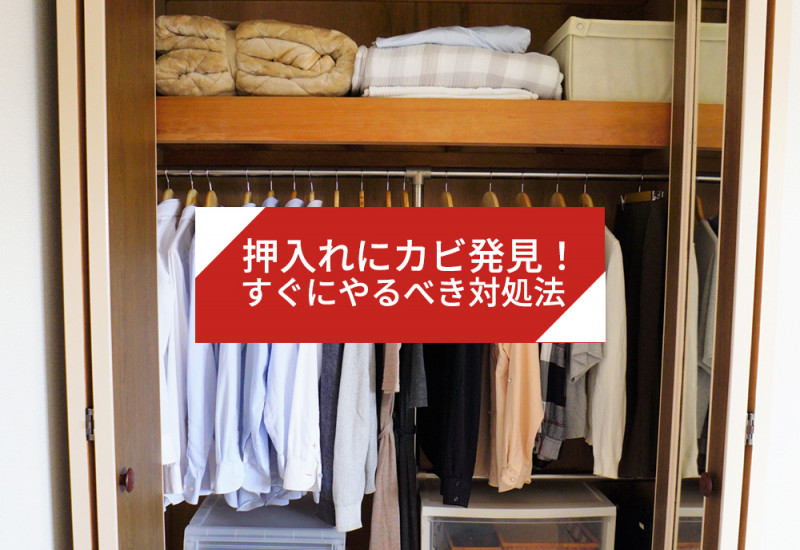



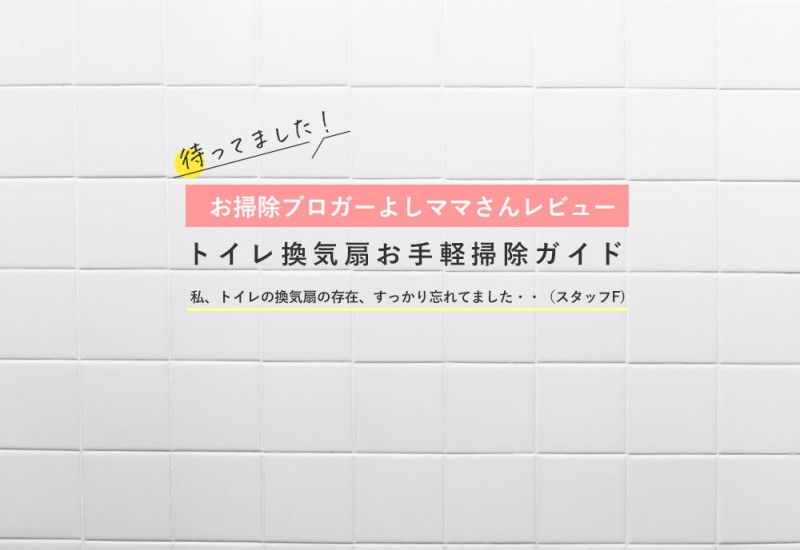
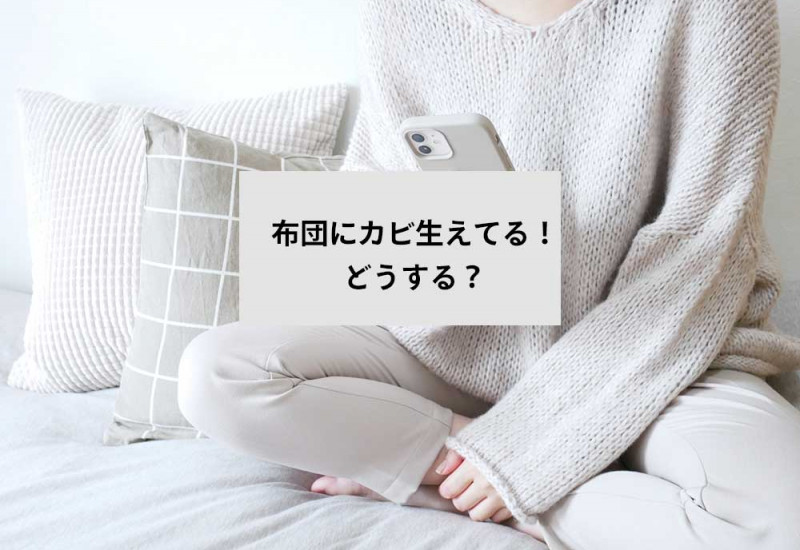
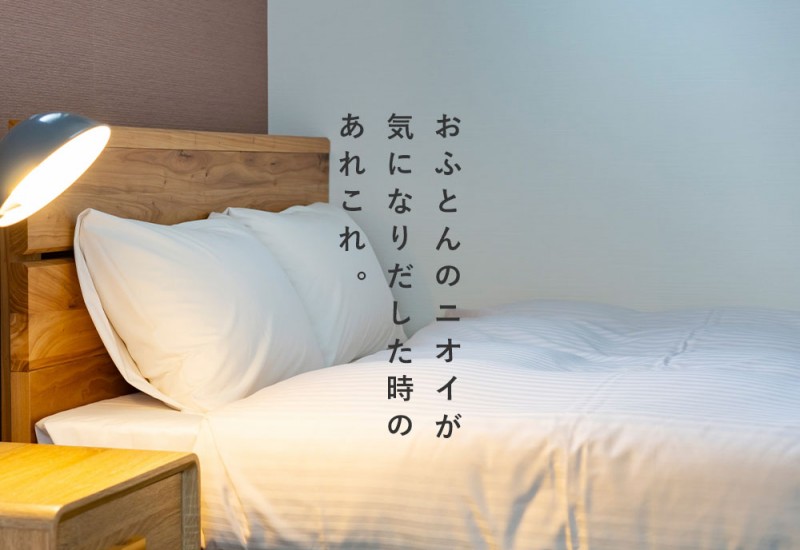
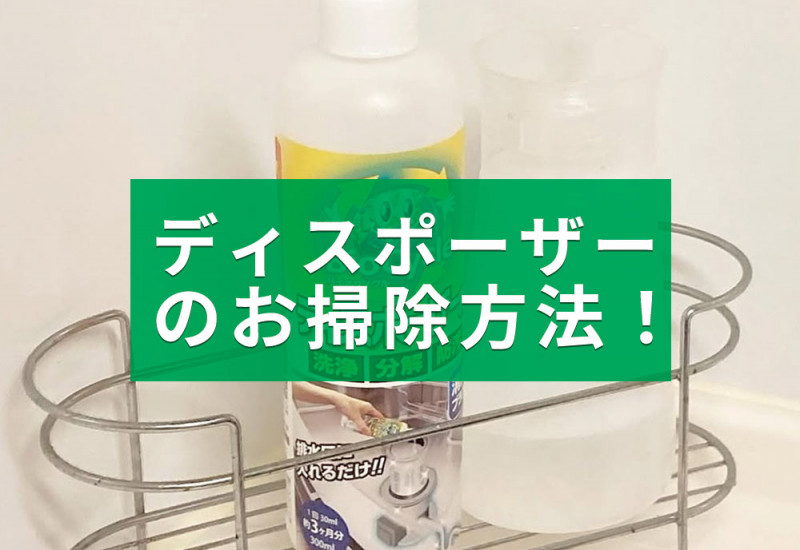

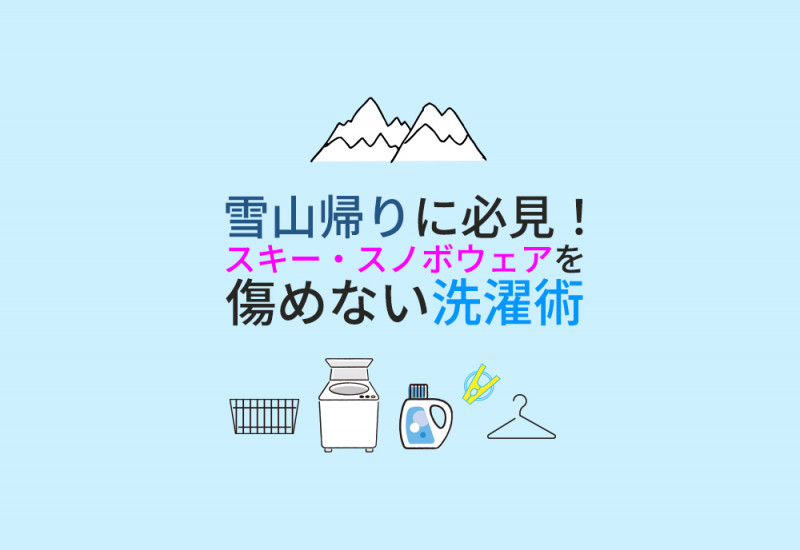
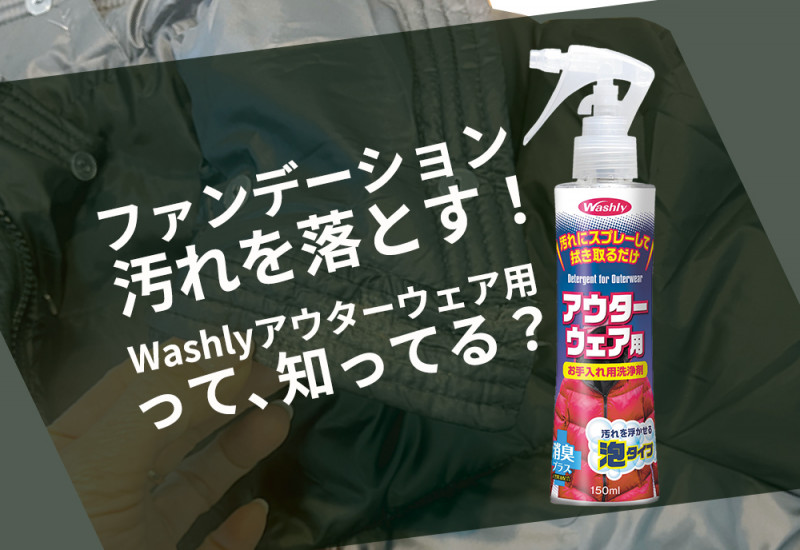


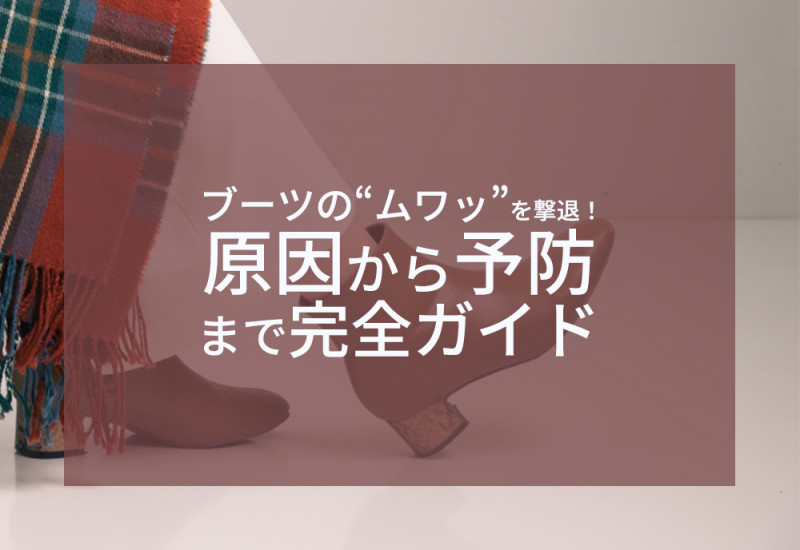
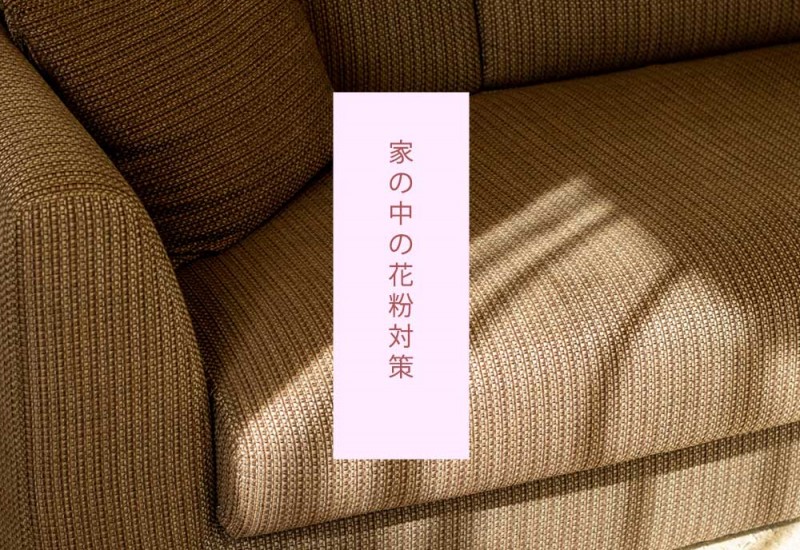

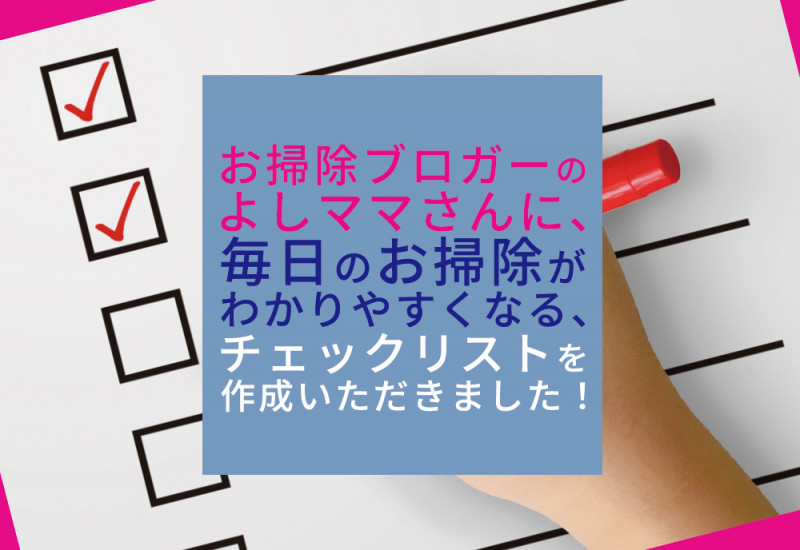

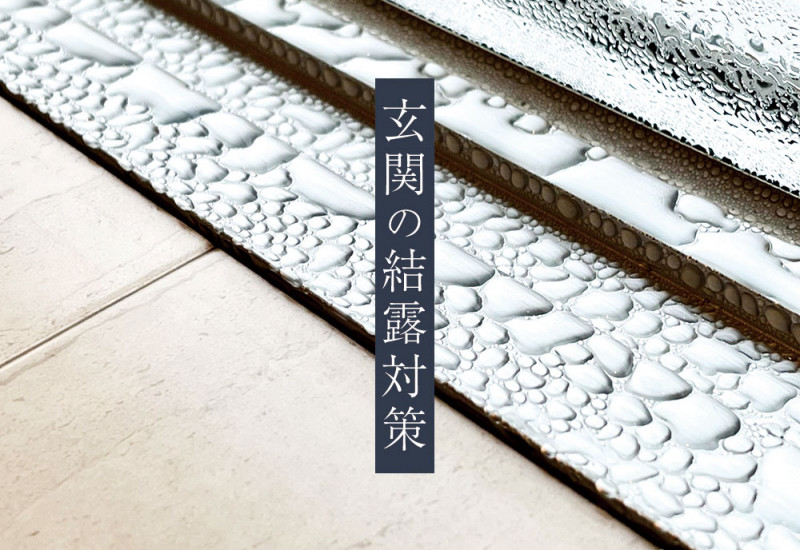

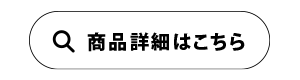



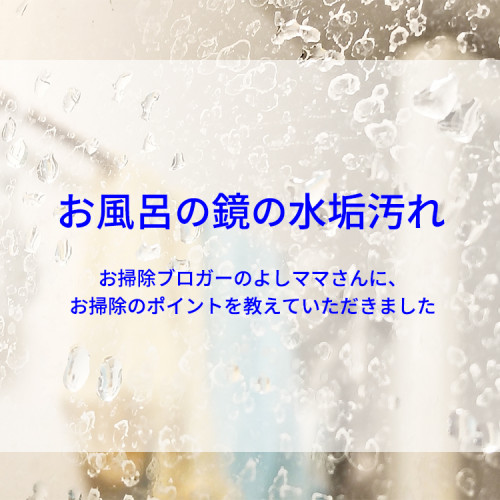




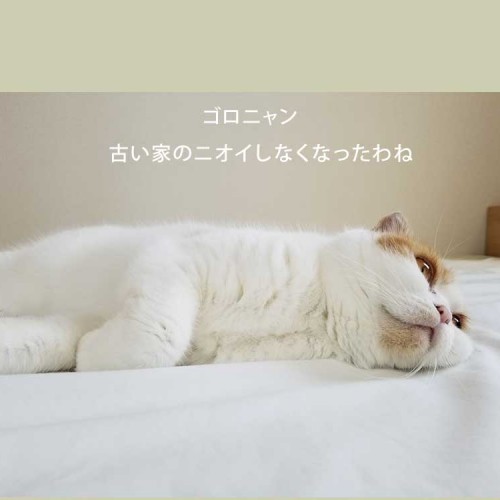


この記事へのコメントはありません。