土用の丑の日にうなぎを食べるのはなぜ?〜意味や由来、2025年の夏土用・丑の日〜
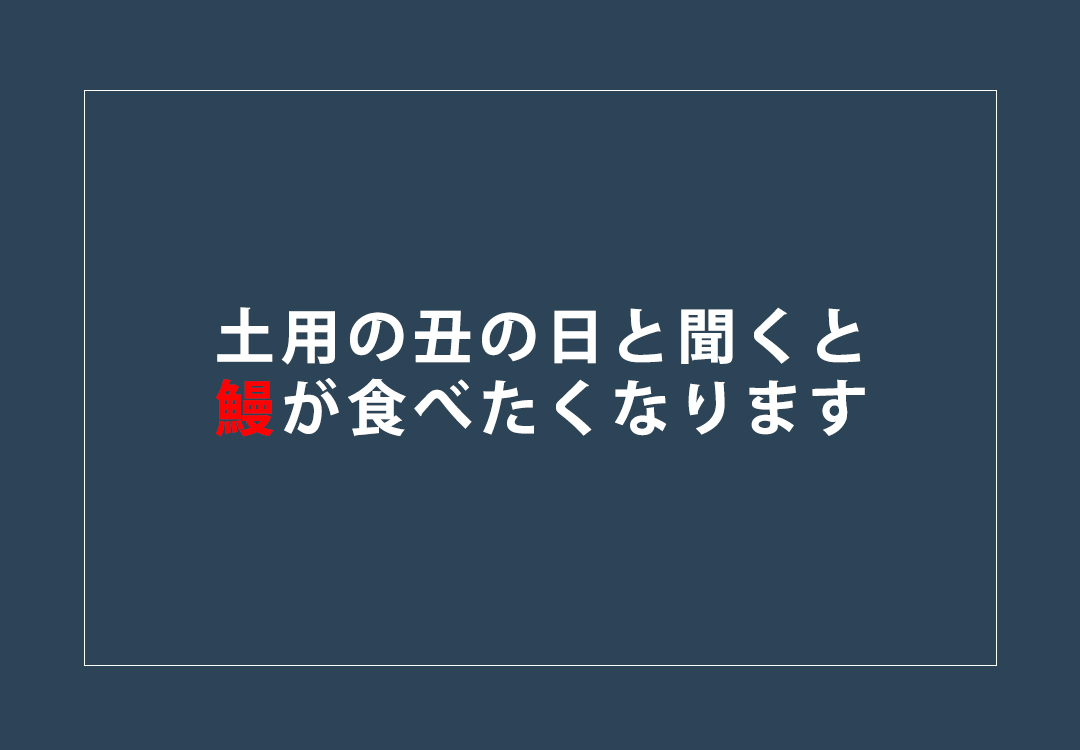
夏場に元気を与えてくれる「うなぎ」。最近では、外国人観光客からの人気も高まっているといいます。そんなうなぎが、ひときわ脚光を浴びるのが「土用の丑の日」です。土用の丑の日といえば、うなぎの蒲焼きがパッと思い浮かぶほど、うなぎを食べる風習が根づいています。
しかし、なぜ、土用の丑の日には、うなぎを食べるのでしょうか。そもそも、土用ってどんな日なのでしょうか?じつは、思っている以上に奥が深い土用。今回は、土用についてご紹介します。
春夏秋冬、季節の変わり目にあたる時期が「土用」
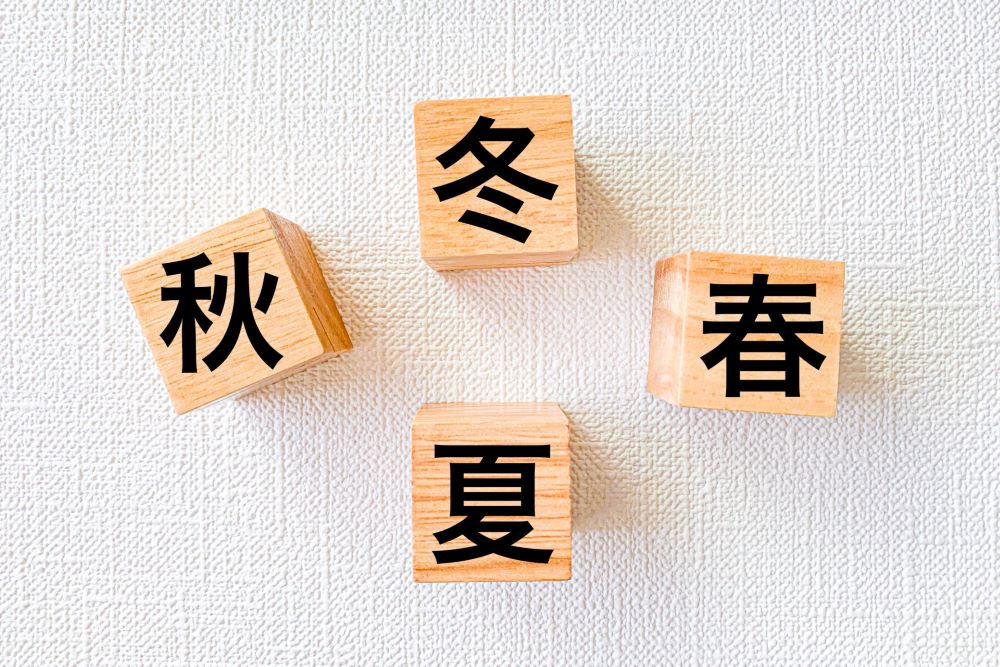
土用といえば、「丑の日のうなぎ」のイメージが強いため、夏にしかないと思われがちです。ですが、実は、どの季節にも「土用」があることをご存知でしょうか。まずは、土用について見ていきましょう。
土用は季節の終わりの18日間のこと
土用は雑節のひとつで、各季節の始まりである「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前の18日間のことを指します。別の言い方をすれば、季節の終わりの18日間のこと。なじみ深い夏土用を例にとると、「立秋」前の18日間が土用期間にあたります。ただし、土用期間は必ずしも18日間とは限りません。というのも、土用の入り(土用期間の初日)は、毎年固定の日ではないからです。例えば、夏土用は「太陽黄経が117度に達した日」という天文学的な現象によって確定されるため、年によっては日数が異なります。
ちなみに、雑節とは季節の変化をつかむための目安となる日の総称のこと。日本の気候や生活・文化に合わせて独自につくられたもので、中国から伝わった「二十四節気」を補う意味合いを持っています。雑節は、二十四節気に比べるとちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんが、それぞれの名称を聞けば、納得できるはず。土用以外の雑節には、以下のようなものがあります。
〜土用以外の主な雑節〜
- 節分
季節の分かれ目を意味し、もともとは各季節の始まりである「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の前日を指しました。ただ、いつしか「立春」の前日のみを節分と呼ぶようになり、いまに至ります。 - 彼岸
「春分」と「秋分」の前後3日、計7日間のこと。初日を「彼岸の入り」、春分と秋分の日の当日を「中日」、終日を「彼岸明け」といいます。 - 八十八夜
立春から数えて88日目にあたる日のことです。この頃から霜が降りなくなり、夏の気配が感じられるようになってきます。 - 入梅
昔は「芒種(ぼうしゅ)」を過ぎたあとの最初の「壬(みずのえ)」と決められていましたが、現在では太陽黄経が80度に達した日とされています。
- 半夏生
かつては、夏至から数えて11目にあたる日を半夏生と呼んでいました。現在は、太陽黄経が100度に達した日とされています。この頃に半夏(別名:カラスビシャク)という草が生えることから半夏生と名付けられました。
こぼれ話~二十四節季とは?
二十四節気についても、簡単にご説明しておきましょう。1年を季節ごとに、春夏秋冬の4つに分け、さらに、それぞれ6つに分かれて二十四節季となります。
〜代表的な二十四節気〜
<春>立春、啓蟄、春分
<夏>立夏、芒種、夏至
<秋>立秋、処暑、秋分
<冬>立冬、冬至、大寒
土の神さま「土公神」がいる期間
では、土用とはどのような期間なのでしょうか。
土用は、「土公神(どくじん、どこうじん)」と呼ばれる神さまの支配下に置かれる期間とされています。土公神は、土を司る神さまで、陰陽道の神さまのひとりです。季節によって居所を変える遊行神でもあり、「春はかまど、夏は門、秋は井戸、冬は庭」の地中にいるといわれています。なので、土用の期間中にやってしまうと土公神の怒りを買うNG行動があるのだとか。詳しくは次項で見てみましょう。
土用の期間には避けたいこと
土用期間中に避けた方がいいとされているのは、「土を動かすこと」「新しいこと」「方角に関すること」の3点です。具体的には次のような行為がNGとされていますが、じつは土用期間中に行ってもOKな日があります。それが「間日(まび)」と呼ばれる日。土公神が土を離れて天上界へ行く日とされており、NG行動をしても大丈夫といわれています。
〜土用期間には避けたい行為〜
<土を動かすこと>土いじり、草むしり、井戸掘り、基礎工事、地鎮祭 など
<新しいこと>新居購入、就職、転職、結婚、結納、開業 など
<方角に関すること>引っ越し、旅行 など
間日(まび)以外の土用期間中は、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあるため、「静かに過ごした方がいい」とされています。新しいことを始めるのは避けた方がいいというのは、そんな理由もあるようです。引っ越しや旅行が好ましくないのは、土用期間中は全方角の縁起がよくないとされているから。ただし、いずれも科学的な根拠があるわけではありません。古くからの言い伝えによるところが大きいため、実際に行うかどうかは考え方次第といえそうです。
夏の土用のなかでもとりわけ「丑の日」が有名なワケ
ここからは、土用のなかでも夏の土用・丑の日がとくに知られている理由について見てみましょう。
夏の土用・丑の日にうなぎを広めたのは、平賀源内!?

夏の土用・丑の日にうなぎを食べるようになったのは、平賀源内のアイデアだったというのが、一般的によく知られている説です。かいつまんで説明すると——。
日本では、古来より丑の日に「う」の付く食べ物をいただくと縁起がよいとされ、うどんや梅干しなど「う」の付くものを食べながら無病息災を願うという風習がありました。源内はその言い伝えを利用し、夏場に売上が落ち込む鰻屋にこんな助言をしたそうです。
【店頭に「本日、土用丑の日」と張り紙をする】
すると、その鰻屋は大繁盛。そのことを知ったほかのお店も真似するようになり、土用丑の日にうなぎを食べる習慣が定着したといわれています。
余談ですが、なぜ夏場にうなぎの売上が落ち込むのかというと、うなぎの旬は冬で、その頃がいちばんおいしいとされているからです。とはいえ、栄養価の高いうなぎ。夏に食べるのも理にはかなっているのです。
丑の日に食べるといいのは、うなぎだけじゃない!
うなぎのイメージがあまりにも強い夏の土用の丑の日ですが、その日に食べるといいとされる食材はほかにもあります。たとえば、以下の食べ物がそう。選択肢の幅がグッと広がるのではないでしょうか。

⚫️「う」の付く食べ物
うどん、ウリやウリの仲間(きゅうり、ゴーヤ、スイカなど)、梅干し など
⚫️「土用」が付く食べ物
土用しじみ、土用餅、土用卵 など
⚫️「黒い」食べ物
黒豆、黒ゴマ、ひじき など
※「黒」というのは、丑の方角を守護するといわれる中国の伝説上の神獣「玄武」の色に由来します。
2025年の夏の土用・丑の日はいつ?

2025年の夏の土用・丑の日は、2回あります。1回目の丑の日「一の丑」は7月19日(土)、2回目の「二の丑」は7月31日(木)です。
補足すると、今夏の土用の期間は7月19日(土)から8月6日(水)までの19日間。
ちなみに、間日は、次の5日です。
・7月21日(月)※祝日「海の日」
・7月22日(火)
・7月26日(土)
・8月2日 (土)
・8月3日 (日)
今夏の土用・丑の日は、「う」のつく食べ物を探してみて
土用の丑の日は、「うなぎを食べる日」といっても過言ではないほど、うなぎを食べる風習が根づいています。たしかに時節柄、うなぎを食べるのは理にかなっているのですが、それ以外にも食べるといいものはあります。たとえば、ウリ(きゅうりやスイカなど)もそのひとつ。体を冷やす働きがあるので、夏にはぴったりの食べ物です。
そもそも、食べ物以前に、土用とはどんな日なのかを意識することはほとんどないのではないでしょうか。土用は、土の神さまの支配下にある期間です。そのため、土いじりや増改築、基礎工事など「土を動かすような行為」は避けた方がいいとされています。今年の夏は、うなぎばかりにとらわれず、土用の日そのものについてもちょっと意識を向けてみませんか。
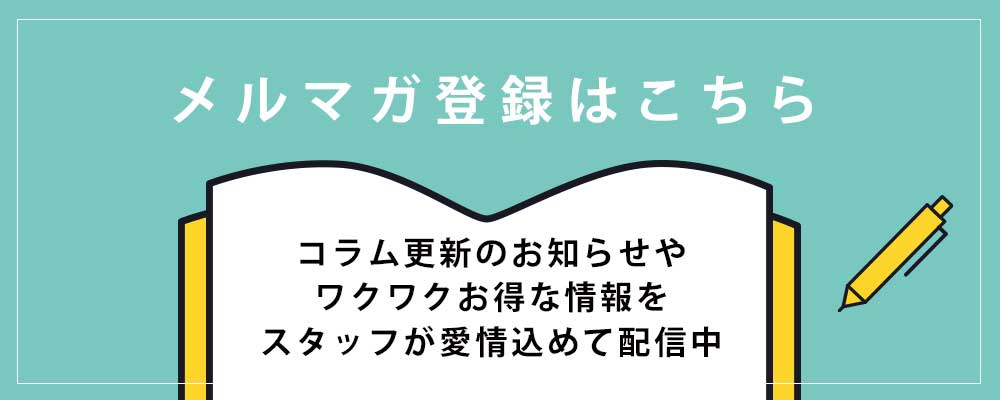
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
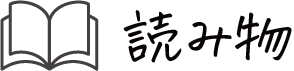
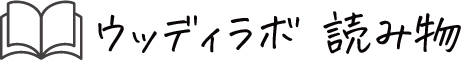


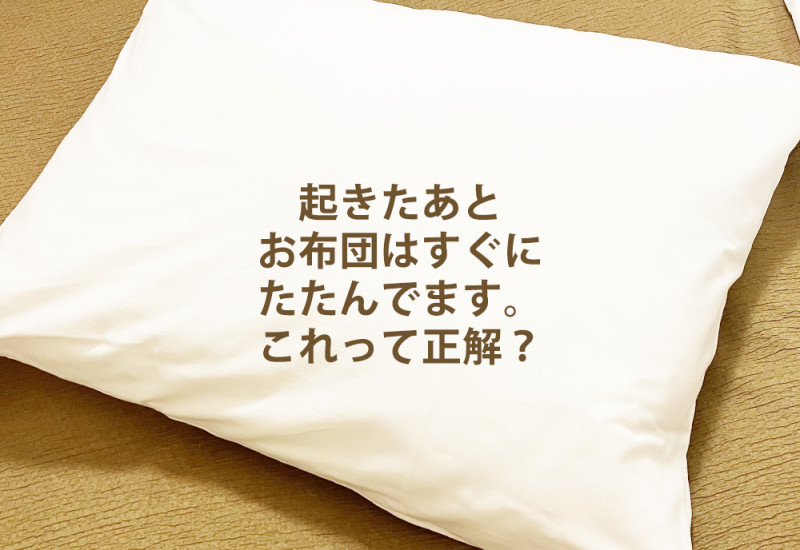
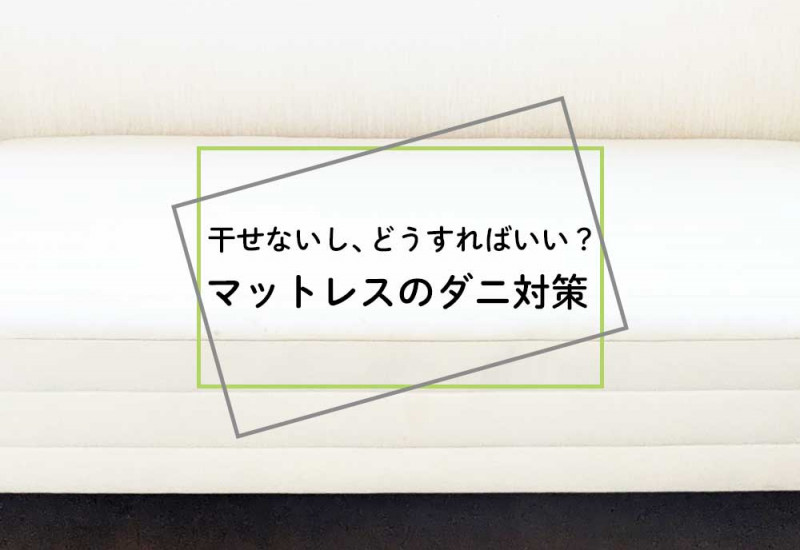
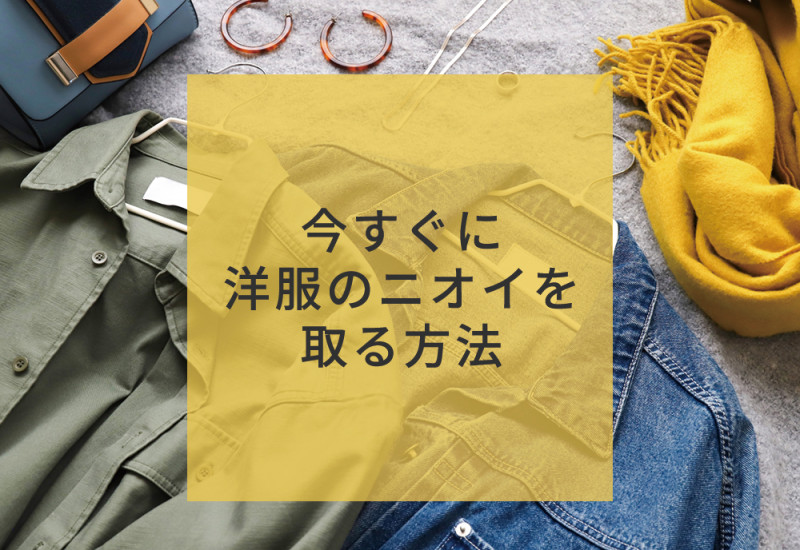
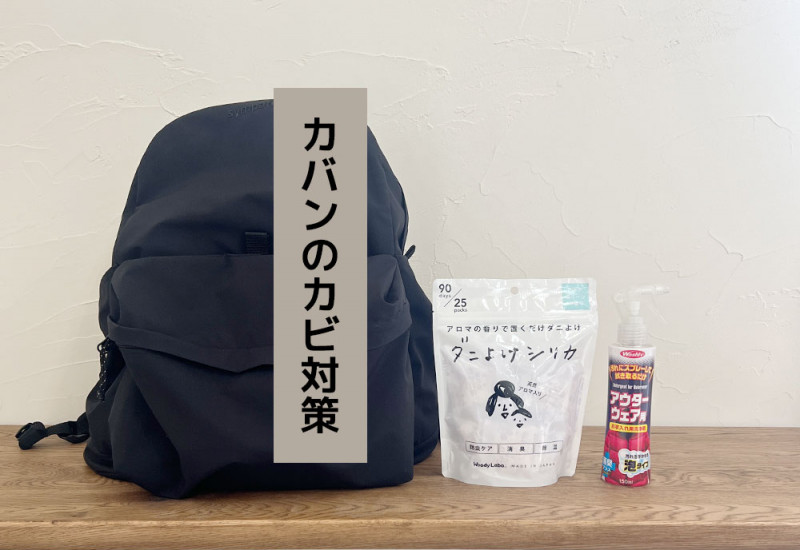


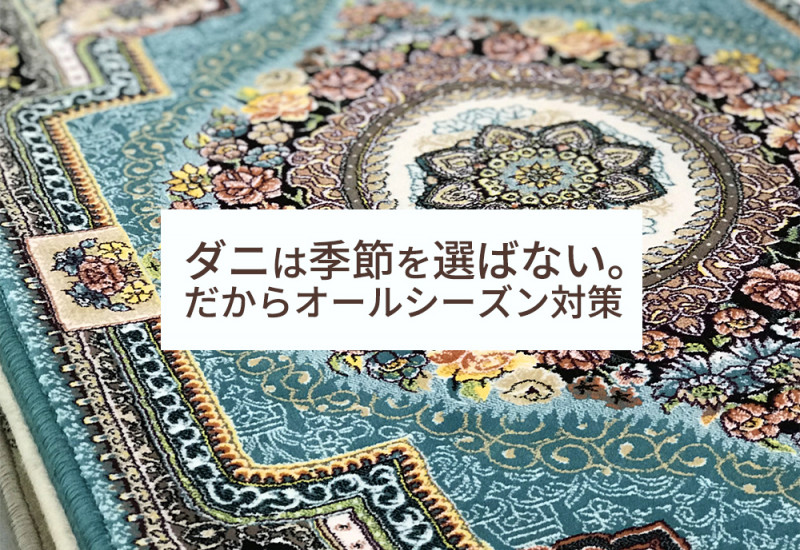


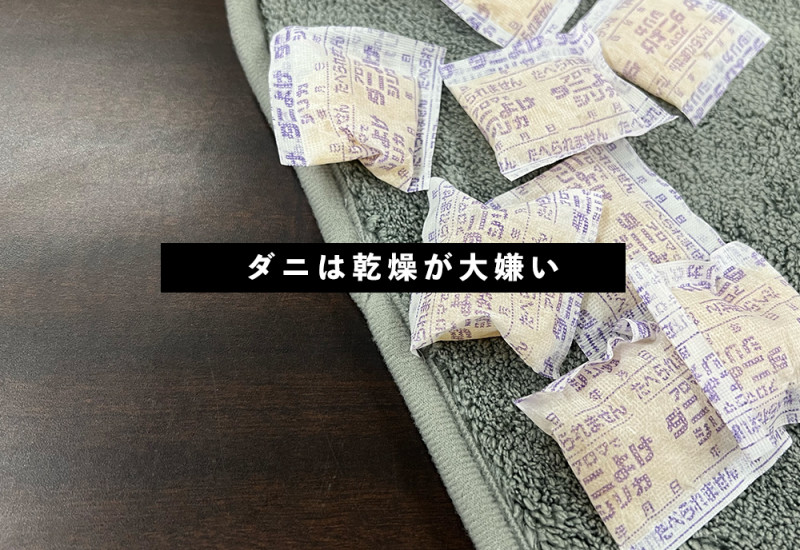


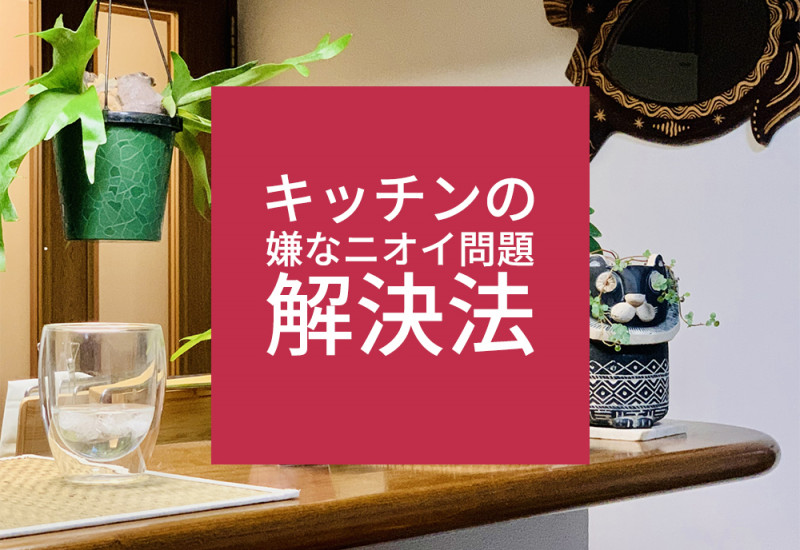
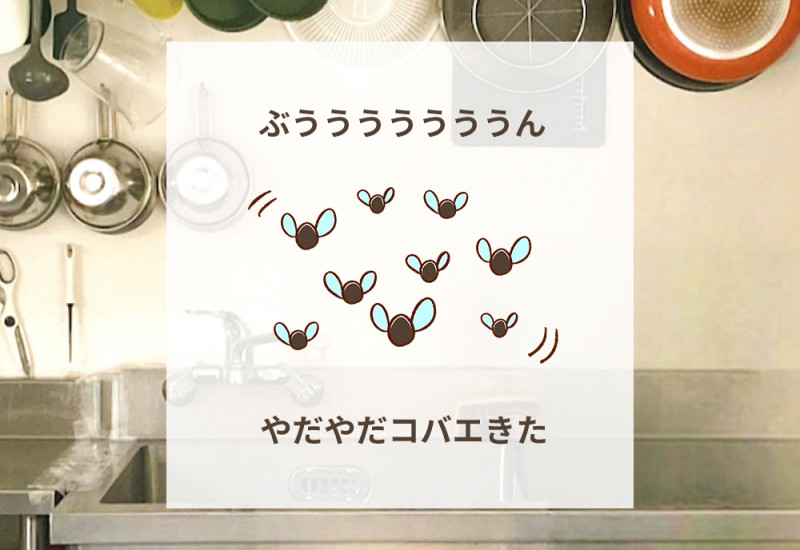

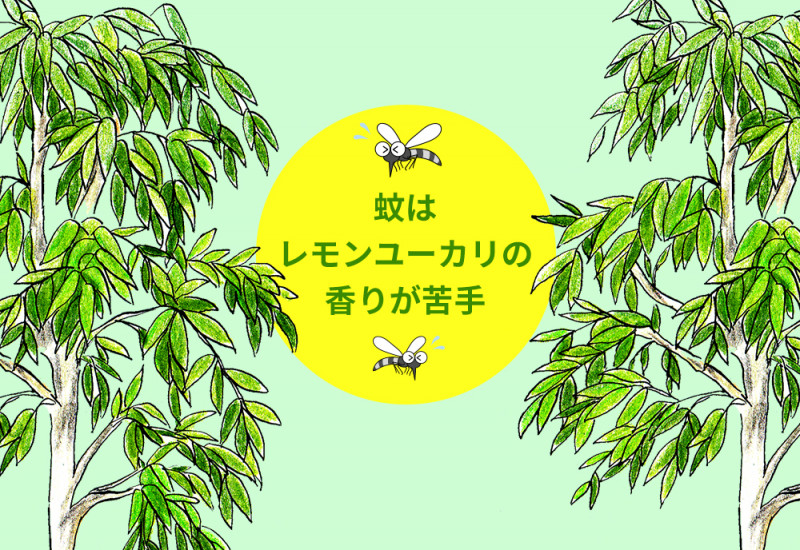
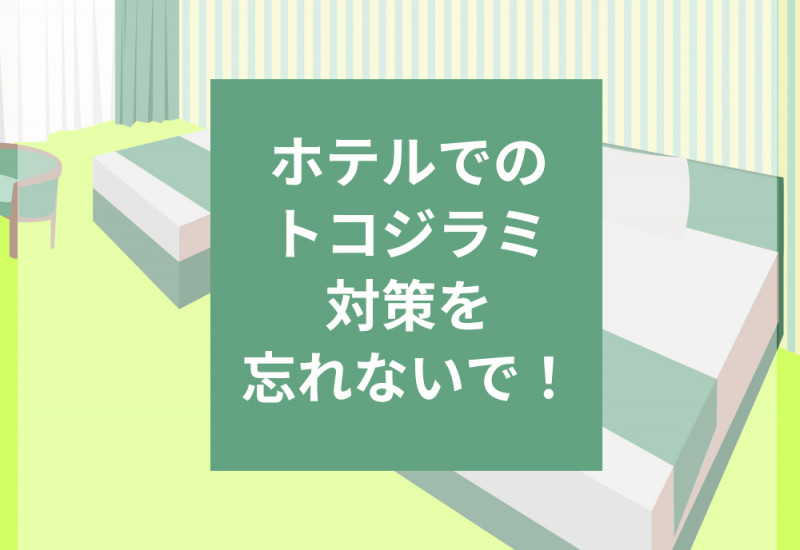



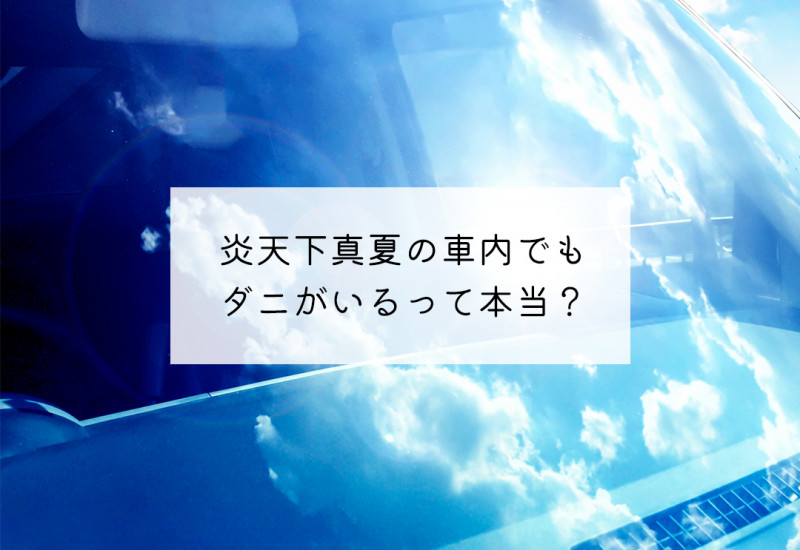
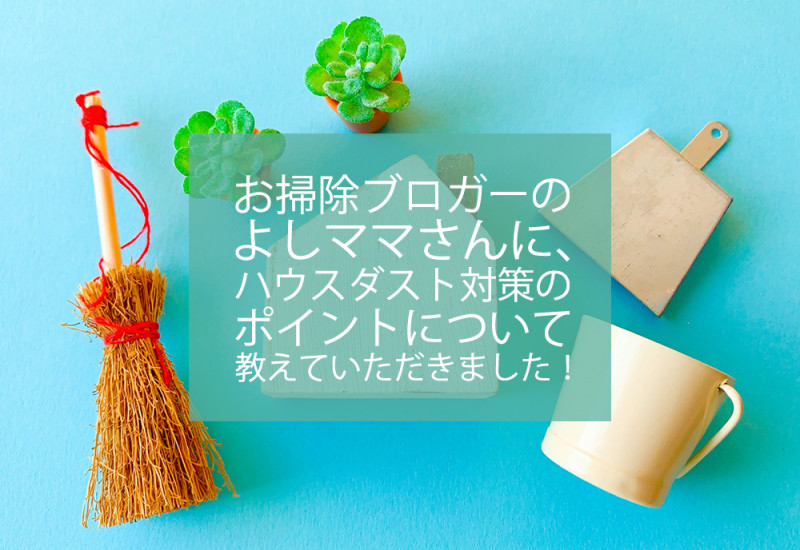
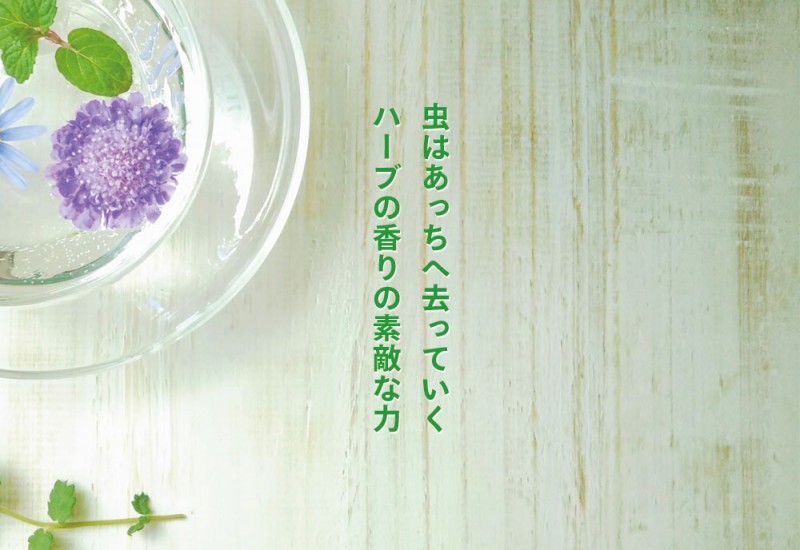
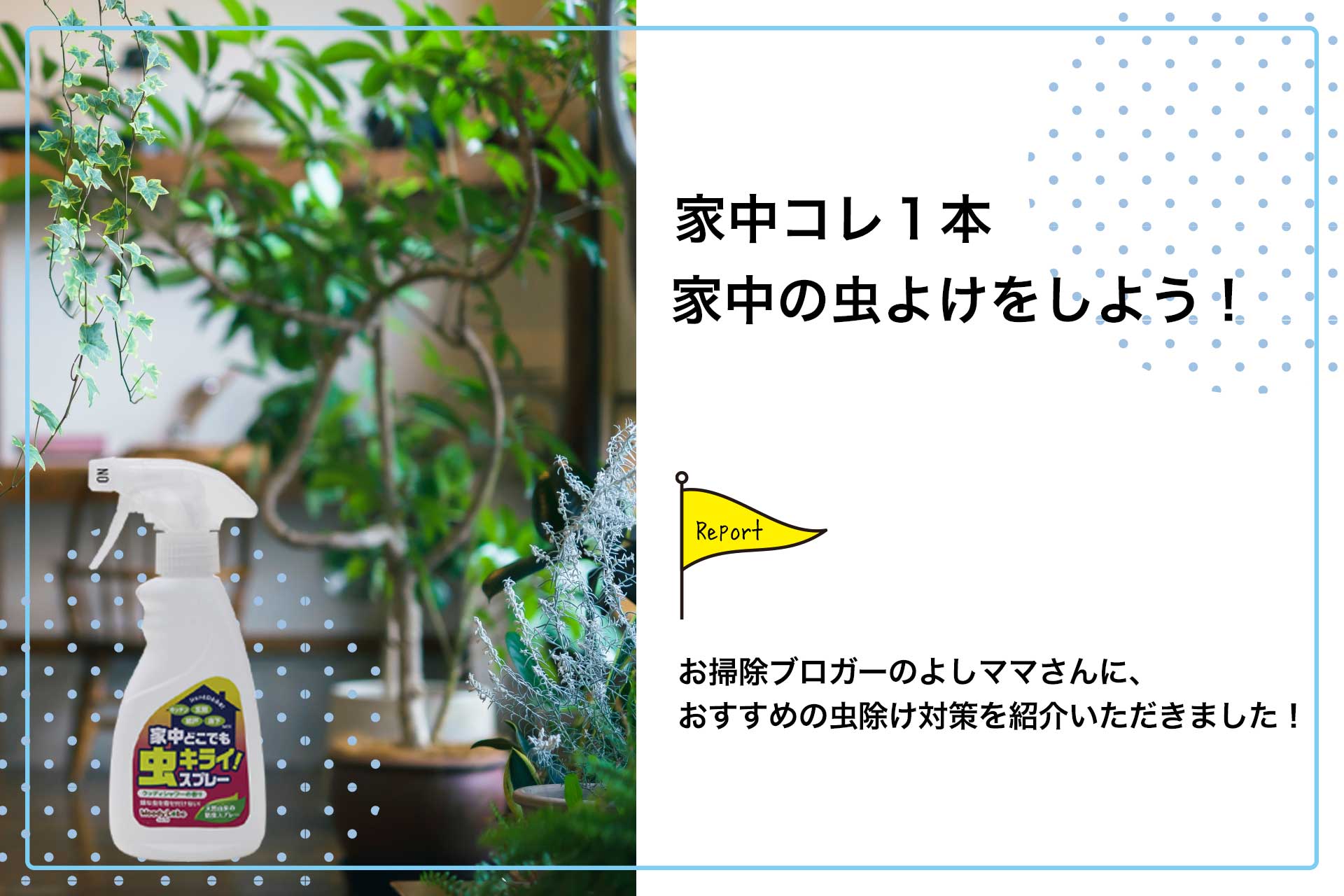
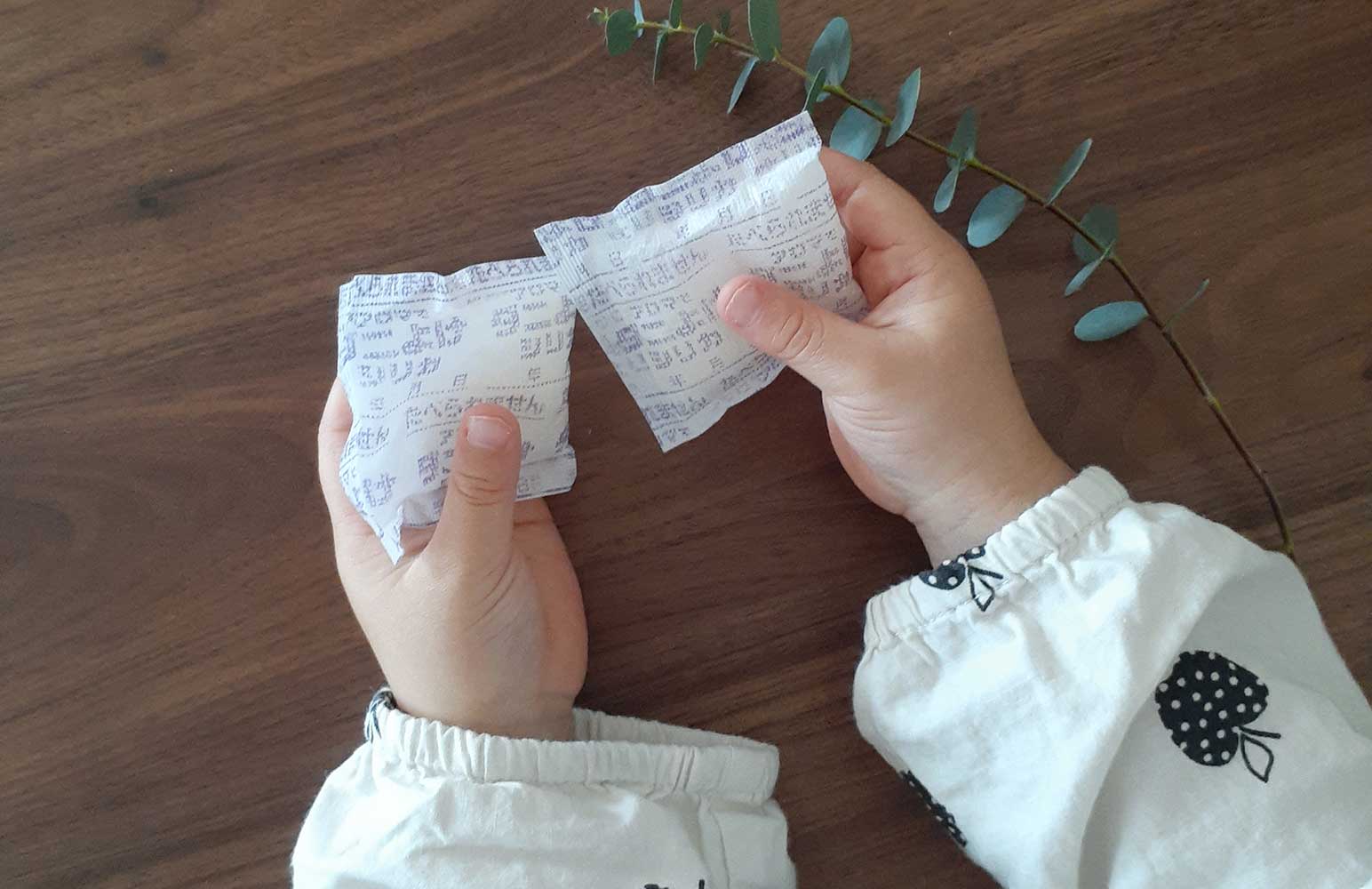

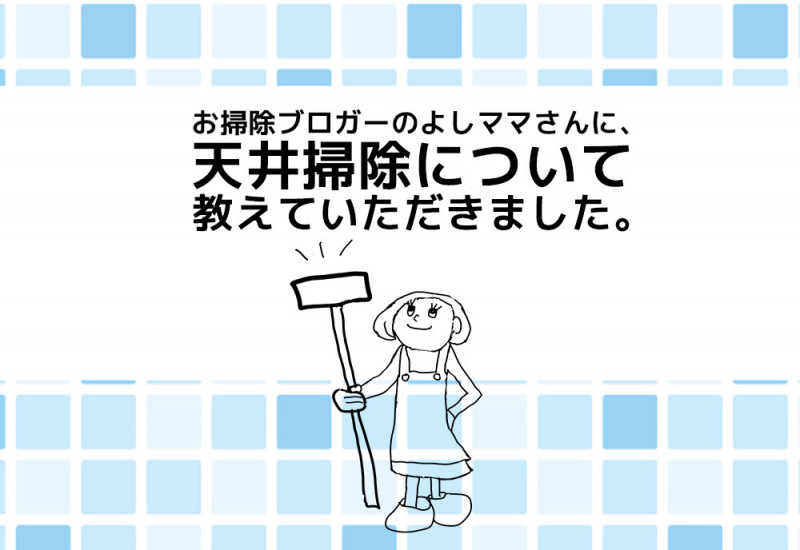
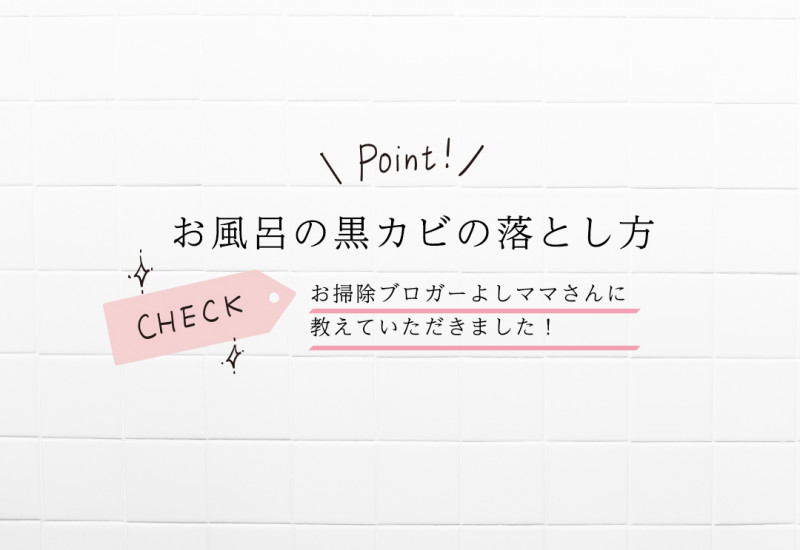



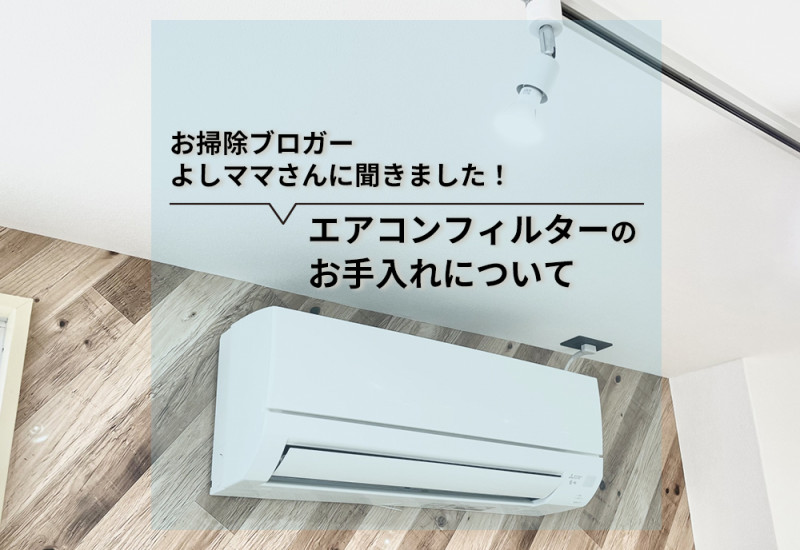
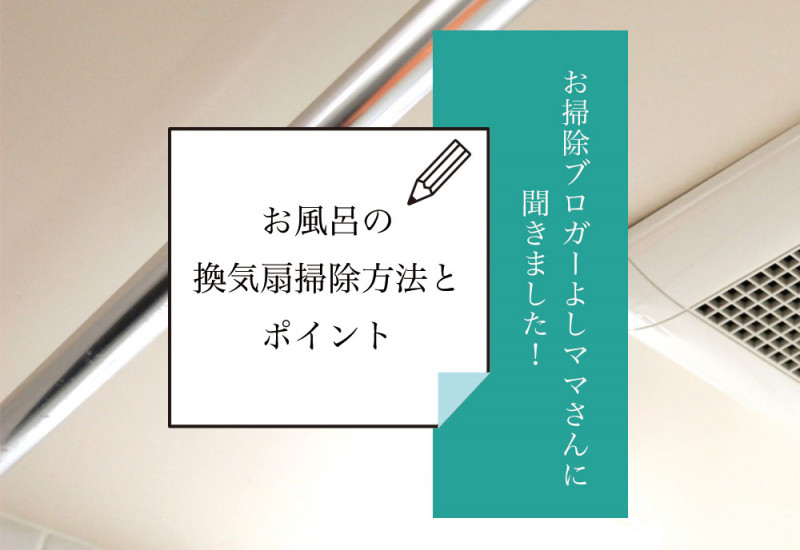

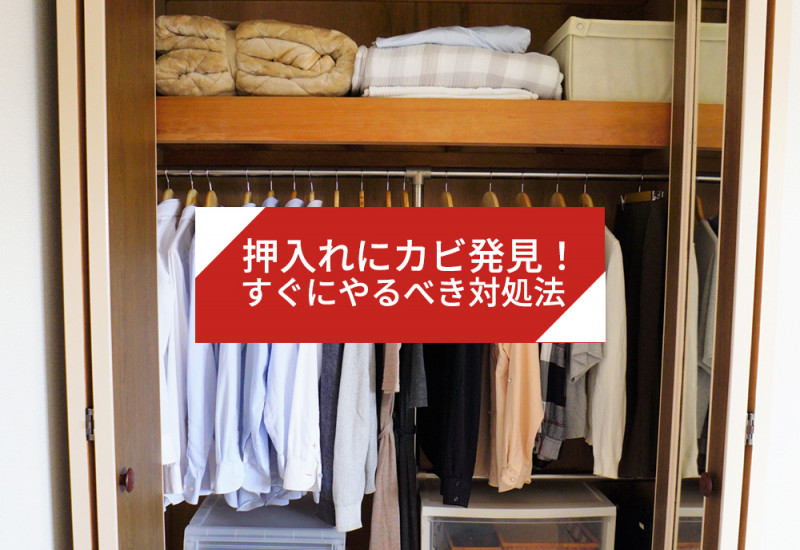



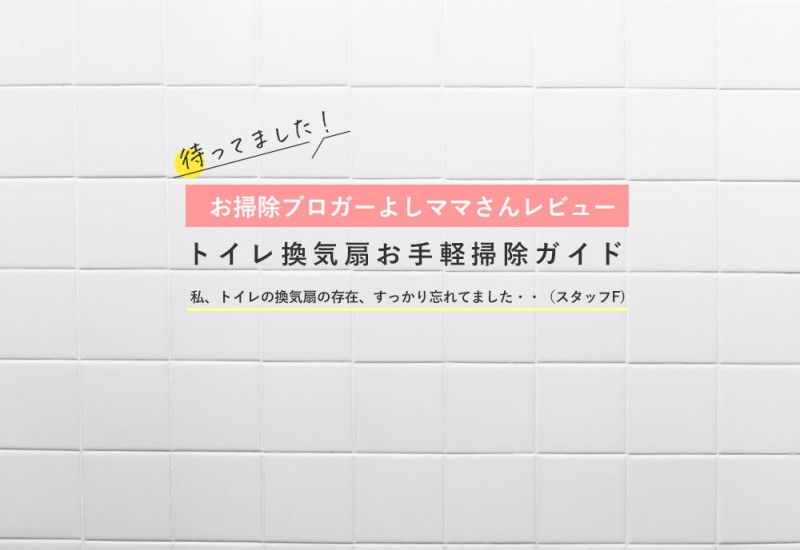
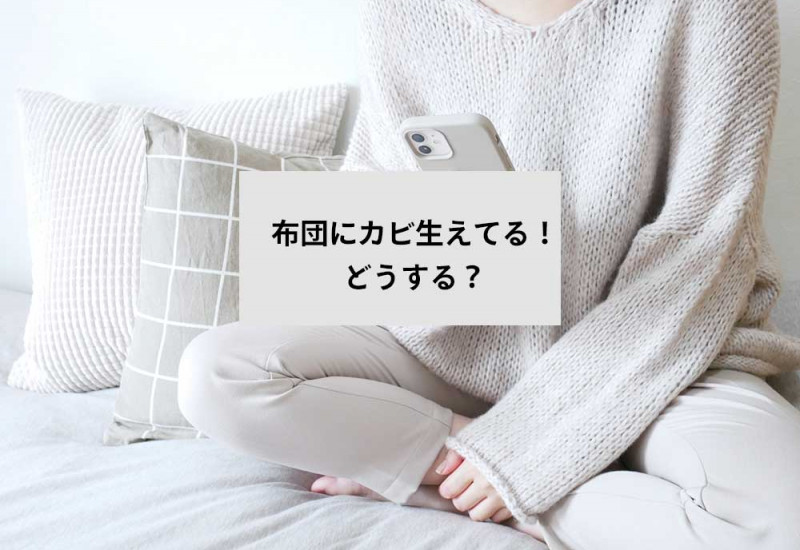
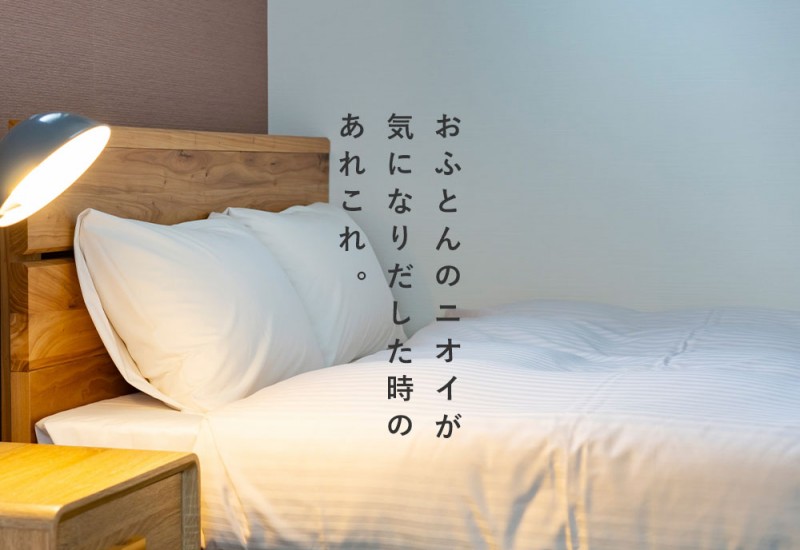
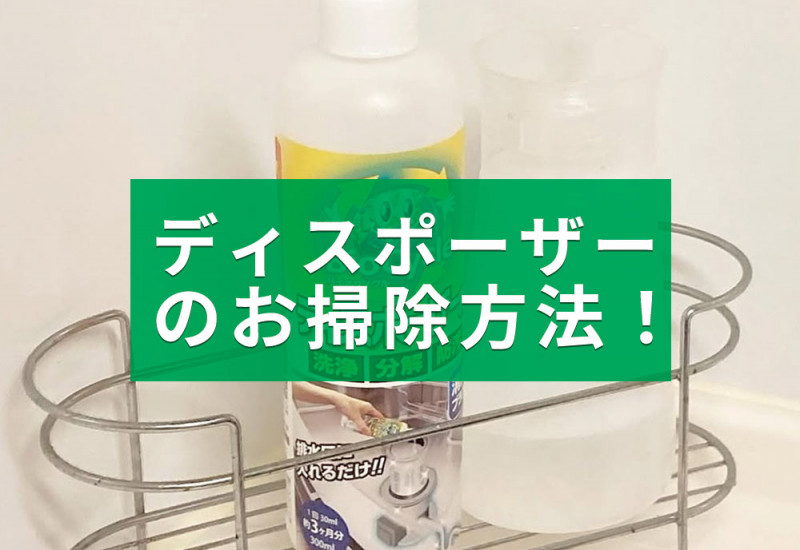

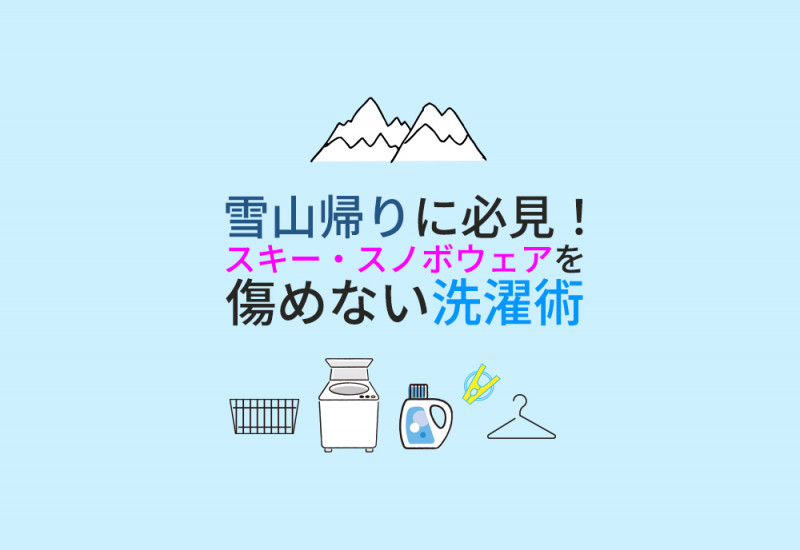
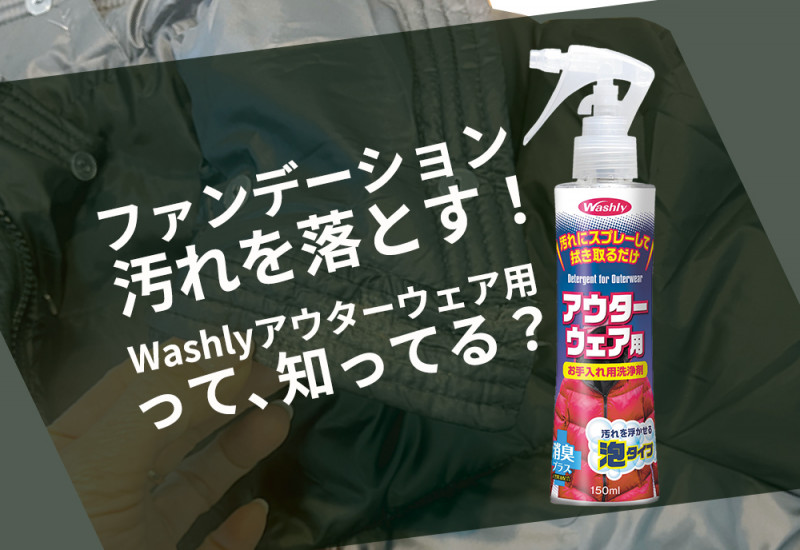


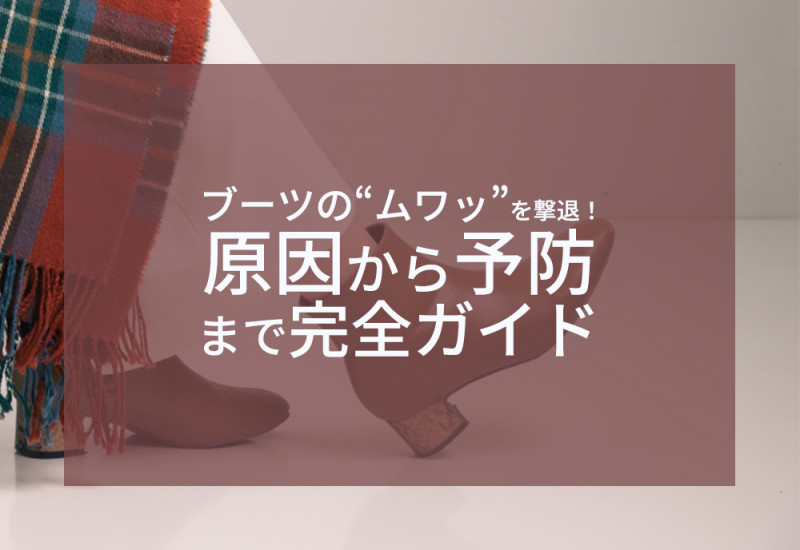
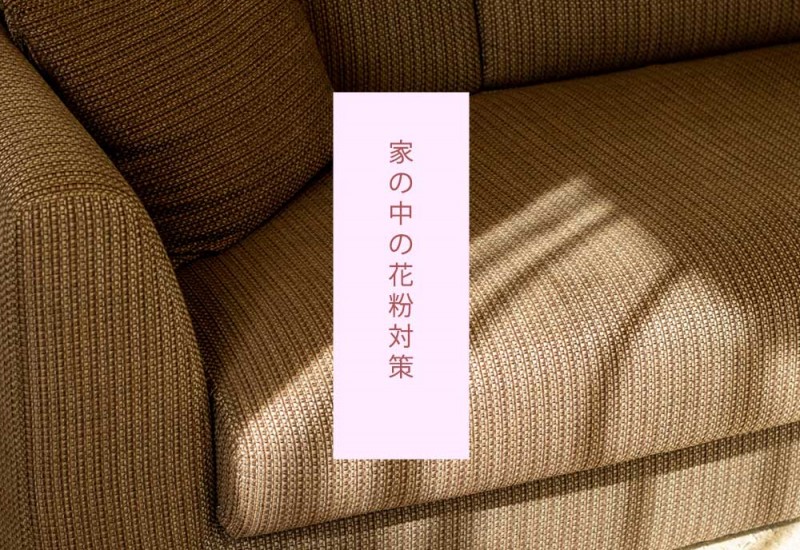

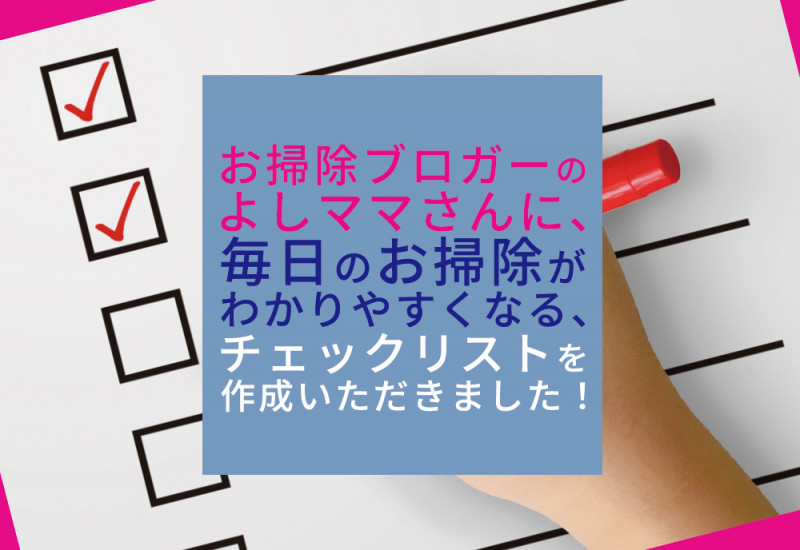

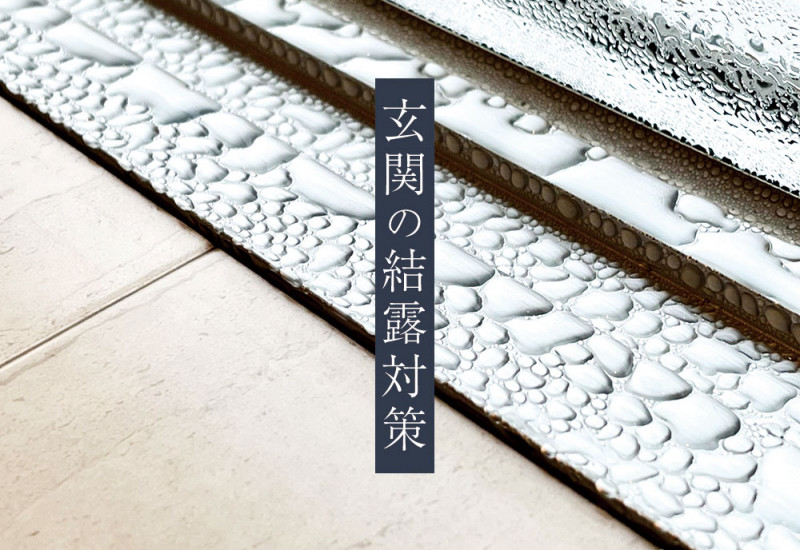

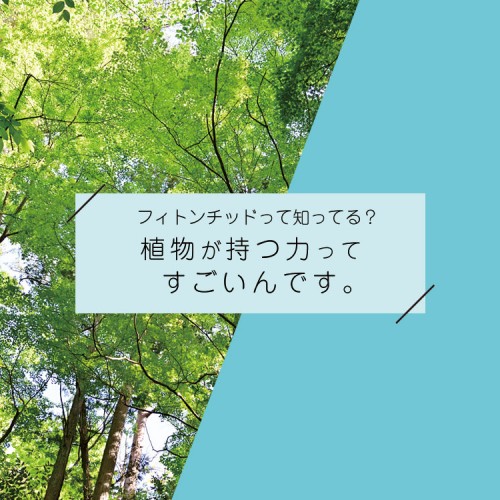
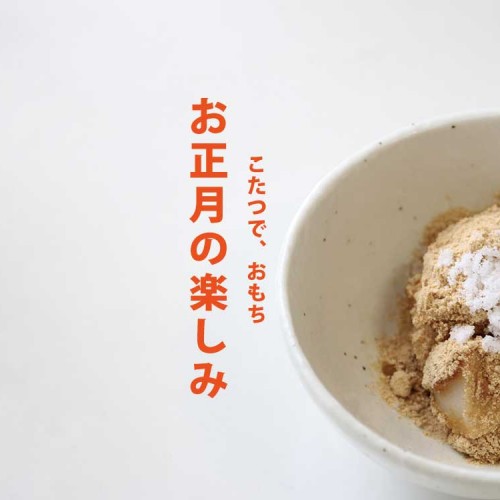
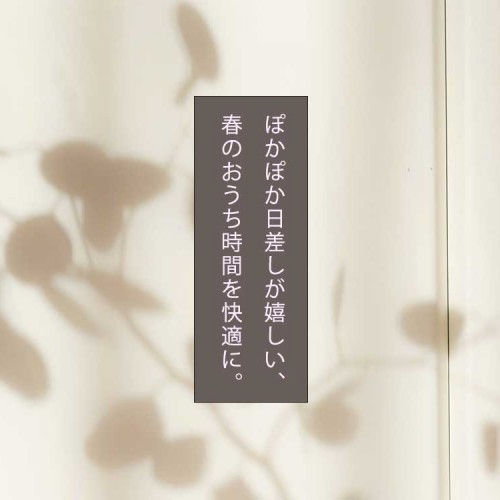
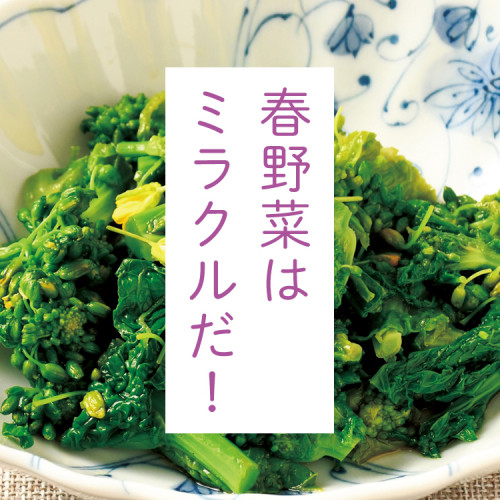
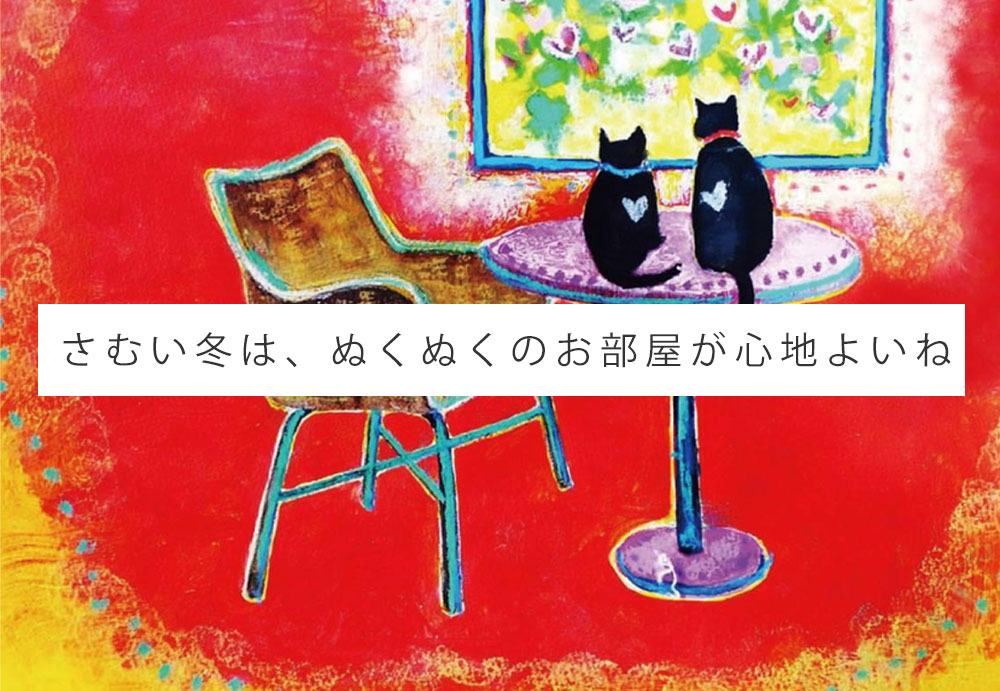

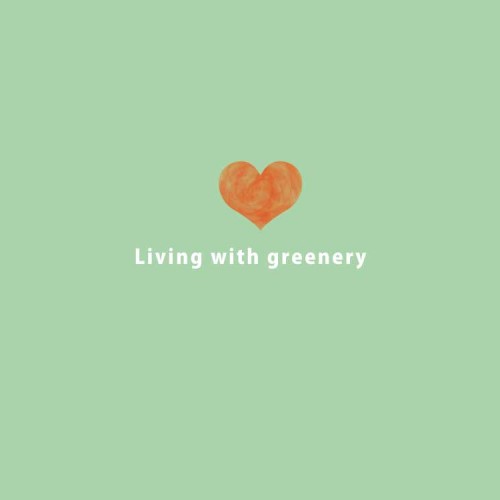
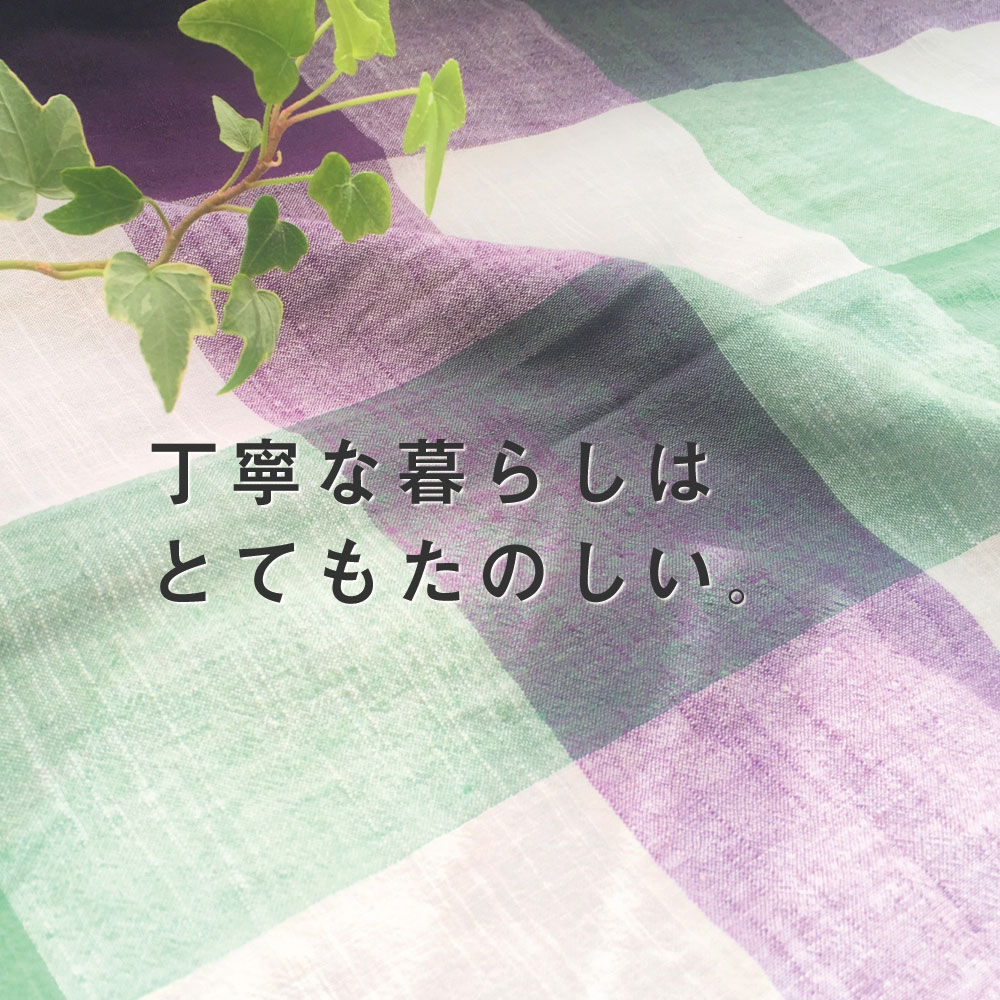
この記事へのコメントはありません。