春の恵みをいただきながら健康づくり〜代表的な春野菜の栄養素と健康効果〜
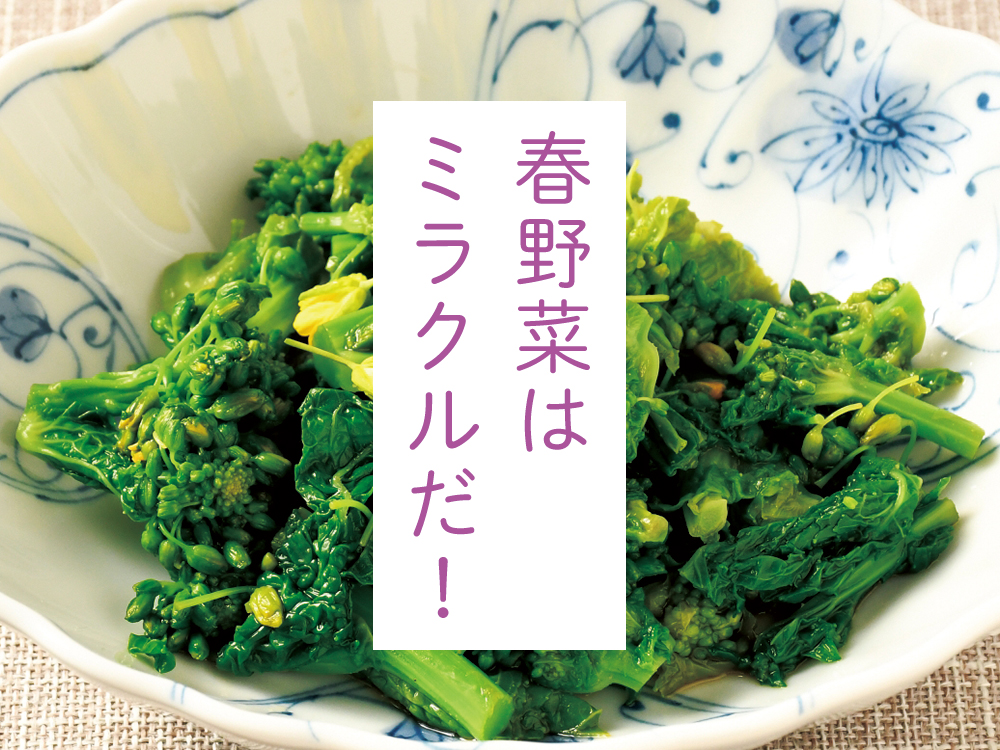
日ごとに春らしくなってきました。明るくポジティブな雰囲気が漂う春ですが、寒暖差の大きさや気圧の変動などにより体調を崩しやすい時期でもあります。今春は、旬の野菜を積極的に取り入れて、体調管理に努めてみませんか? 今回は、春野菜についてのお話です。おいしさもさることながら、この時期に摂りたい栄養素がギュッと詰まった春野菜を楽しみましょう。
「旬の食材は健康にいい」と言われるのはなぜ?
春野菜に限らず、旬のものはカラダにいいといわれています。まずは、その理由を見ていきましょう。

そもそも、「旬」とは?
旬とは、「自然の中でふつうに育てた野菜や果物がとれる季節や、魚がたくさんとれる季節のこと」です(農林水産省HPより)。
ふだん「旬」とひとくちに言うことが多いですが、じつは、旬には三段階の呼び名があります。出始めの頃の「走り」、最盛期の「盛り」、終わりの頃の「名残」です。それぞれの特徴を、以下に紹介します。
- 「走り(はしり)」
「初物(はつもの)」とも呼ばれます。江戸の頃より、走りを楽しむのは「粋」なこととされ、味そのものよりも「希少性」に価値を見出される傾向にあります。 - 「盛り(さかり)」
もっとも味がよくなり、栄養価も高まる時期です。多くの人が「旬」として意識しているのが、この「盛り」のこと。市中に多く出回るので、価格も安くなります。 - 「名残(なごり)」
最盛期に比べると、味わいや風味が落ちるのは否めないものの、調理方法を工夫するなどして親しまれてきました。去りゆく季節を惜しみながら、「来年もまた食べられますように」と願いを込めていただきます。
以上のことからわかるように、「旬」といえば、一般的には「盛り」の段階を指していることがほとんどです。この記事でいう旬もご多分にもれず、盛りのことを指しています。改めて旬を野菜を食べるメリットを2つ紹介しましょう。
旬の食材を食べるメリット① 栄養価が高い

旬の時期に収穫されるものは栄養価が高いといわれています。昔からそういわれているので「そんな感じがする」と感覚的に捉えがちですが、科学的な裏付けがちゃんとあるのです!
1年間毎月、数十種類の同じ野菜・果物を購入し、栄養分の含有量を分析するという研究がなされたそうで、次のような結果が得られたといいます。(※要点のみ抜粋)
- ほとんどの野菜の栄養価は、程度の差こそあれ必ず山(栄養価の高い時期)がある
- その山は3ヶ月ほどつづき、昔からいわれている旬の時期と重なる
- 逆説的にいうと、旬の時期をはずれると野菜の栄養価はグンと低くなり、見た目は同じでも中身は別の野菜というほど違いがある
たとえば、なじみ深い野菜のひとつである「ほうれん草」の栄養価(ビタミンC)は、旬の時期とそれ以外の時期ではおよそ4倍も違うのだそうです。
参考:野菜の旬と栄養価 ~旬を知り、豊かな食卓を~|独立行政法人農畜産業振興機構
旬の食材を食べるメリット② 安価で購入しやすい
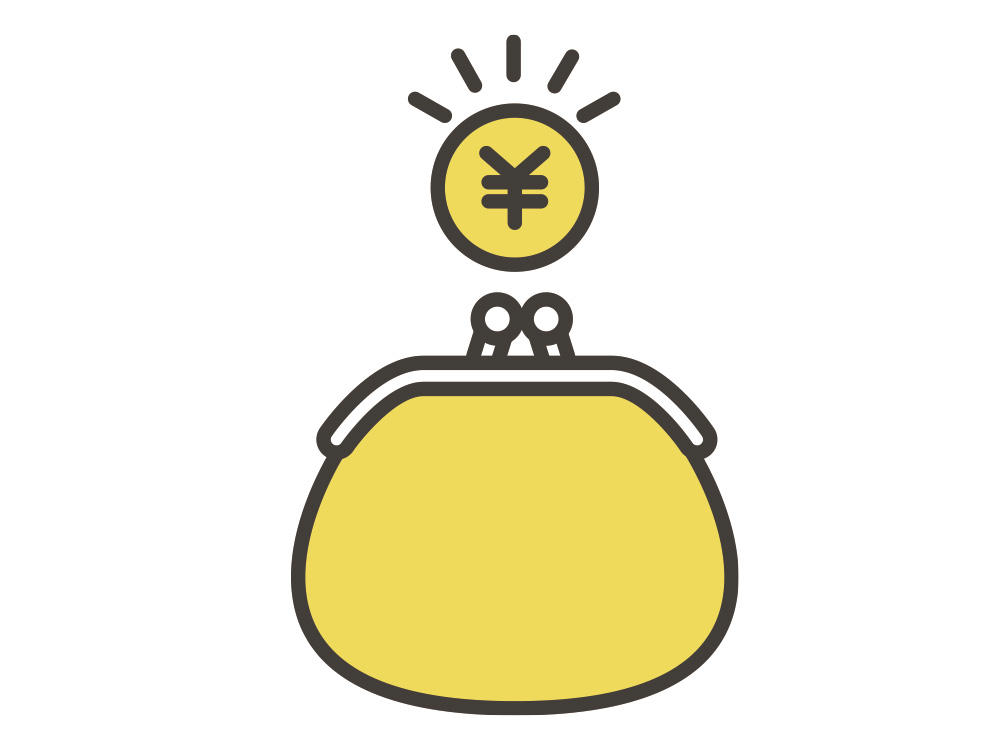
旬の時期は生産量が多く、流通量も増えることから、ほかの時期よりも安く手に入れることができます。
こぼれ話 〜初物を食べると寿命が延びる!?〜
「初物七十五日(はつものしちじゅうごにち)」という言葉をご存知でしょうか。江戸時代に盛んに使われた言葉で、旬の走りや出始めたばかりの「初物」を食べると、寿命が75日延びるという意味になります。古来より初物には特別な生命力が宿るとされ、それをいただくことで新たな活力を得て、長生きできるという考えに由来するそうです。俗説ではあるものの、今なお語り継がれているのは、四季に恵まれ、食材の旬を大切にしてきた日本人ならではの感性に響くものがあるからなのかもしれません。
春野菜の栄養素と健康効果
ここからは、春野菜の健康パワーに迫ります。まずは、春野菜の種類と特徴を見ていきましょう。
春野菜の特徴は「苦味」と「香り」

春野菜の特徴を見ていく前に、どんな種類があるのかを以下に紹介します。(※山菜類も含めます)
*菜の花
*ふきのとう
*たけのこ
*アスパラガス
*セリ
*そら豆
*セロリ
*クレソン
など
上記の食材からもイメージできるように、春野菜の特徴は独特の「苦み」と「香り」にあります。それぞれに含まれている成分や働きは次のとおりです。
- 苦み
春野菜独特の苦味は「植物性アルカノイド」という成分です。老廃物を体の外に出してくれる解毒作用や新陳代謝を促す働きがあります。 - 香り
春野菜が放つ特有の香り成分は、主に「テルペン類」です。テルペン類には、血行促進や抗酸化作用があります。
昔から、春野菜の苦みや香りは「眠っていた冬の体を目覚めさせてくれる」といわれています。それぞれが持つ作用を知ると、なるほど納得ではないでしょうか。ちなみに、冬眠から目覚めたクマが最初に口にするのも「ふきのとう」なのだそうです。体を目覚めさせ、毒素を排泄してくれるのを知っているかのように、せっせと食べるといいます。
代表的な春野菜の栄養素と健康効果
ここでは、春野菜のなかでも広く知られている「菜の花」「ふきのとう」「たけのこ」「アスパラガス」「セリ」「セロリ」の栄養素と健康効果について紹介していきます。
菜の花
真っ先に春の訪れを感じさせてくれる菜の花は、春野菜のなかでもビタミン・ミネラル類が群を抜いて豊富です。とくにビタミンCの含有量が豊富で、ほうれん草のおよそ4倍ともいわれています。皮膚や粘膜の抵抗力を高めて、風邪や感染症の予防に効果的です。
ふきのとう
春先、いっせいに芽を出すことから「春の使者」とも呼ばれるふきのとう。カリウムなどのミネラルやビタミンE、食物繊維が比較的豊富に含まれています。「フキノリド」と呼ばれる香り成分は、胃腸の働きを促進。独特の苦味はポリフェノール類で、新陳代謝を活発にします。ちなみに、ふきのとうは、ふきの「蕾(つぼみ)」の部分です。
たけのこ
たけのこは、竹の地下茎から出てくる「若芽」のことをいいます。食物繊維が豊富で、便秘や大腸がんの予防に効果的です。コレステロール値の改善にも役立つといわれています。たけのこの切り口に見られる白い粉はアクと思われがちですが、チロシンというアミノ酸の一種で、洗い流す必要はないそうです。
アスパラガス
緑黄色野菜であるアスパラガス。βカロテンや葉酸、ビタミンKが豊富に含まれています。とくに注目したいのが、アミノ酸の一種である「アスパラギン酸」です。この成分は名前から察しがつくように、アスパラから発見されました。アスパラギン酸は、体内のエネルギー代謝を活発にする作用があり、疲労回復やスタミナ増強に効果が期待できます。
セリ
春の七草のひとつとしても知られるセリは、日本原産の野菜です。カロテンや葉酸、鉄などが豊富。独特の香り成分は、解熱、解毒作用や胃を丈夫にする働きがあります。抗酸化作用のあるフラボノイドの一種「ケルセチン」も含まれており、カロテンやビタミンCとの相乗効果でがん予防も期待されています。
セロリ
爽やかな香りとシャキシャキとした食感が魅力のセロリには、βカロテンやビタミンB群、カリウムなどが豊富に含まれています。βカロテンは、よく使われる茎の部分よりも葉に多く含まれているので(およそ2倍)、葉も使うようにするといいそうです。特有の香りは「アイピン」という精油成分。精神を安定させる作用があり、不眠やイライラの解消に効果的があります。
体調管理に、春野菜を取り入れてみましょう!

寒暖差や気圧の変動が大きい春は、体の不調が出やすい季節です。旬の野菜には、その季節に必要な栄養素が含まれているので、不調の改善や健康増進に役立つといわれています。とりわけ春野菜は、特有の「苦味」や「香り」を持つものが多く、デトックス効果も期待大。物価高の昨今、野菜ひとつ買うのもためらいますが、旬の時期に出回る野菜は比較的入手しやすい価格帯なのが救いです。今春、体調管理に春野菜を取り入れてみませんか?
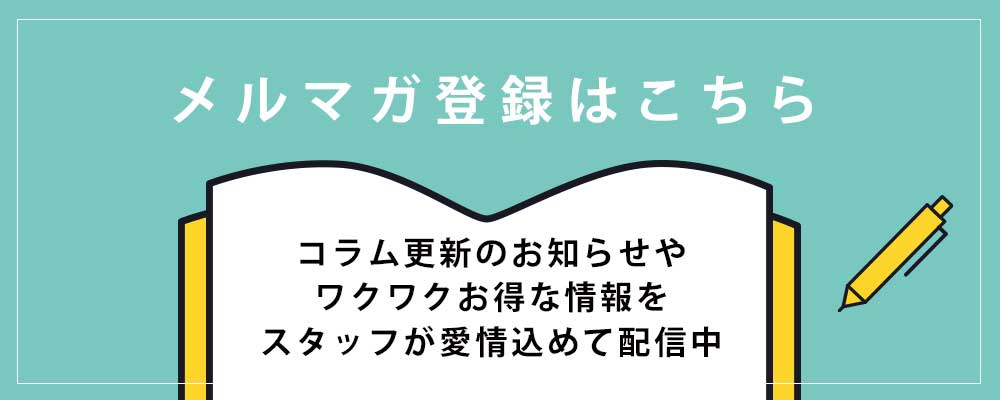
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
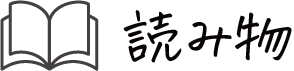
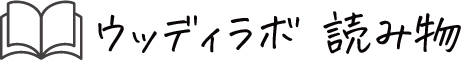


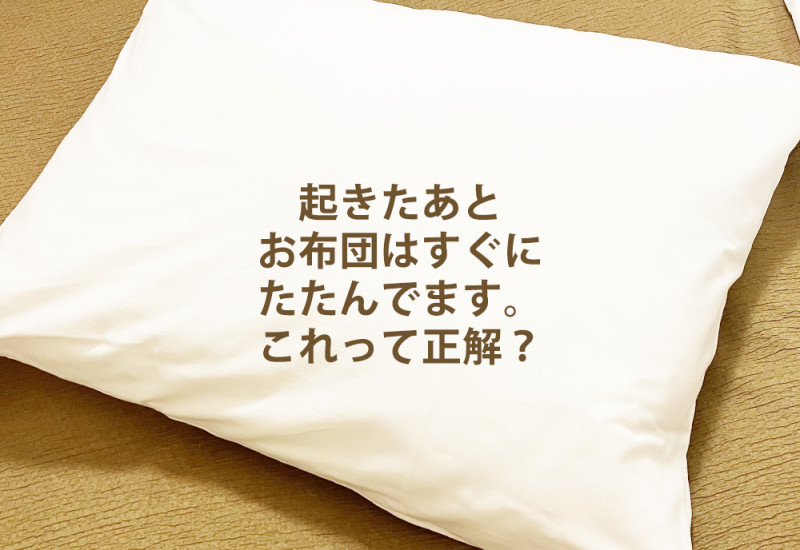
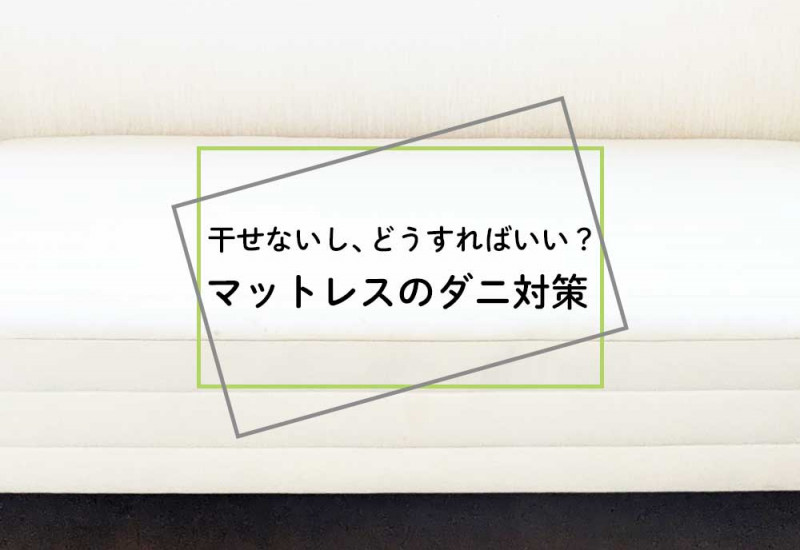
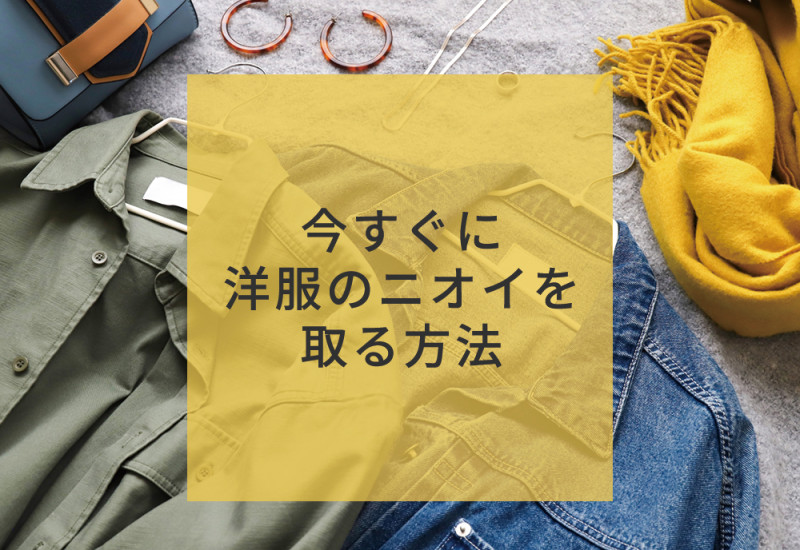
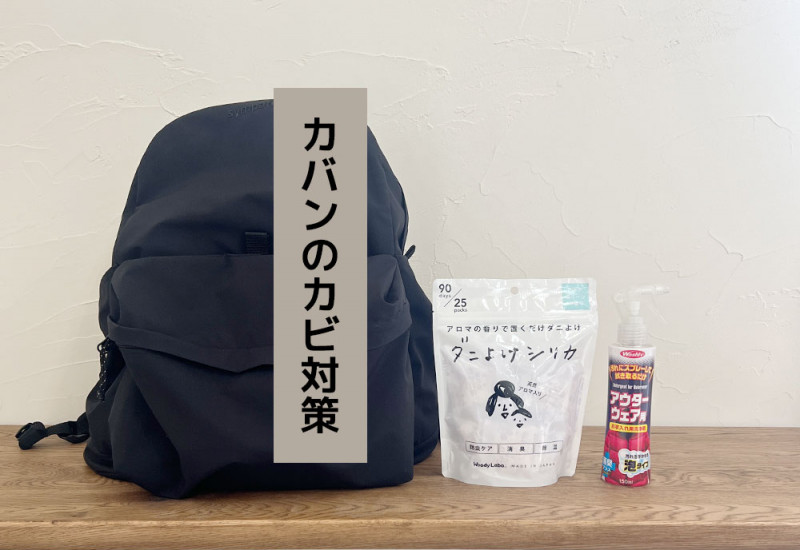


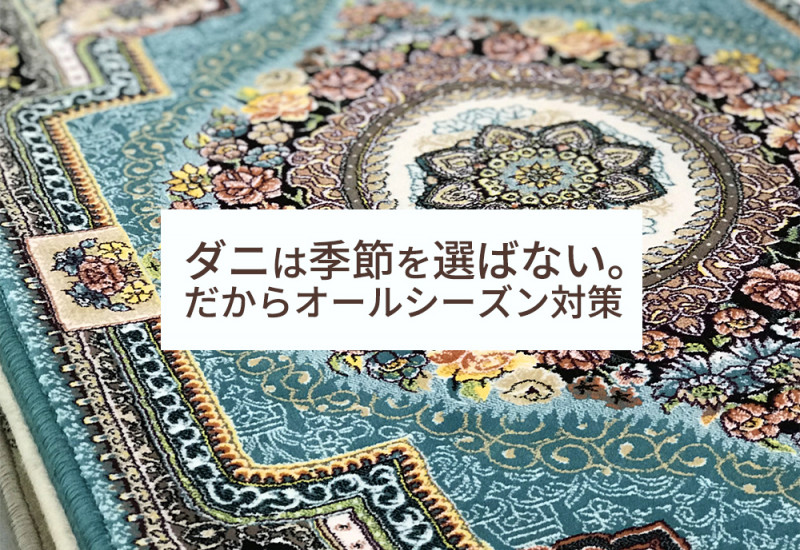


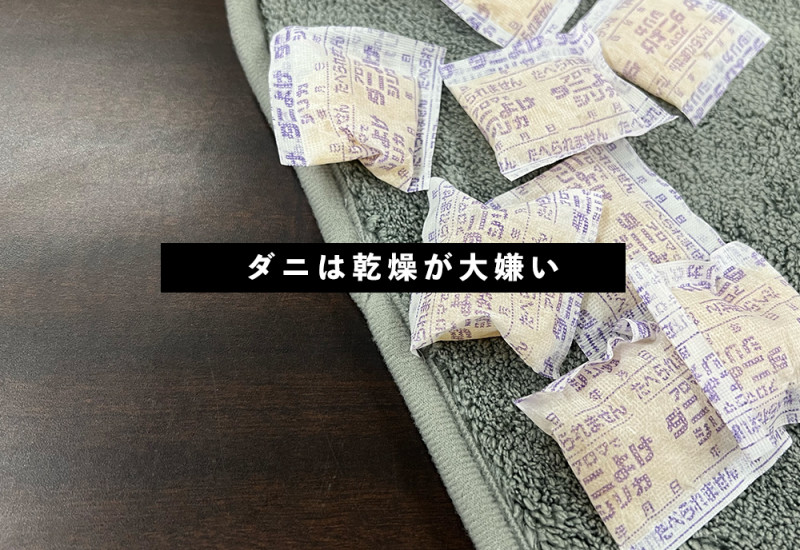


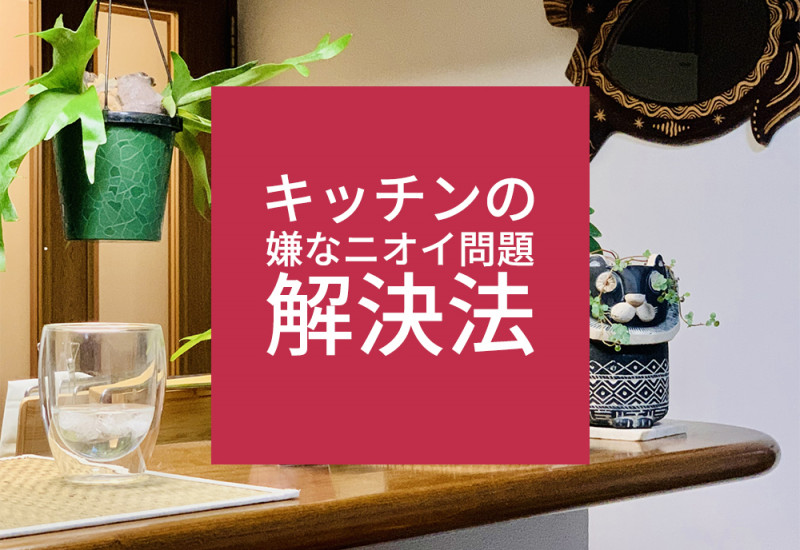
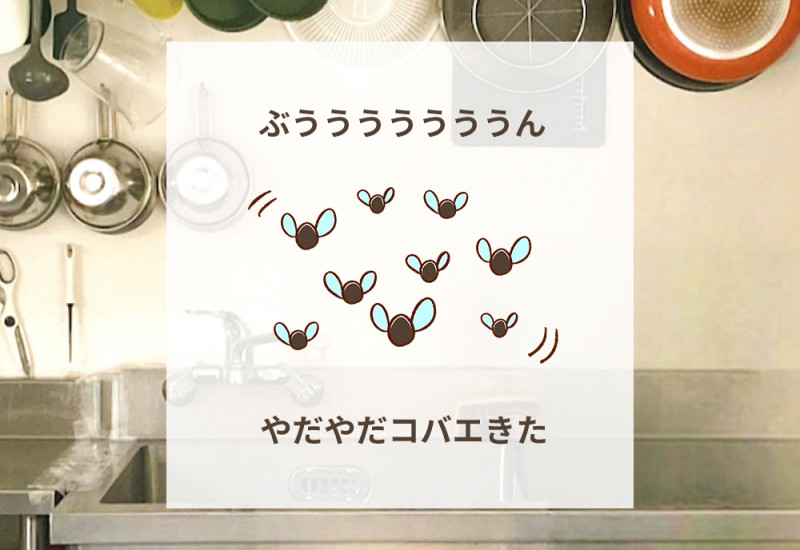

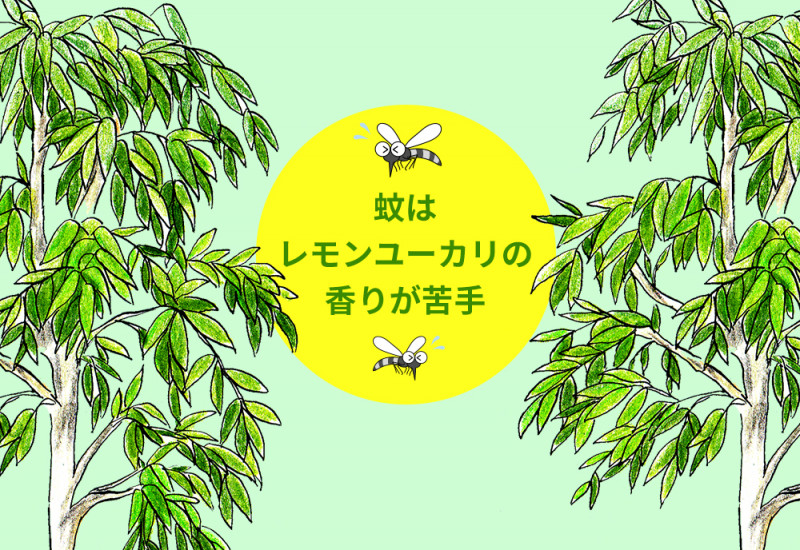
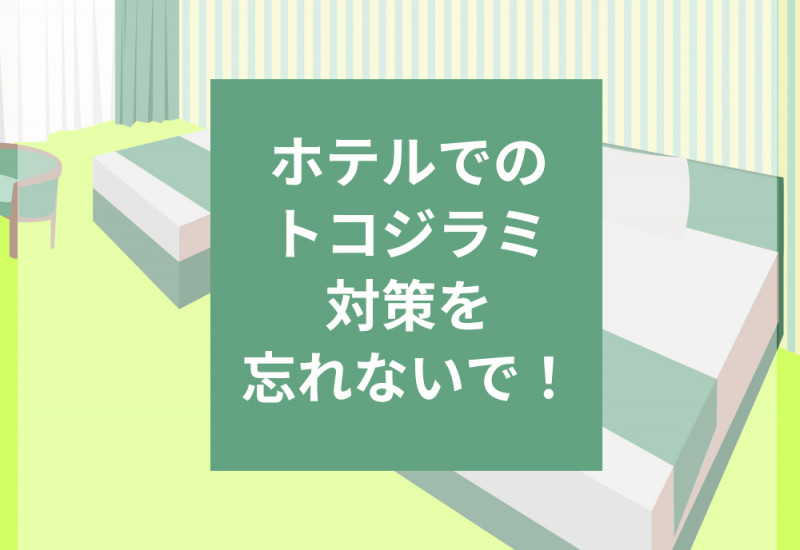



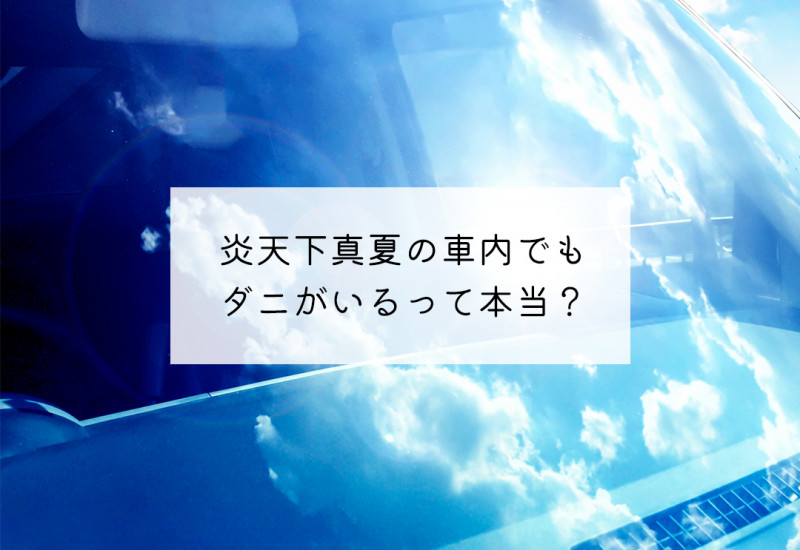
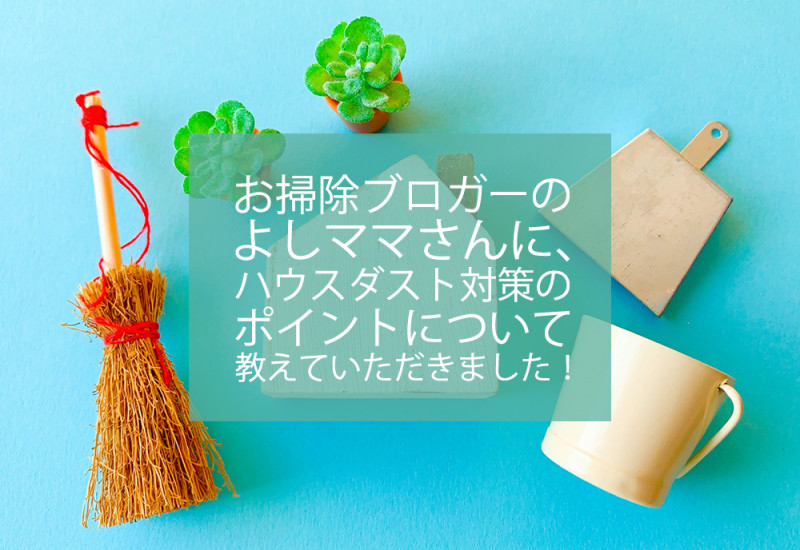
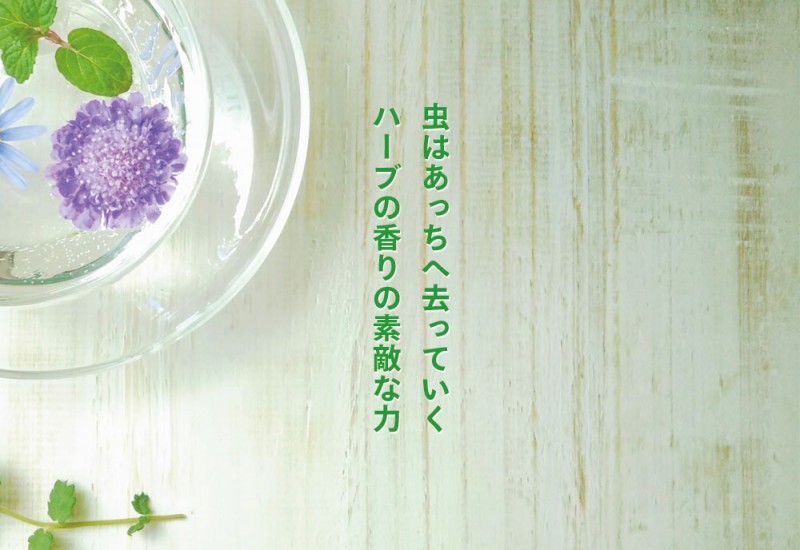
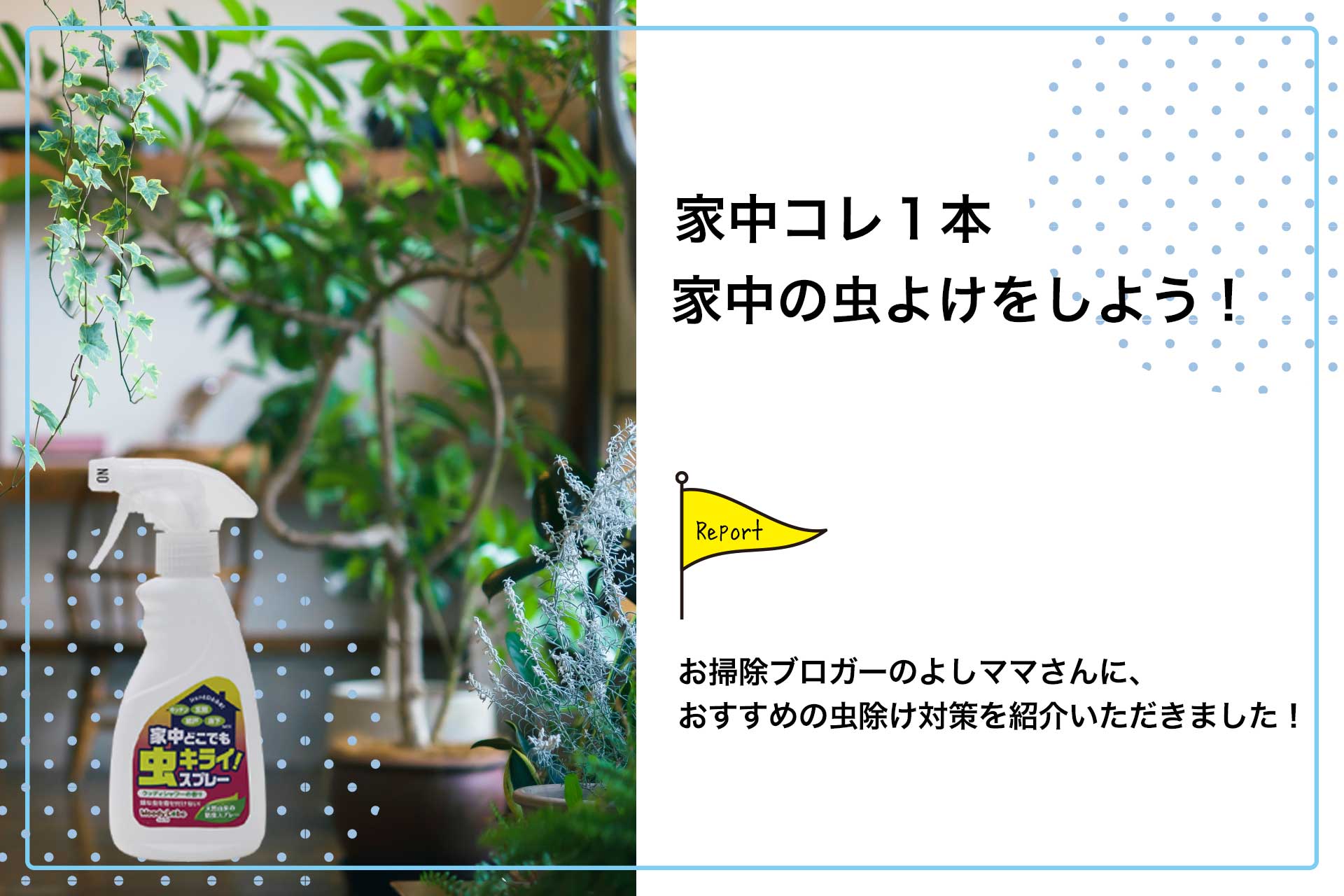
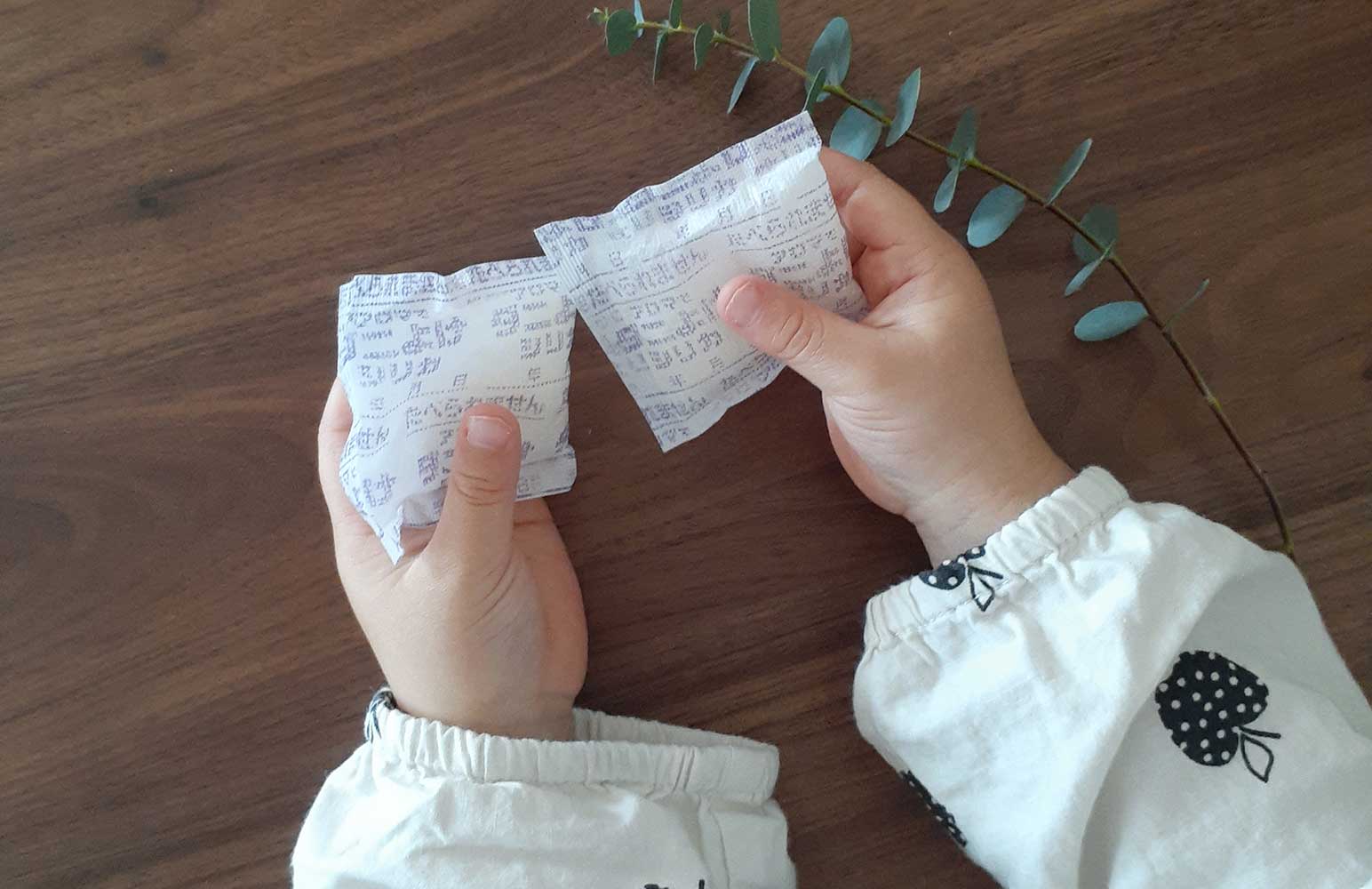

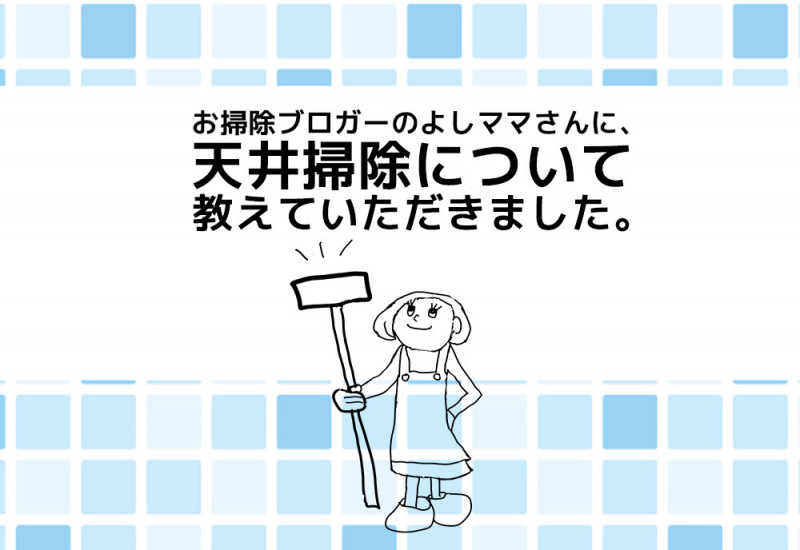
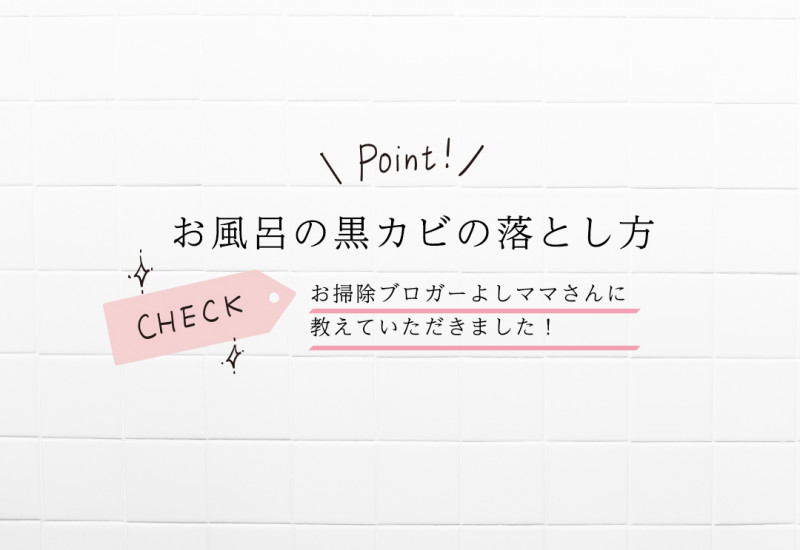



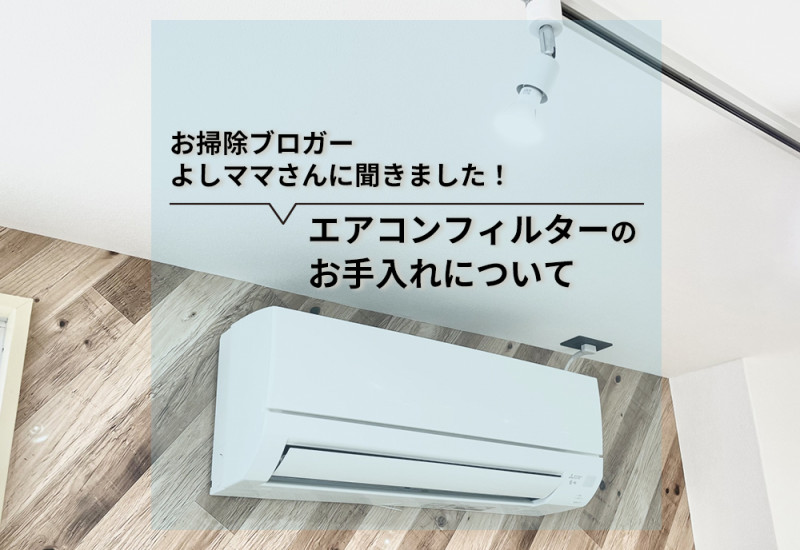
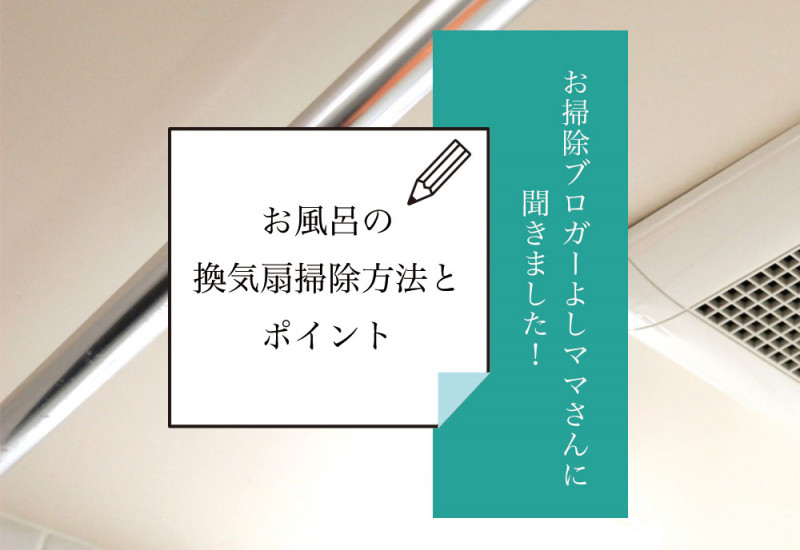

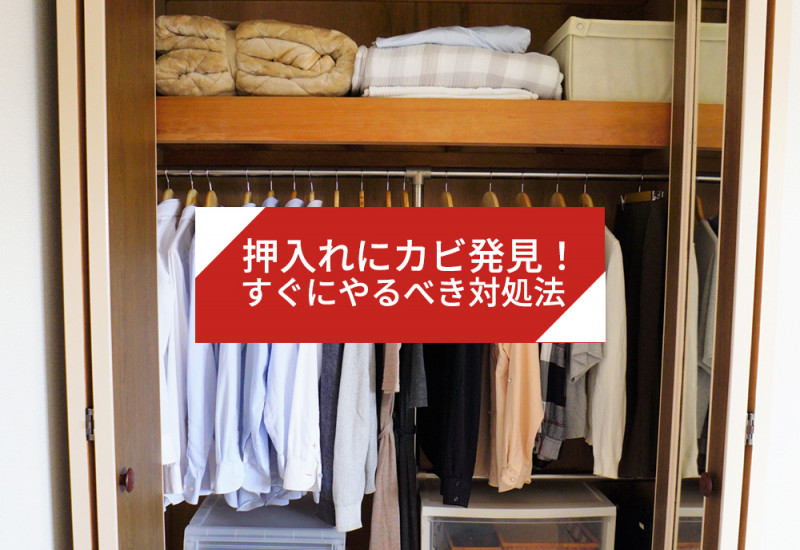



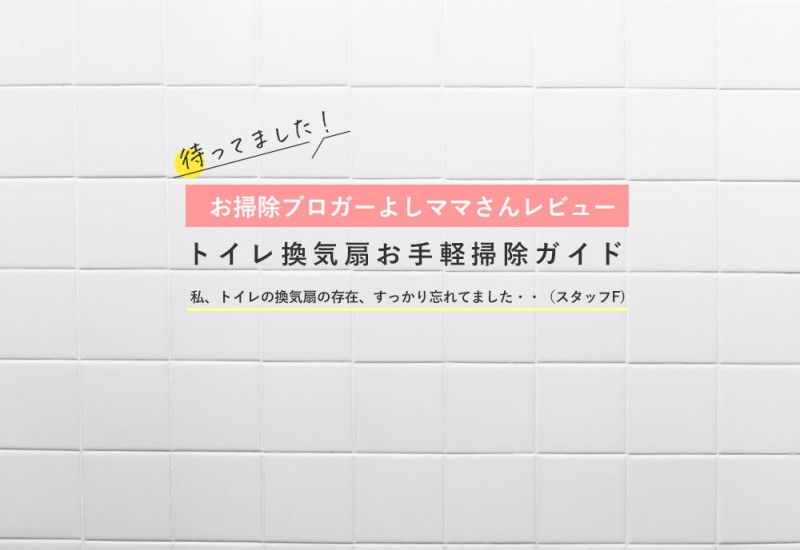
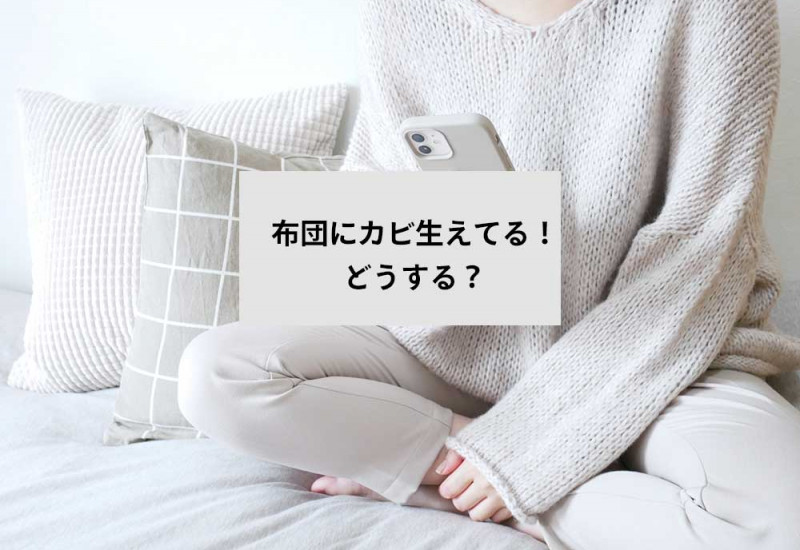
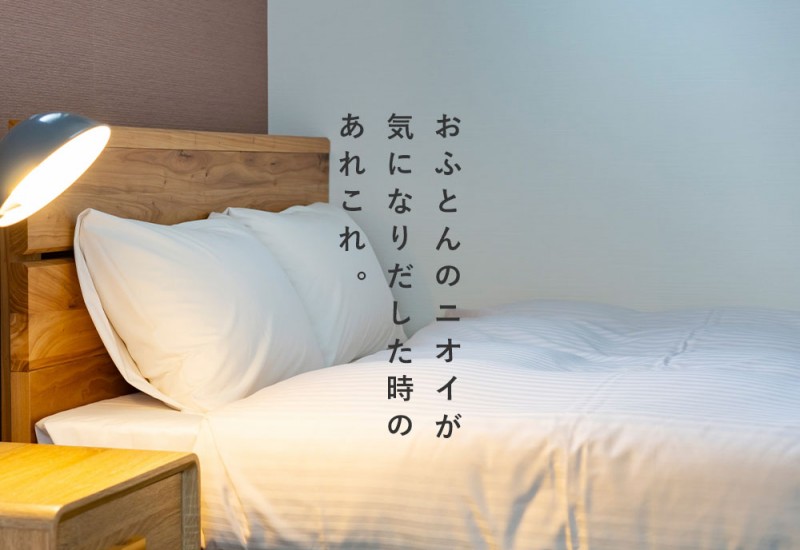
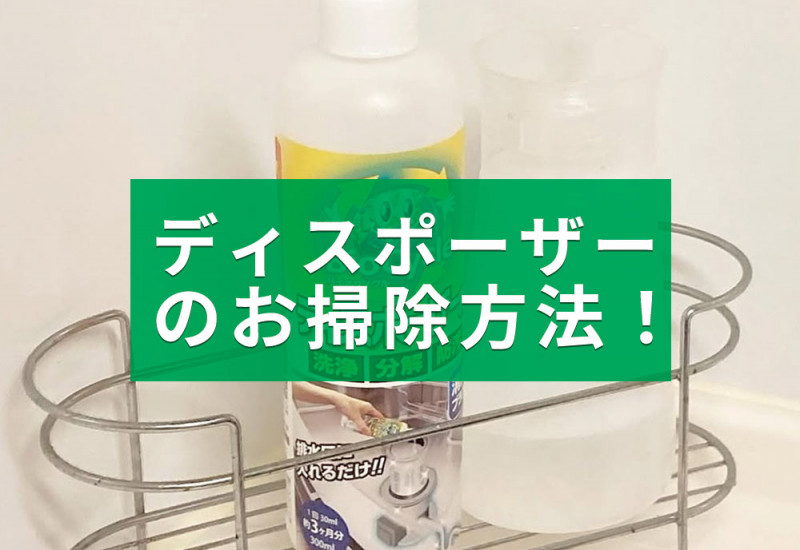
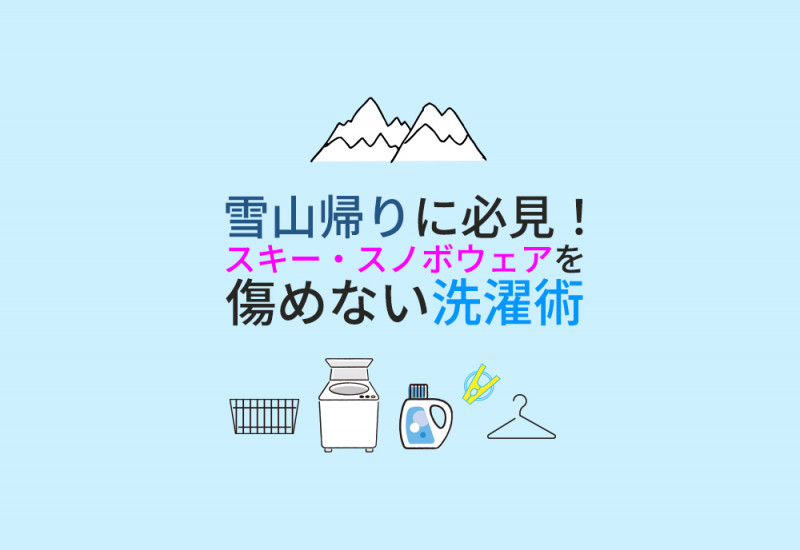




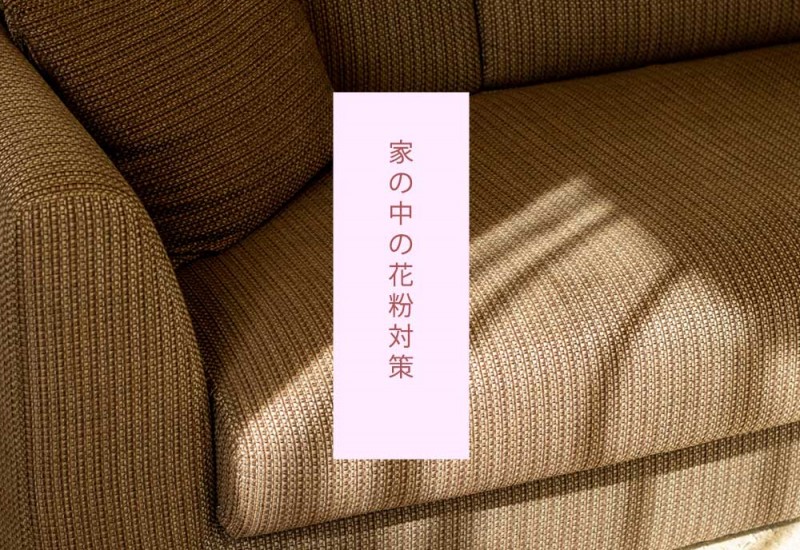
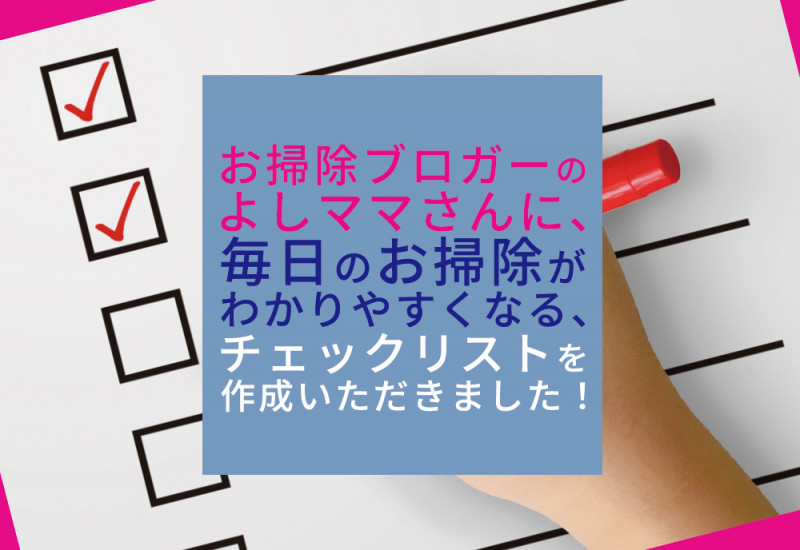

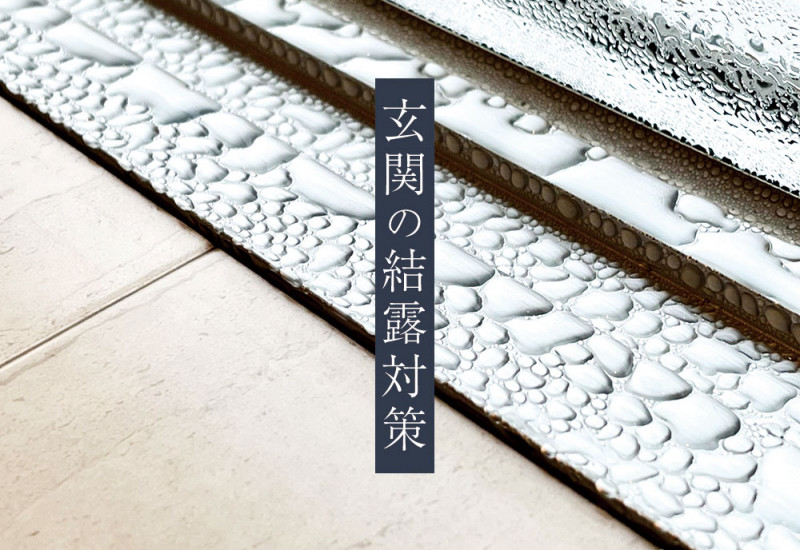



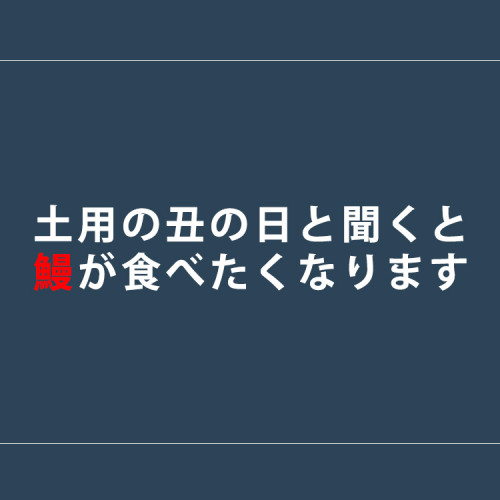

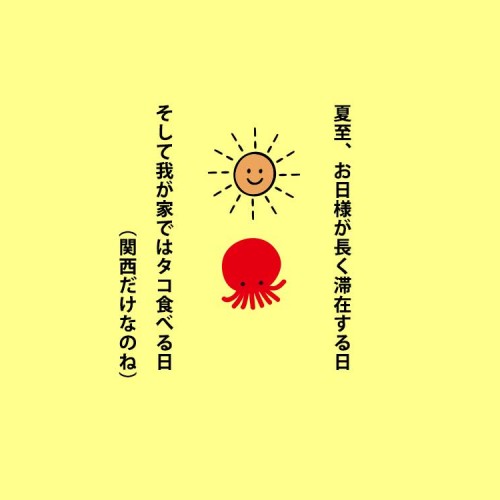

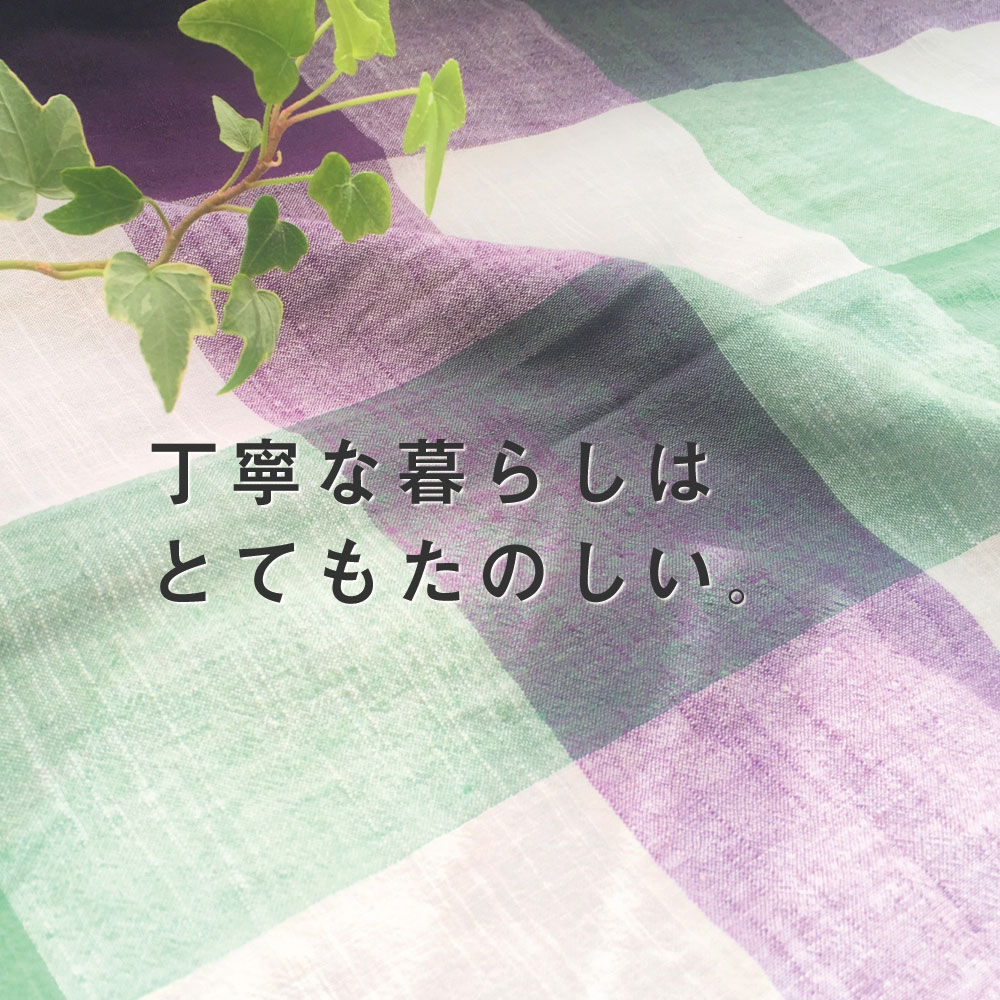

この記事へのコメントはありません。