改めて知りたい「お米」のこと 〜歴史や文化、稲の成長過程まで〜

2024年の夏に始まった「令和の米騒動」。お米の在庫不足や価格高騰などが続き、2025年になってもまだ尾を引いています。たしかにお米の価格は生活に直結する重要な問題ですが、そこだけに終始せず、主食という観点からお米そのものを見つめ直してみませんか。今回は、お米の歴史や文化、さらには稲の成長過程まで多面的に紹介します。
稲はこうして日本へやって来た 〜稲のたどって来た道〜

稲はどこで生まれ、どのようにして日本へやって来たのか? まずは稲のルーツを見ていきましょう。さまざまな文献や科学的な考察が進み、私たちが知る歴史的な情報には時代とともに変化しています。もしかすると、かつて学校で習ったあの説は覆っているかも!?
稲作の起源の有力説は「長江流域」
稲作の起源については、これまで数多くの学説が出されています。最新の研究によると、もっとも有力なのは、中国の「長江流域」説です。その根拠となるのが、長江下流域に位置する浙江省の河姆渡(かぼと)遺跡。およそ7,000年前の炭化米や稲作に使われたと思われる道具、稲穂の文様が描かれている黒陶(※1)などが出土しており、稲作はここからインド・アジア各地へ広がっていったと考えられています。
では、日本へはどのような経路をたどって伝わったのか、というと、これも諸説ありますが、有力視されているのは次の3つのルートです。
〜日本への稲作の伝播経路【有力説】〜
⚫️中国の江淮地帯(※2)から朝鮮半島南部を経て伝わった説
⚫️長江下流部から直接九州に伝わった説
⚫️中国南部から台湾・琉球を経由して南九州に伝わった説
※1 黒陶(こくとう)…中国の新石器時代の後期にあたる「竜山文化」を代表する黒色の土器。
※2 江淮(こうわい)地帯…長江と淮河(わいが)に挟まれた地域。
日本へ稲作が伝わったのは「縄文時代」

日本で稲作が始まった時期は、長らく「弥生時代」とされてきましたが、近年の研究で「縄文時代の後・晩期」の可能性が高いことがわかってきました。
根拠のひとつにあげられるのが、佐賀県にある菜畑(なばたけ)遺跡です。この遺跡は、縄文時代前期から弥生時代中期にかけての遺物が多く出土しており、縄文時代晩期の地層からは水田遺構が見つかりました。現時点では日本最古の水田遺構です。このことは、遅くとも縄文時代晩期には稲作が伝来していたことを示します。
注目すべき点はもうひとつ。その当時の稲の栽培方法は「焼畑スタイル」が主流だと考えられてきましたが、地域によってはすでに水田耕作も始まっていたことが明らかになりました。弥生時代に入ると、水田耕作は本格的になり、日本各地へ急速に広がっていきます。
社会、経済、文化に大きな影響を与えたお米 〜稲作の歴史と日本の成り立ち〜

日本各地に広がり、定着していった稲作。単に食料生産の手段というだけでなく、富や権力の象徴を意味するようになります。ここからは、社会や国家の成り立ちにも密接に関わる稲作の歴史をたどっていきましょう。
食料を「獲る」から「生産する」へ大転換 〜縄文から古墳時代〜
稲作が伝わる以前、食べ物は主に狩猟・採取により自然界から調達していました。主食は、クリやクルミ、ドングリなどの堅果類(けんかるい)だったといいます。それらの痕跡は弥生時代の遺跡にもしばしば見られることから、稲作伝来後すぐに主食がお米へと置き換わったわけではないと推測されています。この時期は、いわば移行期間。食料を「獲る」から「生産する」へ、主食が「堅果類」から「お米」へと大きく変わっていく時期だったといえます。古墳時代には、水路の整備が行われ、広範囲に田んぼがつくられるようになりました。
富や権力の象徴となっていったお米 〜飛鳥時代から鎌倉時代〜
お米を「税」として徴収するようになったのが、飛鳥時代です。「班田収授の法」が導入され、国が口分田(くぶんでん=田んぼ)を分け与えるかわりに、人民は収穫したお米を「租(=税金)」として納めるシステムが出来上がりました。奈良時代に入ると、「墾田永年私財法」により開墾した個人が田んぼを永久に所有できるようになります。そのため、有力な貴族や寺社が競うように土地を開墾。私有地である「荘園」が広まっていきます。平安時代に入っても荘園は増え続け、次第に土地争いが起こるように。荘園の実質的な支配主であった有力な農民は、争いごとや税の取り立てなどから身を守ために武装し、武士団をつくって軍事力を強めていきます。鎌倉時代に武士が台頭し、貴族に代わって実権を握るようになったのは、このような背景がありました。お米は、単に食べ物というだけではなく、税として、ひいては富や権力の象徴になっていったのです。
お米をめぐる権力争いと経済基盤の確立 〜室町時代から江戸時代〜
室町時代に入ると、治水技術や農民の自治組織である「惣(そう)」が発達します。やがて農民は荘園という枠を超えて団結し、大規模な一揆を起こすように。大規模化した一揆は、幕府を弱体化させるほどのものでした。こうして世は乱れ、戦国時代に突入。大名たちはいかに領土を拡大し、お米の収量を上げるかに心血を注ぎます。お米をより多く生産できる土地を持つことは、経済・軍事・政治的な力を持つことを意味したからです。この概念はその後も基本的には変わらず、江戸時代に至ります。徳川幕府は、各地を治める藩をお米の石高(こくだか=生産量)で格付けしました。
このように、江戸時代でもお米は経済の基盤でしたが、必要な物資を購入するには現金化する必要がありました。そのため、幕府米や藩米を換金する商人があらわれ、米相場を決めるようになっていきます。こうして力を持つようになった商人は経済を支配しはじめ、町人文化も花開いていくのです。
お米が育んだ日本の文化
お米は、祭祀とも深く結びつき、豊かな文化を育んできました。豊作を祈る歌や踊りはさまざまな地域で独自に発展し、秋にはお米の収穫を祝うお祭りが全国各地で催されます。食文化の中核を担うのもお米です。お祝い事には欠かせないお赤飯、お正月の行事食であるお雑煮、節句に食べるちまきなど、ハレの日の食卓を彩ります。そもそも、「和食」はごはんを中心とした食事スタイル。栄養バランスに優れているだけでなく、「自然を尊ぶ」日本人の精神性に根ざした食習慣として、2013年にはユネスコ無形文化遺産に登録されています。お酒や味噌、醤油、酢など調味料の原料でもあるお米。日々の暮らしのなかに米文化は息づいています。
おいしいお米ができるまで

「米」という字を分解すると「八」と「十」と「八」に分かれ、八十八と読むことができます。そのため、昔からお米をつくるには、88もの手間がかかるといわれてきました。実際に88の工程があるというよりは、大変さや苦労の比喩表現ではありますが、機械化が進んだ現代でも、30以上もの工程があるそうです。ここでは、お米ができるまでの過程を紹介します。
3月~種の準備
おいしいお米をつくるための種の準備が始まります。次のような作業を行います。
- もみを「塩水選」する
※塩水を使うのは、中身の詰まった重い粒とそうでない粒を見分けるため。重い粒は底に沈むので、それを種もみとして使います。 - 種もみを消毒する
- 種もみを水につける
※芽が出やすくなるように、1週間ほど水につけて水分を吸収させます。
4月~育苗と土づくり
苗を育て、田んぼの土づくりを開始。うまい米は土づくりからといわれるほど、土づくりはとても重要な作業です。
- 種をまく
※育苗箱という箱を使います。 - 苗を育てる
※育苗箱をビニールハウスなどに入れて育てます。 - 田んぼの土づくり(田おこし)
※田んぼの土をトラクターでやわらかく掘りおこし、肥料を入れます。
5月~田植え
いよいよ田植えですが、その前に「代かき(しろかき)」という作業を行います。ちなみに、「代」とは田んぼのことです。
- 代かき
※田んぼに水を入れ、機械を使って土がトロッとするまでかき混ぜながら、土の表面を平らにしていきます。苗の根が張りやすいようにする作業です。 - 田植え
6-8月~稲の成長を見守る
稲を育てる期間です。以下のようなさまざまな作業があります。
- 生育調査
- 除草
- 農薬の散布
- 追肥
- 水管理
- 中干し
※稲がある程度育つと、田んぼの水を抜いて土を乾かし、根を空気に触れさせます(酸素を供給するため)。出穂時期になると、水を抜いては入れるという作業を数日おきに行います。
9・10月~稲刈り、出荷
収穫期を迎えます。おいしいお米が消費者の元へ届くまでは、まだまだやることがあります!
- 稲刈り
※「コンバイン」という機械を使うのが一般的です。「刈り取り」から「脱こく」、「もみの選別」まで同時に行えます。 - もみを乾燥させる
※ライスセンターやカントリーエレベーターなどお米の乾燥施設に運ぶのが一般的です。 - もみすりして玄米にする
- 品質検査を行う
- 農業協同組合などを通じて市場に出荷する
お米が日本人の主食となった背景を見つめ直してみましょう
2024年の夏に始まった「令和の米騒動」以降、お米に関するニュースを目にする日が増えました。主食であるお米の価格は生活に直結する重要な問題です。だからこそ、価格の変動だけにとらわれず、なぜお米が日本人にとって大切なのか、なぜ「主食」となったのか。その背景を見つめ直してみませんか。
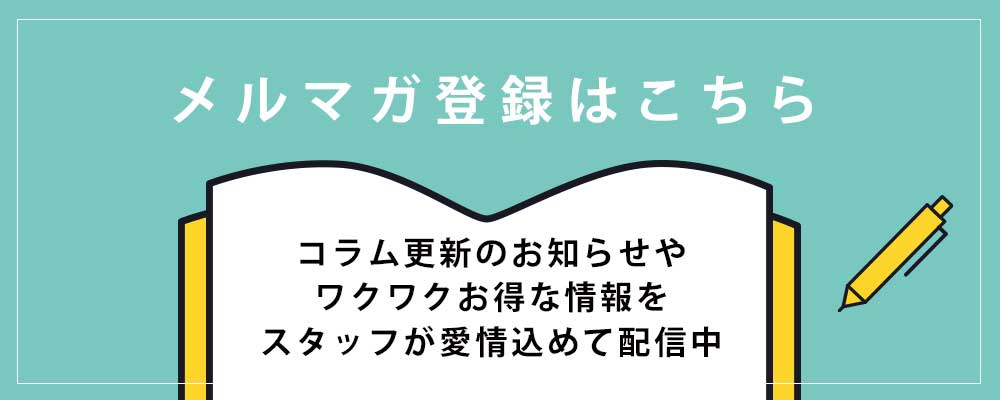
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
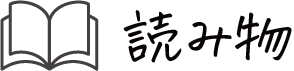
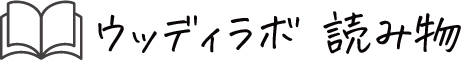


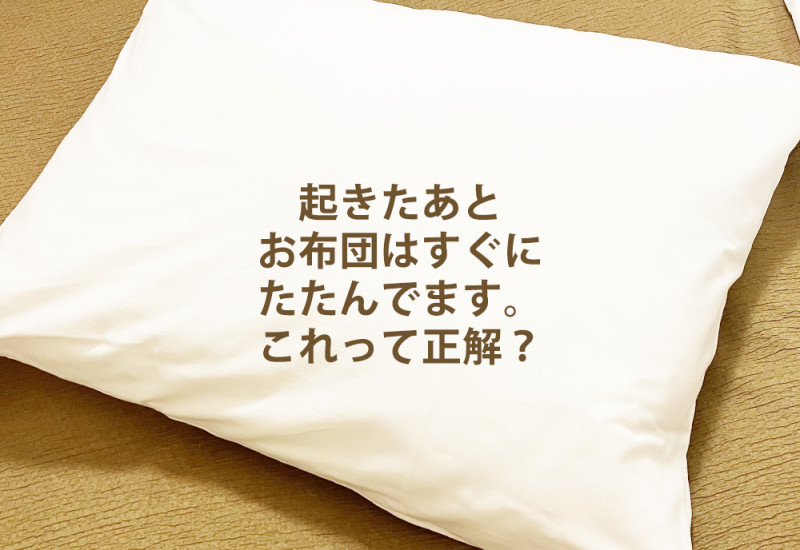
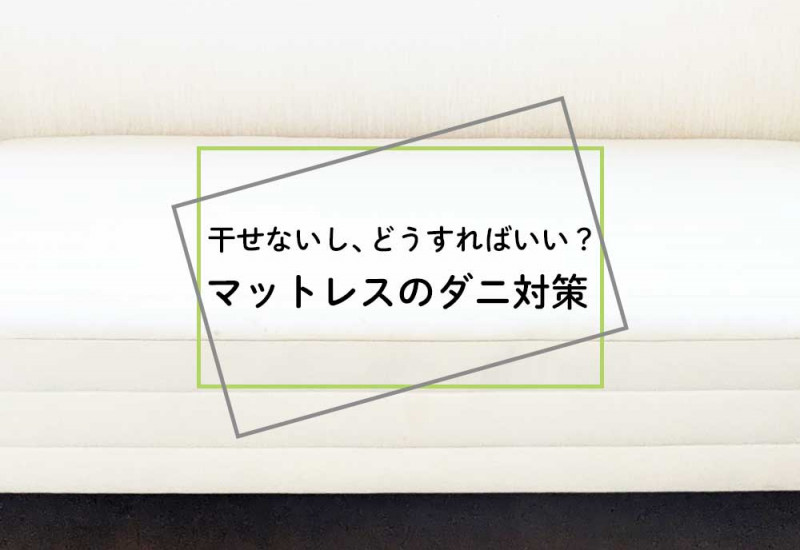
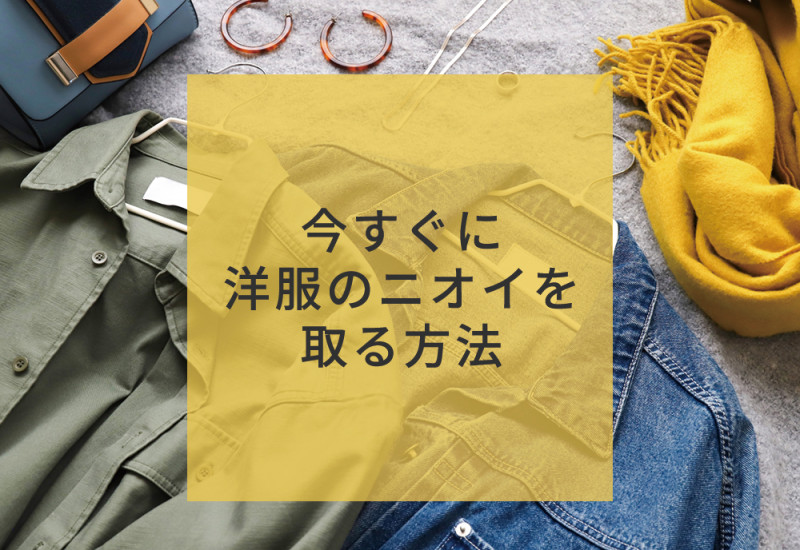
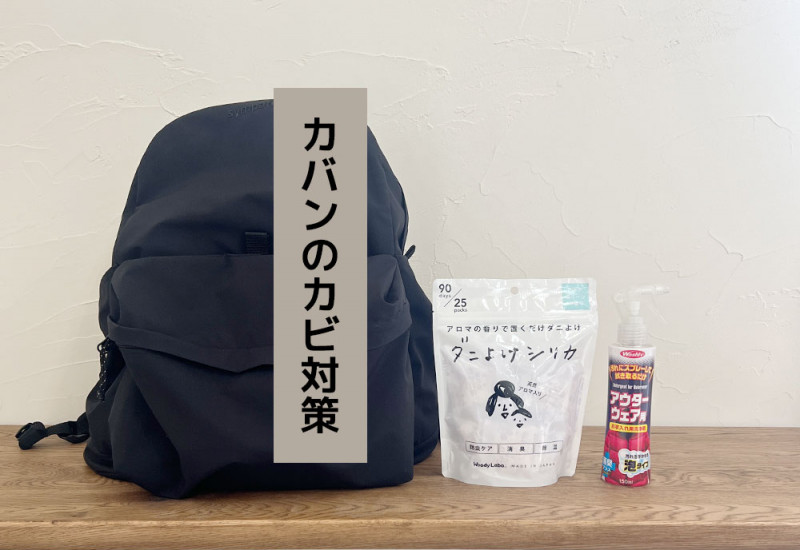


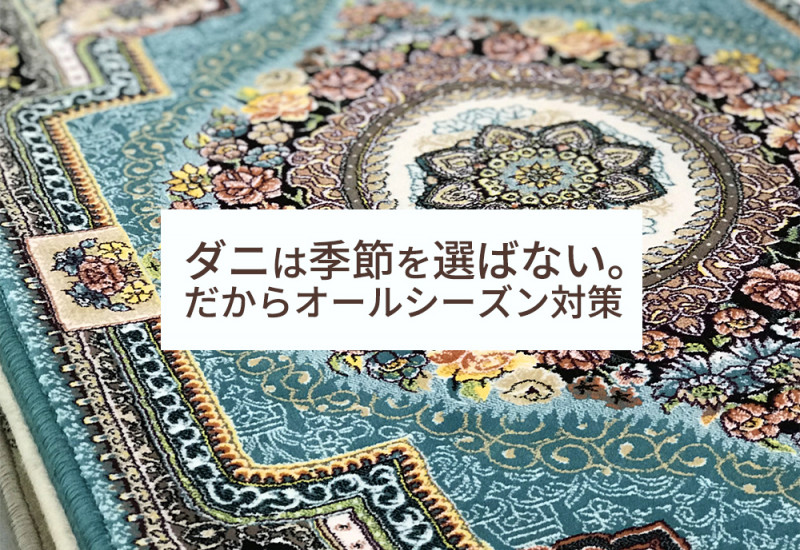


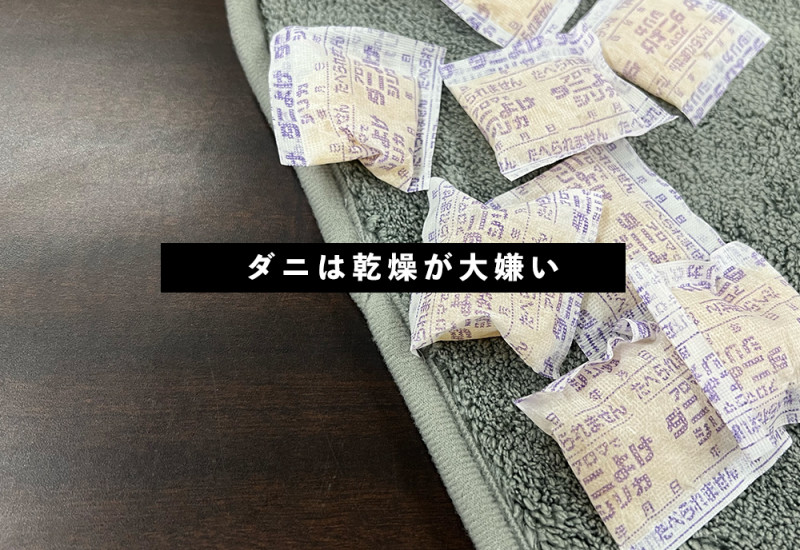


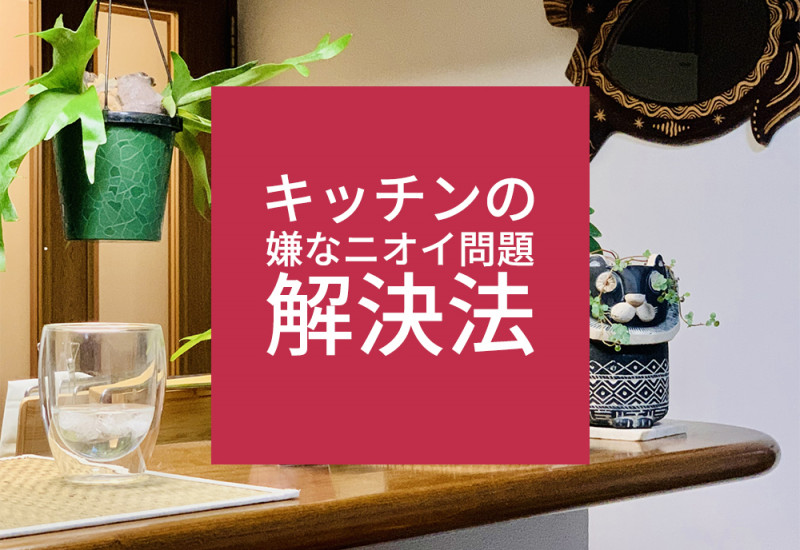
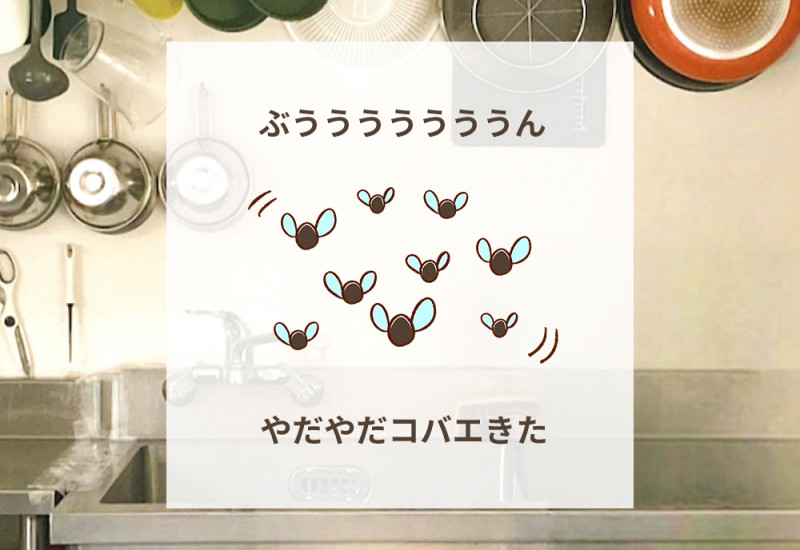

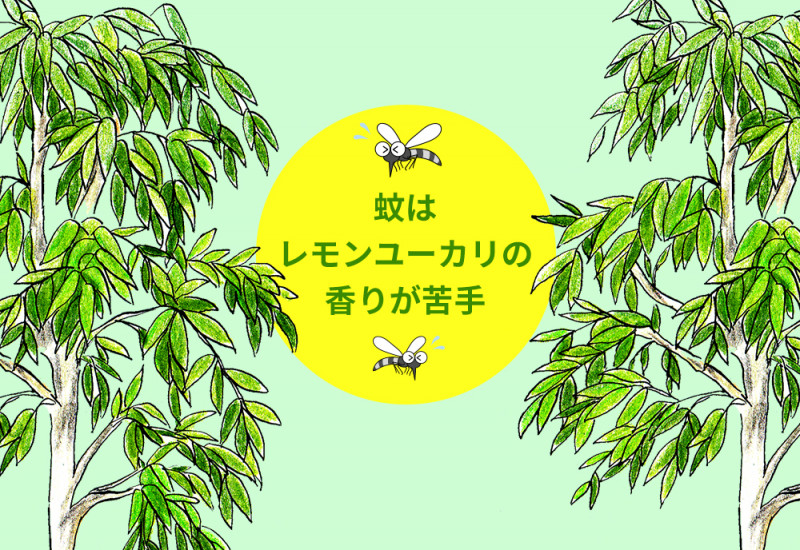
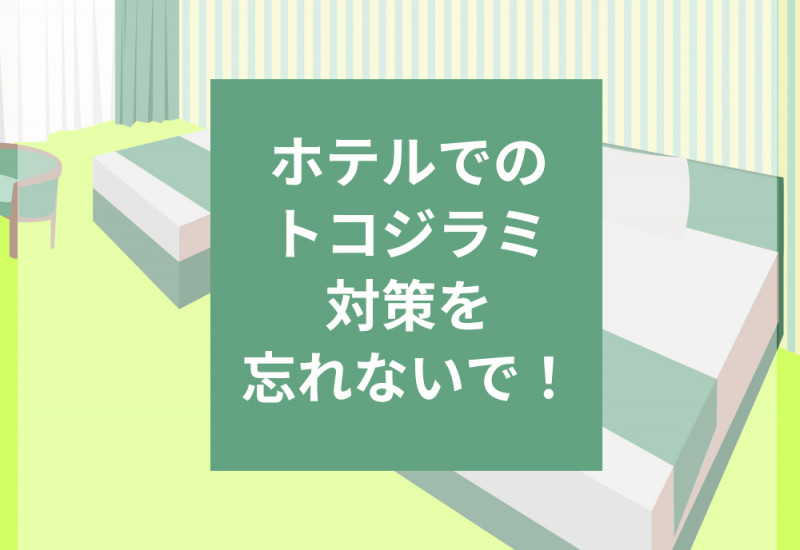



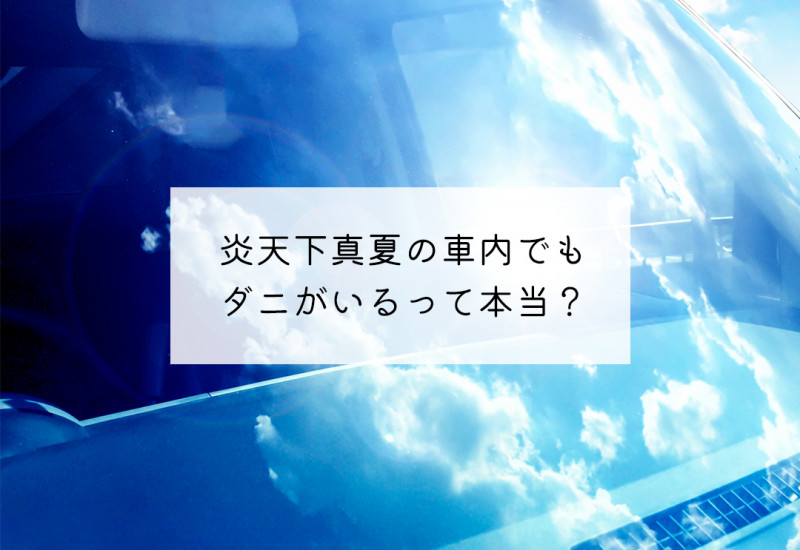
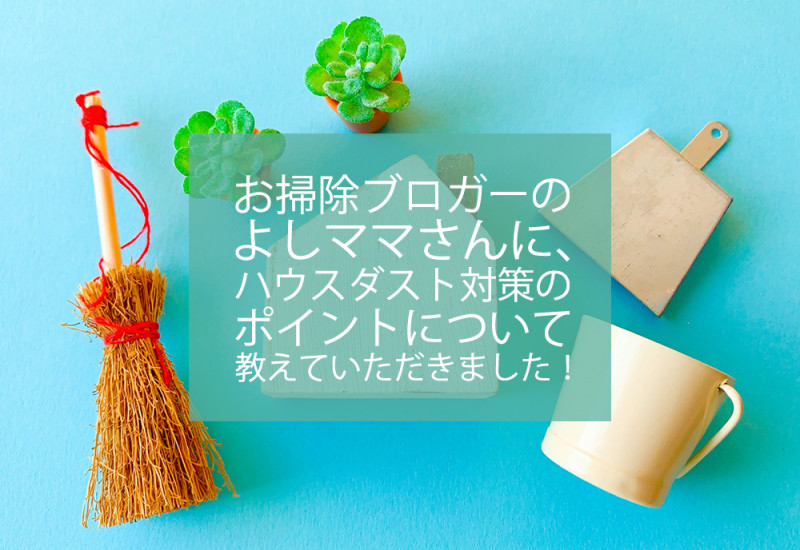
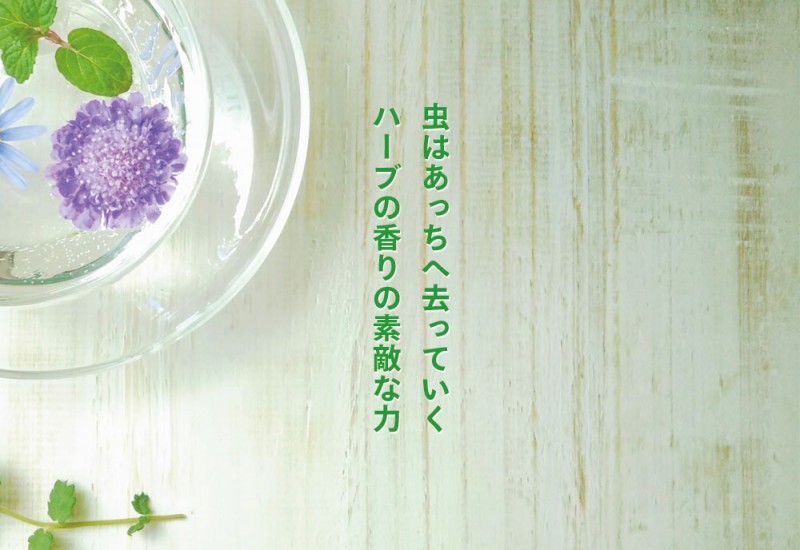
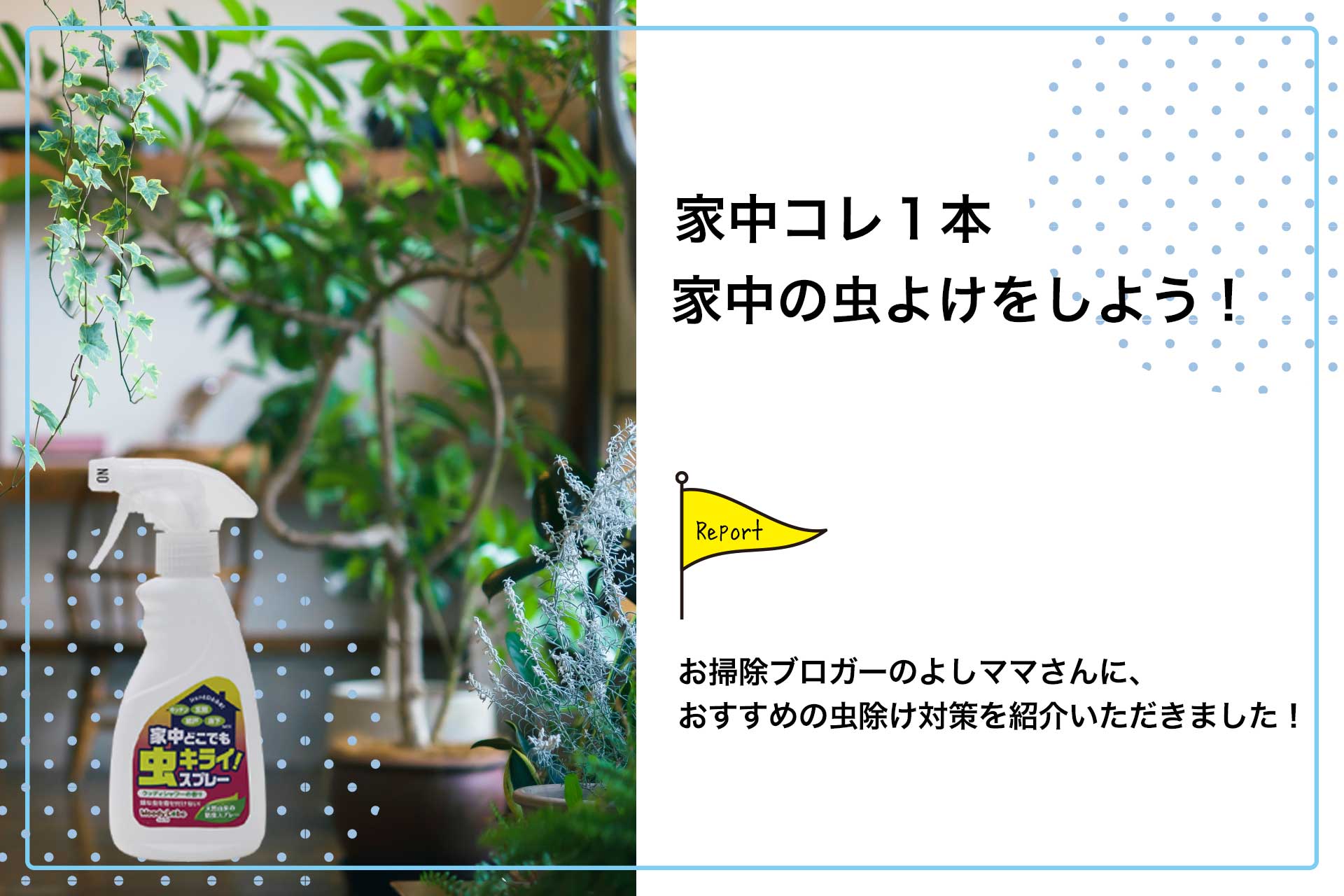
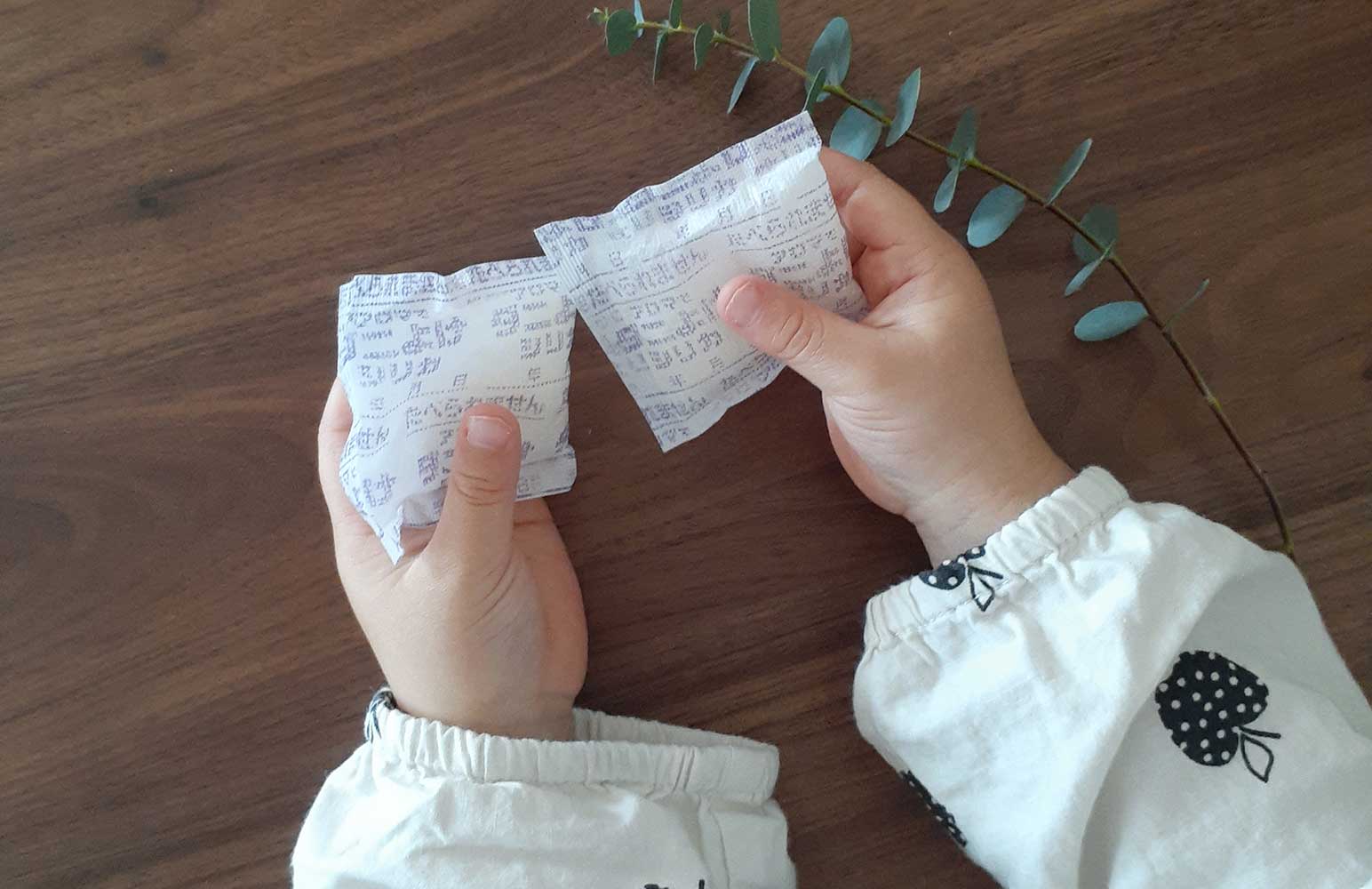

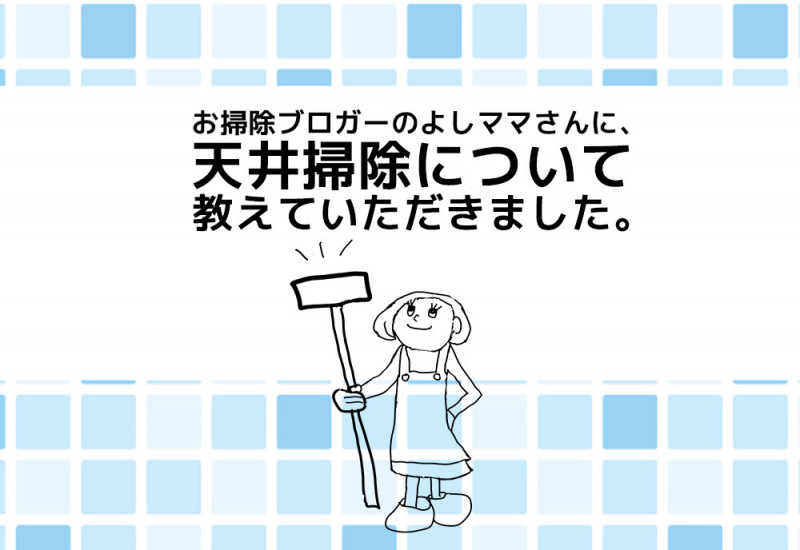
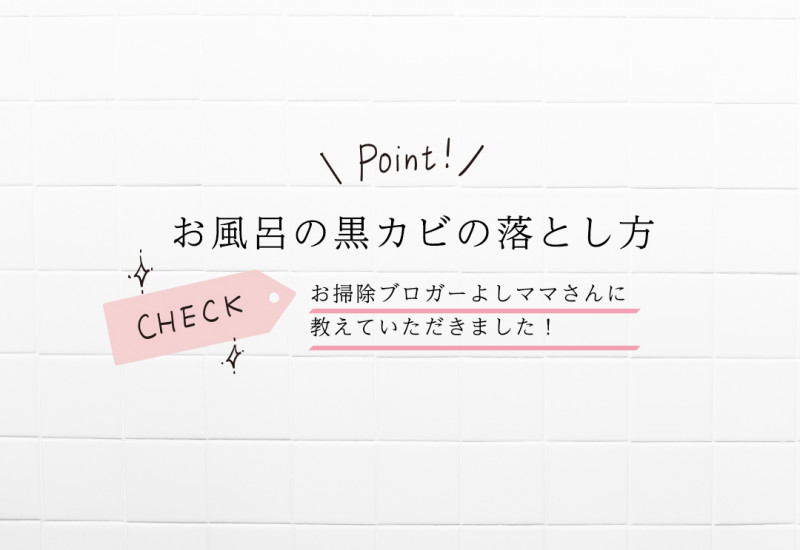



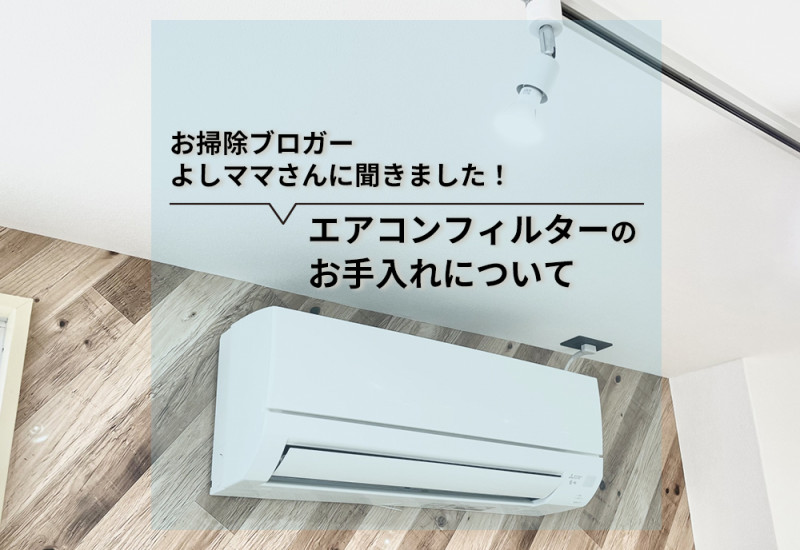
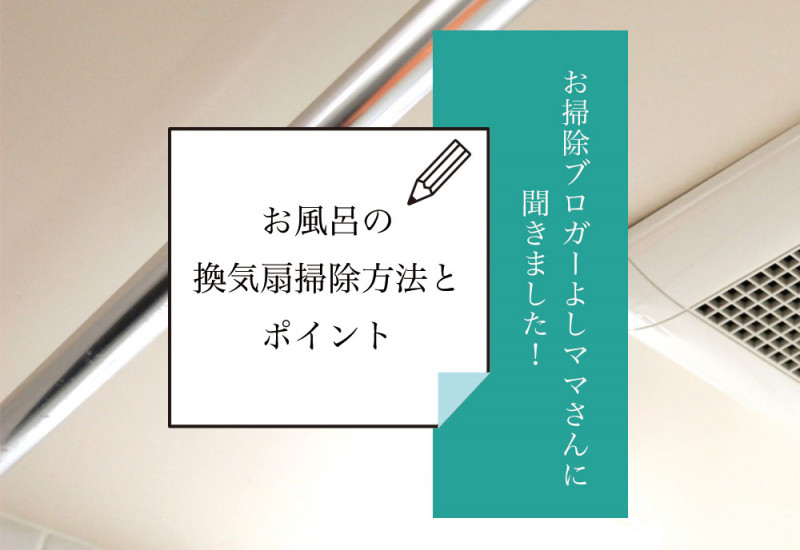

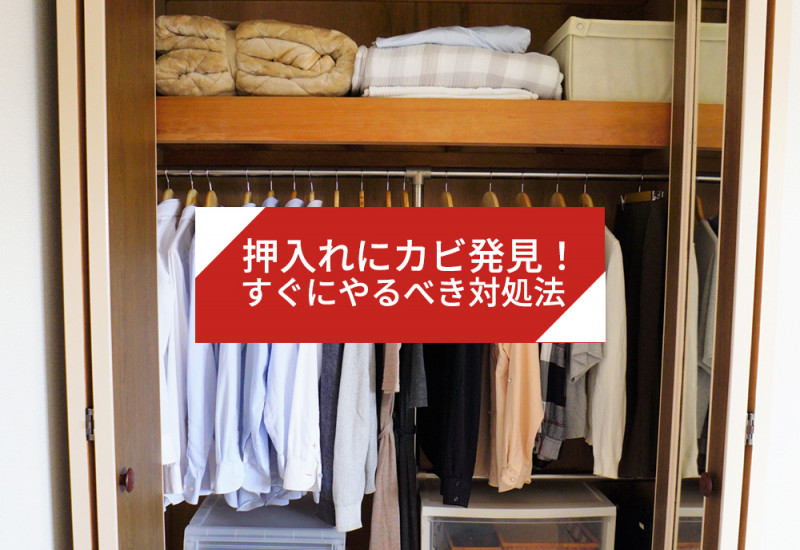



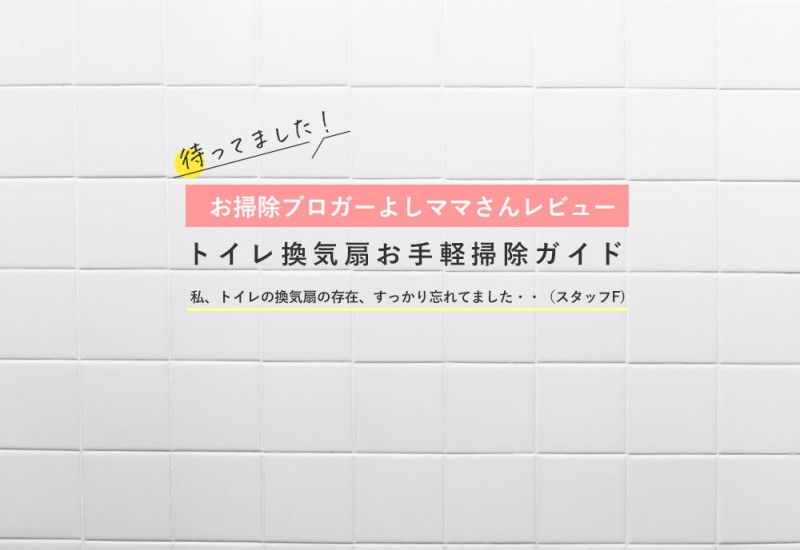
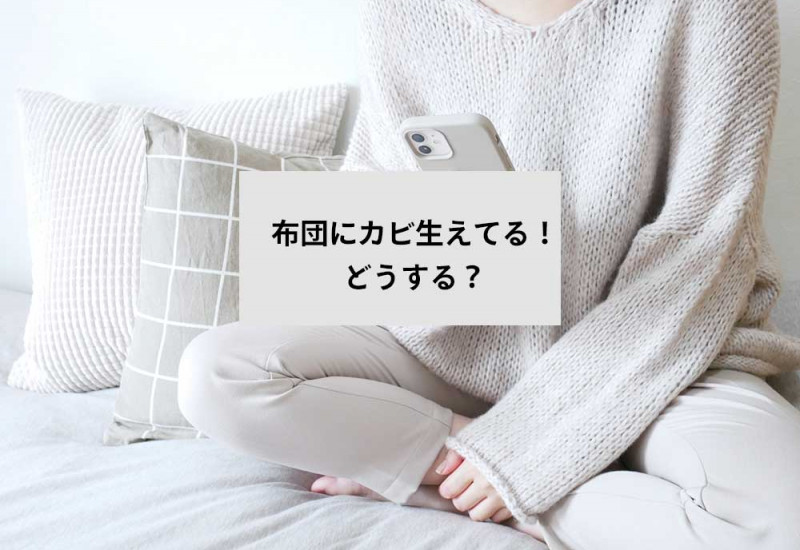
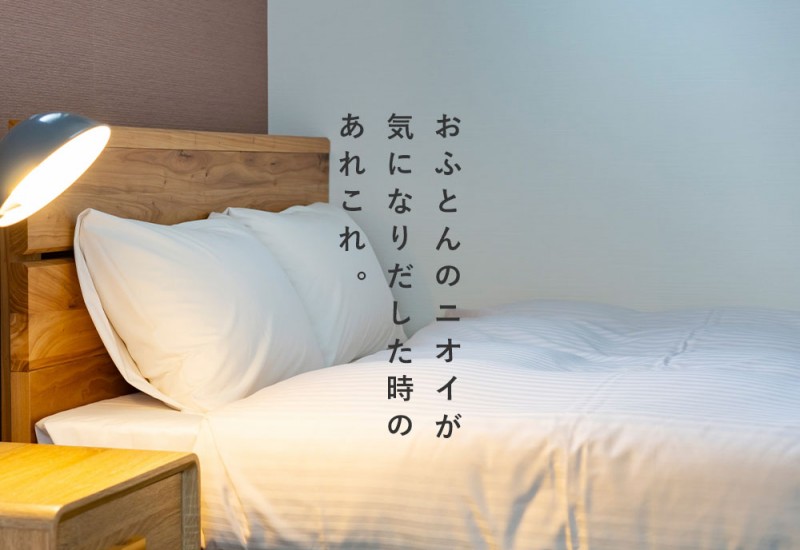
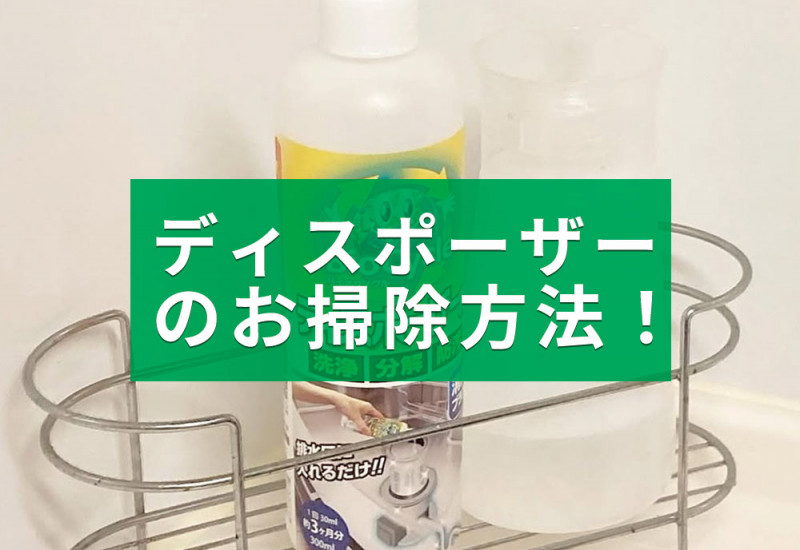

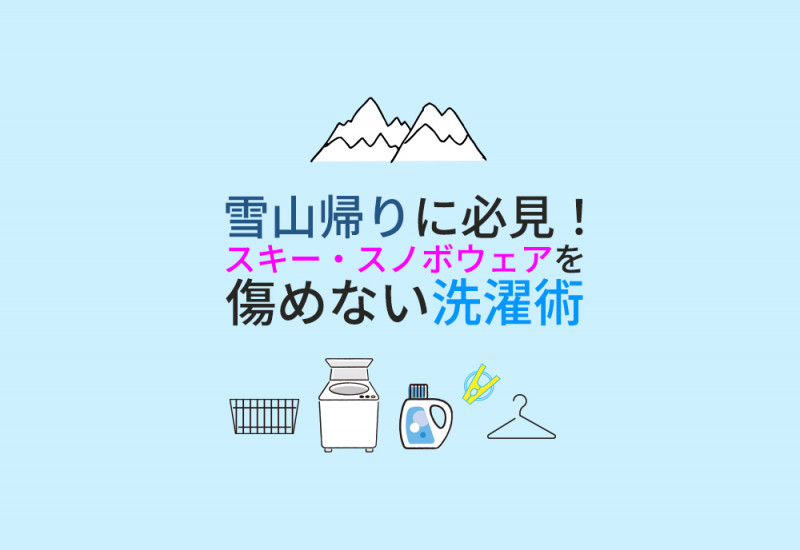
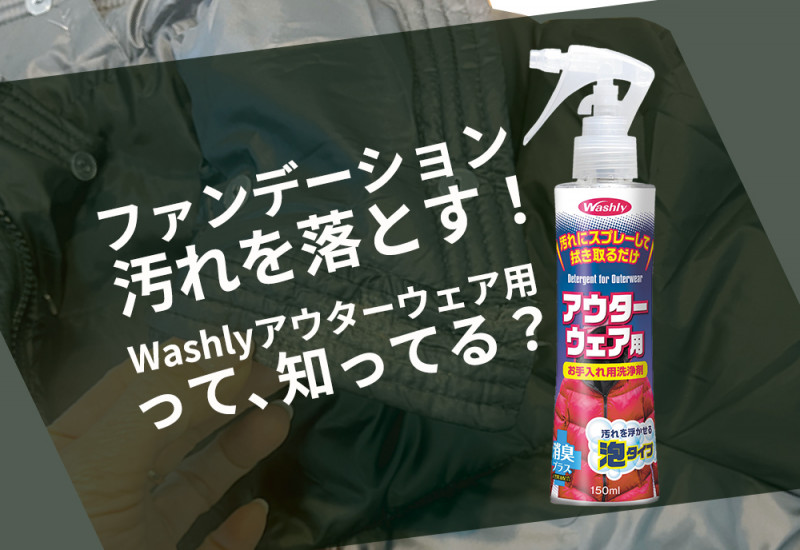


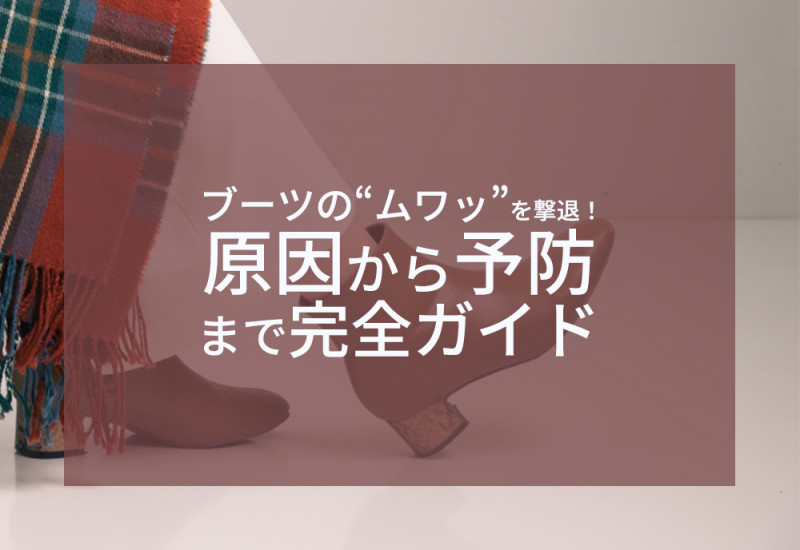
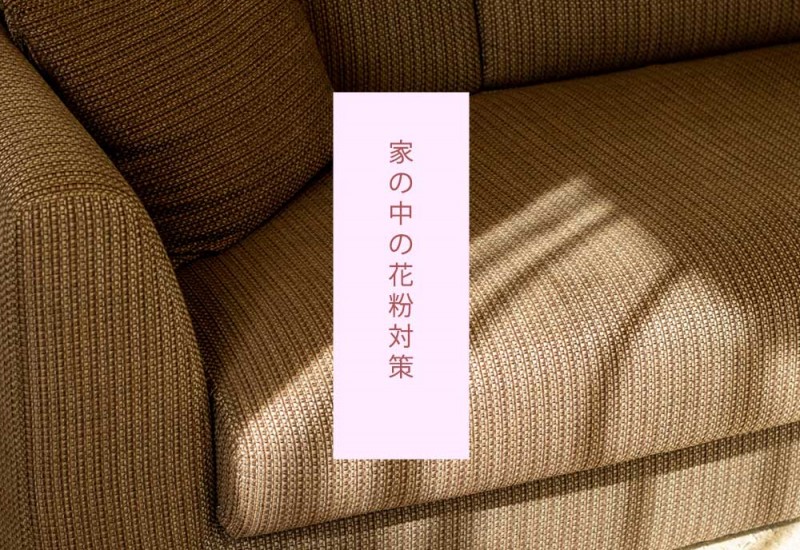

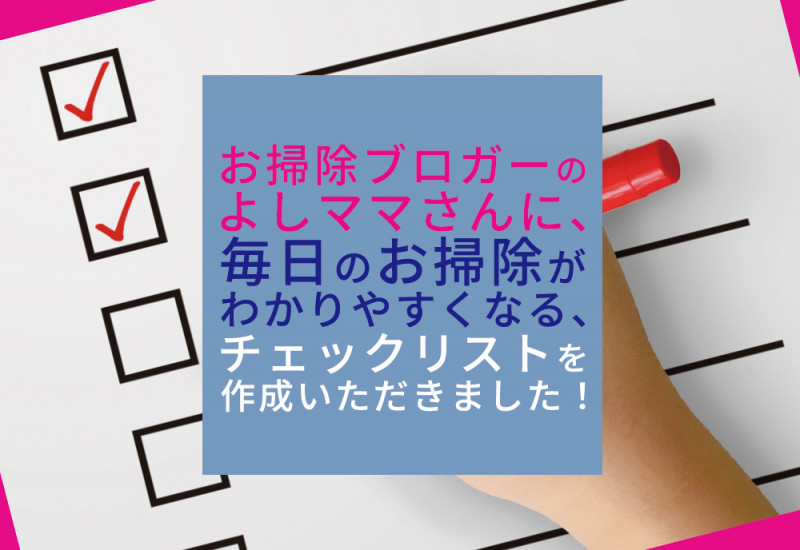

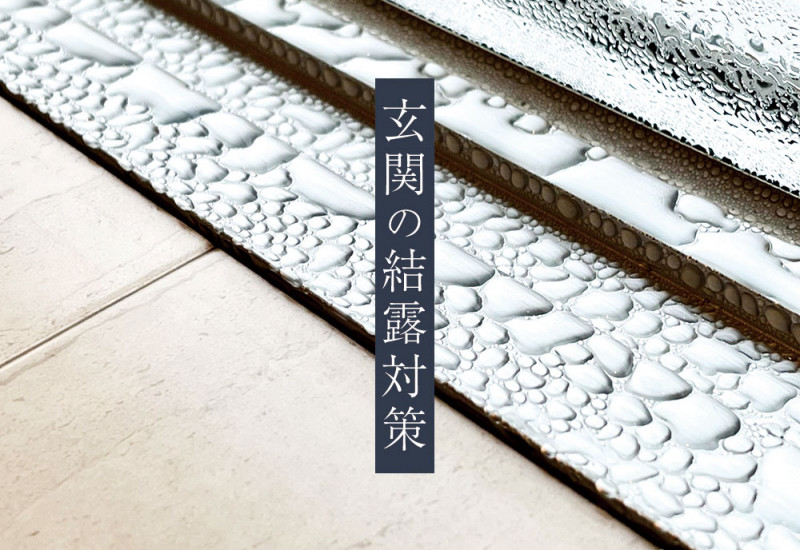

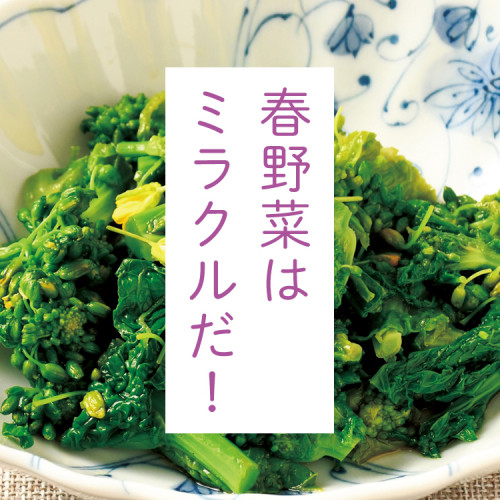


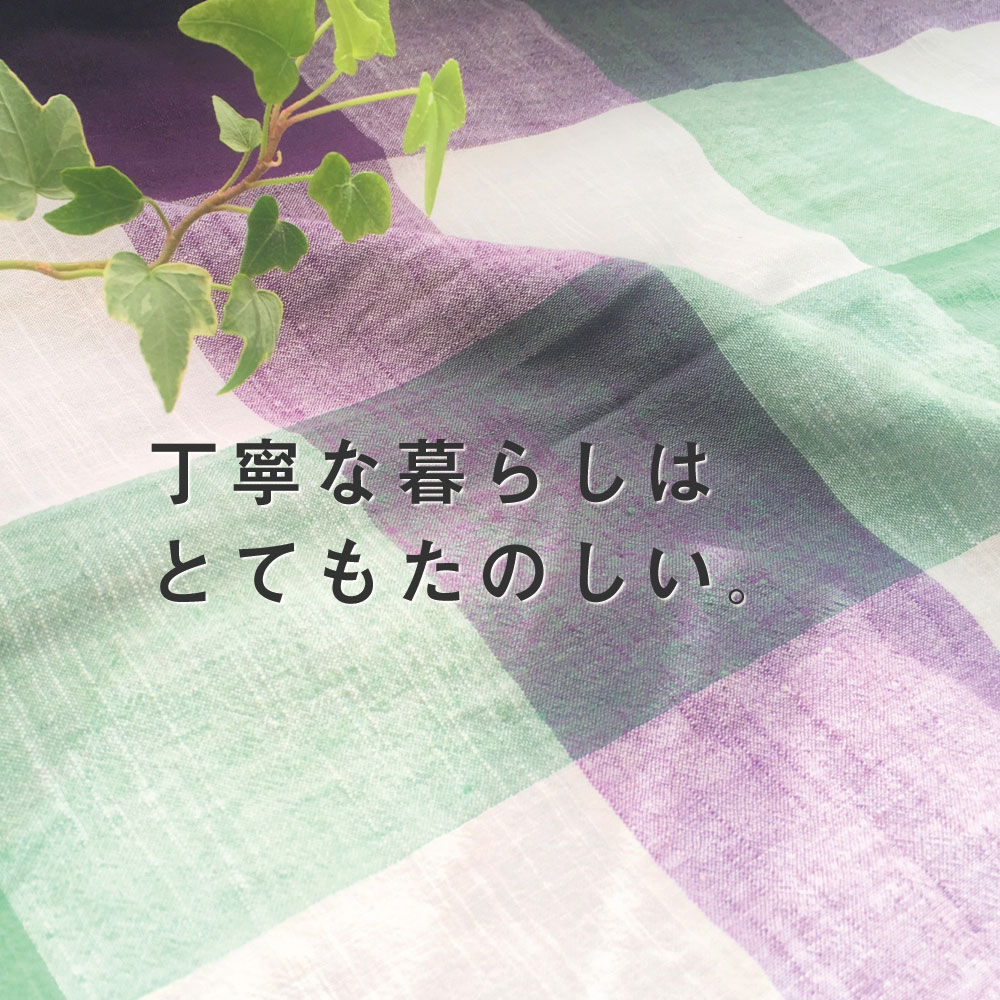
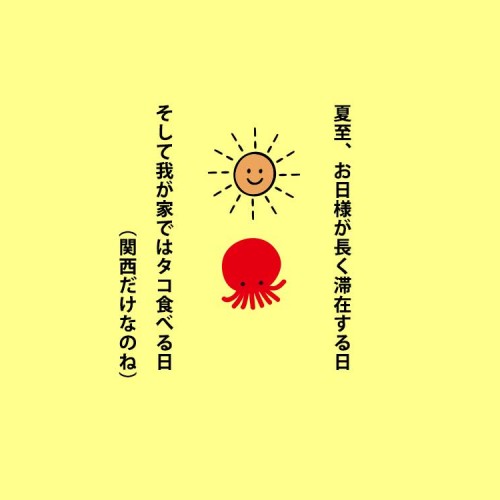



この記事へのコメントはありません。