断捨離でお部屋も心もスッキリ!〜春の断捨離のススメ〜
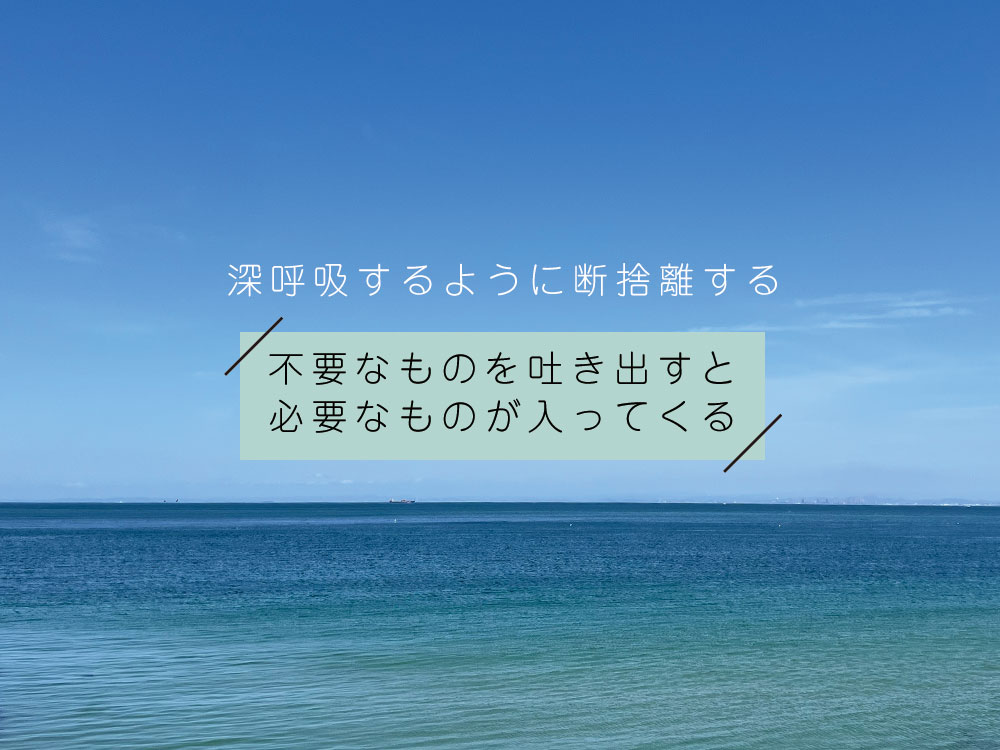
草木が芽吹き、心地よい風を感じる季節になりました。うららかな陽気に誘われて、何か新しいことにチャレンジしたいと思っている人も多いかもしれませんね。動き出したいけど、何をしたらいいかなと考えている人は、手始めに「断捨離」を楽しんでみませんか? 実は、春は断捨離をする最高のタイミングなんです。今回は、初心者でも気軽に実践できる断捨離について紹介します。
そもそも、断捨離とは?
いまではすっかり浸透している断捨離という言葉。ものを「捨てる」と同義で使われることがしばしばありますが、本来の意味は少し違います。さっそく見ていきましょう。
ヨガの思想がベースになっている断捨離

断捨離とは、もともとヨガ哲学の「断行・捨行・離行」を元につくられた言葉で、「ものにとらわれずに生きていこう」とする考え方のこと。それぞれの行法には、次のような意味があります。
<ヨガの3つの行法哲学>
- 断行…入ってくるいらないものを断つ
- 捨行…今あるいらないものを捨てる
- 離行…執着しているものや事柄から離れる
上記の考え方を応用し、誰もが実践できる「片付け」に落とし込んだのが「断捨離」です。捨行のイメージばかりが先行しがちですが、それだけではないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
断捨離が春におすすめな理由
年末の断捨離と並び、春も絶好のタイミングといわれるのは、次のような理由があります。

- 「要不要」がクリアになる
日本では、春に新学期や新年度がスタートします。入園、入学、就職、転勤など生活環境が大きく変わる時期でもあり、ライフスタイルの見直しをする方も多いことでしょう。このタイミングだからこそ、必要なものと不要なものが見えやすくなります。
- ポジティブな気持ちで「お別れ」がしやすい
長く使ってきたものを捨てるときは、悲しみや罪悪感、寂しさといった負の感情が湧き上がるもの。気持ちが前向きになる春は、ものとの別れもポジティブに受け止められる傾向があるそうです。
- 春の衣替えがきっかけとなる
衣替えは断捨離のいいきっかけになります。とりわけ春は、かさばりがちな冬物のスリム化を図れるチャンス。シーズン中に使わなかったアイテムを洗い出すなど、クローゼットの中を見直せるのもプラスαのメリットです。
初心者も気軽にできる!〜断捨離の基本的な手順〜
春は断捨離しやすい季節とはいえ、なんとなく面倒くさそうなイメージもあるかもしれません。でも、手順を踏めば、意外と簡単に取り組めるものです。ステップにそって、実践してみましょう。
断捨離ステップ① 片付ける場所を決める

まずは、片付ける場所を決めるところから。ここも!あそこも!と一気に手をつけるのはNG。家の中をエリアごとに分けて考えてみましょう。「キッチン」「リビング」など部屋ごとの単位では大きく感じる人は、キッチンの「引き出しの1段目」やリビングの「サイドボードの左扉の中」など、小さなところから始めてみるのもアリです。
| 〜ワンポイントアドバイス〜 引き出しやサイドボードといった小さな場所でも躊躇してしまう人は、お財布やカバンなど身の回りのものから始めてみるのもいいでしょう。 |
ステップ② 決めた場所にあるものをすべて出す
断捨離する場所が決まったら、そこにあるものをいったんすべて取り出して、全体量を把握します。何が、どれだけあるかを確認することが大切だからです。なので、「何か捨てられそうなものはないかな?」と探しながら不用品だけを取り出すのではなく、まずは全部取り出してくださいね。
ステップ③ 出したものを3つに分類する
すべてを取り出したところで仕分けします。広げたものを「必要」「不要」「保留」の3つにカテゴライズしていきます。ただ、要不要の分類が難しいですよね。迷ったときには、以下に掲げた判断基準の一例を参考にしてみてください。
<判断基準の例>
| 【必要】 | 【不要】 |
| ・頻繁に使っているもの ・使う頻度は少ないものの、必ず使うもの ・見るだけで楽しい気分になるもの | ・壊れているもの ・1度も使っていないもの ・1年以上使っていないもの |
ステップ④ 「必要」と判断したものを収納する
ステップ③で「必要」と判断したものは、ジャンル分けしながら収納していきます。ジャンル分けといっても難しく考えることはありません。使用頻度の高いもの、低いものに分けるくらいでOKです。
ステップ⑤ 「不要」と判断したものは処分する
ステップ③で「不要」と判断したものは、処分します。その手段は、下記のとおり大きく分けて3つあります。
- 捨てる…地域のルールに従って出す、もしくは不用品回収業者に依頼する。
- 譲る…新品か新品同様のもので、家族や友人の趣味に合えば引き取ってもらう。
- 売る…フリマアプリやリサイクルショップを利用する。
箱組する〜ワンポイントアドバイス〜
処分は期限を設けて行うこと。「譲る」「売る」場合は、自分の思いだけではスムーズにいかないこともあるからです。
ステップ⑥ 「保留」と判断したものはいったん寝かせる
取り扱いが悩ましいのが「保留」と判断したものです。後悔しないためにも、時間をおいて(半年から一年ほど)じっくり考えること。
| 〜ワンポイントアドバイス〜 無理に捨てようとするのは絶対にやめましょう。とくに、思い出が詰まったものは焦って判断する必要はありません。 |
断捨離がスムーズに進むコツと注意点
初心者でもスムーズに断捨離が進められるコツと注意点についても紹介します。
断捨離がスムーズに進むコツ

断捨離の最大のコツは、「一度に片付けようとしないこと」です。意気込んで一気に終わらせようとすればするほど、成功から遠のきます。まずは、愛用のポーチの中や引き出しの1段だけやってみる。それだって立派に断捨離なのですから、焦らず、着実にいきましょう!
〜【アイテム別】断捨離のコツ〜
⚫️洋服…1年着なかった服は手放す。
※1年に抵抗がある場合は3年を目処に自分なりの期限を設けましょう。
⚫️本…扱っている情報が古くなっているものは手放す。
⚫️書類…契約や権利に関わる重要書類以外は、基本的には処分しても問題ありません。以下に一例を紹介します。
| <読んだらすぐに捨てていい書類> | <一定期間は保管が必要な書類> |
| ・各種パンフレット、チラシ ・インターネット上で手に入る情報(取扱説明書や自治体のゴミ分別ルールなど) | ・公共料金(電気・ガス・水道など)の領収書 ・医療費の領収書 ・自治体や地域のお知らせ |
断捨離の注意点
不要な物を捨てることで、次のような物理的・精神的メリットが得られるのは確かです。
<物理的メリット>
・部屋がスッキリする
・必要なものが取り出しやすくなる など
<精神的メリット>
・片付けたという達成感(→自己肯定感アップ)
・スッキリとした部屋を見る爽快感
・心の余裕 など
一見すると良いことづくめですが、時として仇となることも。断捨離にはある種の「快感」が伴うため、それを求めるあまり、捨てる行為がエスカレートしていくことがあるからです。下記の項目のうち、3つ以上当てはまったら要注意です。「断捨離依存症」に陥っているかも?
<断捨離依存症チェックリスト>
・毎日、何か捨てないと落ち着かない
・必要なものまで捨ててしまう
・捨てることを家族にも強要する
・家族のものまで勝手に捨ててしまう
・贈り物が迷惑に感じる
・他人の家のことまで気になる
・ものが少ないことが正義だと思っている
・人生がうまくいかないのは、まだまだものを捨てていないからだと思う
など
断捨離依存症とは、もの捨てることに執着して、生活に支障をきたしている状態のこと。「ものへの執着」から離れるための断捨離が、「ものを捨てることへの執着」になっては本末転倒です。
断捨離依存症を防ぐためには、捨てることを目的にしないこと。自分にとって本当に大切なものを見つめ直し、「何を残すか」を目的に断捨離しましょう。あらかじめ断捨離の頻度を決めておくのも◎。おすすめは「半年に1度」といわれています。
断捨離で、新たな一歩を踏み出しましょう
春に行う断捨離は、年末と並んで絶好のタイミングといわれています。どちらも、新たな年度や年が始まる時期。心機一転してスタートを切れるという共通点がありますが、春ならではの利点も。まず、衣替えの時期と重なることです。漫然と入れ替えるだけなら単なる衣替えで終わりますが、必要・不要の視点を持つだけで、衣替えプラス断捨離までできてしまいます。なにも意気込んでするだけが断捨離ではありません。穏やかな季節のなかで、肩肘張らずに断捨離を実践してみませんか?
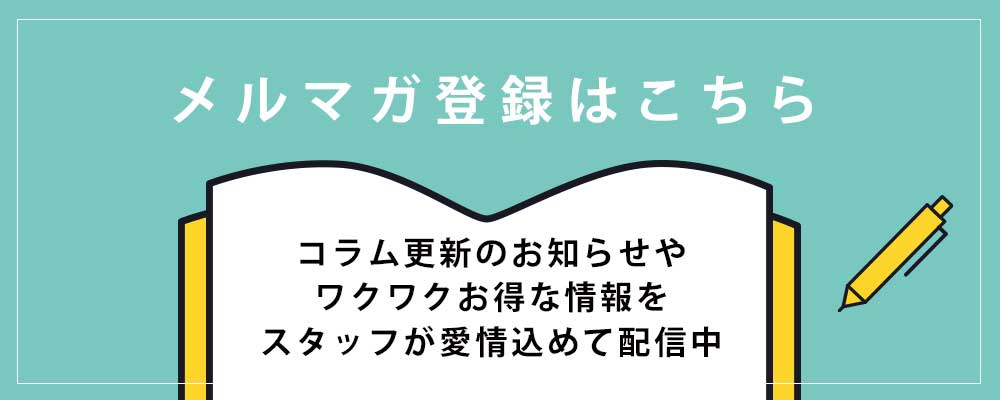
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
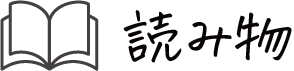
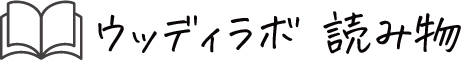


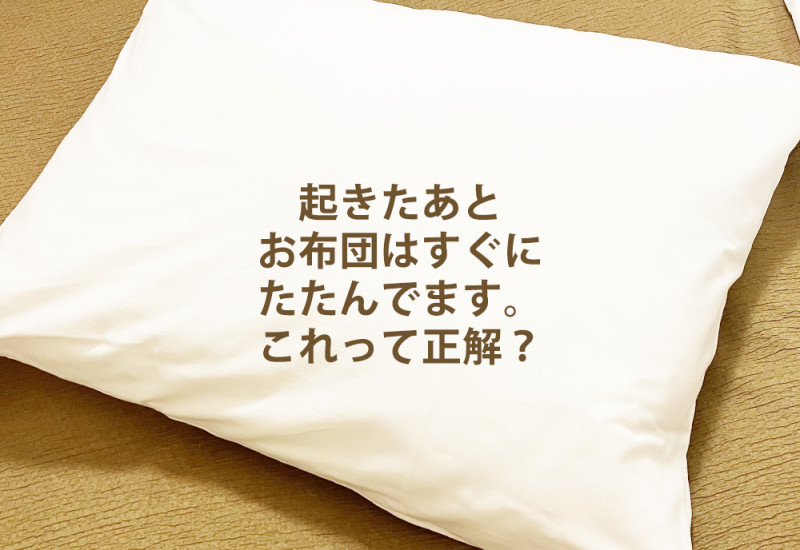
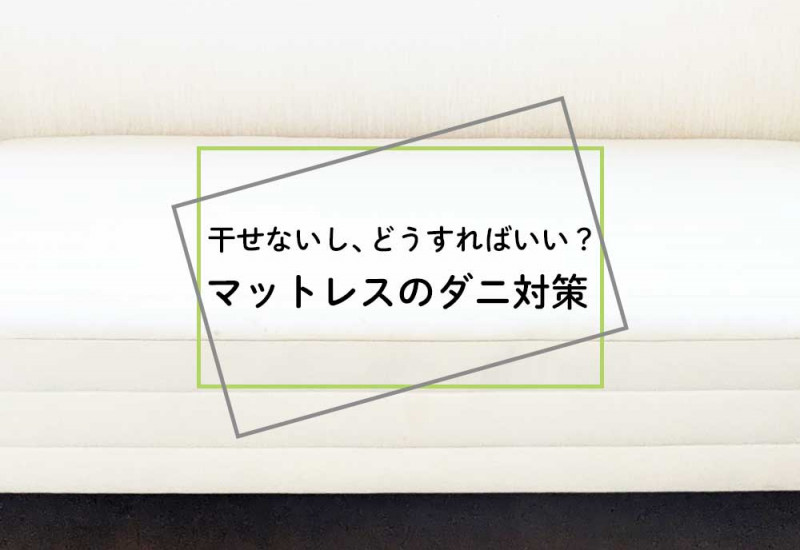
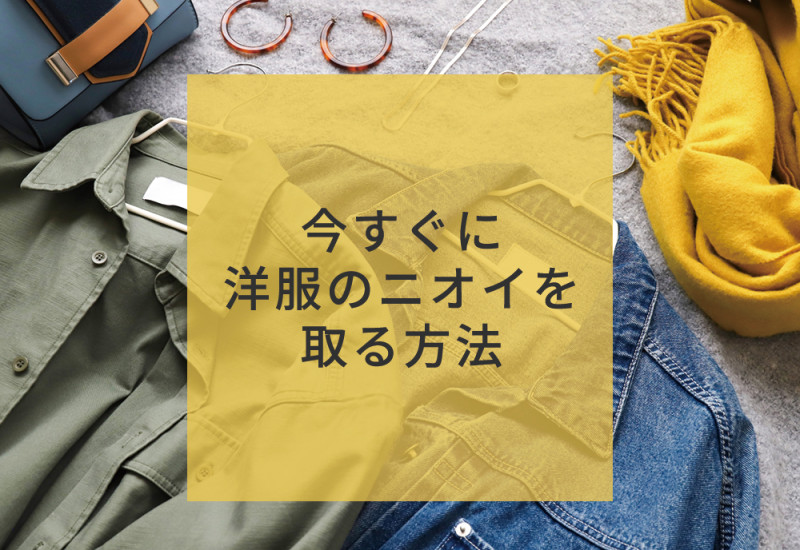
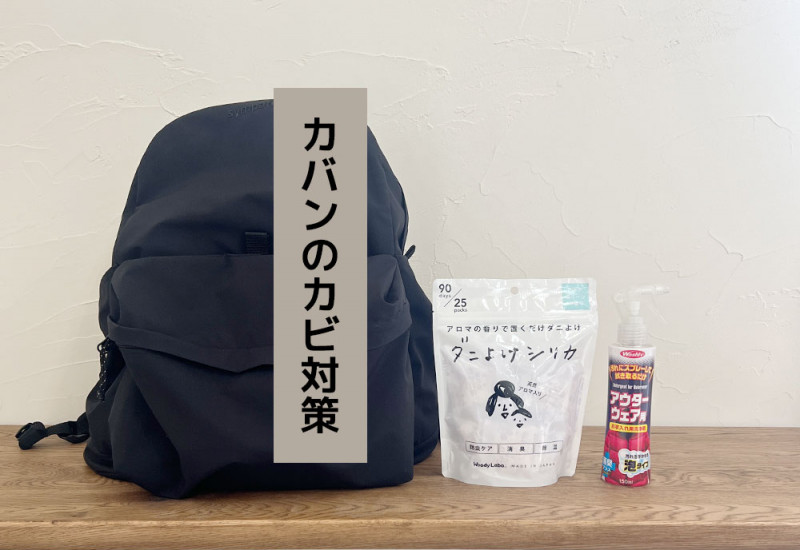


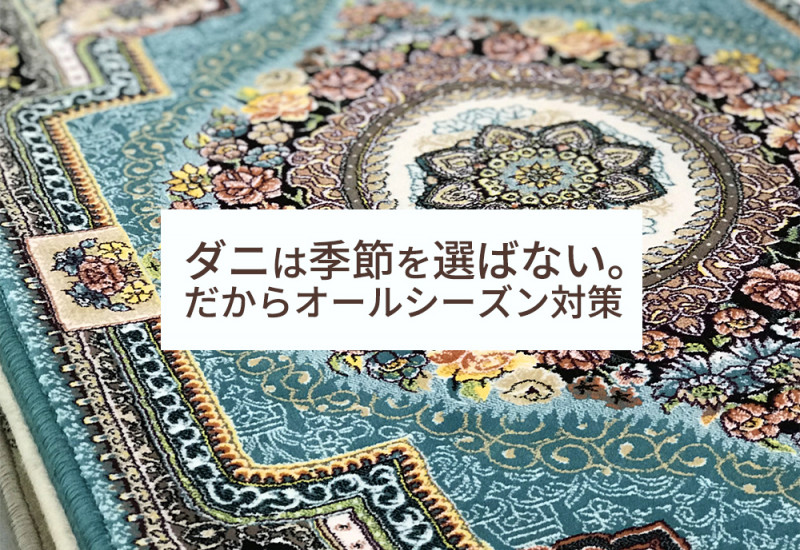


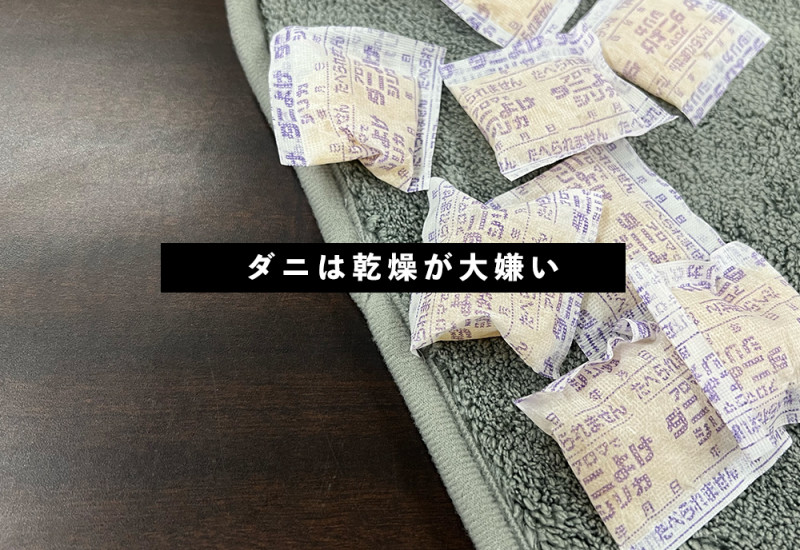


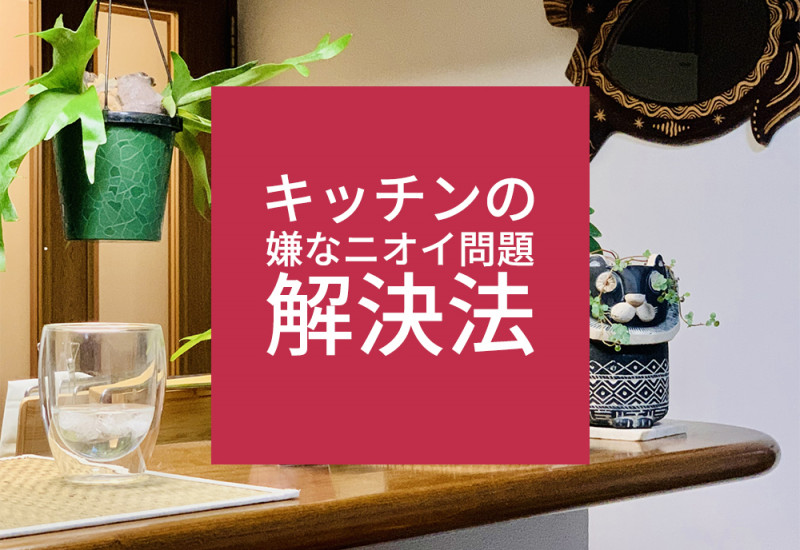
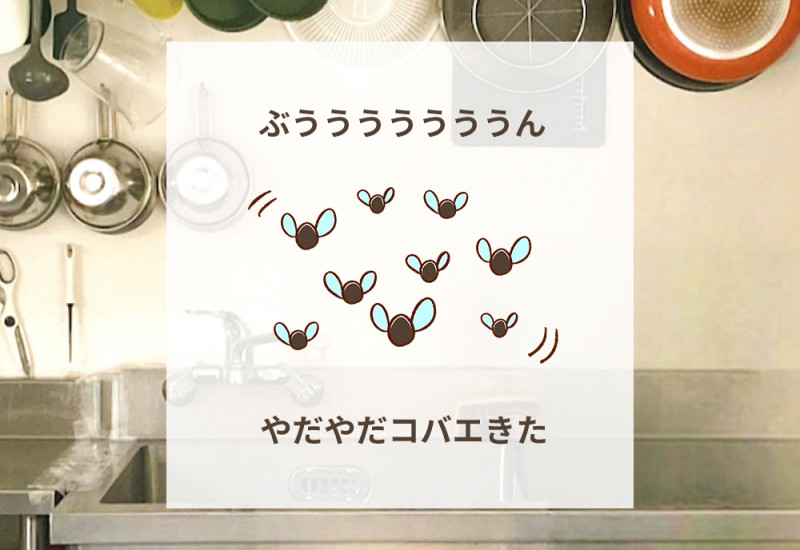

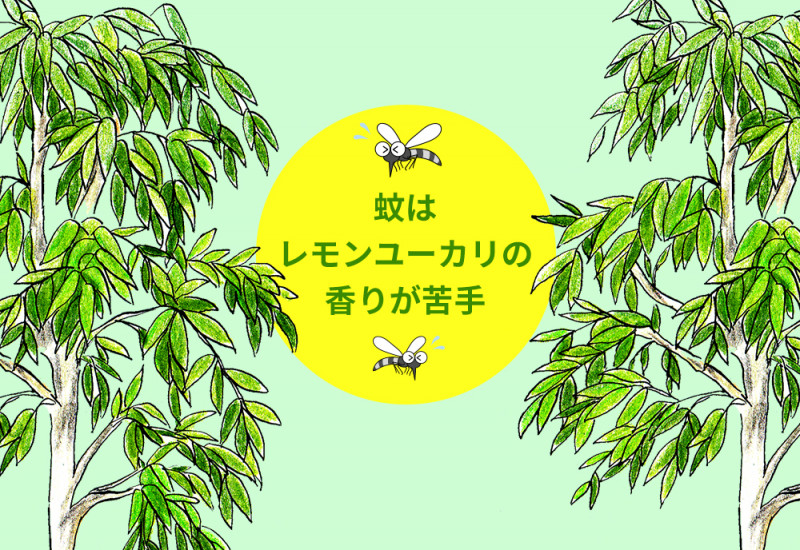
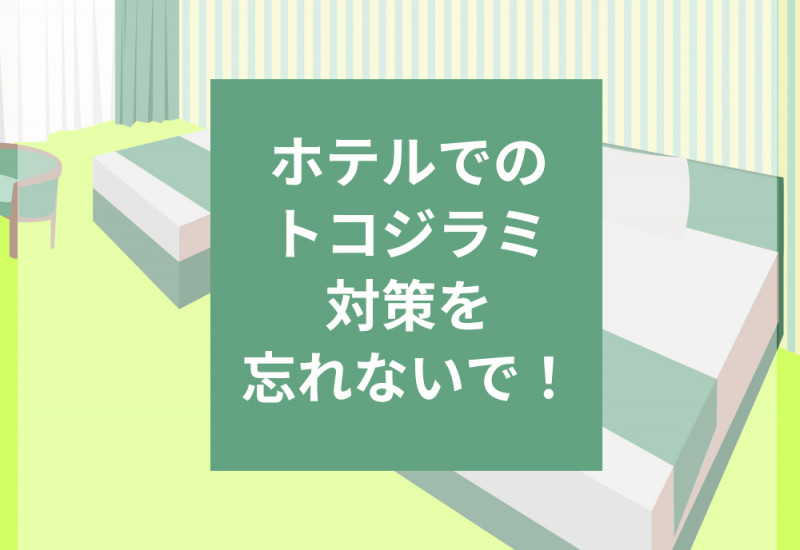



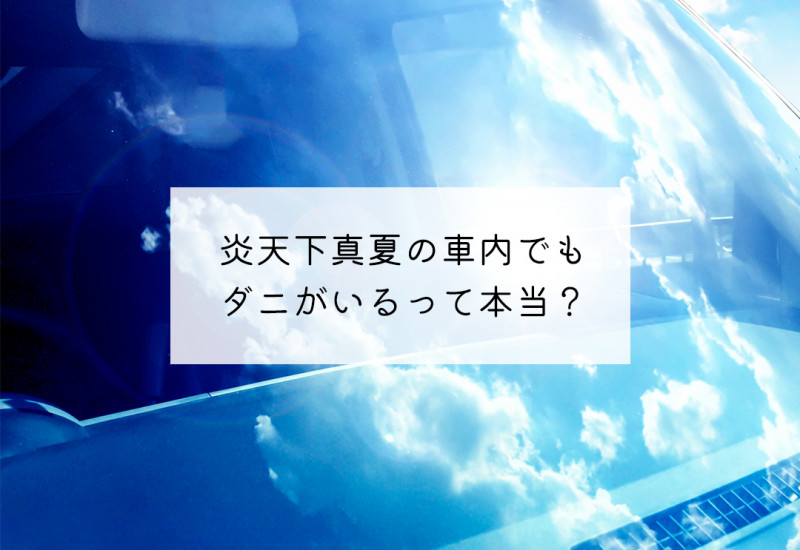
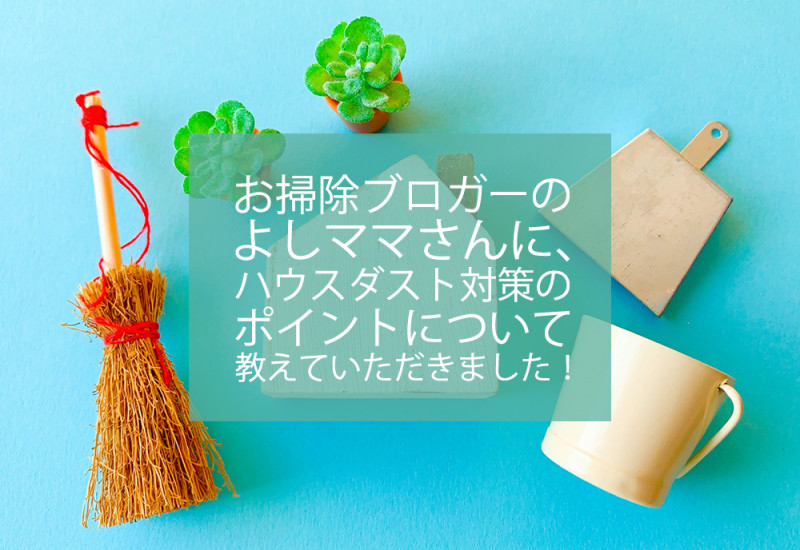
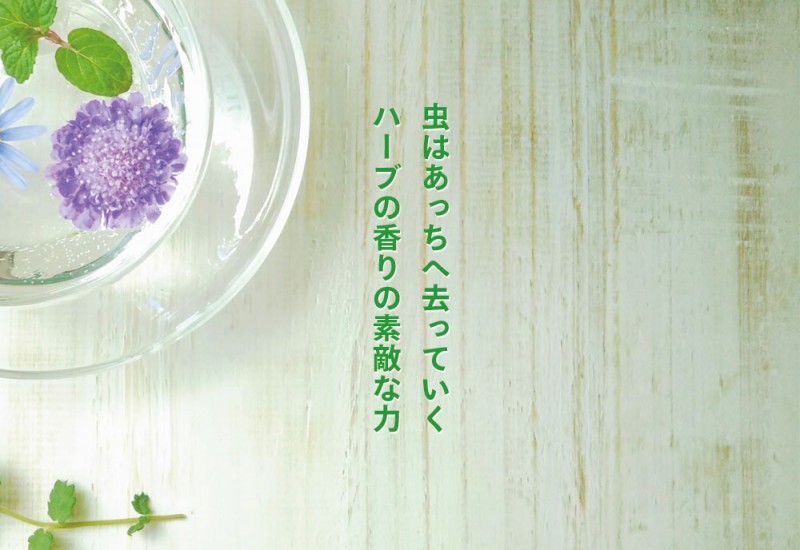
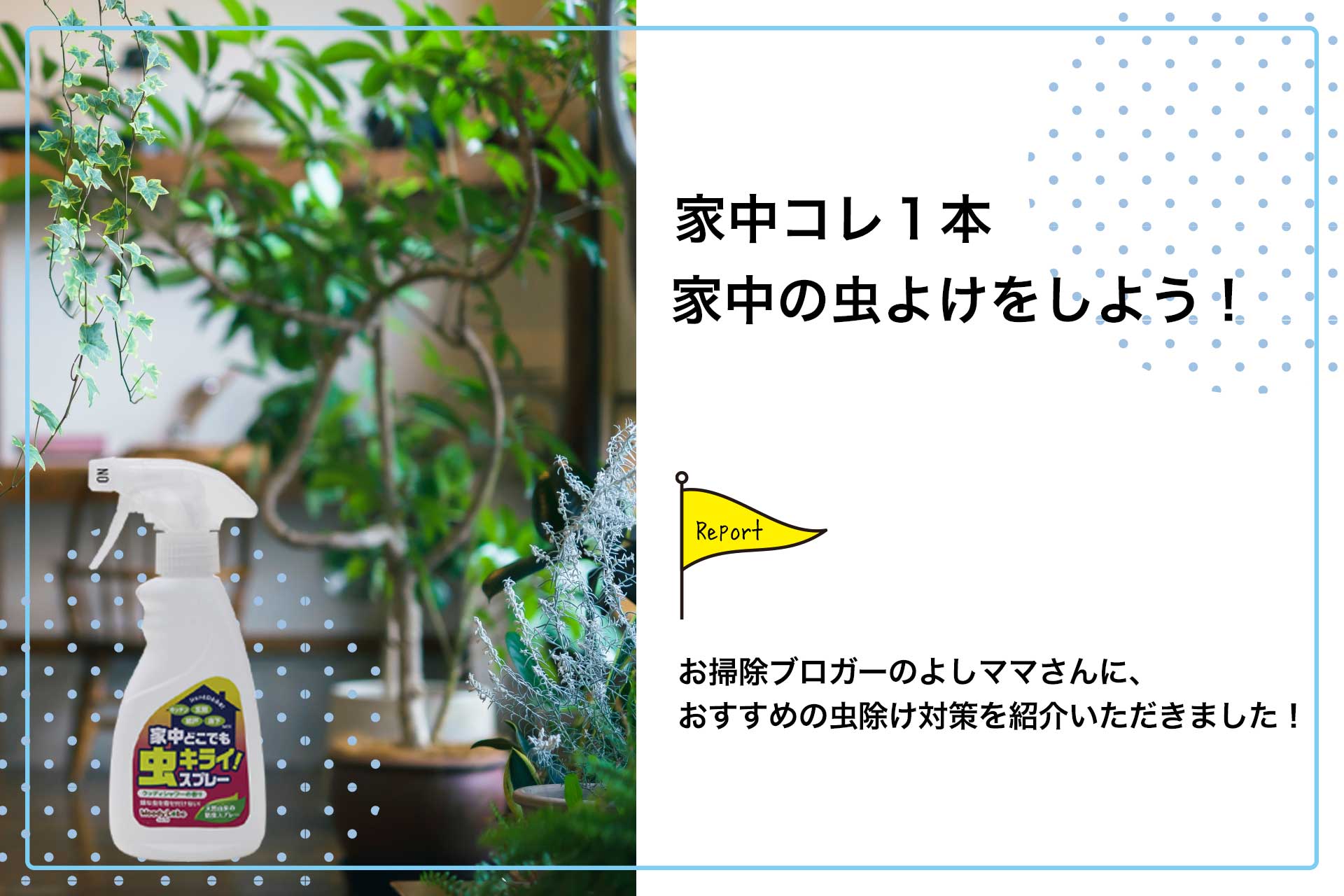
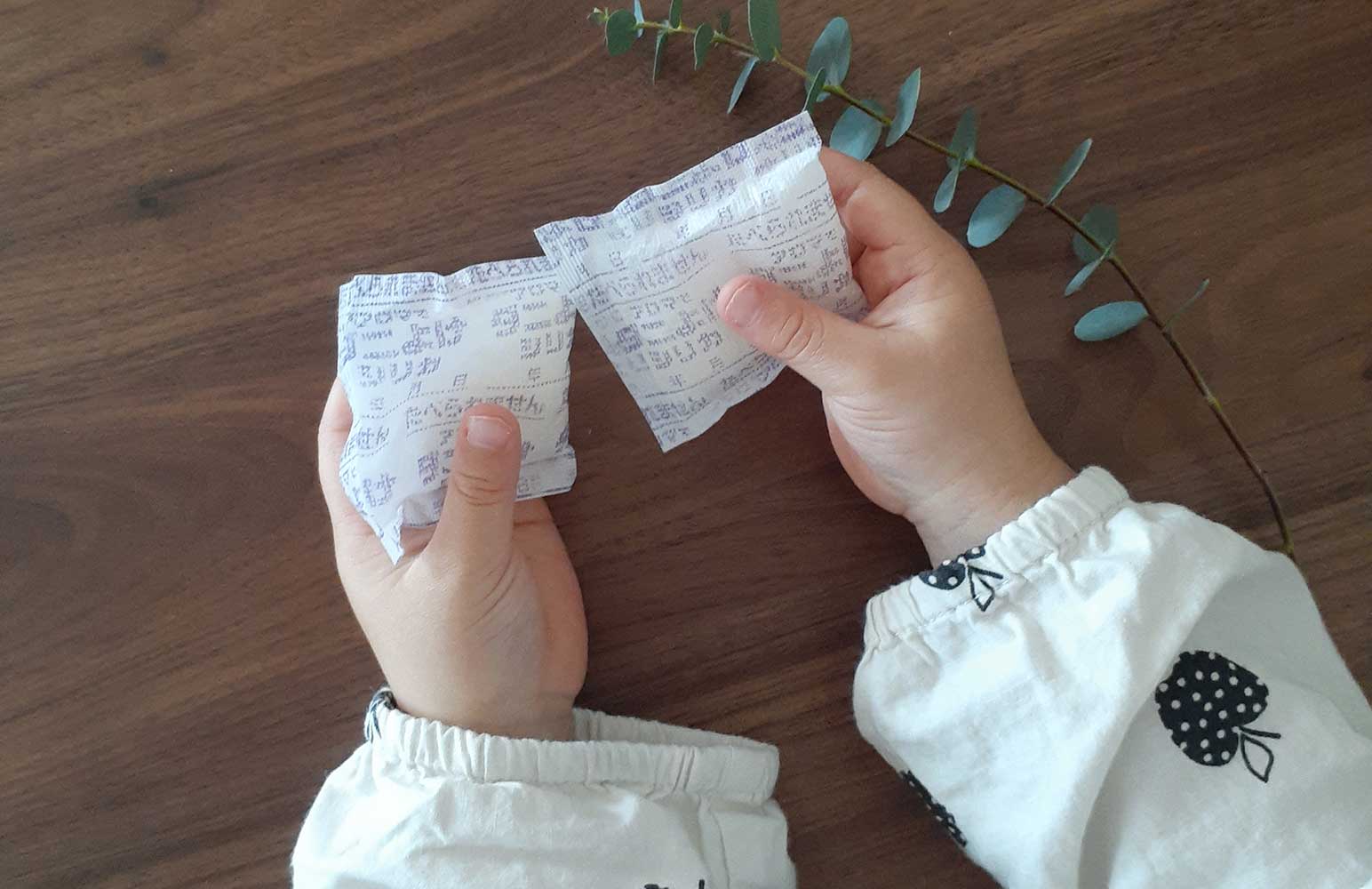

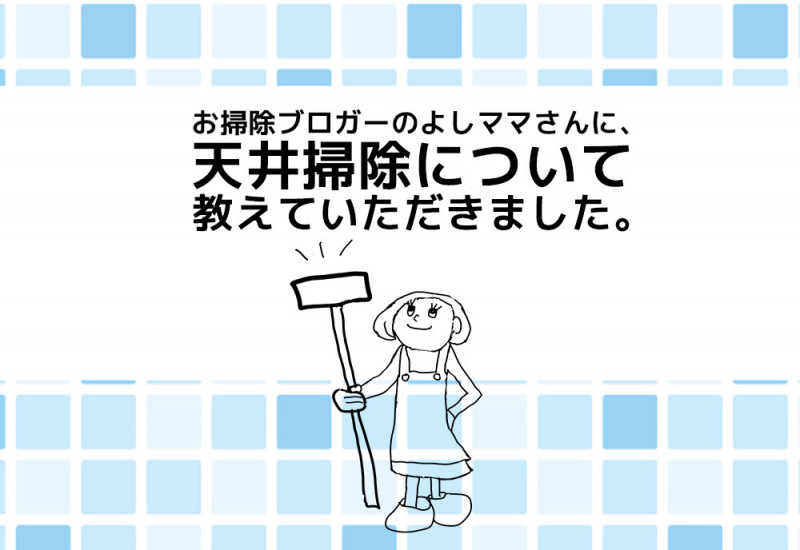
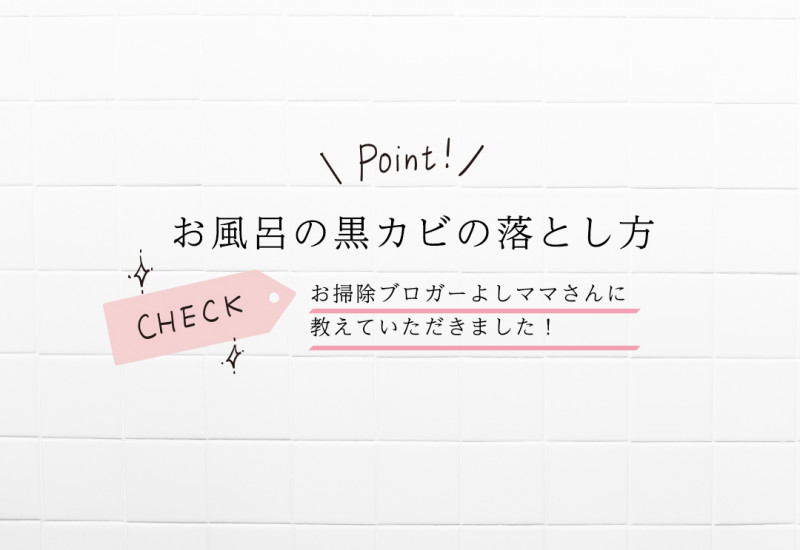



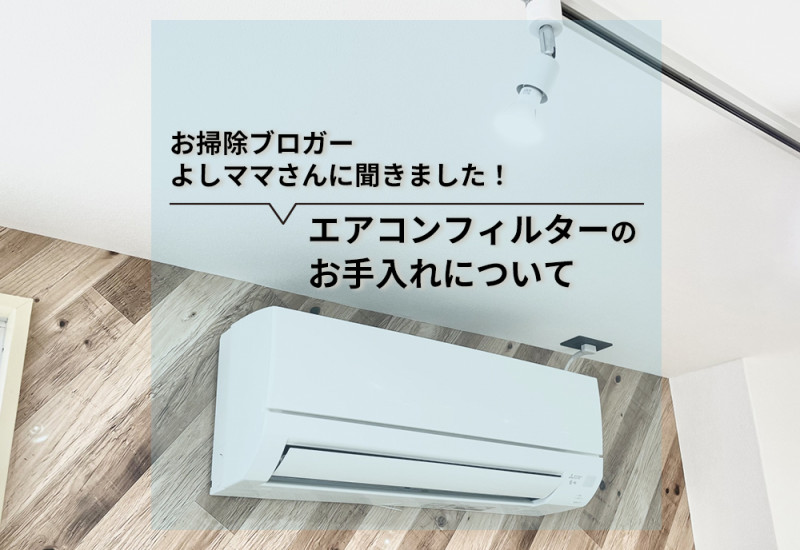
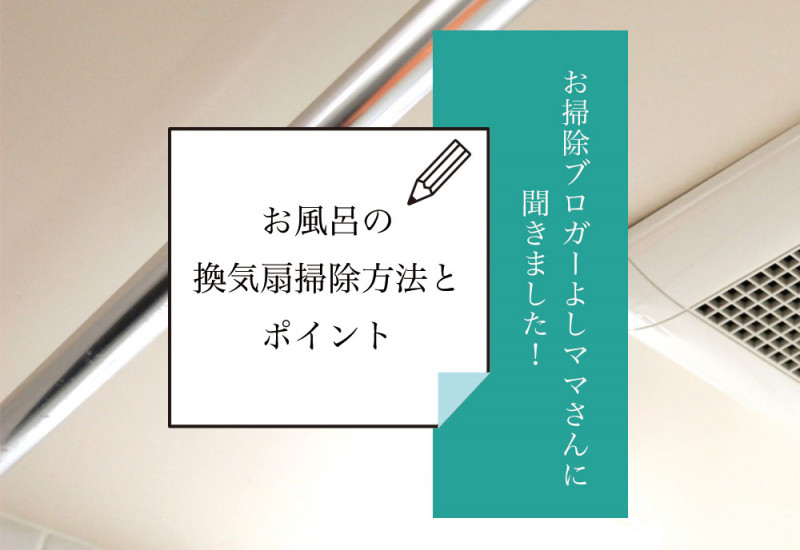

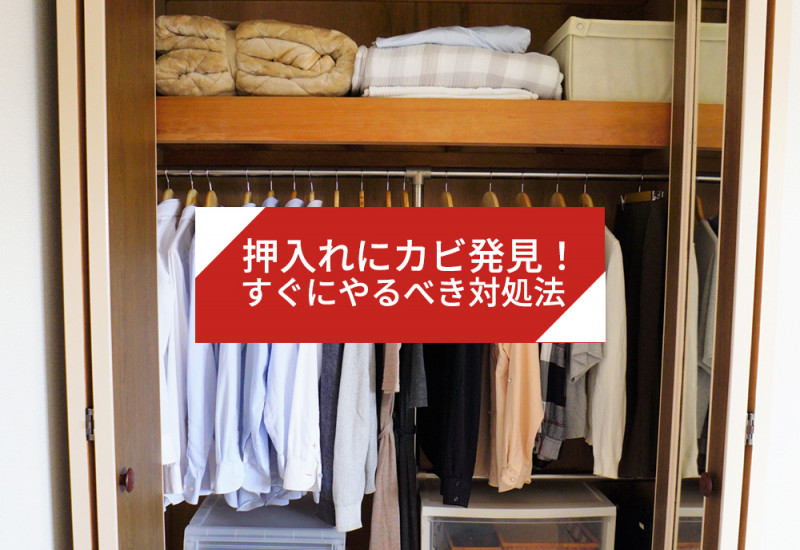



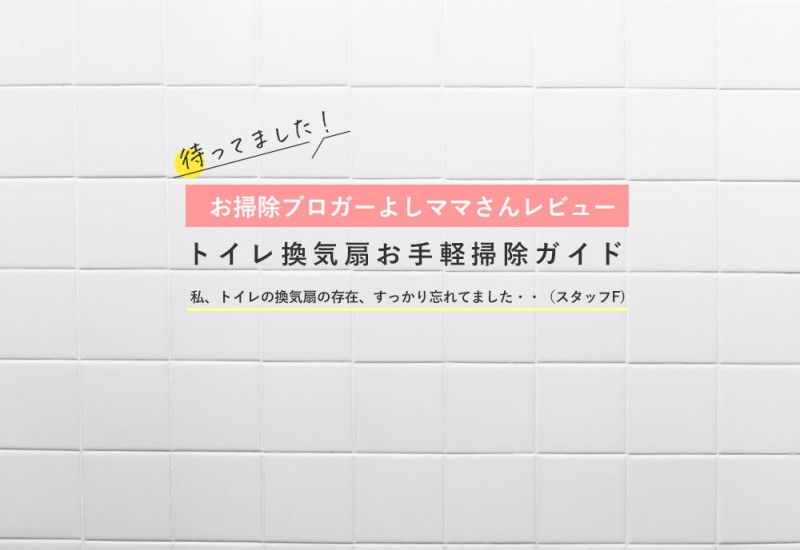
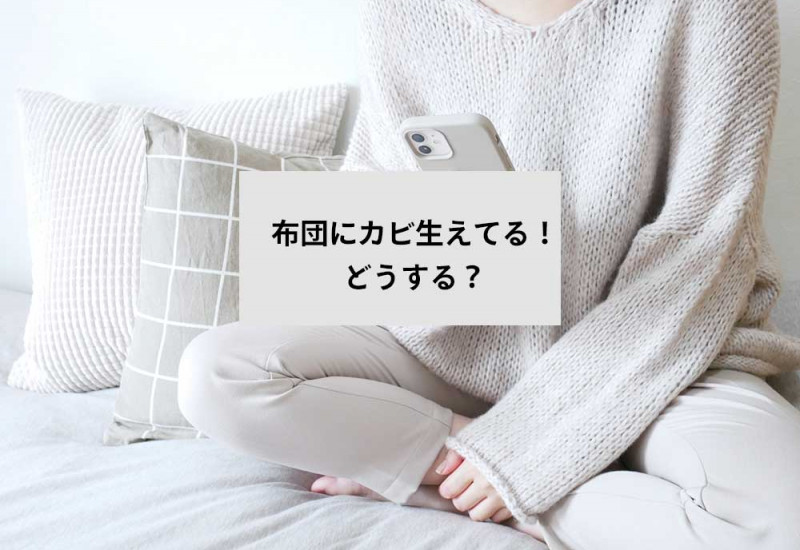
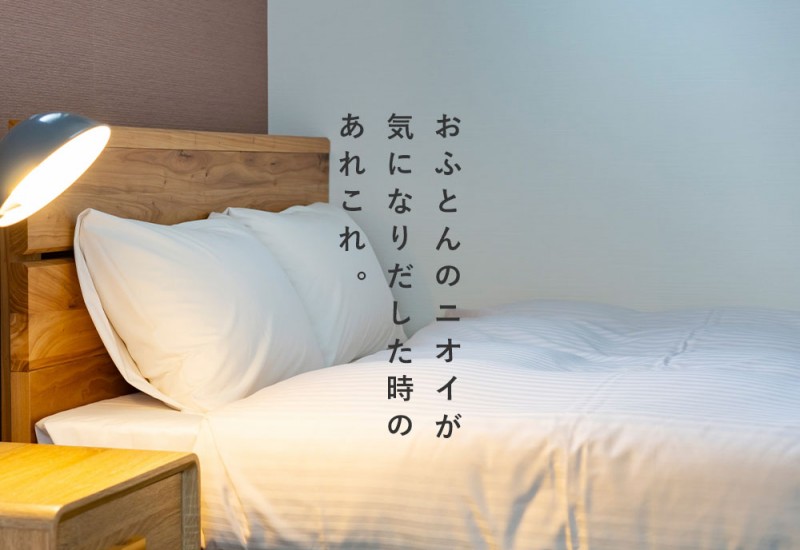
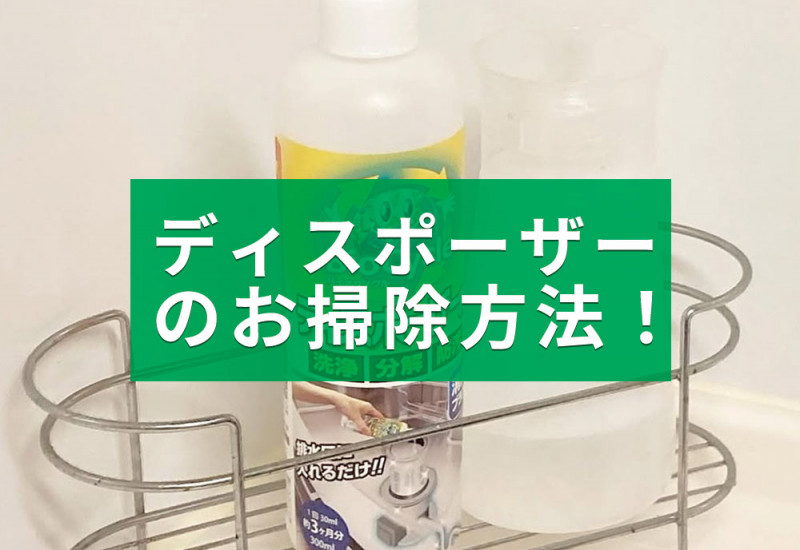
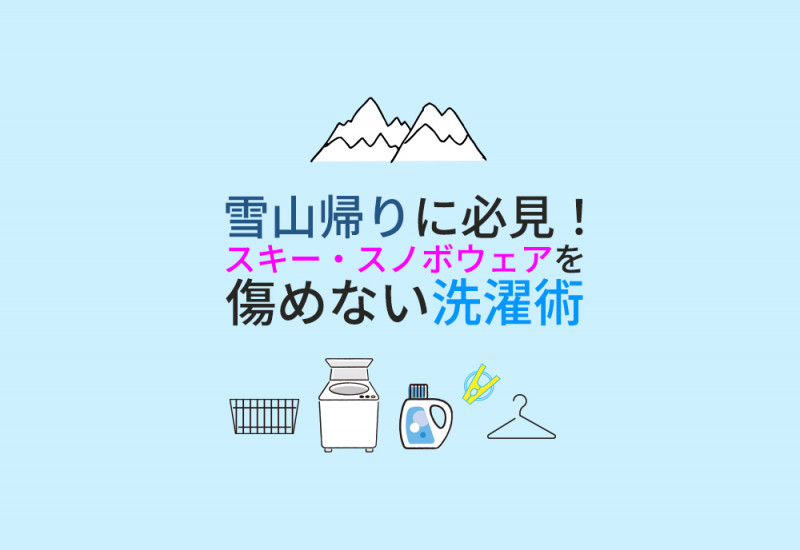




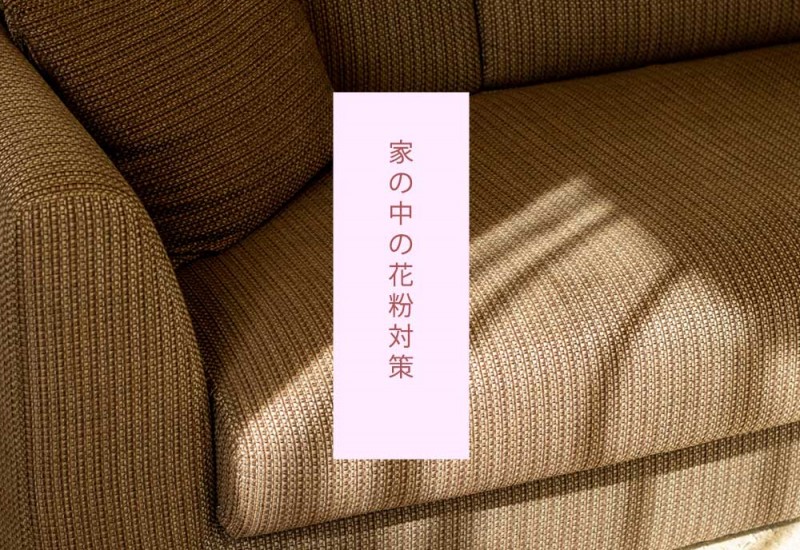
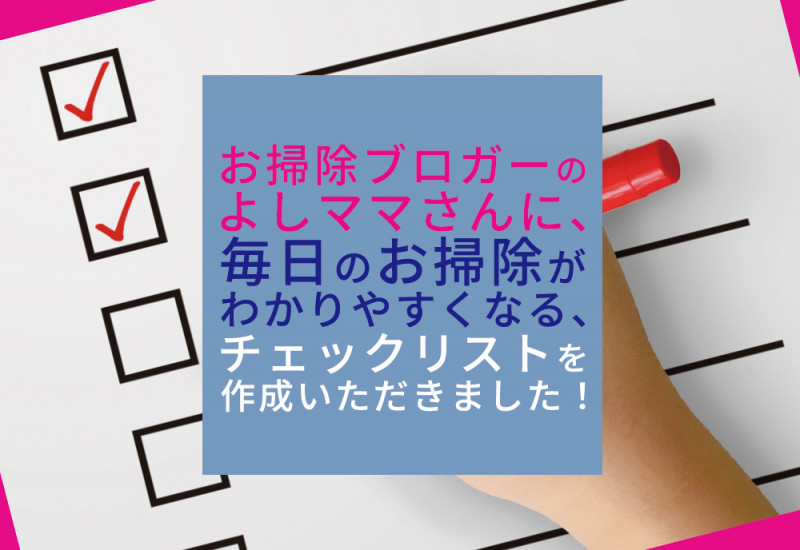

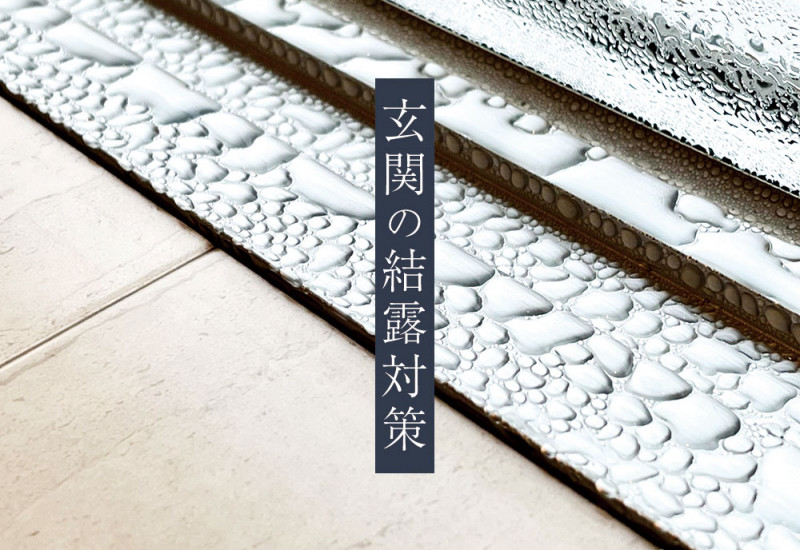



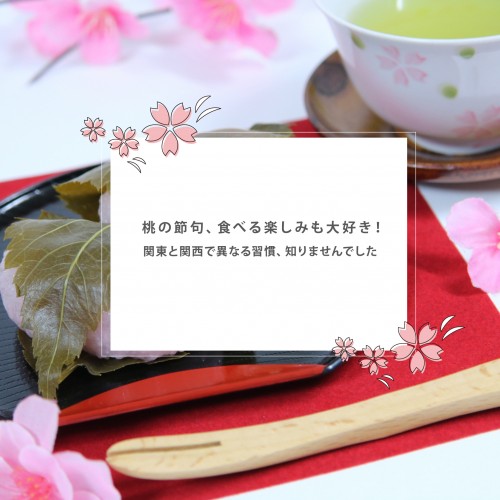


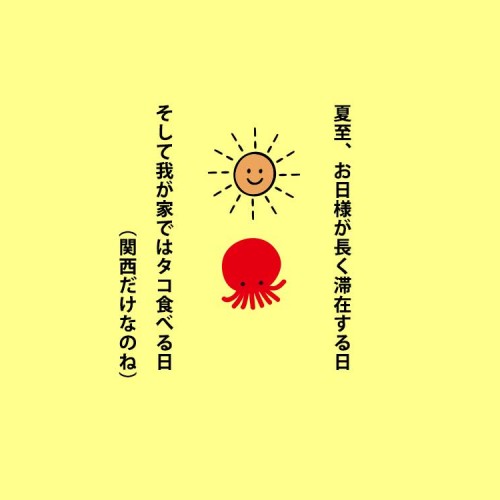


この記事へのコメントはありません。