防災グッズの点検していますか?〜必ず備えておきたい非常用品〜

日本は地震多発国であり、近年は大雨による甚大な被害がでるなど、誰しも災害に合ってしまう可能性があります。みなさん、災害への備えはしていますか? そう遠くない将来には、南海トラフ地震をはじめとするいくつかの大規模地震が高い確率で発生するとも予測されています。そんな脅威にさらされているいま、非常用品について見つめ直してみませんか。今回は、最低限備えておきたい、本当に必要な非常用品について紹介します。
「防災の日」は非常用品を見つめ直すいい機会

災害に備えて非常用品を備蓄・点検しておくことは、個人でもできる重要な防災対策のひとつです。ただ、なにかと慌ただしい日常、つい後回しにしがちな領域でもあるのではないでしょうか。それを返上できるいい機会が「防災の日」です。まずは、防災の日について見ていきましょう。
「防災の日」が制定された背景
防災の日(毎年9月1日)は、昭和35(1960)年6月11日の閣議了解により、制定されました。9月1日という日が選ばれた理由は2つあります。ひとつは、「関東大震災」が発生した日であること。もうひとつは、暦上の「二百十日(にひゃくとうか)」にあたる頃で、台風シーズンが本格化する時期だからです。2つ目の理由は意外と知られていないかもしれません。
じつは、防災の日が創設される契機となったのは、関東大震災ではなく、創設の前年(昭和34年)に発生した「伊勢湾台風」です。日本の災害史上最大の風水害といわれる伊勢湾台風は、死者・行方不明者が5,000名を超える未曾有の被害をもたらしました。
昭和35年9月1日発行の官報資料には、「防災の日」創設の趣旨が載っています。激甚化する自然災害の脅威にさらされているいまだからこそ、心に留めておきたい内容です。以下に紹介します。
『政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しようというのが、『防災の日』創設のねらいである。もちろん、災害に対しては、常日ごろから注意を怠らず、万全の準備を整えていなければならないのであるが、災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限に止めるには、どうすればよいかということを、みんなが各人の持場で、家庭で、職場で考え、そのための活動をする日を作ろうということで、毎年9月1日を『防災の日』とすることになったのである』
「二百十日」とは?
二百十日は雑節のひとつで、「立春(2月4日頃)」から数えて210日目の日です。立春の日は天文学的な理由により毎年同じとは限らないので、二百十日もおのずと変動しますが、だいたいは9月1日頃に収まります。この時期は、稲の開花と台風の襲来が重なるため、古くから農家の厄日とされてきました。
ちなみに、2025年の二百十日は8月31日(日)です。
最低限これだけは備えておきたい非常用品
ここからは、「非常用品」について具体的に紹介していきます。まずは、非常用品とは何かについて見ていきましょう。
非常用品は大きく分けて2つ
ひとくちに「防災グッズ」と言いがちな非常用品ですが、じつは「備蓄品」と「非常持ち出し品」の2つに分けられます。この2つを一緒くたにしている人は少なくないかもしれません。必要なものは災害の経過とともに変わってきます。そこを踏まえて、備蓄品・非常持ち出し品の意義を見てみましょう。
- 備蓄品
災害が発生すると、電気やガス、水道、通信などのライフラインが止まり、普段通りの生活ができなくなる恐れがあります。ライフラインが止まっても自力で生活できるように備えておくのが「備蓄品」です。 - 非常持ち出し品
災害の状況によっては、避難を余儀なくされることがあります。自宅から避難所などへ避難する際に持ち出すものが「非常持ち出し品」です。
最低限備えておきたい「備蓄品」

少なくとも3日分、できれば1週間分を自宅や自家用車などに保管しておきたいものを以下に列挙します。
*飲料水(1人1日3リットルを目安に)
*食料品(アルファ米などのご飯、カンパン、ビスケット、板チョコなど)
*簡易トイレ
*カセットコンロ
*非常用バッテリー
*懐中電灯(予備電池も)
*救急用品
*衛生用品
*生理用品
*現金(小銭を中心に2万円ほど)
飲食物の備蓄にはローリングストックを!
ずいぶん認知されてきた「ローリングストック」。普段から使う食品や日用品などを少し多めに買い置きし、消費したらその分をまた買い足すことで、常に一定量を備蓄する方法をいいます。この方法ならば、防災対策にちょっと難しさを感じる人でも、無理なく始められるのではないでしょうか。
最低限備えておきたい「非常持ち出し品」

非常持ち出し品には、「一次持ち出し品」と「二次持ち出し品」があります。順に紹介していきます。
一次持ち出し品リスト
「一次持ち出し品」とは、避難するときに最初に持ち出すものです。次のようなものがあり、リュックなどに入れる重さの目安は男性で15kg、女性で10kg程度といわれています。
*飲料水
*食料品
*救急用品(ばんそうこう、包帯など)
*衛生用品(マスク、ウェットティッシュ、手指消毒用アルコール、体温計など)
*生理用品
*ヘルメット、防災ずきんなど
*軍手(手袋)
*ヘッドランプ
*懐中電灯(予備電池も)
*携帯ラジオ(予備電池も)
*衣類(下着など)
*タオル
*防寒用アルミシート
*貴重品(預金通帳、印鑑、運転免許証、マイナンバーカード、現金など)
*医療関係備品(健康保険証、お薬手帳)
*常備薬
※乳幼児がいる場合は、ミルク・哺乳瓶・おむつなども
※高齢者がいる場合は、老眼鏡、入れ歯なども
二次持ち出し品リスト
「二次持ち出し品」とは、避難後、少し余裕ができた際に持ち出すもの・必要になるものです。具体的には以下のものがあります。
*飲料水
*食料品
*お皿、コップ、箸、鍋、やかんなどの生活用品
*キッチン用ラップ
*カセットコンロ(カセットコンロ用ボンベや固形燃料も)
*新聞紙
*洗面具
*歯ブラシ
*毛布
*寝袋
「0次の備え」も準備して!
外出先での災害に備えて普段から防災グッズを持ち歩くことを、「0次の備え」といいます。毎日持ち歩いているものにプラスαで、次のものを用意しておくといいでしょう。
*食べ物(飴、チョコ、羊羹など)
*救急用品(ばんそうこう、アルコール消毒液など)
*生理用品
*ビニール袋
*簡易トイレ
*ホイッスル
*防犯ブザー
*現金(公衆電話用の10円硬貨があると便利)
上記のものをポーチに入れておくと◎。ポーチは、軽量で耐久性の高いものを選んでみてください。
災害の経過とともに必要なものは変わってくる
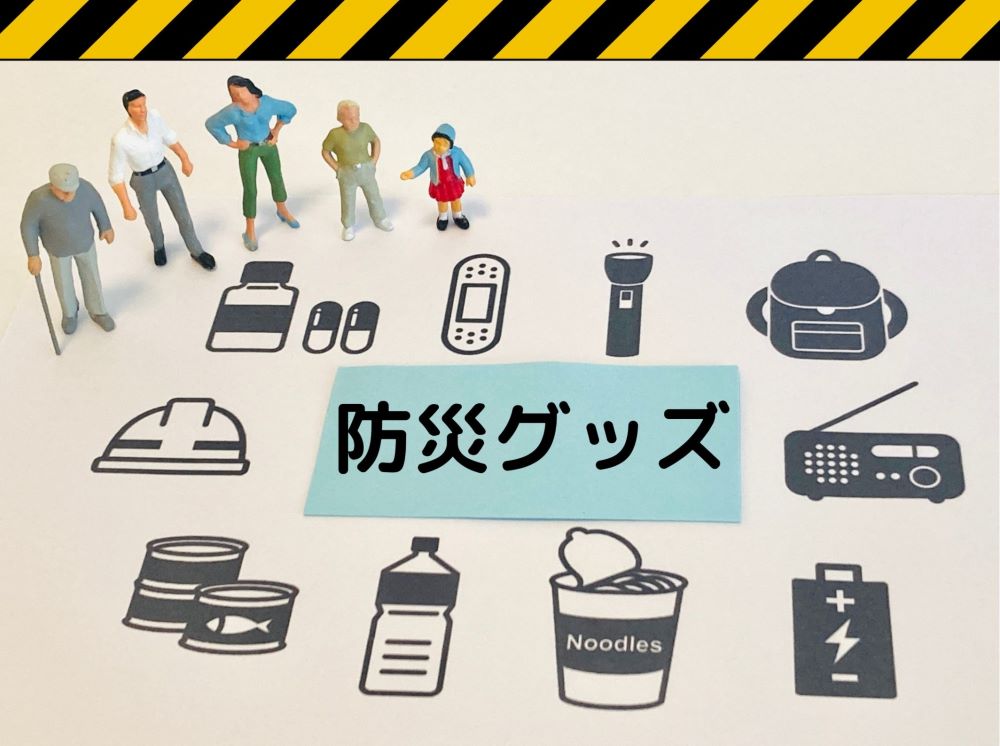
非常用品のことをひとくちに防災グッズと言いがちですが、じつは大きく2つに分かれています。自宅や自家用車に備えておきたい「備蓄品」と非難する際に必要な「非常持ち出し品」です。非常持ち出し品は、さらに「一次持ち出し品」と「二次持ち出し品」に分かれます。言われてみればなるほどですが、一緒くたに考えている人も少なくないのではないでしょうか。災害の経過とともに必要なものが変わることを意識すると、準備もはかどるかもしれません。
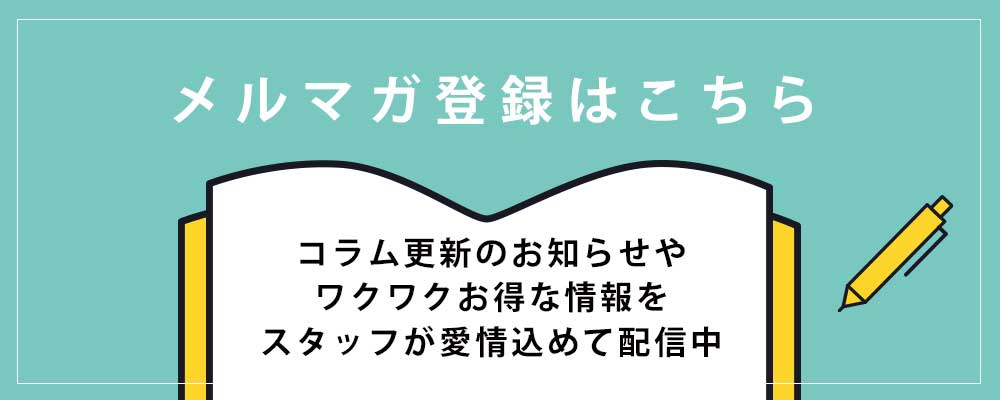
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
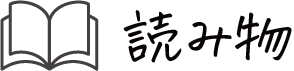
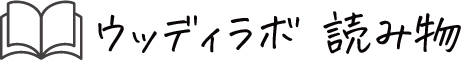


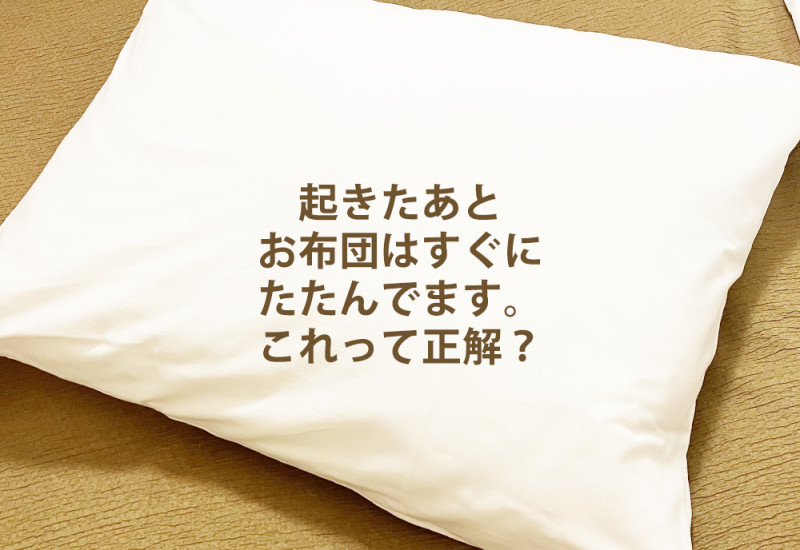
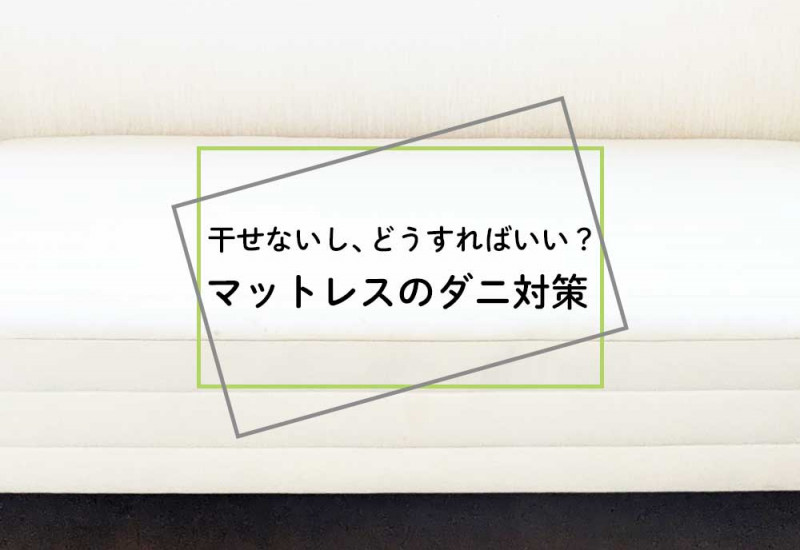
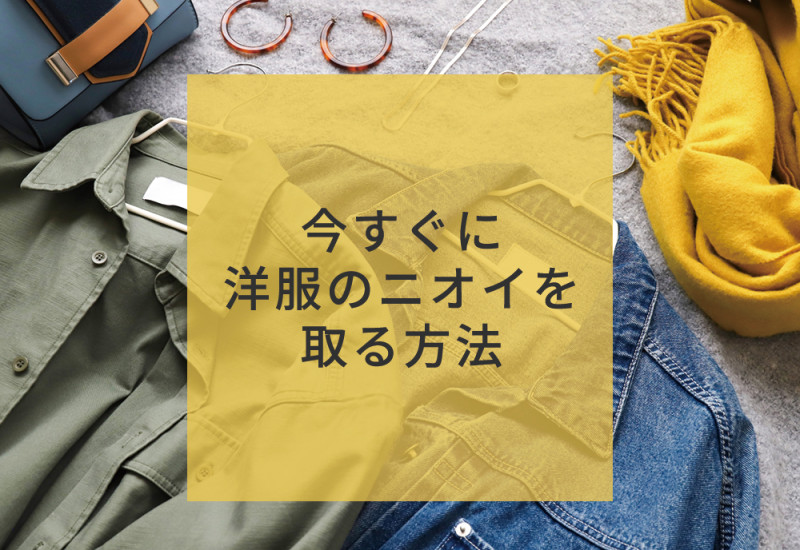
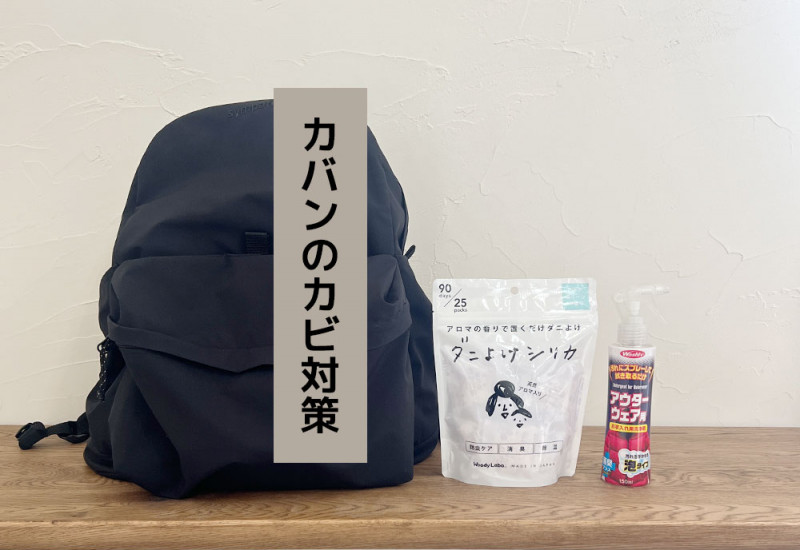


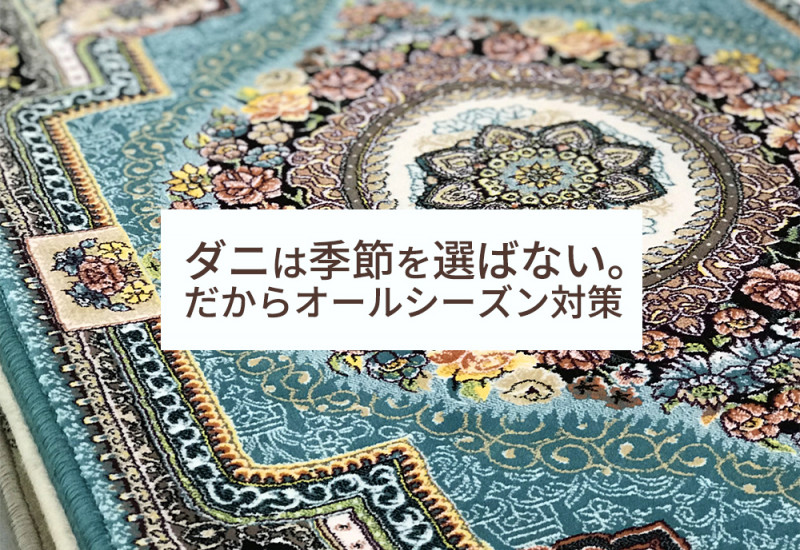


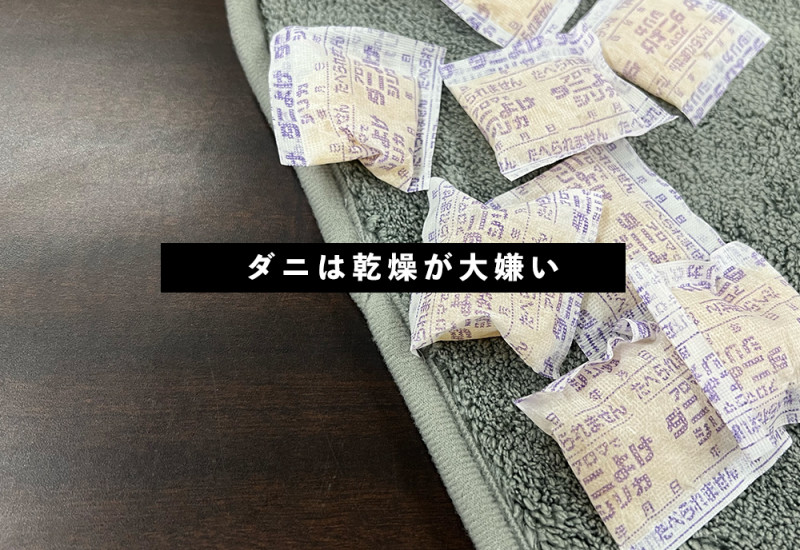


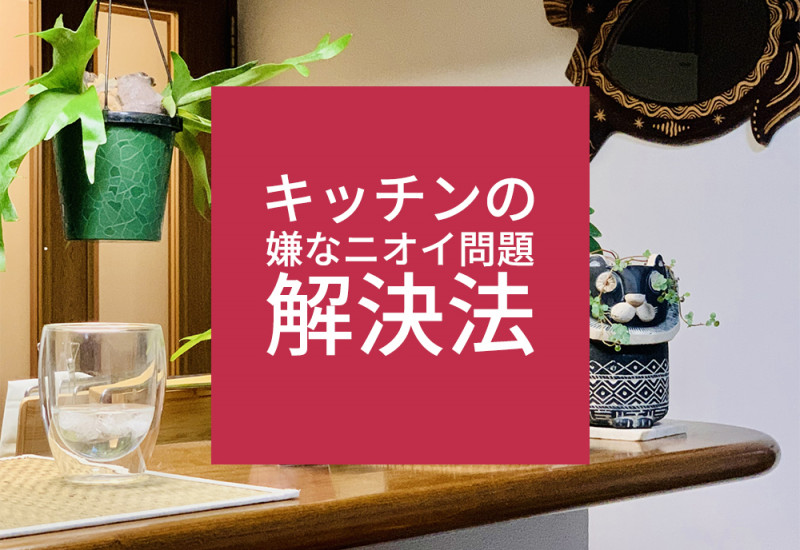
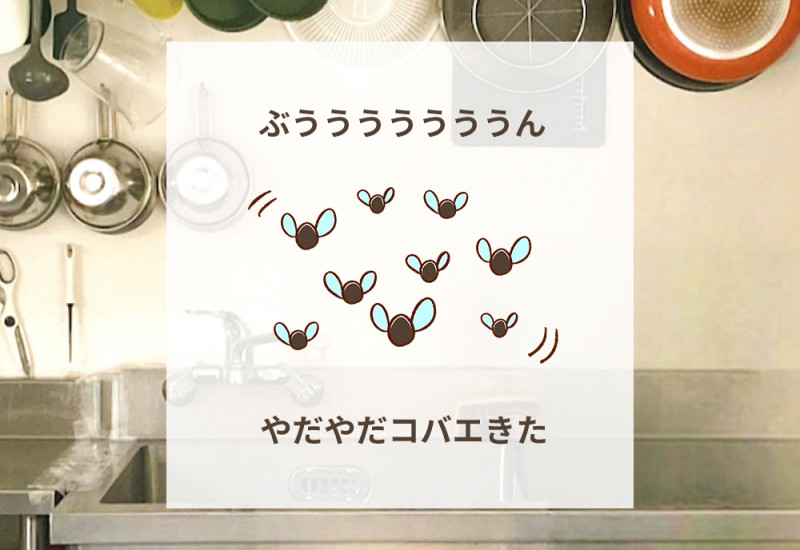

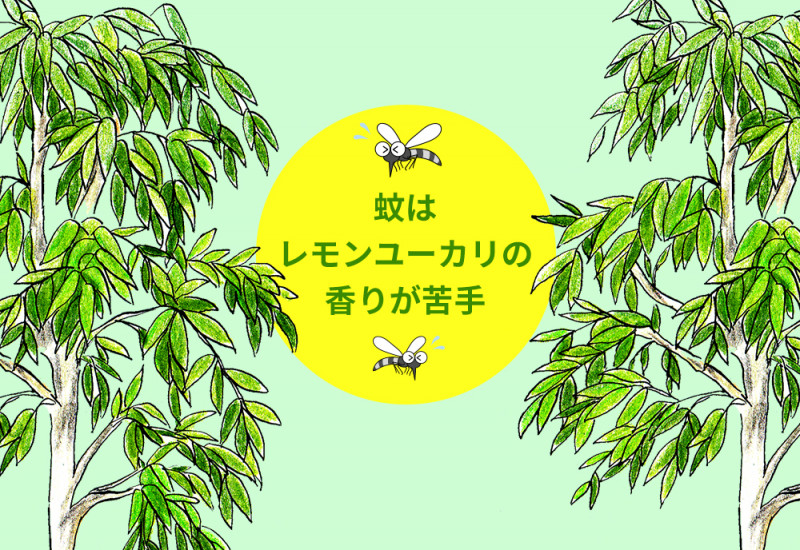
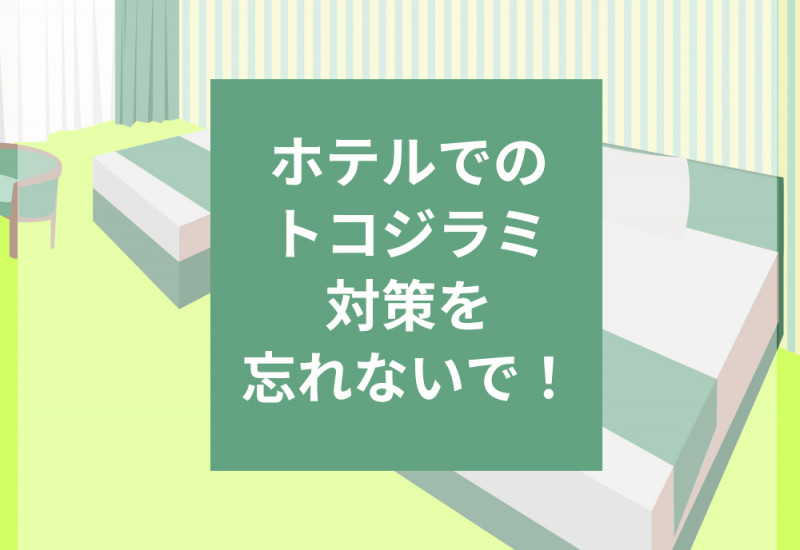



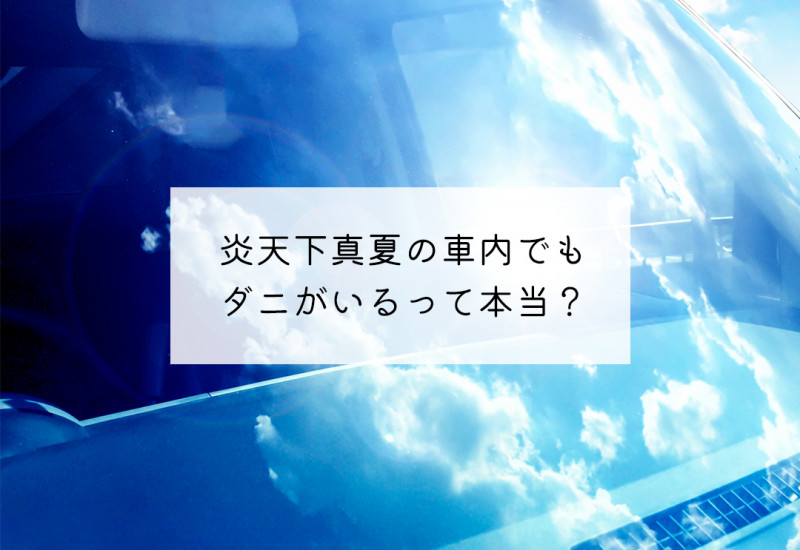
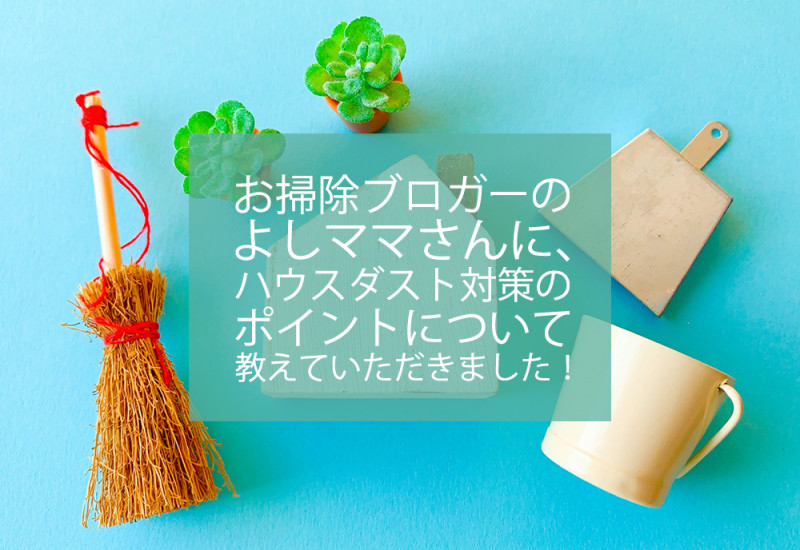
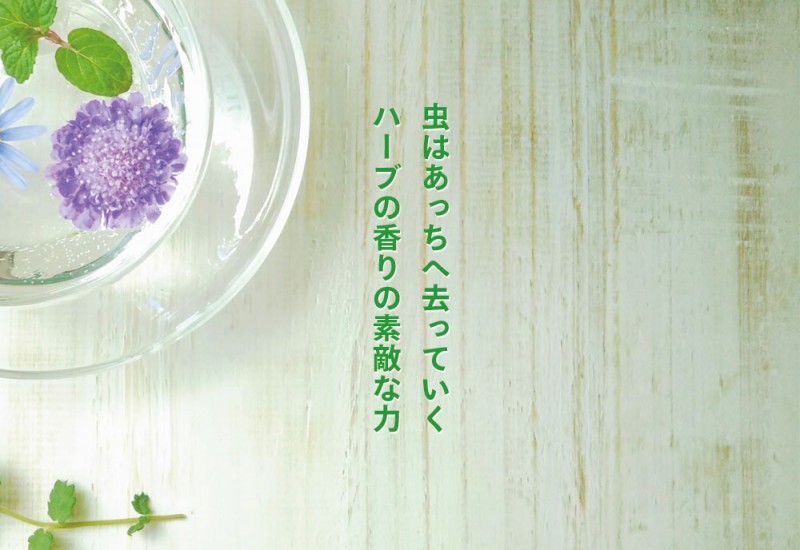
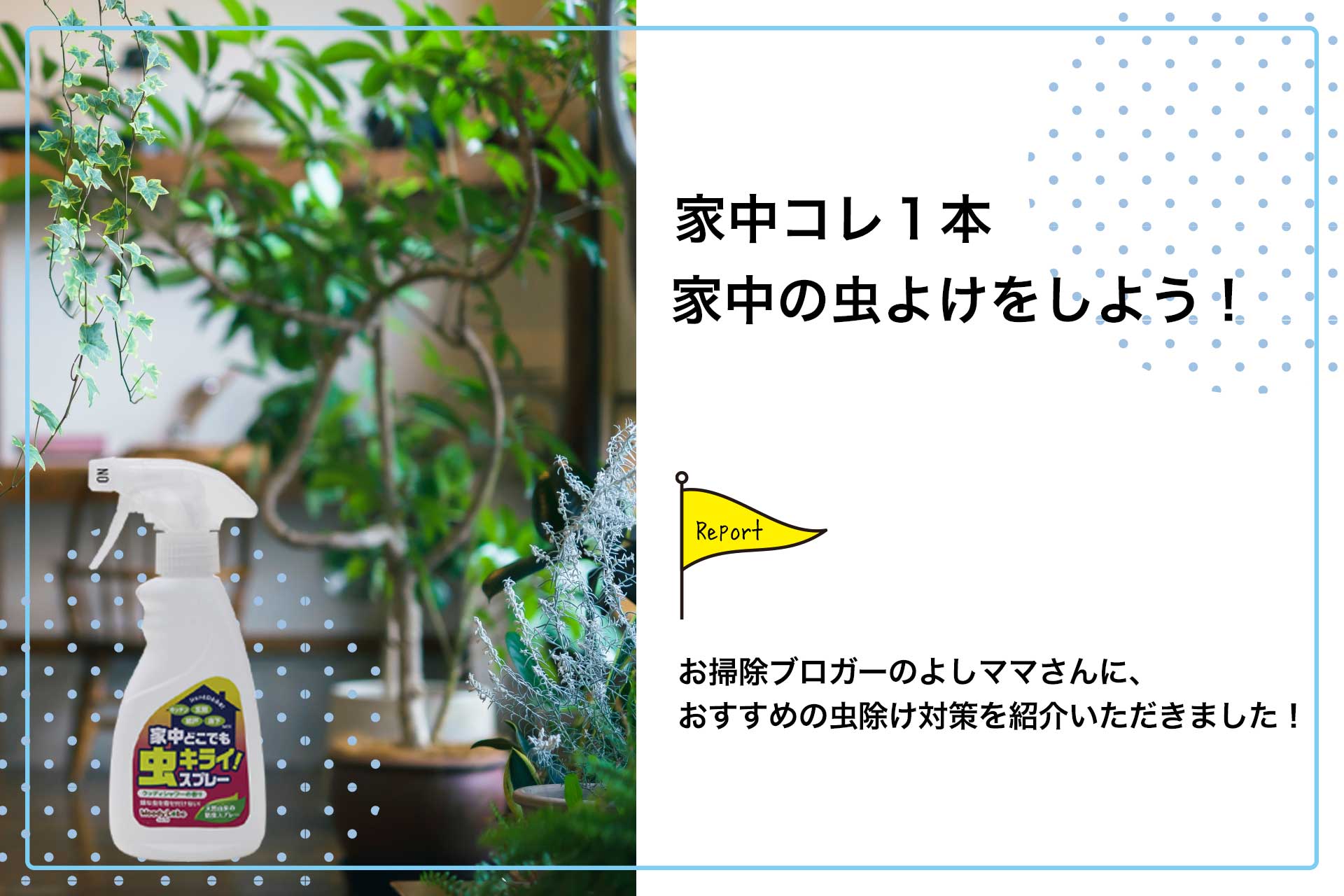
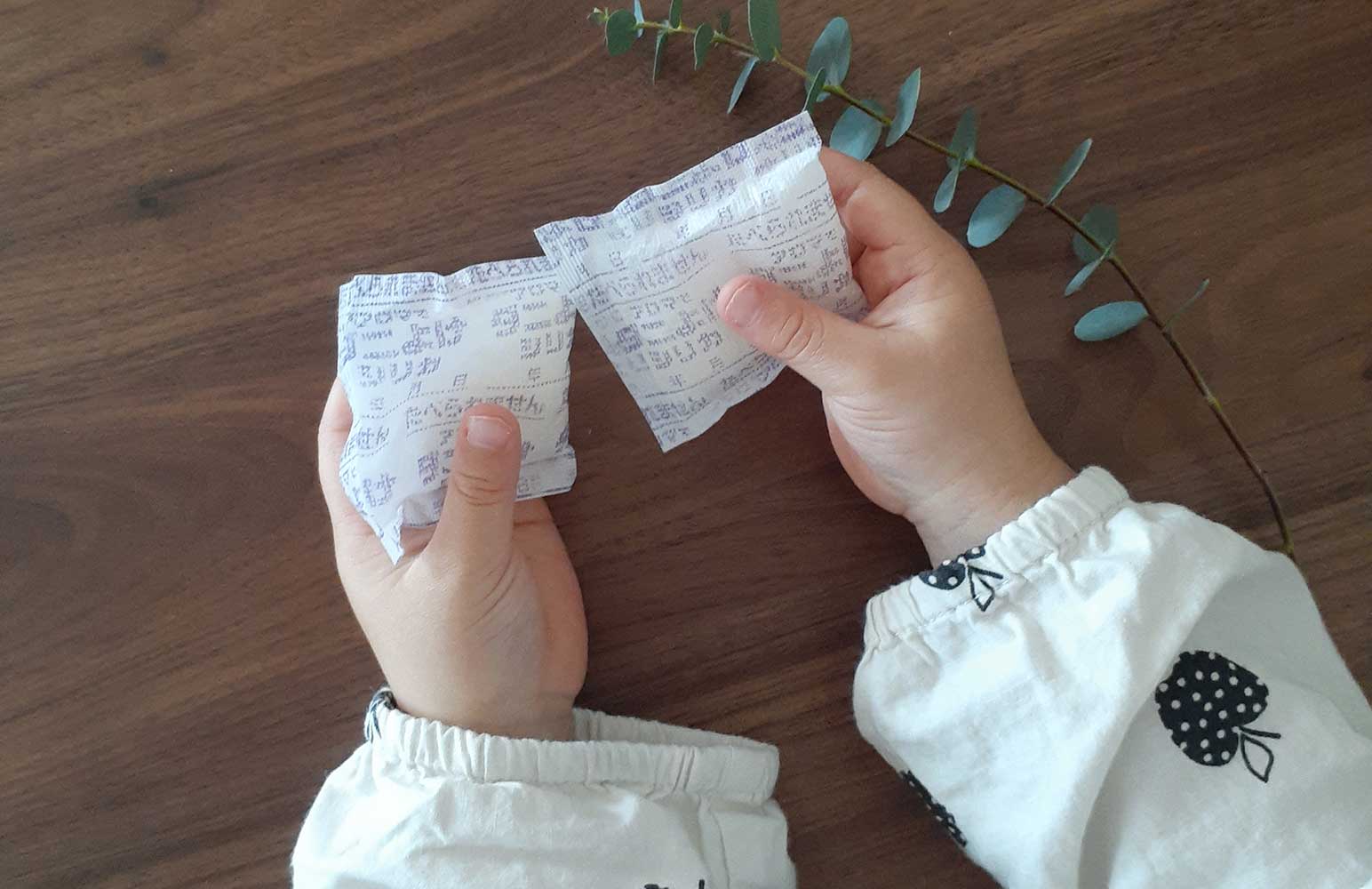

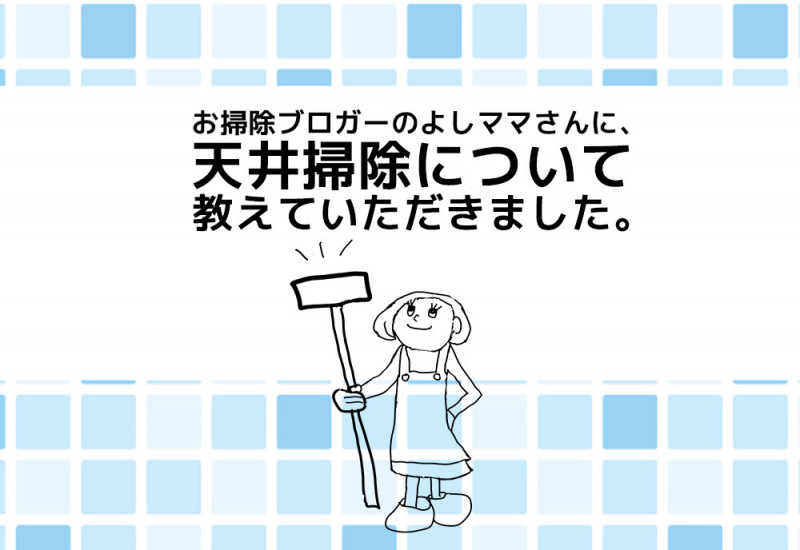
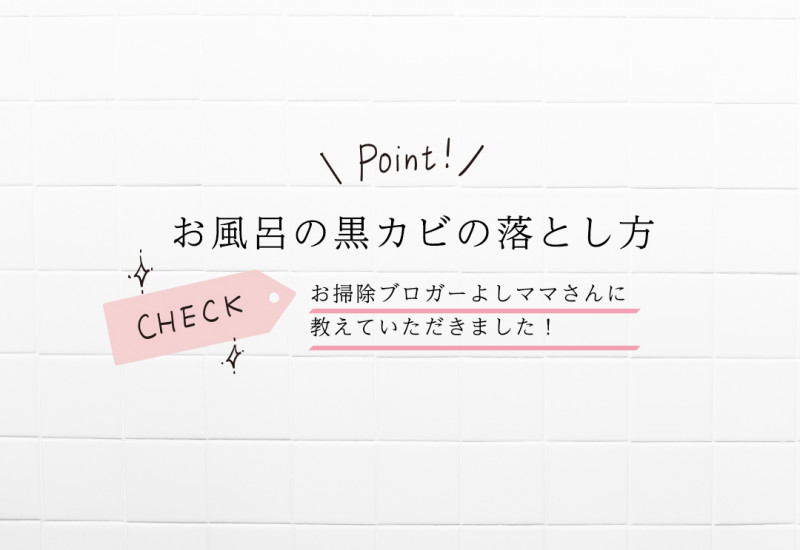



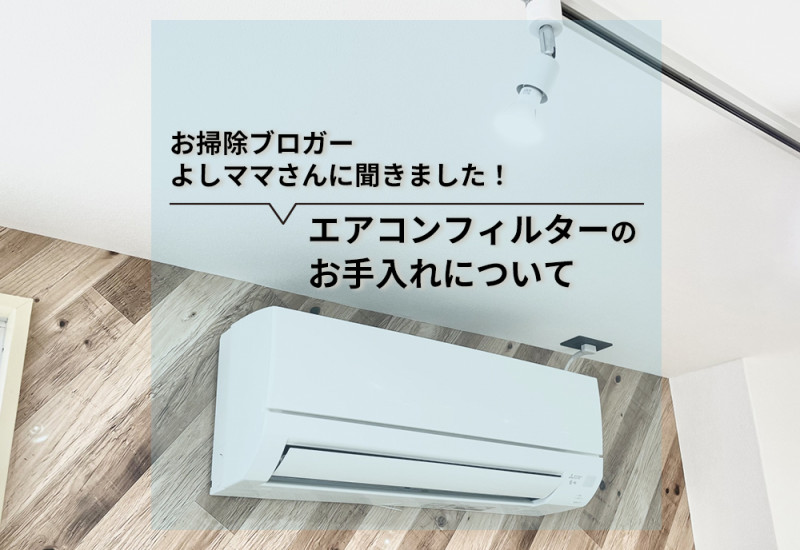
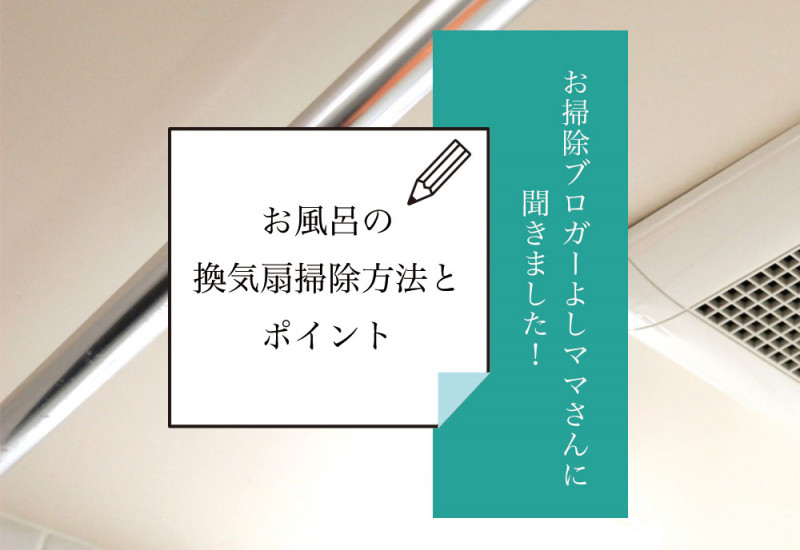

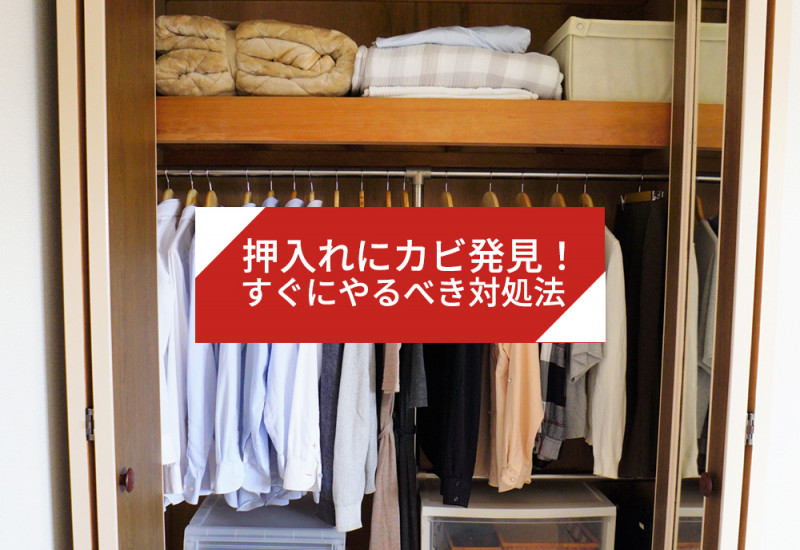



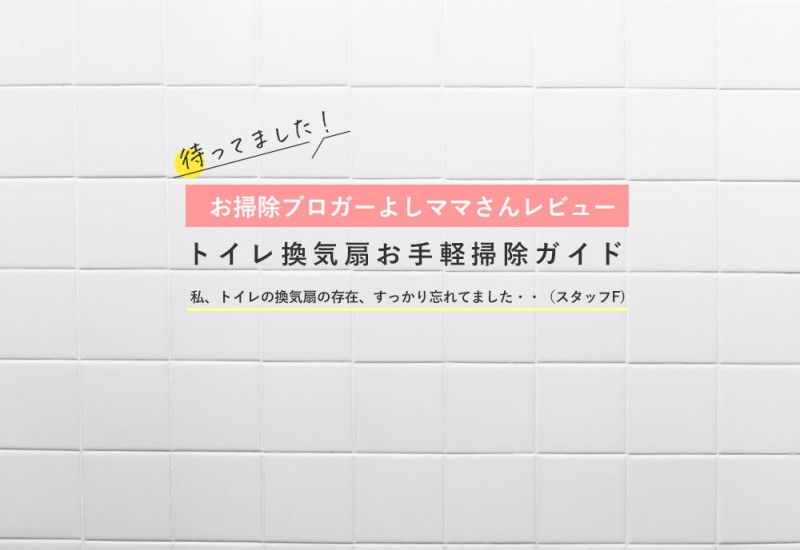
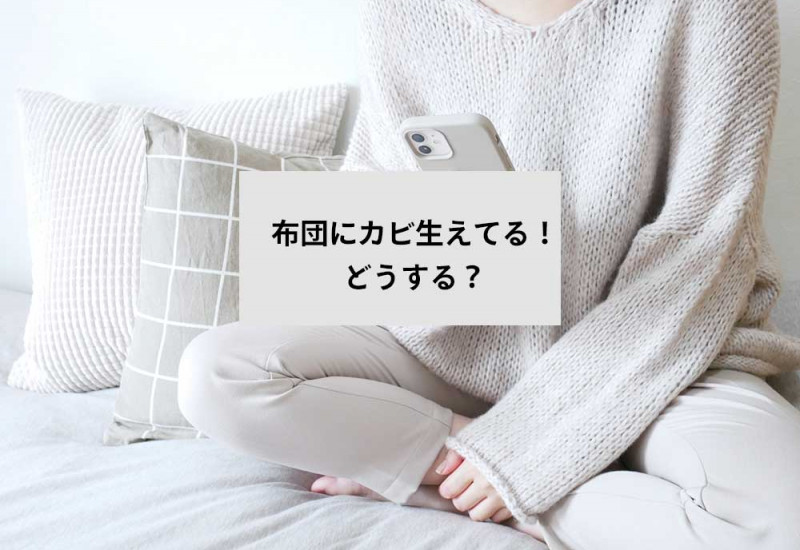
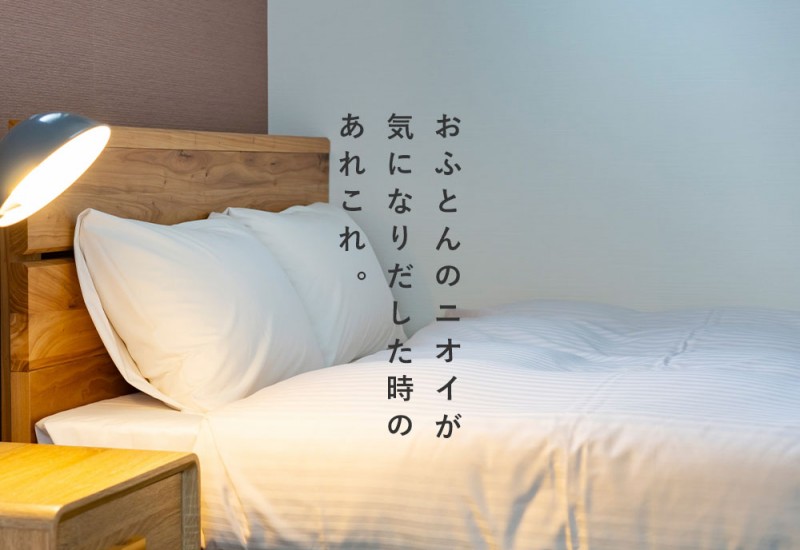
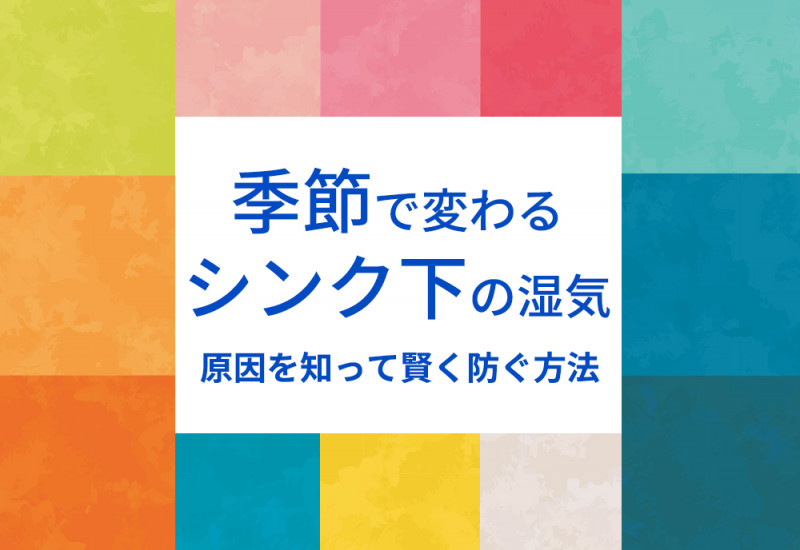
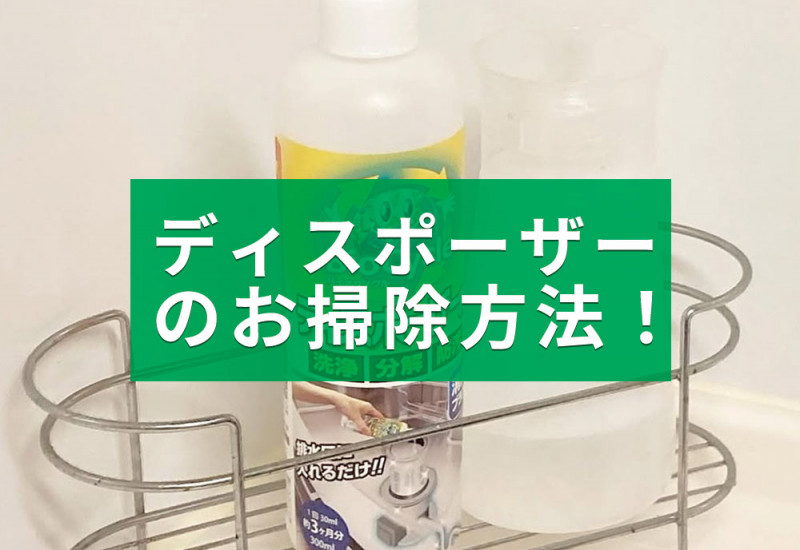

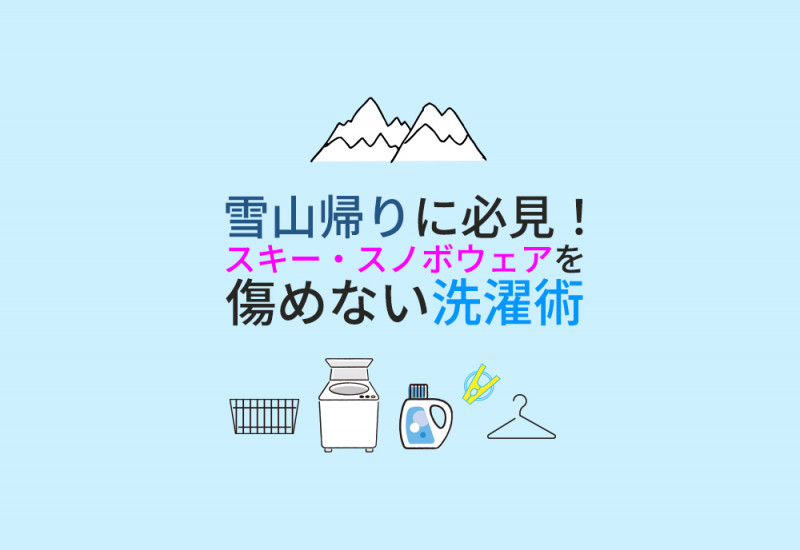
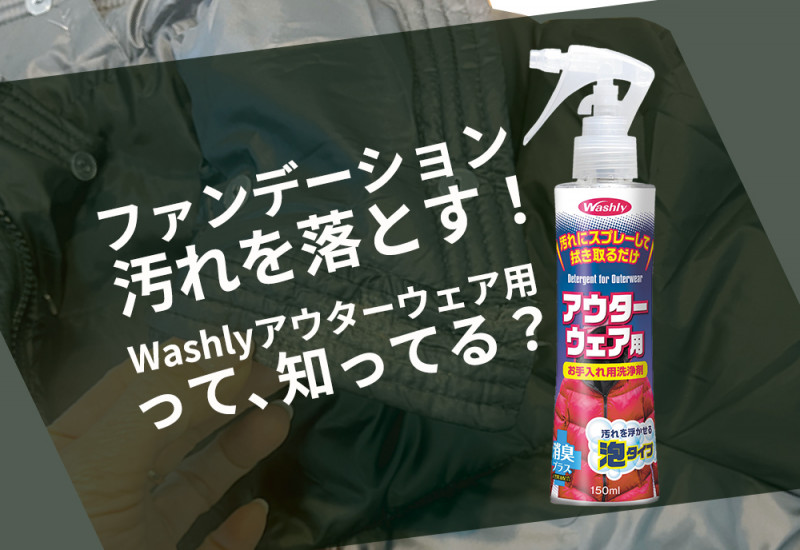

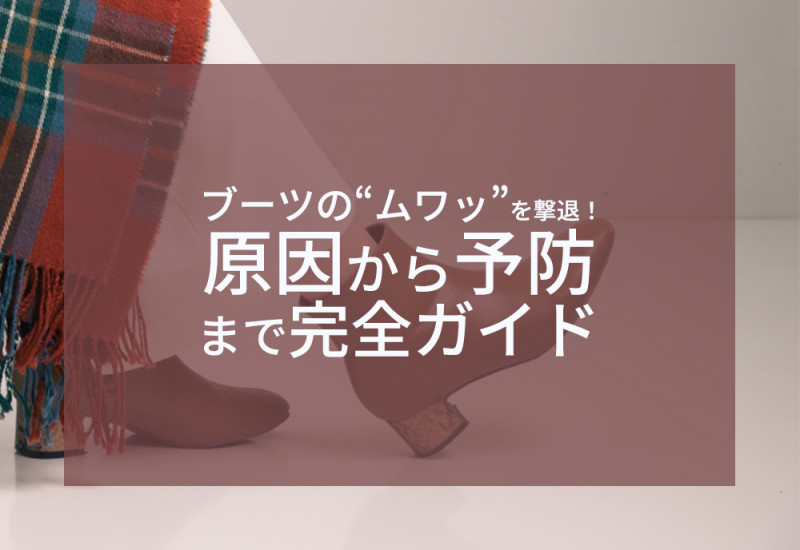
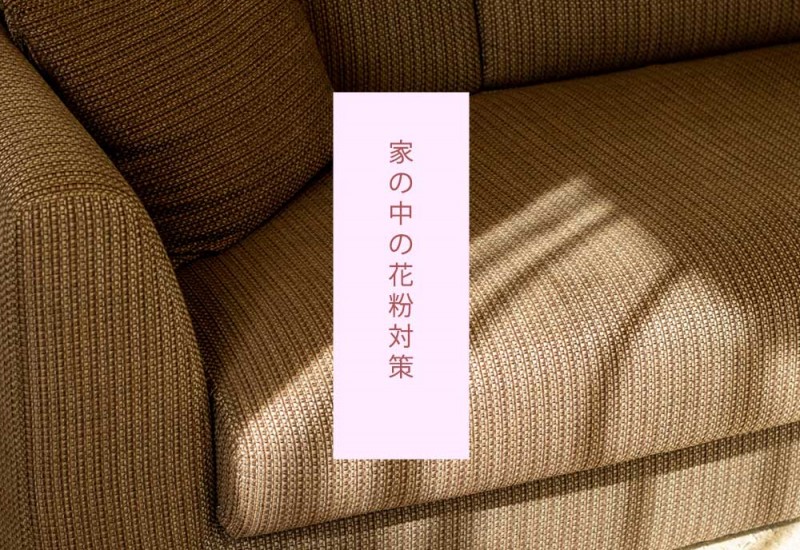


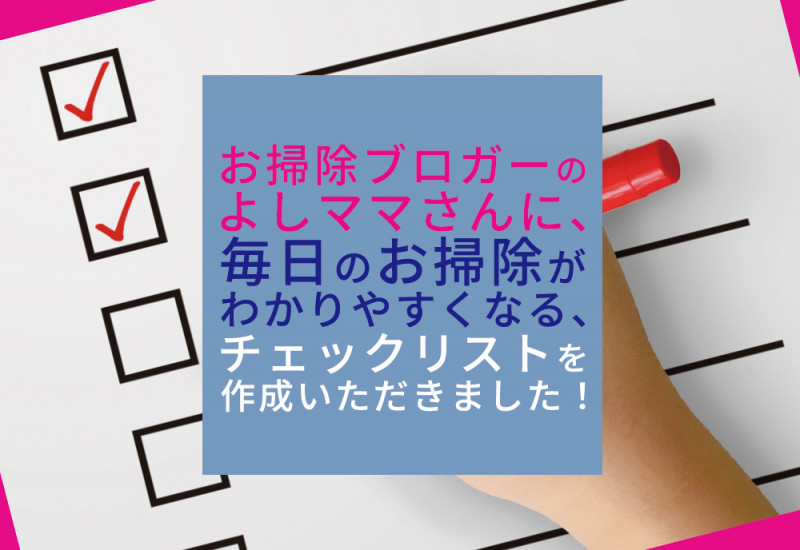

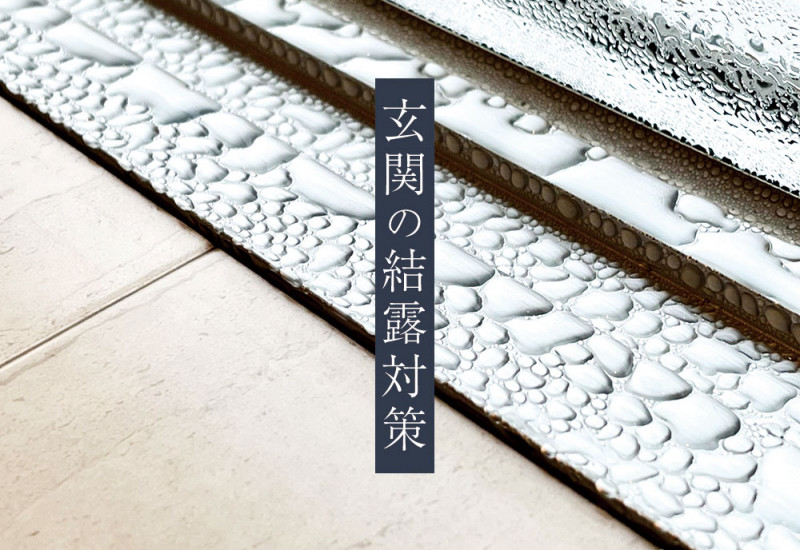

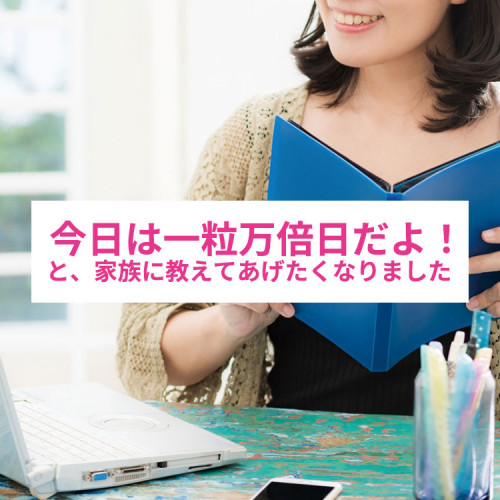
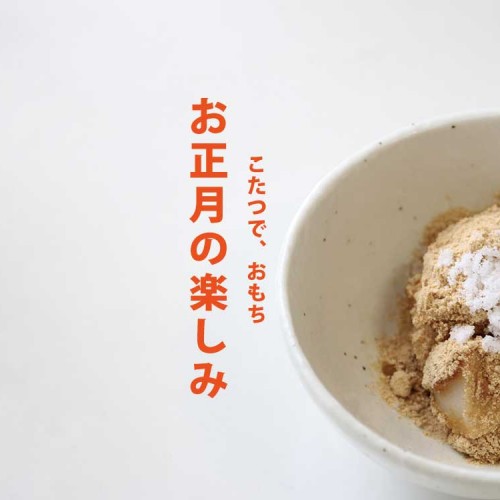
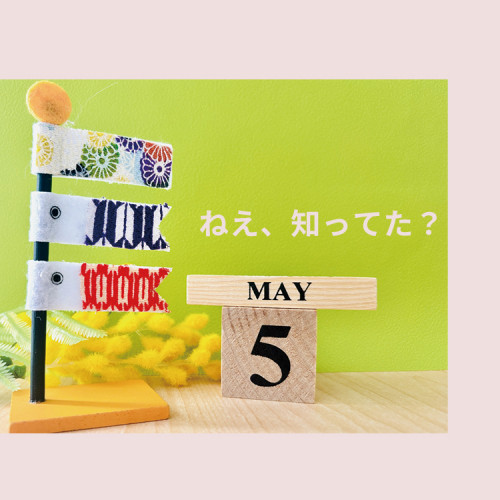


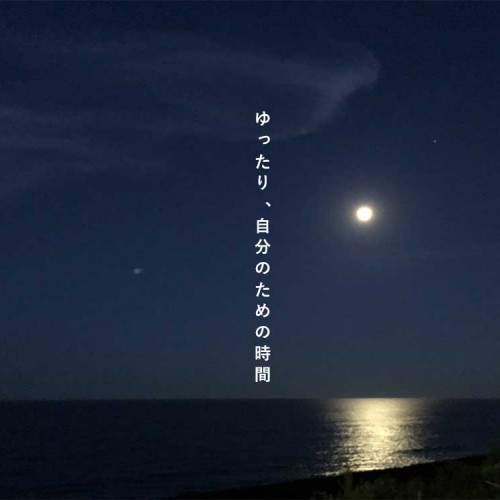
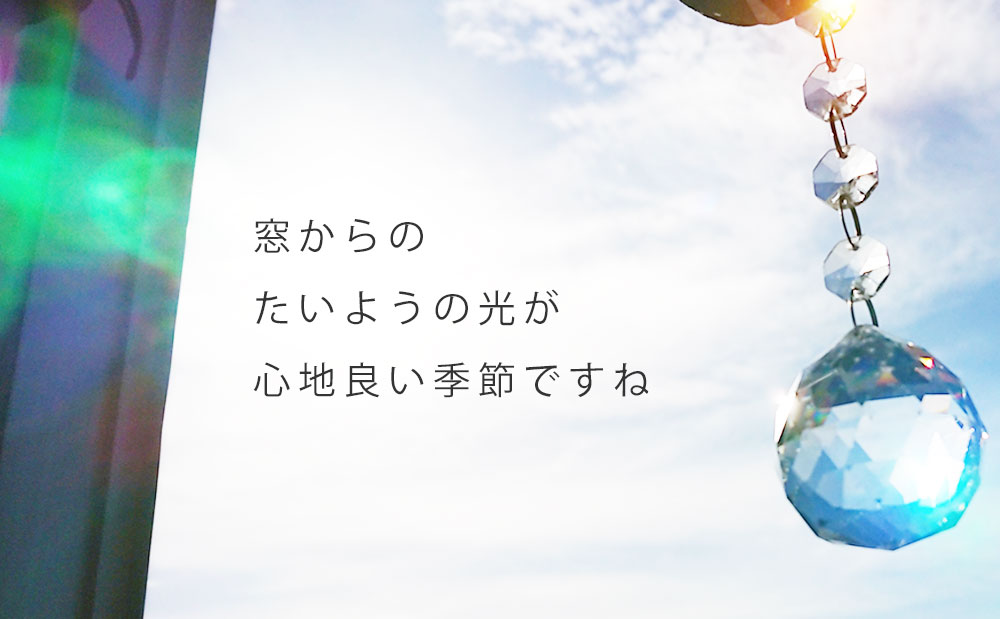
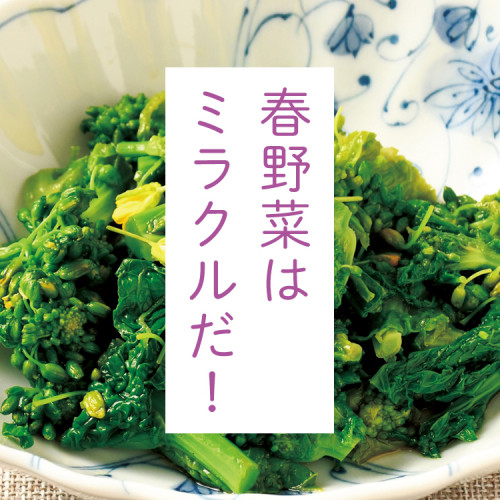
この記事へのコメントはありません。