「こどもの日」と「端午の節句」はどう違う?~端午の節句に込められた意味と行事食
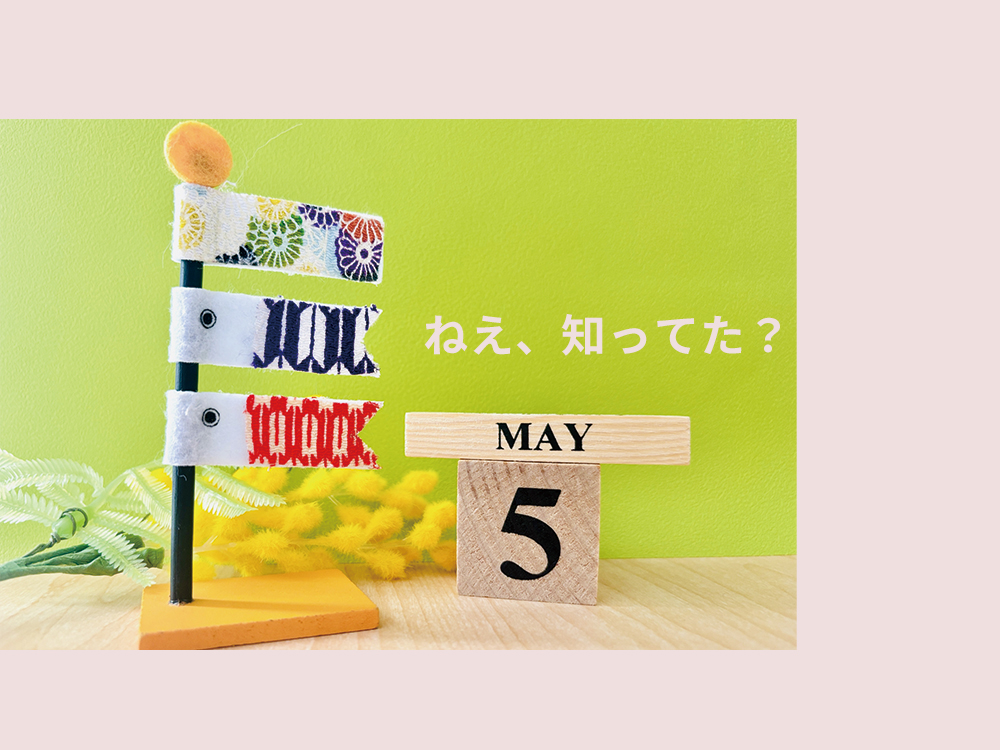
五月晴れの空に泳ぐ鯉のぼりは、初夏の風物詩のひとつです。ただ、最近はその姿を地域コミュニティのなかで見かけるよりも、「こどもの日」の目玉として商業施設や河川敷などで目にする機会が多いかもしれません。そのため、鯉のぼりは「こどもの日の装飾品」と思われがちですが、実際は「端午の節句」にまつわるもの。今回は、春の年中行事「端午の節句」についてお話しします。
「こどもの日」と「端午の節句」って同じ行事じゃないの!?
実は、「こどもの日」と「端午の節句」は同じ行事ではありません。日にちが同じこともあり、混同している人は少なくないのですが、お祝いするようになった背景は大きく違います。それぞれどのような行事なのか見ていきましょう。
「こどもの日」とは

こどもの日は、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に基づいて、1948年(昭和23年)に制定された国民の祝日の一つです。祝日法の第2条では、こどもの日を次のように定めています。
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」
法律の上では、こどもの日はお母さんに感謝する日でもあるのです。お母さんに感謝の気持ちを表す日といえば、「母の日」が定着しています。こどもの日を定義した条文のなかに、母への感謝も明記されているなんて、ちょっと意外ですよね。
「端午の節句」とは

端午の節句は、「男の子」の誕生を祝うとともに、その健やかな成長と幸せを祈る行事です。「節句」は、季節の節目となる日のことをいい、さまざまな行事が執り行われます。江戸時代に入ると、幕府がとくに重要な5つの節句(五節句※)を祝日と定め、そのうちの1つが「端午の節句」です。
古代中国から伝わった考え方・風習がもとになっており、伝来当初は多くの種類が存在していました。五節句(※)の一つであり、古代中国の風習が起源とされています。ただ、日本へ伝わった当初は、現代のような意味合いはなく、しきたりもずいぶん違うものでした。いまのような形になったのは「江戸時代」といわれています。では、端午の節句の変遷を、江戸時代以前・以降に分けて見ていきましょう。
※五節句…人日の節句(1月7日)、上巳の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、七夕の節句(7月7日)、重陽の節句(9月9日)
公家の時代の「端午の節句」は“魔除け”が目的

古来より中国における民間信仰では、旧暦の5月は「毒月(悪月とも)」、5日も「毒日」とされてきました。なぜ、「毒」などという不穏な文字が当てられているのかというと、旧暦の5月は、今の6月ごろにあたり、日に日に気温や湿度が高まる時期。伝染病や虫害などが発生しやすく、体調を崩す人はおろか亡くなる人も多くいたといいます。そこで、人々は魔除けのために「菖蒲」を用いたのだとか。菖蒲には独特の強い芳香があるうえに葉の形が「剣」に似ていることから、邪気を払うと考えられていたのです。そんな菖蒲は、端午節の必須アイテムとなり、庭や門戸、軒先に吊されたり、菖蒲の根を漬け込んだお酒を飲んだりする風習が生まれました。
この風習が日本へ伝来したのは、奈良時代といわれています。『日本書紀』には、5月5日に「薬狩り」と称して野山に薬草を摘みに行ったという記述があり、採取した薬草には、菖蒲や蓬(よもぎ)など香りの強い植物が多く含まれていたことがわかっています。『続日本紀』は、「端午の節」という言葉が初めて出てくる日本最古の書物です。聖武天皇が「端午の節会(※1)」を催したことが記されており、菖蒲でつくった「菖蒲鬘(※2)」をつけない者は宮中に参内させないという記述までみられるといいます。
平安時代には、端午の節会が宮中で盛大に催されるようになりました。軒には菖蒲や蓬を挿し、柱には菖蒲の葉でつくった薬玉を下げ、臣下の者たちは菖蒲鬘をするなど、薬草を飾りつけるだけでなく、災いをもたらす悪鬼を退治するために、騎射(※3)や競馬(※4)といった勇壮な催しも行われたそうです。
このように、奈良時代から平安時代にかけては、端午の節句を行うのは主に貴族で、「魔除け」を目的としていました。
※1 節会(せちえ):一年の節目の日に、宮廷で催される宴会のこと。
※2 菖蒲鬘(あやめのかずら):菖蒲でつくった髪飾りや冠の飾りのこと。
※3 騎射(きしゃ):うまゆみ(馬弓)とも。馬上から弓を射ること。
※4 競馬(くらべうま):2頭の馬を走らせて、走行速度や騎手の乗馬技術などを競う競技。
武家の時代に「男の子」の誕生と成長を祝う行事へ変化

貴族よりも武士の力が強くなった鎌倉時代。端午の節句は、主に武士が行う行事へと変わっていきました。というのも、「菖蒲(しょうぶ)」の音が、武道を重んじるという意味の「尚武(しょうぶ)」に通じることから、縁起がいいとされたのです。
江戸時代に入ると、端午の節句は幕府の公式な祝日に。大名や旗本は式服で江戸城へ参上し、お祝い奉じるようになりました。将軍家にお世継ぎが生まれると、城内に幟(のぼり)を立て、薙刀や兜、鎧などを飾り、盛大にお祝いしたといいます。天下泰平の世が続くようになると、端午の節句を行うのは武家ばかりでなく、庶民にも広がっていきました。ただ、庶民は幟を立てることを許されていなかったため、その代わりとして「鯉のぼり」を立てるようになったのだそうです。これが、今につながる端午の節句の原型といわれています。
江戸時代になると、端午の節句は「魔除け」の要素を残しつつも、「男子誕生のお披露目の儀式」として広く浸透していきました。
「端午の節句」は何をする日?

ここからは、「端午の節句」には何をするのか、具体的に見ていきましょう。
五月人形を飾る
五月人形は「内飾り」と呼ばれ、武者人形よりも、甲冑(鎧・兜)を指すことがほとんどです。甲冑を飾るのは武家社会の風習が色濃く残っています。鎧や兜は「戦の道具」というイメージが強いものの、自分の身を守る大切な道具であり、武士の精神的な象徴である宝物でもありました。現代では「身を守る」という意味から、事故や病気などからこどもを守ってくれるようにと願いを込めて飾られます。
鯉のぼりを揚げる
鯉のぼりは、江戸時代に町民階層から生まれたお飾りで、「外飾り」と呼ばれています。なぜ、鯉なのかというと、理由は2つあります。ひとつは、「鯉は滝を登ると龍になる」という中国の故事にちなみ、立身出世を願って。もうひとつは、鯉は清流だけでなく、沼など濁った水の中でも生きてゆける強い生命力の魚であることから、どんな環境でもたくましく育ってほしいという願いが込められているからです。
菖蒲湯に入る
「端午の節句」は、別名「菖蒲の節句」といわれるほど、古くから菖蒲が珍重されてきました。邪気を払うと信じられてきた強い芳香には、多くの薬効もあるそうです。たとえば、「テルペン類」や「オイゲノール」といった香り成分には、血行促進や疲労回復といった効果があるといわれています。菖蒲湯に浸かるのは、健康面からみても大変理にかなったものなのです。
行事食をいただく
端午の節句の代表的な行事食は「柏餅」と「ちまき」です。なぜ食べられるようになったのか、順に見てきましょう。
なぜ、「柏餅」なのか?

端午の節句に「柏餅」を食べる風習が生まれたのは、江戸時代といわれています。柏の葉は、新芽が出ないと古い葉が落ちないという特性があることから、新芽をこども、古い葉を親に見立て、「家系が途絶えない」ひいては「子孫繁栄」を願って用いられるようになりました。
なぜ、「ちまき」なのか?

端午の節句に「ちまき」を食べるのは、中国の風習に由来します。旧暦の5月5日は、楚国の政治家であり詩人でもあった屈原(くつげん)が川へ身投げをした日で、その死を悼むために、人々はちまきを川へ投げ入れたそうです。それ以降、国の安泰を祈願する行事として中国全土に広まり、端午節にはちまきを食べるという習慣が残ったといわれています。
「こどもの日」と「端午の節句」は別の行事です!
桃の節句に比べると、やや地味な印象がある「端午の節句」。5月5日は「こどもの日」でもあるため、混同されがちですが、由来も意味もまったく違います。「こどもの日」は国民の祝日の一つで、「端午の節句」は連綿と続く日本の伝統的な行事です。五月晴れの空を泳ぐ「鯉のぼり」にも、「五月人形」や「菖蒲湯」にも、行事食である「柏餅」と「ちまき」にも深い意味があります。それを知ると、5月5日がこれまでとは違って見えてくるはず。今年は、新たな気持ちで「端午の節句」を迎えてみませんか。
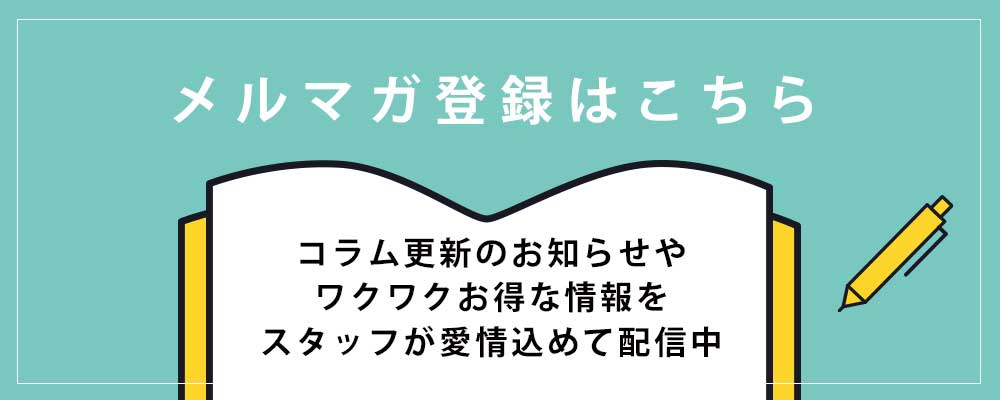
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
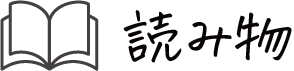
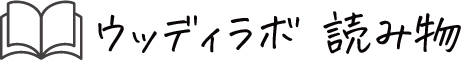
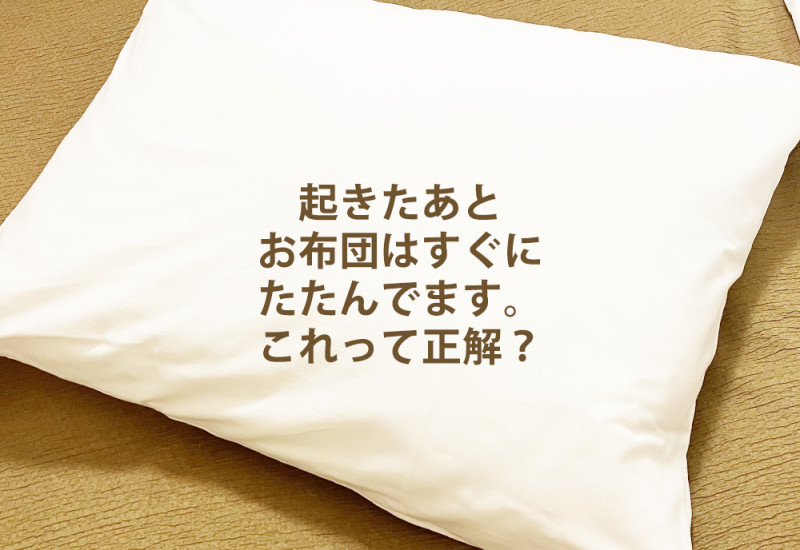
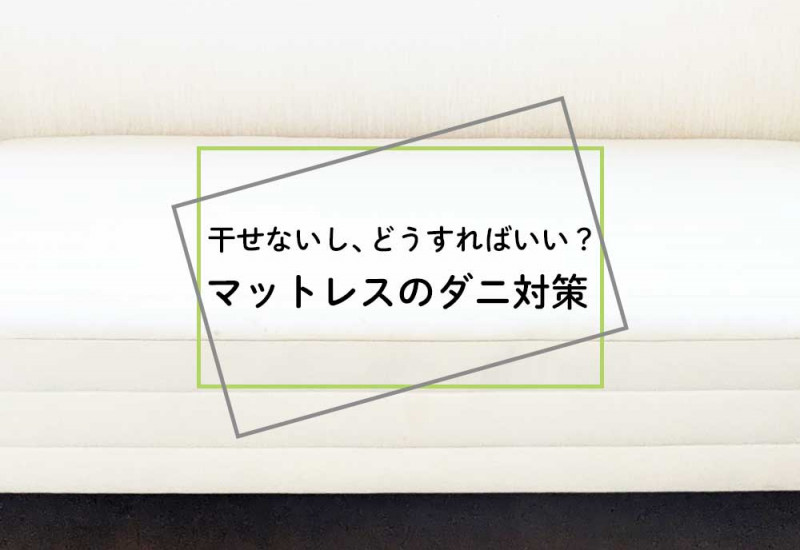
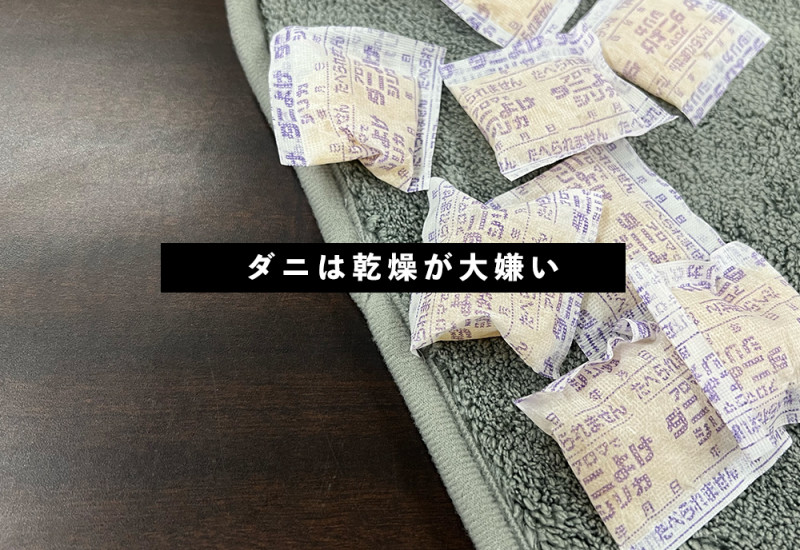









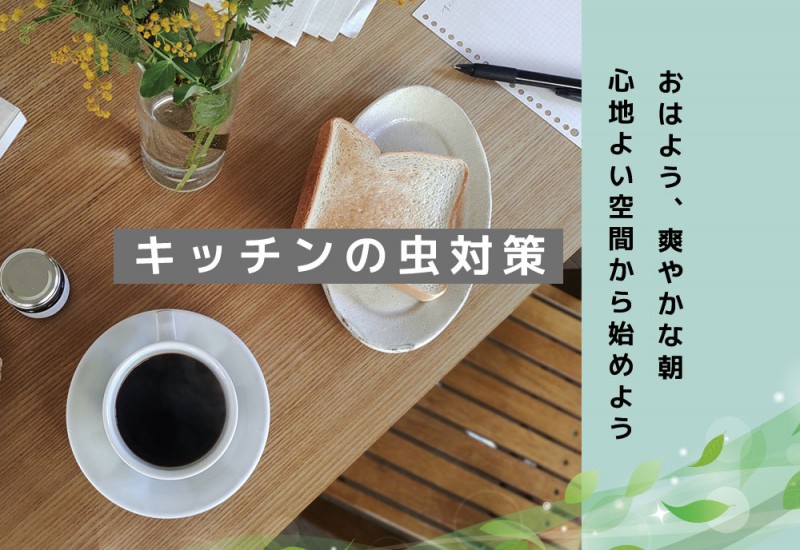
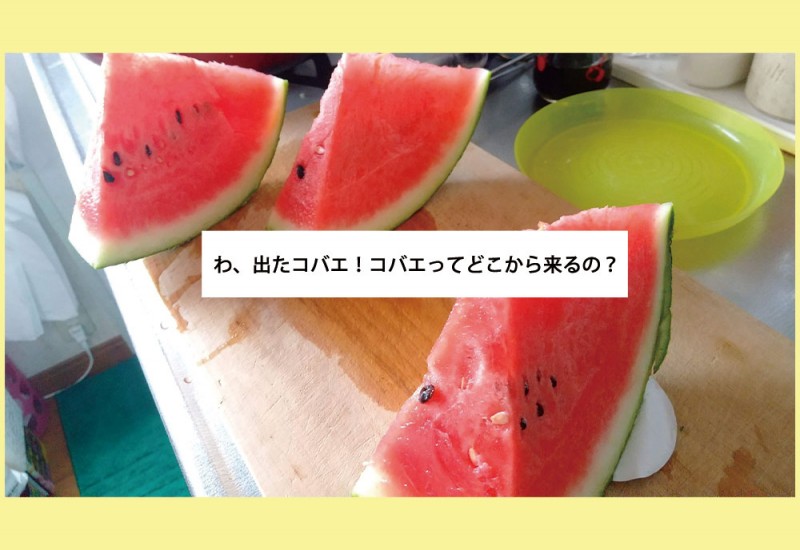
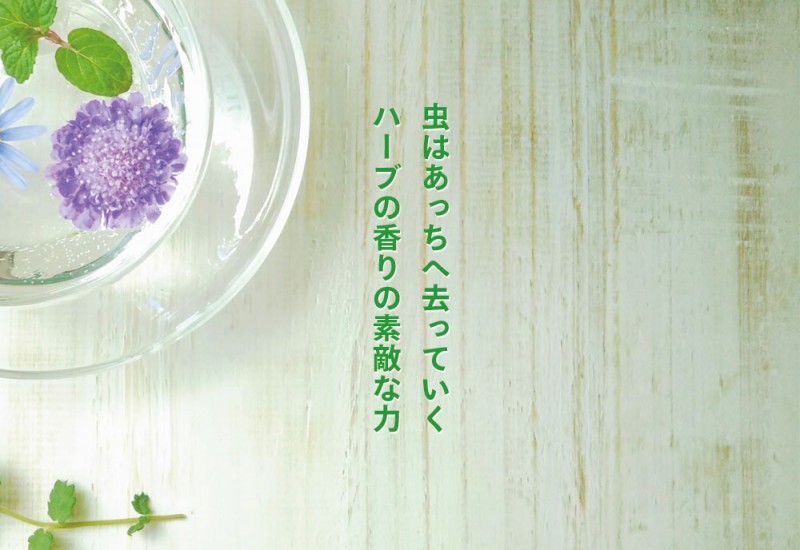







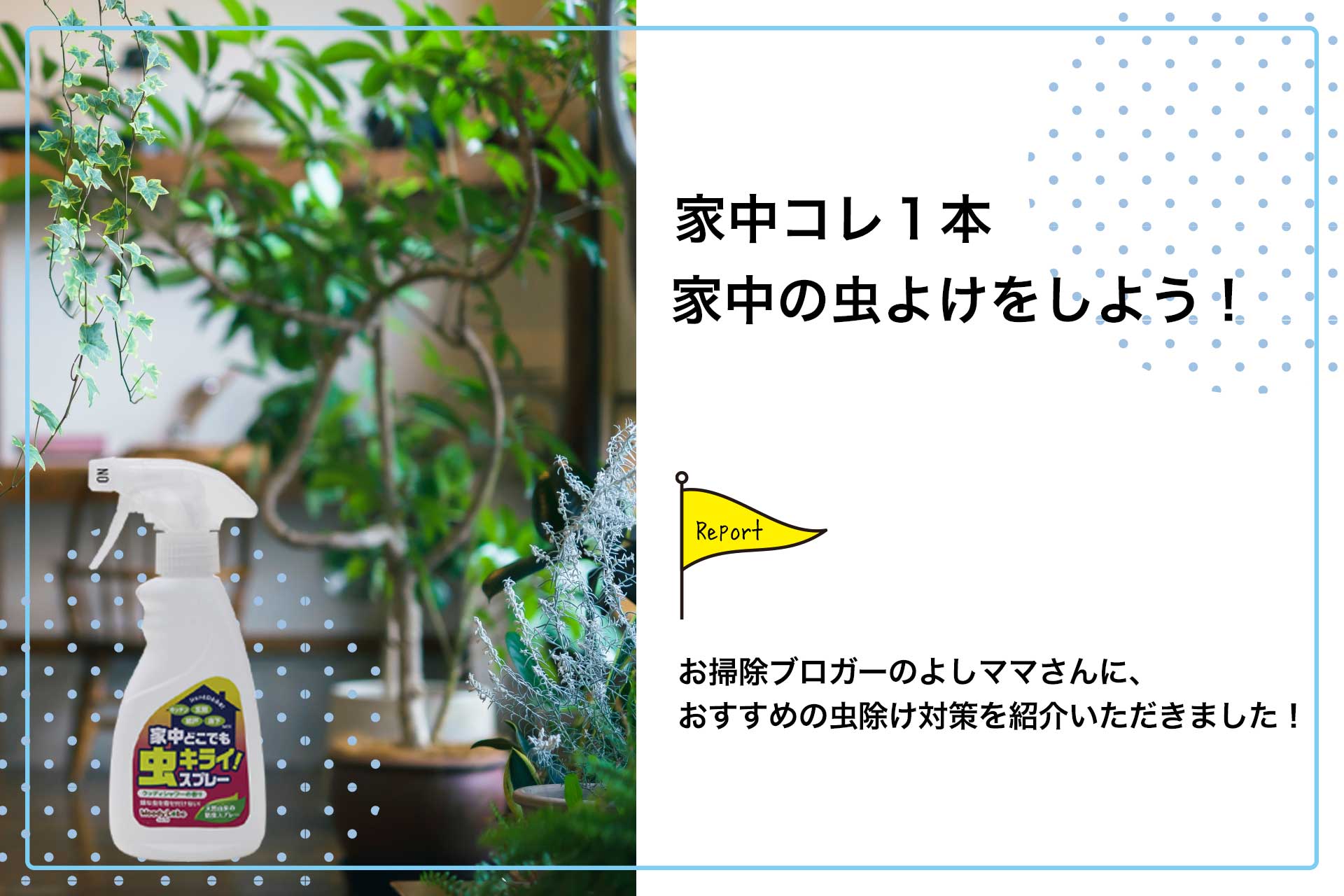
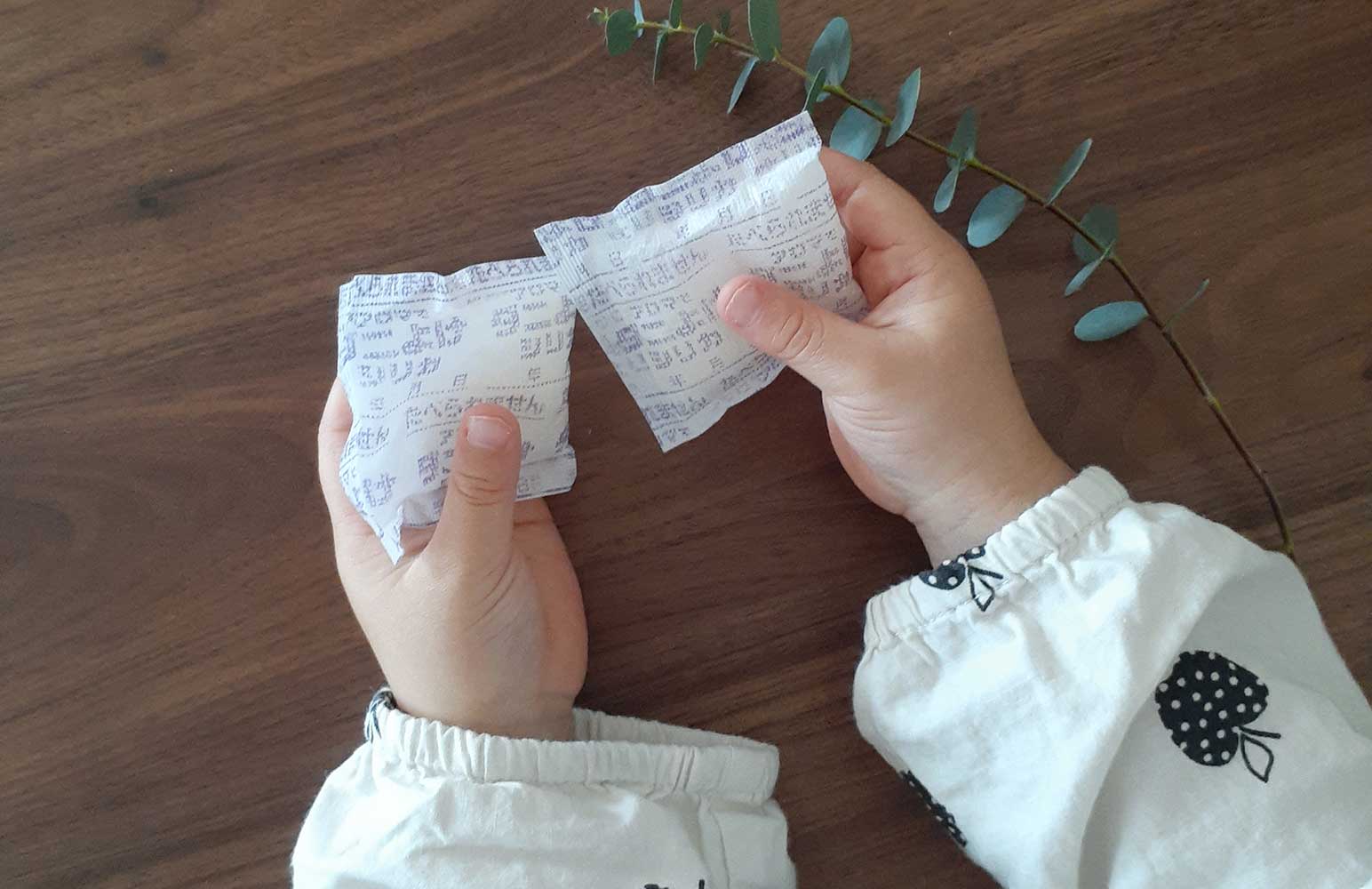
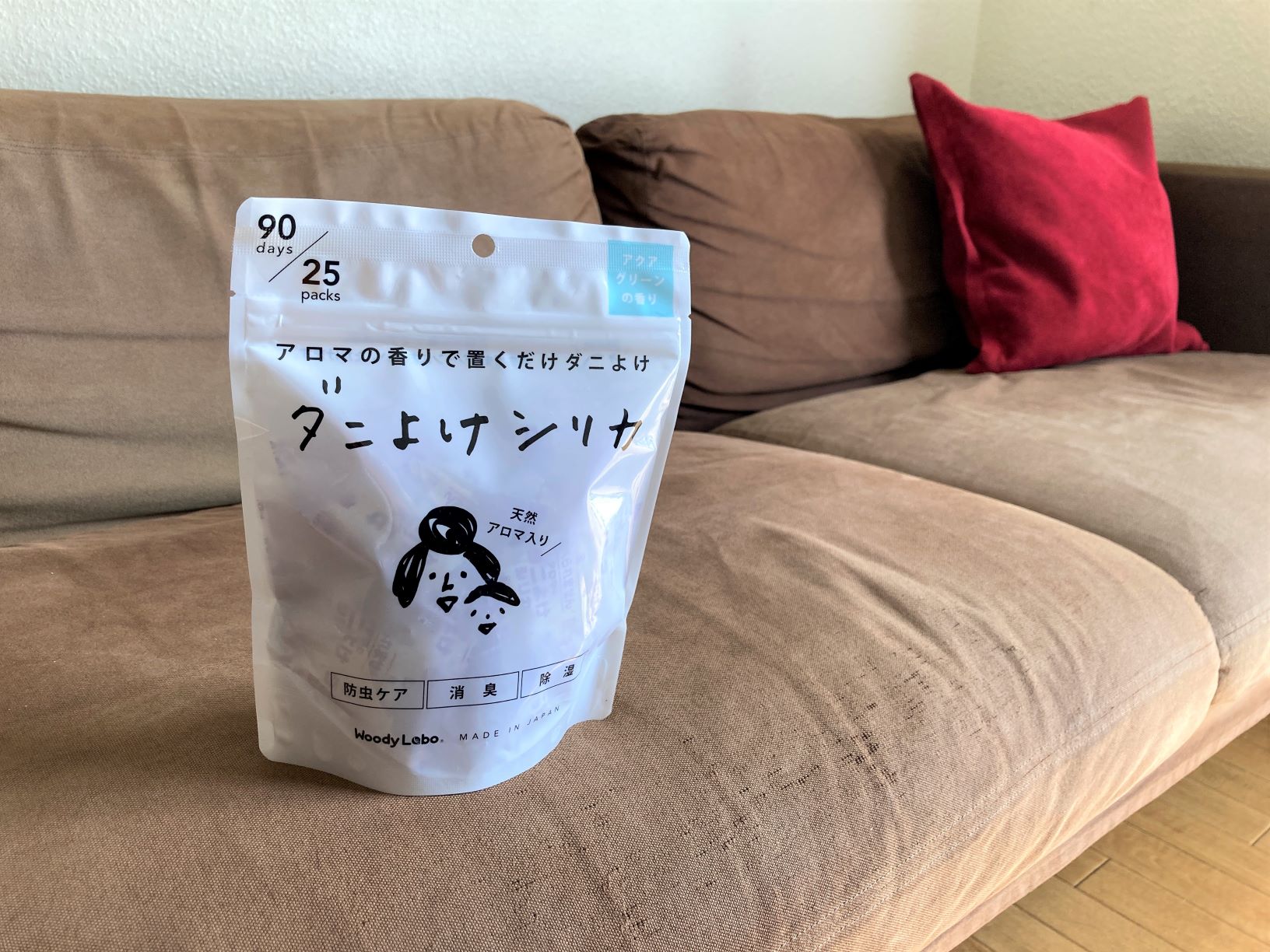

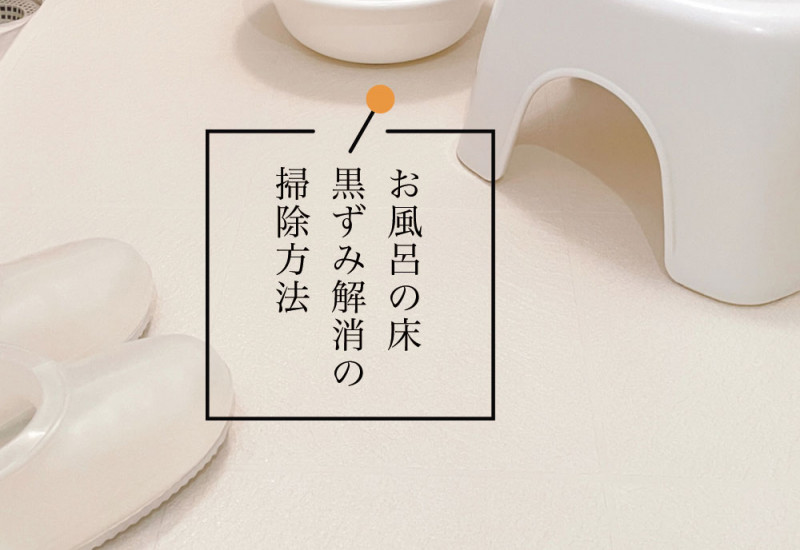

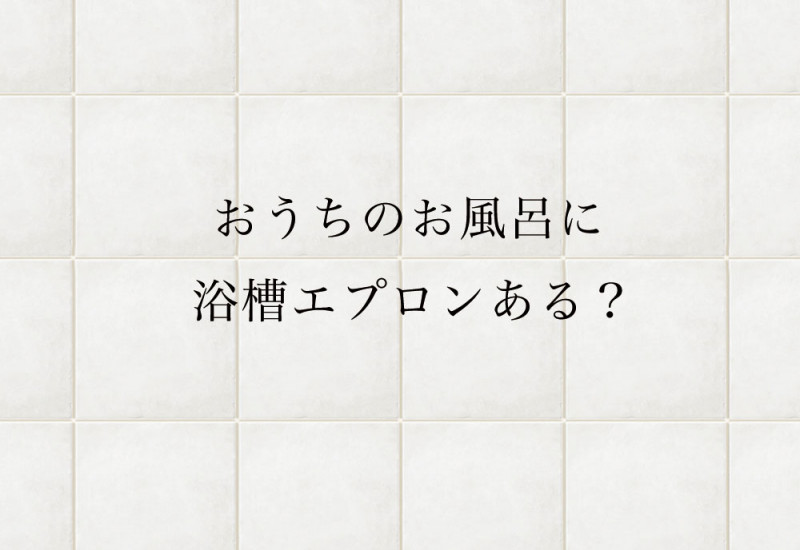
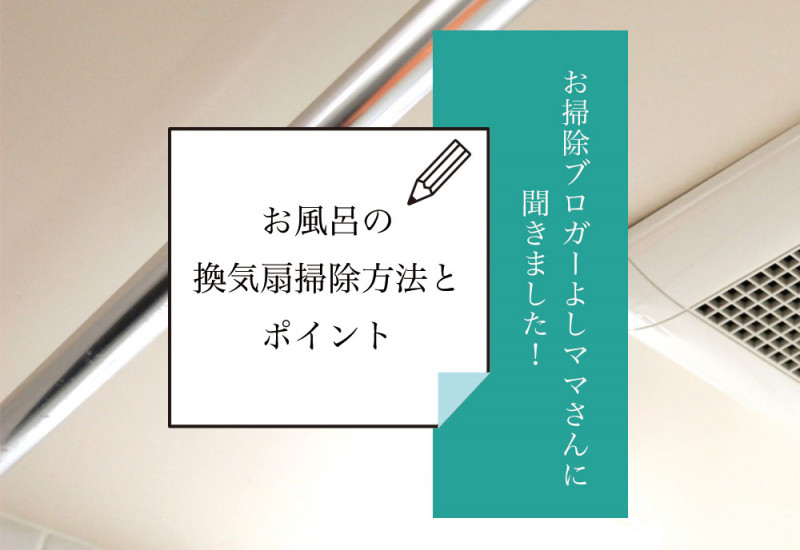
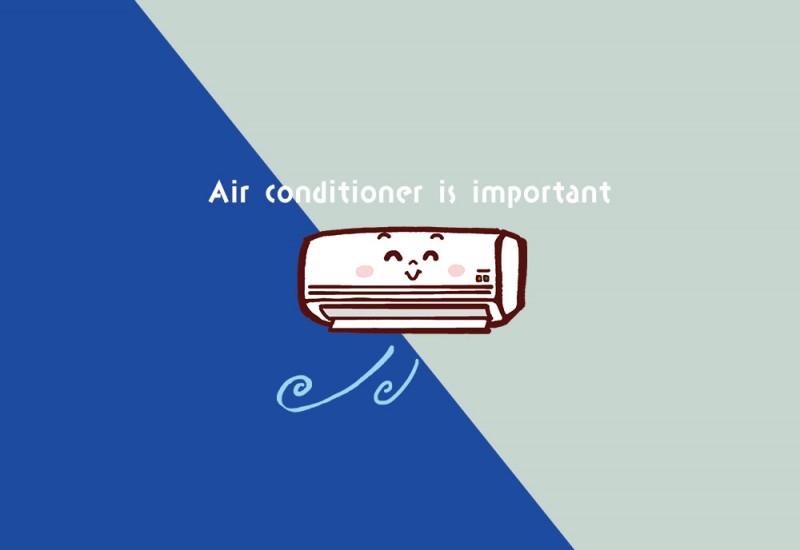


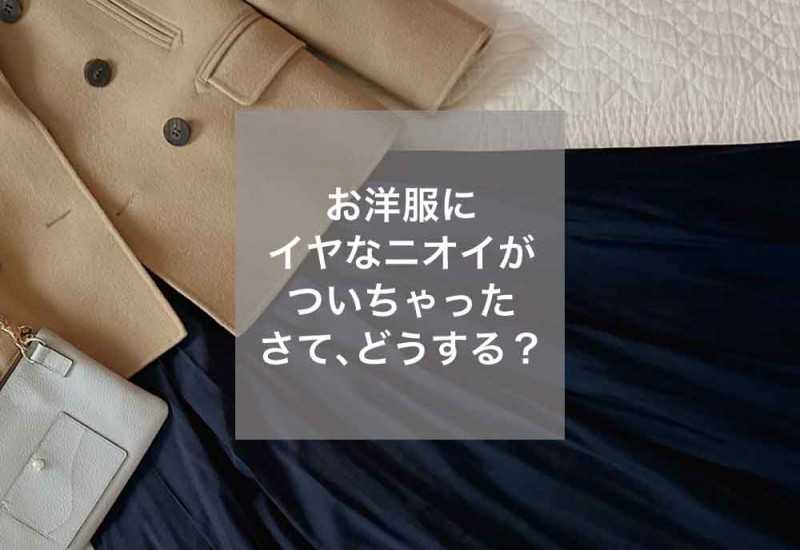
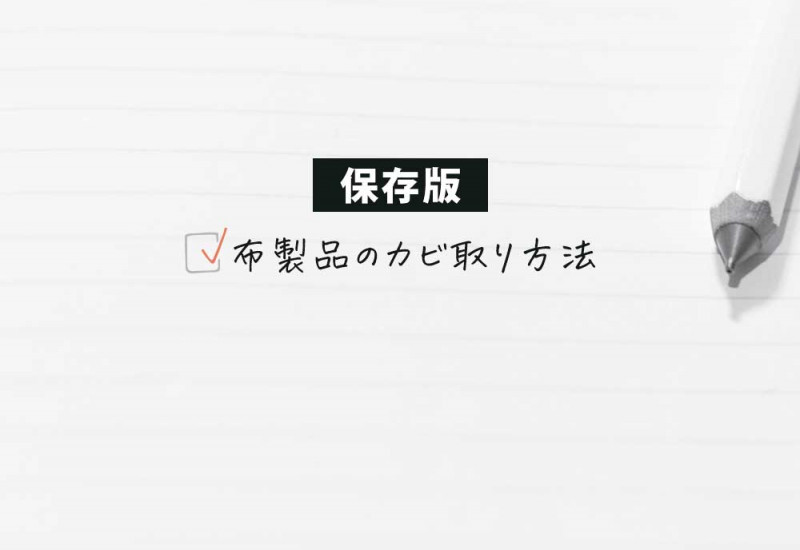

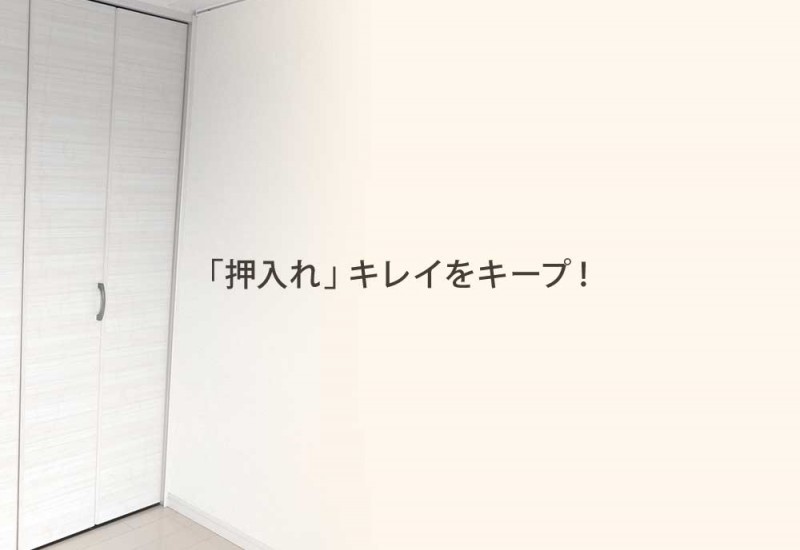

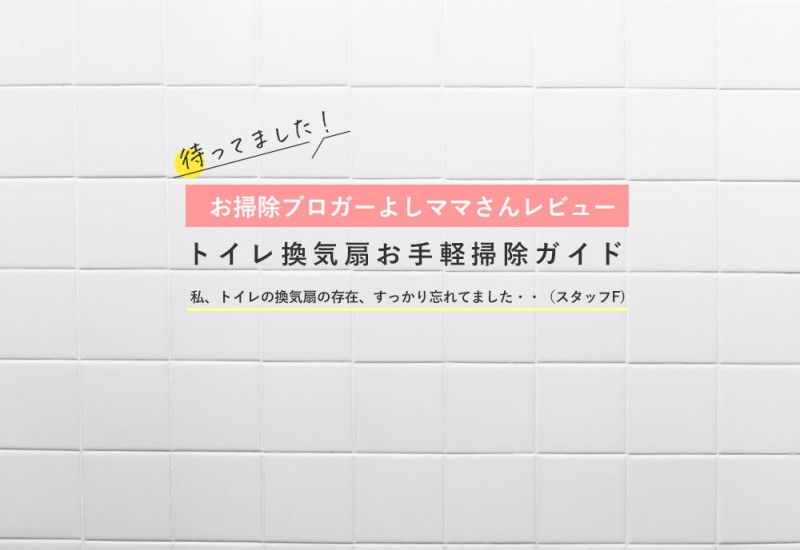
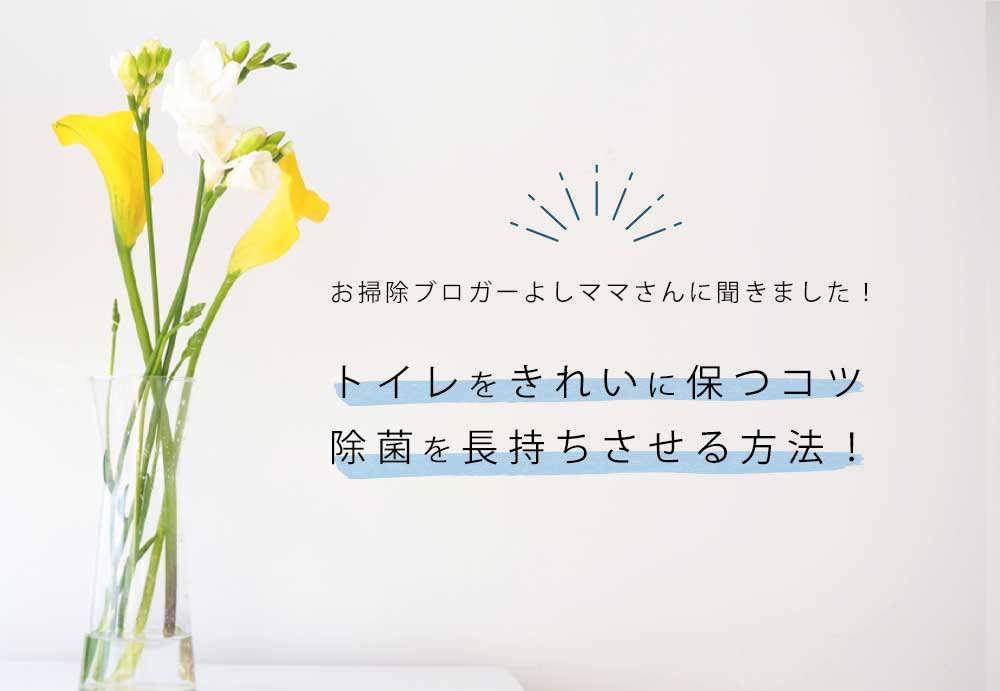
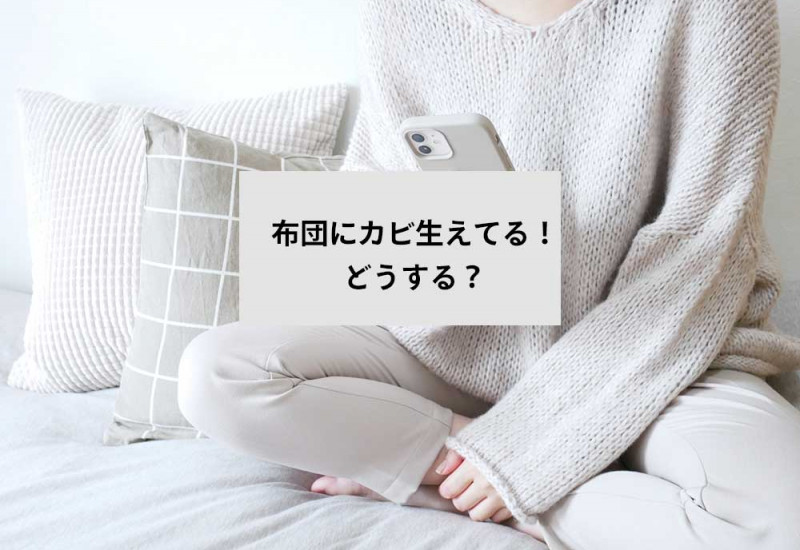
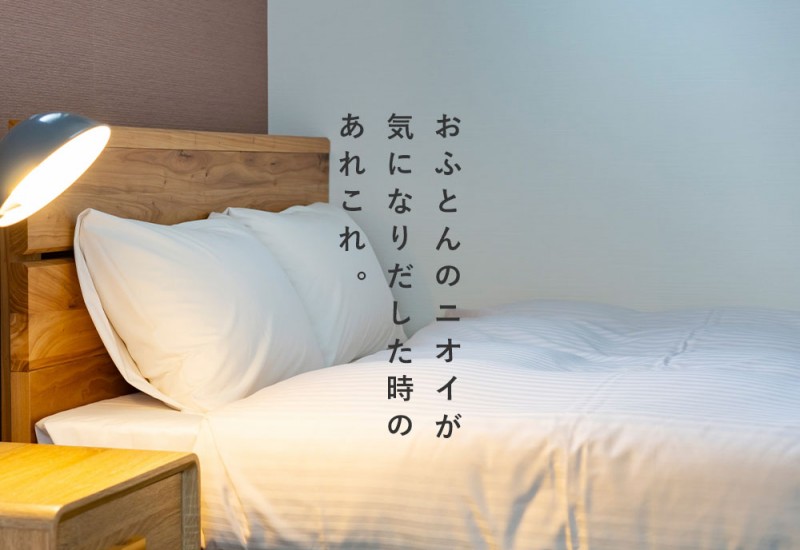

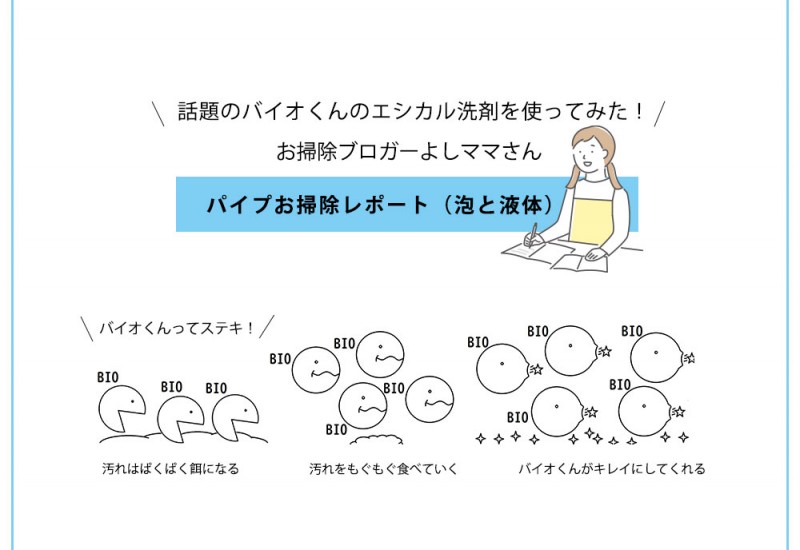

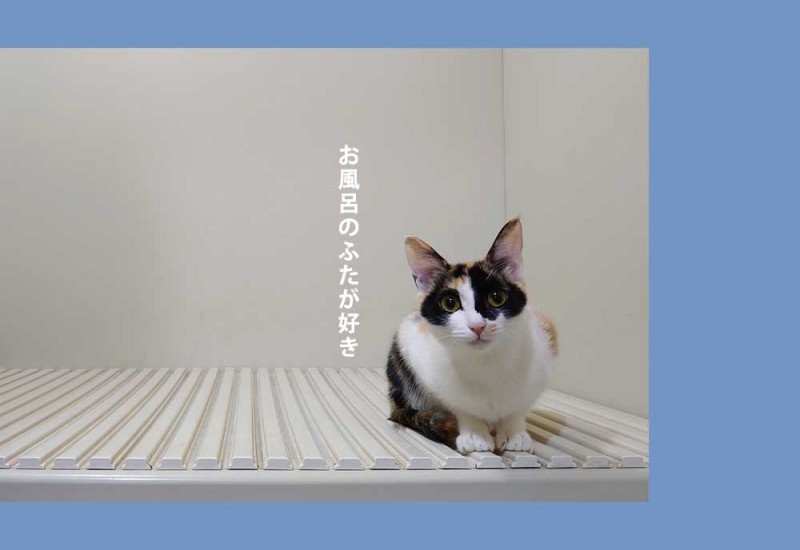
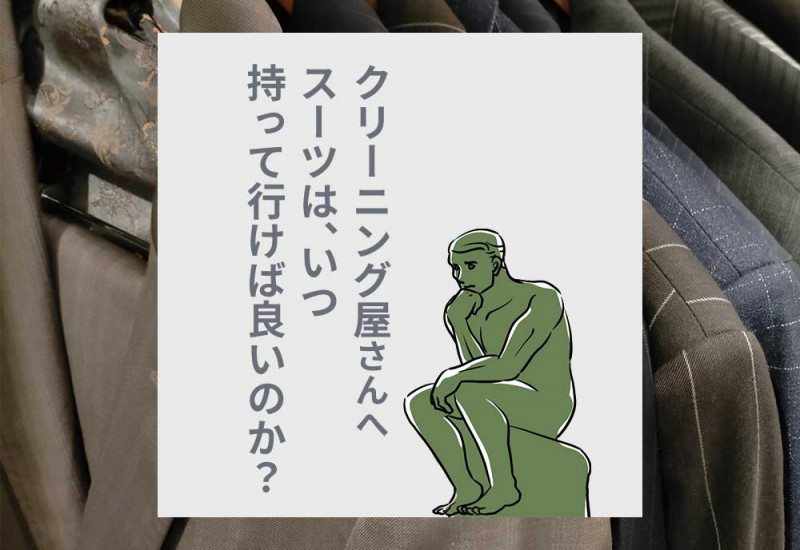
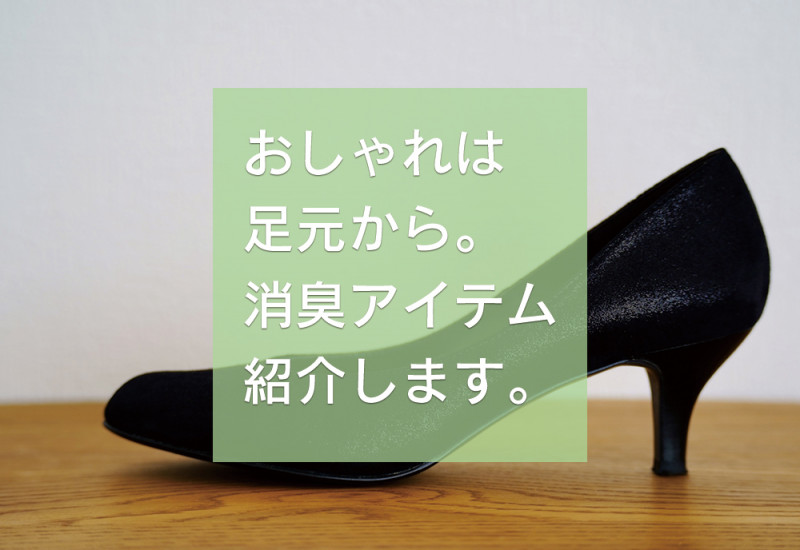
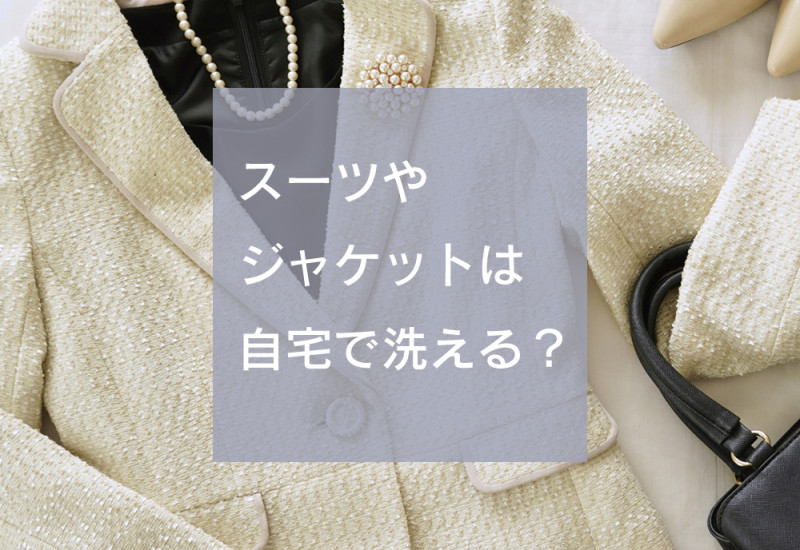


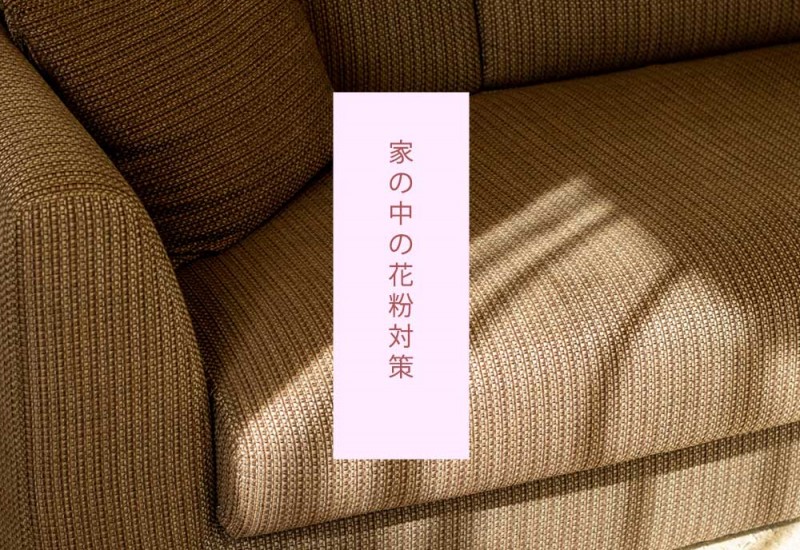
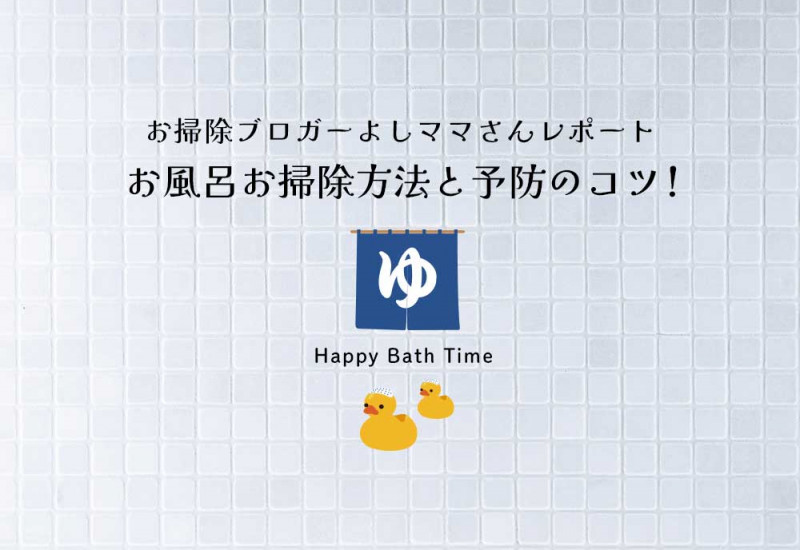
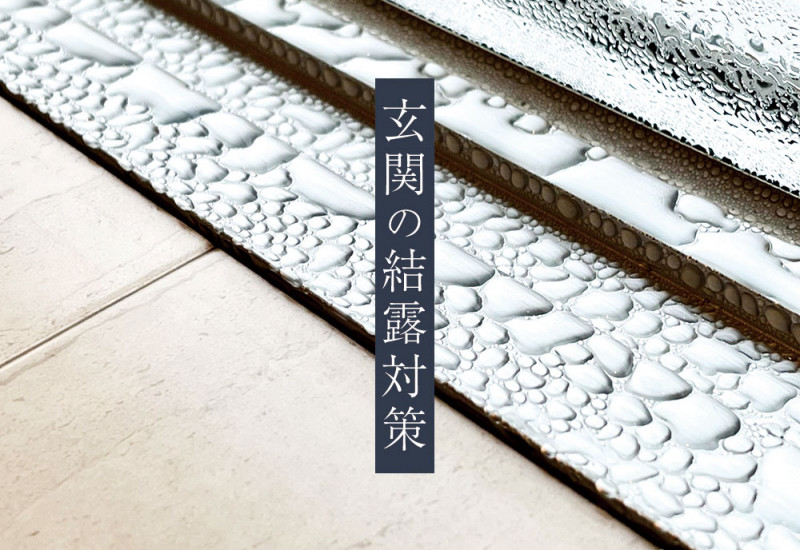

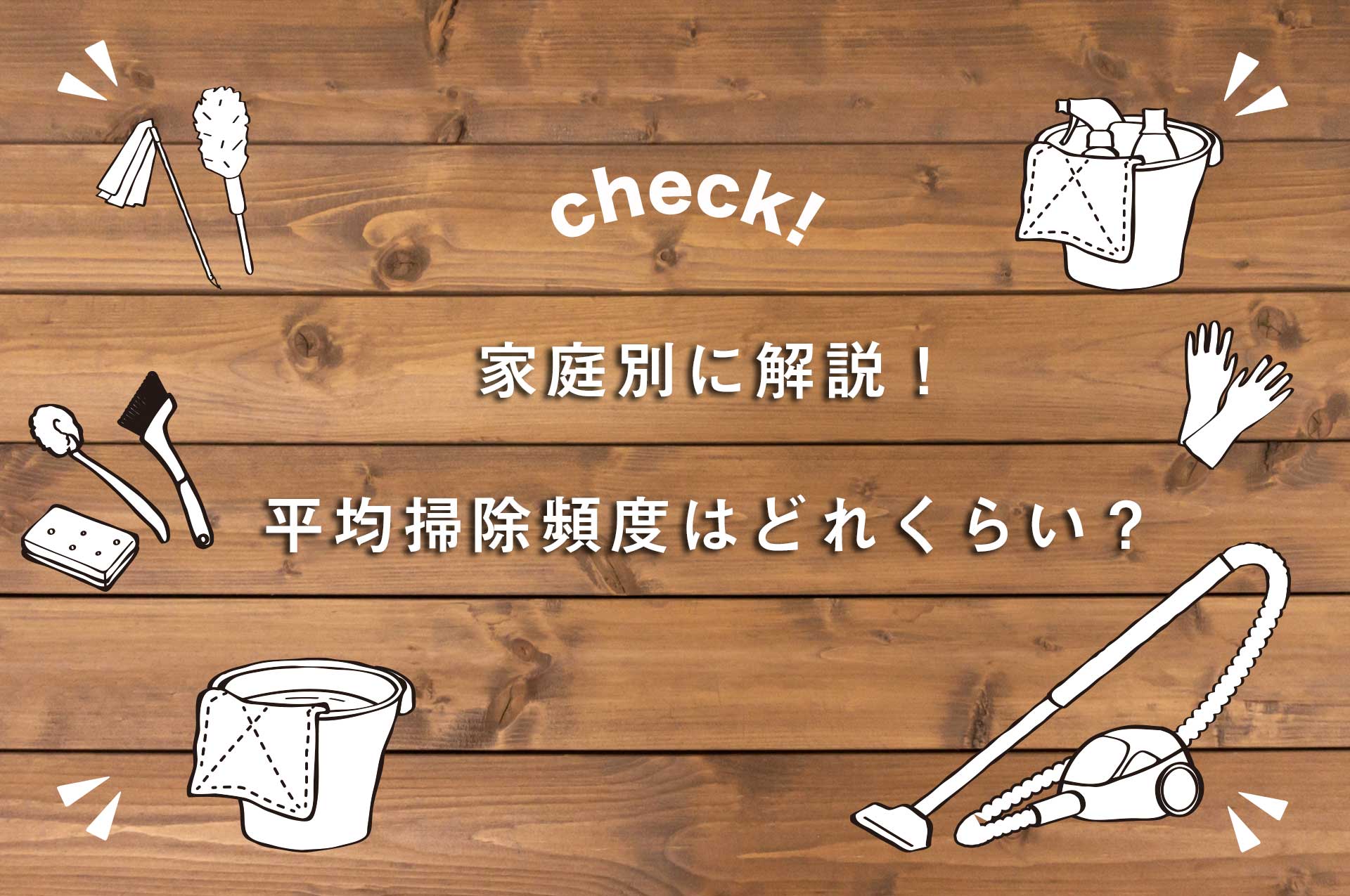


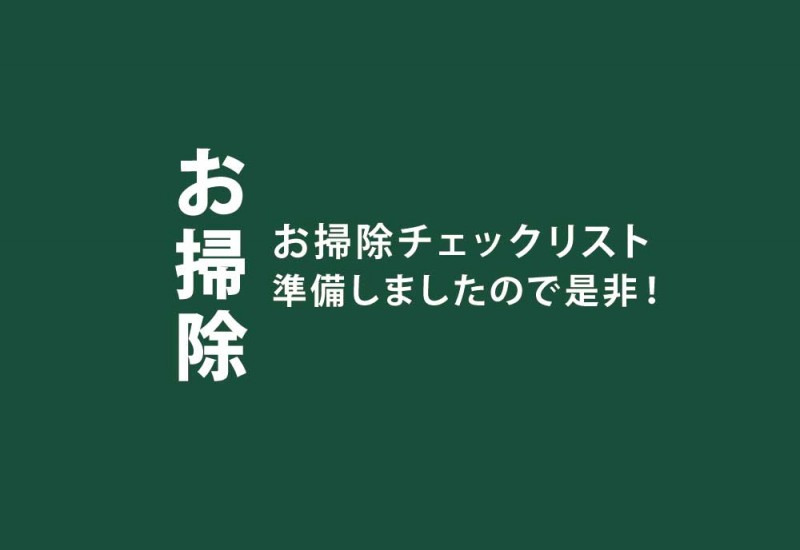



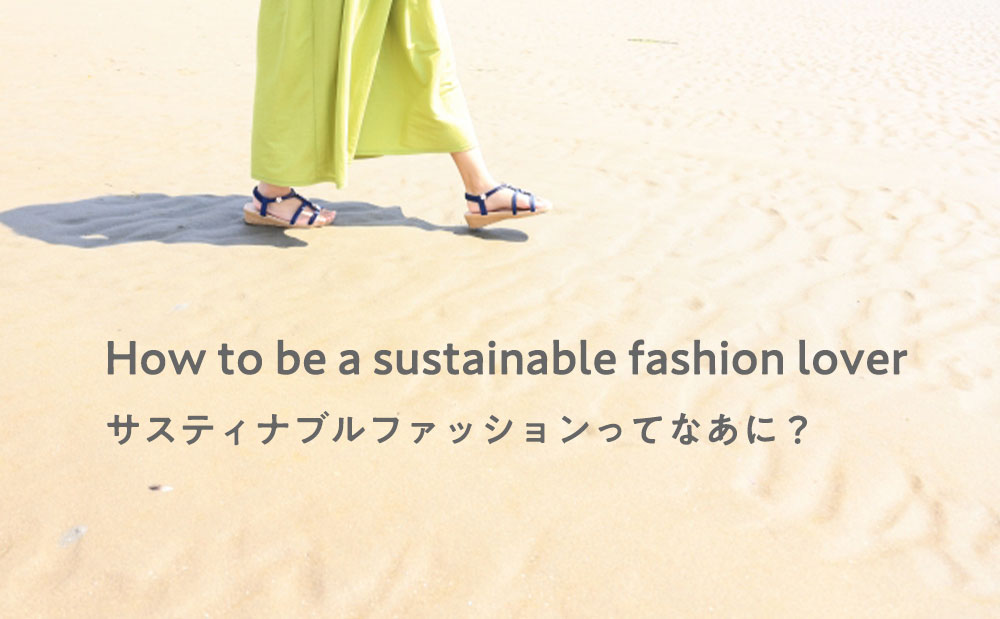


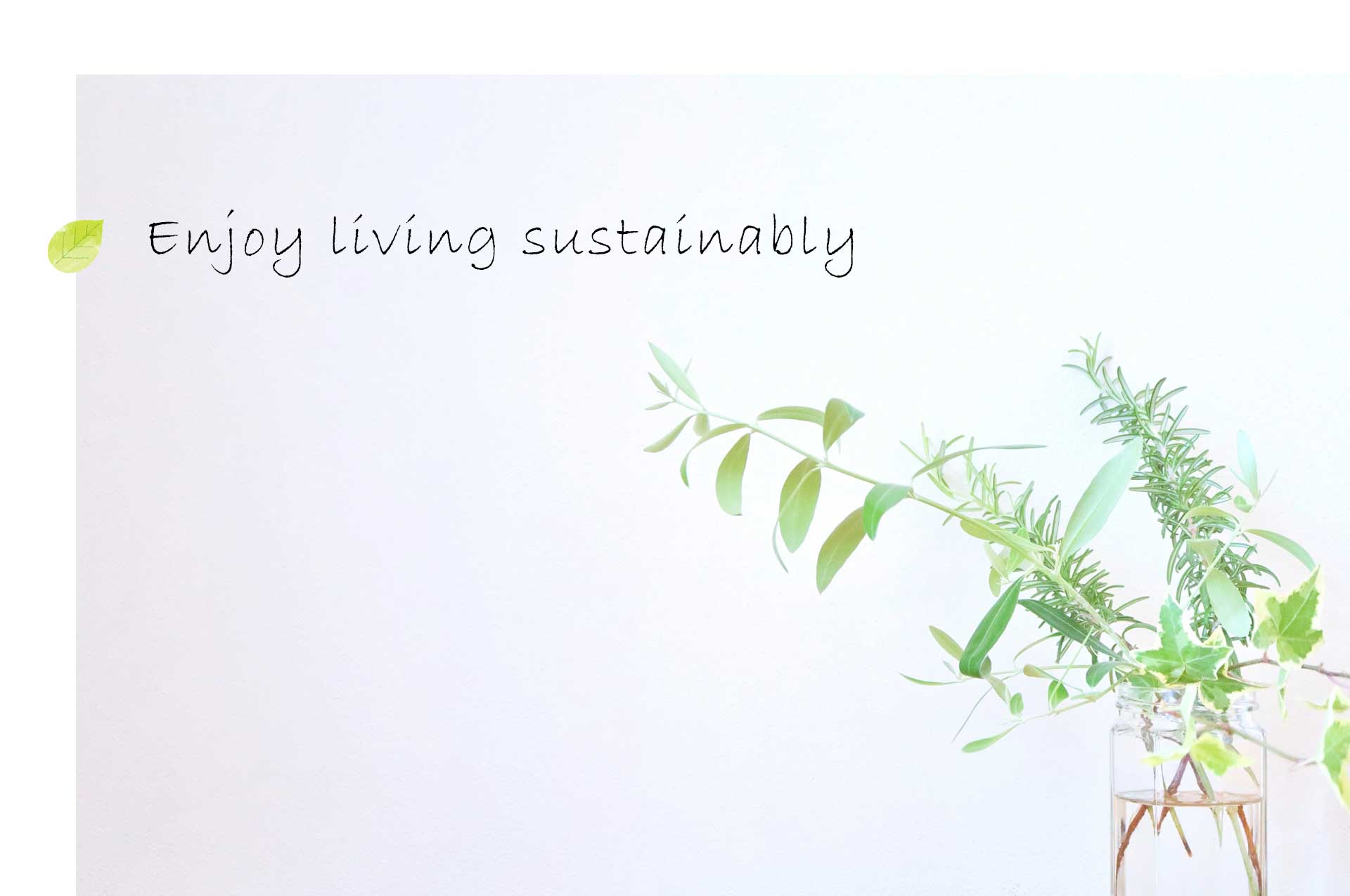
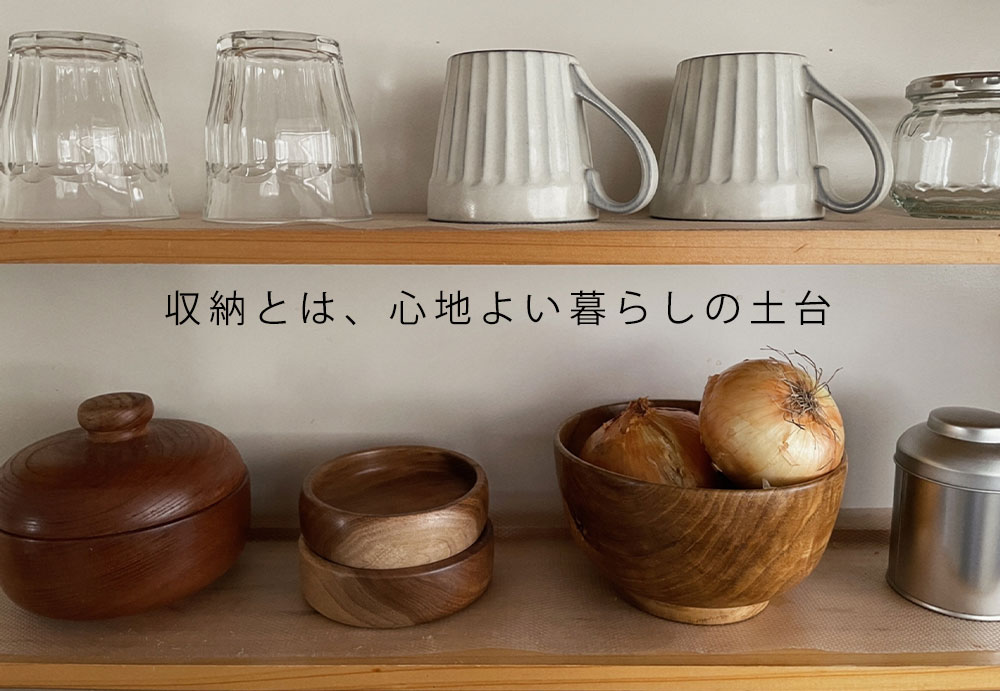
この記事へのコメントはありません。